夏の花
158件の記事があります。
2013年06月05日北の丸公園の自然
皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花
本日も快晴です。園内の芝生広場では、暑さに負けない元気なお子様達の声が響き渡っています。
6月5日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

キョウチクトウ
キョウチクトウ科キョウチクトウ属の常緑低木、もしくは常緑小低木です。鮮やかなピンクが美しい花ですが、毒をもっています。人や家畜などが体内に取り入れた場合、中毒や死に至る事がある為注意が必要な植物です。

ヘメロカリス
ユリ科ヘメロカリス属です。性質は丈夫なので育てやすく、大きさや花色が非常に多様です。

属名はギリシア語hemera(一日の意)とkallos(美の意)に由来し、花が一日でしぼむことにちなんでいます。園内のヘメロカリスはまだ蕾がたくさんあるので、しばらくの間お楽しみいただけます。

ドクダミ(八重)
以前「ドクダミ」を紹介しましたが、こちらは八重咲のドクダミです。花びらに見える苞(つぼみを包んでいた葉の部分)が八重になっています。本体の花は黄色い部分で、花びらはありません。
.jpg)
6月5日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

キョウチクトウ
キョウチクトウ科キョウチクトウ属の常緑低木、もしくは常緑小低木です。鮮やかなピンクが美しい花ですが、毒をもっています。人や家畜などが体内に取り入れた場合、中毒や死に至る事がある為注意が必要な植物です。

ヘメロカリス
ユリ科ヘメロカリス属です。性質は丈夫なので育てやすく、大きさや花色が非常に多様です。

属名はギリシア語hemera(一日の意)とkallos(美の意)に由来し、花が一日でしぼむことにちなんでいます。園内のヘメロカリスはまだ蕾がたくさんあるので、しばらくの間お楽しみいただけます。

ドクダミ(八重)
以前「ドクダミ」を紹介しましたが、こちらは八重咲のドクダミです。花びらに見える苞(つぼみを包んでいた葉の部分)が八重になっています。本体の花は黄色い部分で、花びらはありません。
.jpg)
2013年06月03日北の丸公園の自然
皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花
梅雨入りはしましたが、昨日、今日と、晴れ渡った青空が広がっています。サンサンと降り注ぐ太陽の下、園内の芝生広場では日光浴をするお客様の姿も見られました。
6月3日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

ビヨウヤナギ
オトギリソウ科オトギリソウ属の半常緑小低木で、中国原産です。

枝先が少し垂れ下がり、ヤナギの葉に似ているのでこの名がつきましたが、ヤナギの仲間ではありません。

モンシロチョウ
この蝶を知らない人は少ないのではないでしょうか。日本全土に分布しています。成虫になったときの天敵は、鳥類、カマキリ、トンボなどです。

ハナショウブ
アヤメ科アヤメ属の多年草です。以前紹介した「カキツバタ」はハナショウブの隣の浮島に植栽されており、この2種は大変似ています。慣用句で、「いずれがアヤメかカキツバタ」というものがありますが、これは「優劣がつけがたい」「見分けがつきがたい」という意味で用いられます。

6月3日(月)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

ビヨウヤナギ
オトギリソウ科オトギリソウ属の半常緑小低木で、中国原産です。

枝先が少し垂れ下がり、ヤナギの葉に似ているのでこの名がつきましたが、ヤナギの仲間ではありません。

モンシロチョウ
この蝶を知らない人は少ないのではないでしょうか。日本全土に分布しています。成虫になったときの天敵は、鳥類、カマキリ、トンボなどです。

ハナショウブ
アヤメ科アヤメ属の多年草です。以前紹介した「カキツバタ」はハナショウブの隣の浮島に植栽されており、この2種は大変似ています。慣用句で、「いずれがアヤメかカキツバタ」というものがありますが、これは「優劣がつけがたい」「見分けがつきがたい」という意味で用いられます。

2013年05月29日北の丸公園の自然
皇居外苑いきもの / バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花
今日から関東甲信地方は梅雨入りをしたようです。園内では、この季節ならではの植物が次々と開花し始めています。
5月29日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

タイサンボク
吉田茂像周辺に、白色の大きな花が咲き始めました。
モクレン科の常緑高木で、北米中南部原産です。日本では公園によく植えられています。

アメリカ合衆国南部を象徴する木とされていて、ミシシッピー州とルイジアナ州の州花に指定されています。

バイカウツギ
アジサイ科バイカウツギ属の落葉低木で、別名はサツマウツギ。名前の由来は梅に似た花を咲かせることから来ています。5月22日(水)に紹介した「ブラシノキ」の側に植栽されています。

シチダンカ
ユキノシタ科アジサイ属の落葉低木で、ヤマアジサイの一種です。

アオダイショウ
池の近くの生け垣にアオダイショウが現れました。毒はありませんが、個体によって性格が違うので、もし見つけたらそっとしておきましょう。

5月29日(水)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

タイサンボク
吉田茂像周辺に、白色の大きな花が咲き始めました。
モクレン科の常緑高木で、北米中南部原産です。日本では公園によく植えられています。

アメリカ合衆国南部を象徴する木とされていて、ミシシッピー州とルイジアナ州の州花に指定されています。

バイカウツギ
アジサイ科バイカウツギ属の落葉低木で、別名はサツマウツギ。名前の由来は梅に似た花を咲かせることから来ています。5月22日(水)に紹介した「ブラシノキ」の側に植栽されています。

シチダンカ
ユキノシタ科アジサイ属の落葉低木で、ヤマアジサイの一種です。

アオダイショウ
池の近くの生け垣にアオダイショウが現れました。毒はありませんが、個体によって性格が違うので、もし見つけたらそっとしておきましょう。

2013年05月24日北の丸公園の自然
皇居外苑バックナンバー2013 / 北の丸公園ブログ / 夏の花 / 春の花
本日も爽やかな晴天となりました。青々とした園内を吹き抜ける風が、心地よい気分にさせてくれます。
5月24日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤマボウシ
ミズキ科ミズキ属の落葉高木です。

名前の由来は中央の花穂を頭に、4枚の白い花びらは頭巾に見立てて、延暦寺の山法師になぞらえてつけられたそうです。

アザミ(ノアザミ)
世界には300種以上のアザミがあるそうです。そのうちの3分の1が日本にあります。葉の先端は刺(とげ)がありますのでご注意下さい。花期は5月~8月です。

アジサイ(セイヨウアジサイ)
アジサイ科アジサイ属の落葉低木です。少しずつブルーに色づいてきています。

場所により、同じ種類でも色が異なりますので、これから梅雨にかけて様々な色のアジサイを楽しむことができます。

5月24日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)

ヤマボウシ
ミズキ科ミズキ属の落葉高木です。

名前の由来は中央の花穂を頭に、4枚の白い花びらは頭巾に見立てて、延暦寺の山法師になぞらえてつけられたそうです。

アザミ(ノアザミ)
世界には300種以上のアザミがあるそうです。そのうちの3分の1が日本にあります。葉の先端は刺(とげ)がありますのでご注意下さい。花期は5月~8月です。

アジサイ(セイヨウアジサイ)
アジサイ科アジサイ属の落葉低木です。少しずつブルーに色づいてきています。

場所により、同じ種類でも色が異なりますので、これから梅雨にかけて様々な色のアジサイを楽しむことができます。

2012年08月24日北の丸公園の自然
皇居外苑バックナンバー2012 / 北の丸公園ブログ / 夏の花
2012年08月16日北の丸公園の自然
皇居外苑バックナンバー2012 / 北の丸公園ブログ / 夏の花
夏真っ盛りの公園、木陰が一服の清涼剤です。
(*画像をクリックすると拡大します)


サルスベリの花が見頃となってきました。
中国南部生まれの落葉高木。
名前の由来はサルが滑りそうなくらい木肌が
すべすべしているところから。
花期が長いことから漢字で「百日紅」とも書かれる。

隣には赤色の花を咲かせている木もあります。


タマアジサイが咲き出しました。
他のアジサイより遅咲きで7月~9月頃に咲きます。
名前は蕾が玉のような形をしていることに由来しています。


カンガレイという珍しい水性植物が小穂をつけています。
池や沼などの湿地に生える多年草。
7~9月頃に先の尖った楕円形の小さな穂をつけます、
茶褐色になります。
名前は冬になっても枯れた茎が残っているという意味でつけられたようです。

(*画像をクリックすると拡大します)


サルスベリの花が見頃となってきました。
中国南部生まれの落葉高木。
名前の由来はサルが滑りそうなくらい木肌が
すべすべしているところから。
花期が長いことから漢字で「百日紅」とも書かれる。

隣には赤色の花を咲かせている木もあります。


タマアジサイが咲き出しました。
他のアジサイより遅咲きで7月~9月頃に咲きます。
名前は蕾が玉のような形をしていることに由来しています。


カンガレイという珍しい水性植物が小穂をつけています。
池や沼などの湿地に生える多年草。
7~9月頃に先の尖った楕円形の小さな穂をつけます、
茶褐色になります。
名前は冬になっても枯れた茎が残っているという意味でつけられたようです。












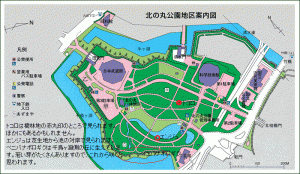











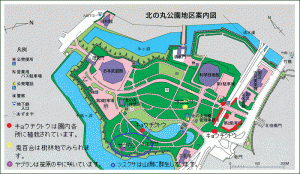
6月7日(金)の北の丸公園自然情報をお届けします。
(※画像をクリックすると拡大します。)
ナツツバキ
別名シャラノキ(沙羅の木)といいます。
ツバキ科ナツツバキ属の落葉高木です。
朝に開花し、夕方には落花する一日花で、涼しげな装いの花です。吉田茂像の背面に植栽されているので、是非ご覧下さい。
ツユクサ
ツユクサ科ツユクサ属で、花期は梅雨頃です。別名、蛍草(ほたるぐさ)、帽子花(ぼうしばな)、青花(あおばな)、鴨跖草(おうせきそう)。日本全土で見られる、朝に咲き午後にはしぼんでしまう一日花です。
ムラサキシキブ
クマツヅラ科ムラサキシキブ属です。秋になると実が紫色になり、駄菓子のガム?のようになります。花言葉は、「愛され上手」、「上品」、「聡明」です。
モノサシトンボ
モノサシトンボ科モノサシトンボ属です。比較的おとなしく、近づいてもあまり逃げません。池や沼、日陰を好むトンボで、名前の通り腹部に目盛りのような模様があります。5月末頃から9月中旬頃まで見ることができます。
イチョウノキ(顔に見える幹)
ふと視線を感じて幹を見てみると・・・顔がありました!随分驚いているようですが、こちらの方が驚きました。