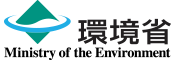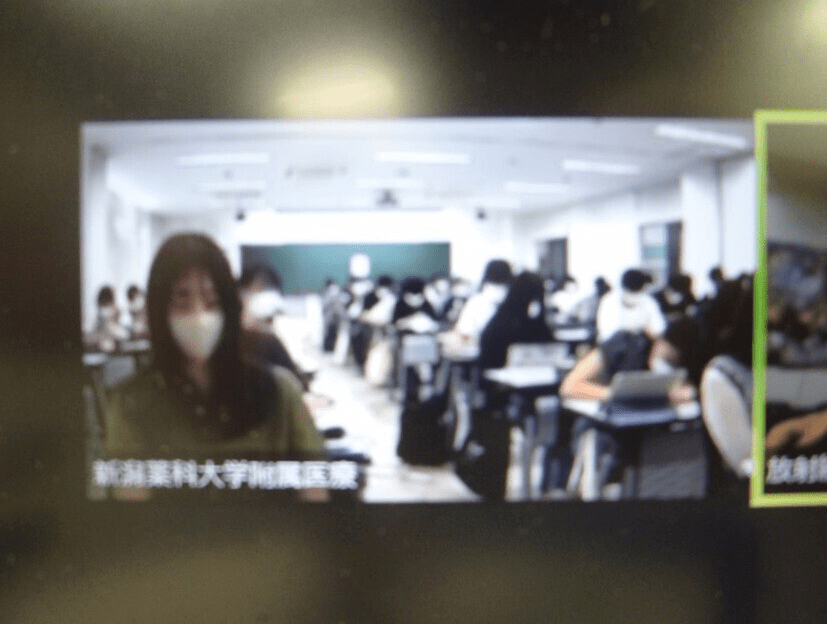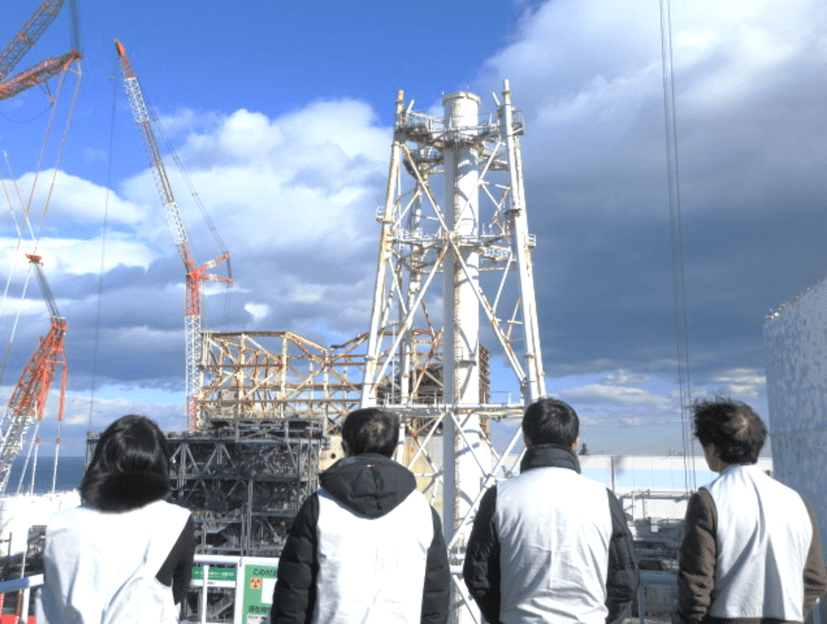放射線教育
支援内容
小学校
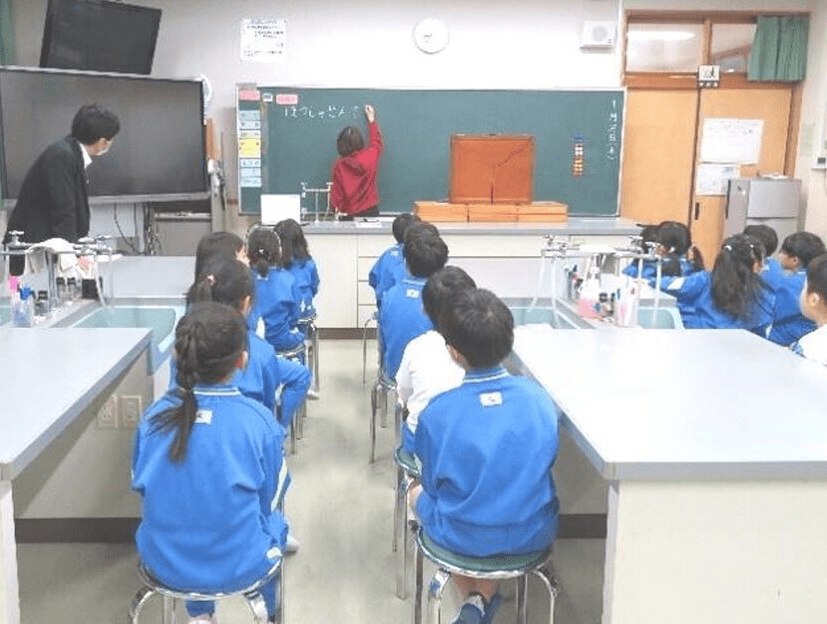

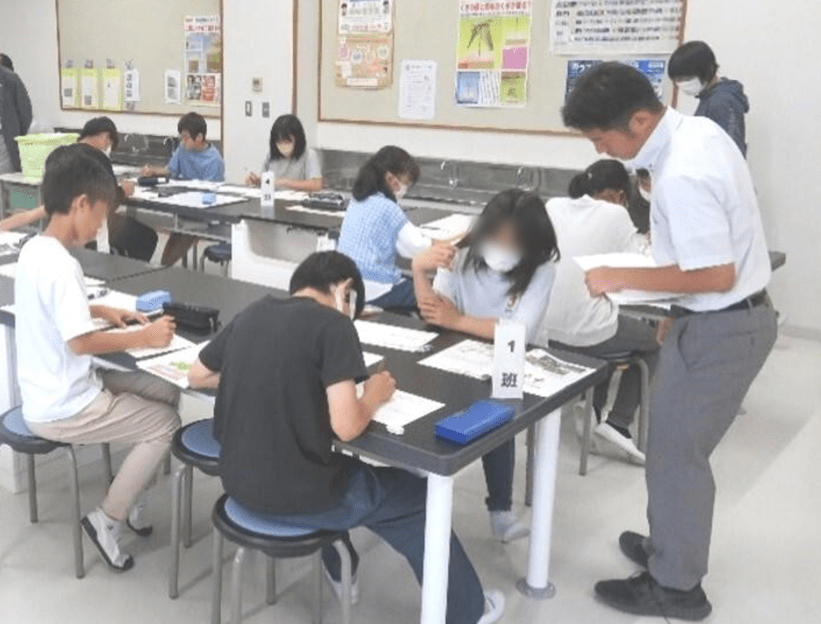
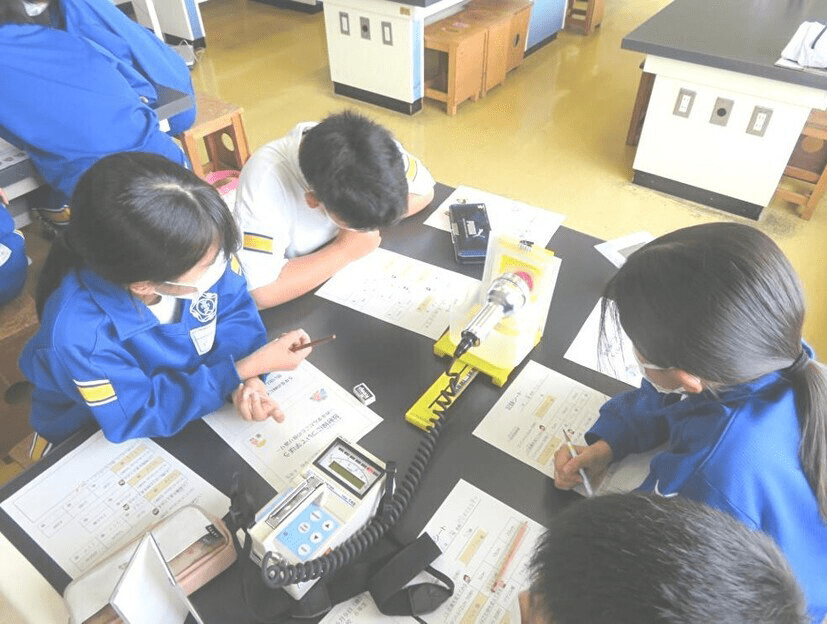

中学校

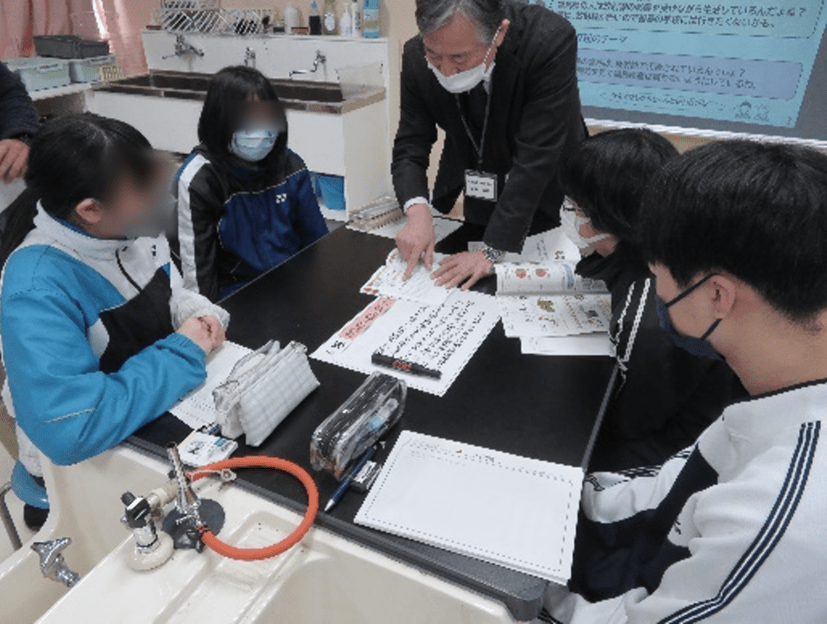
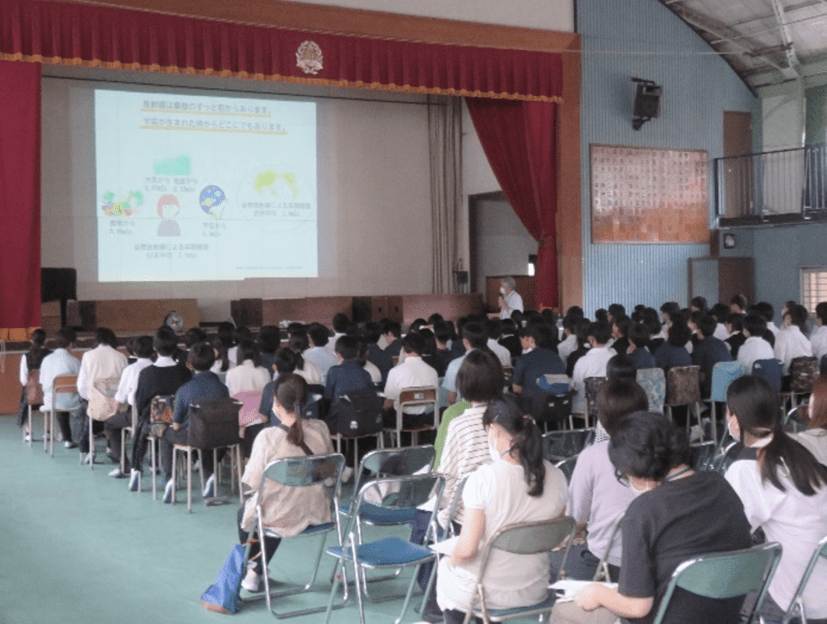
高校
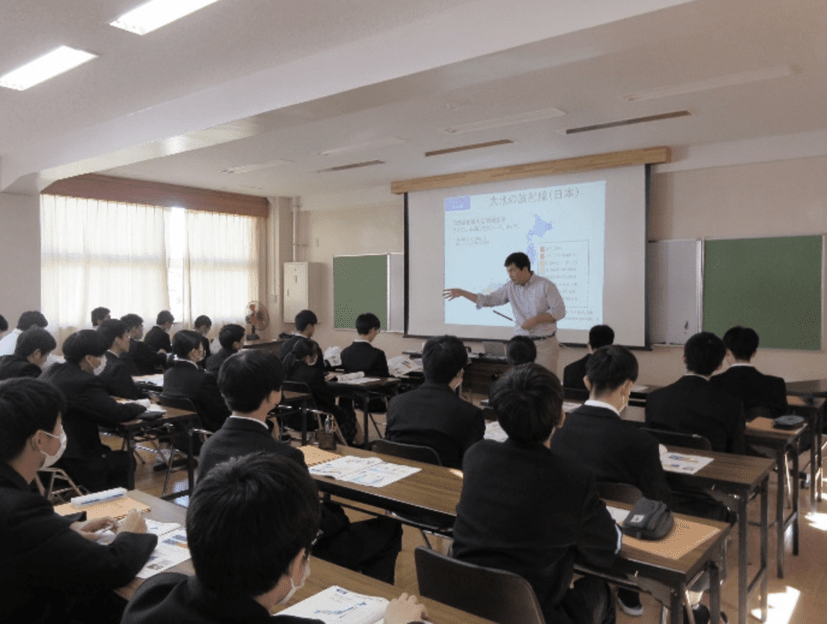
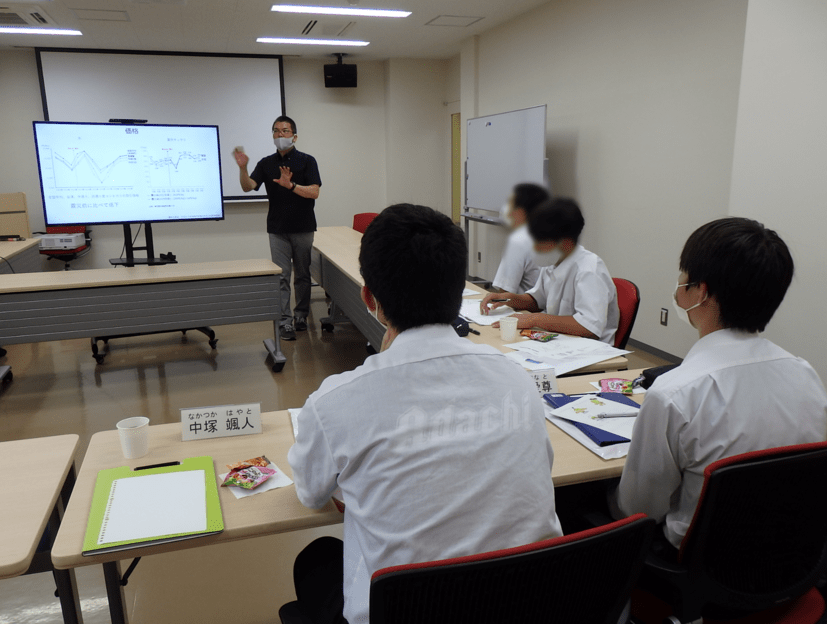
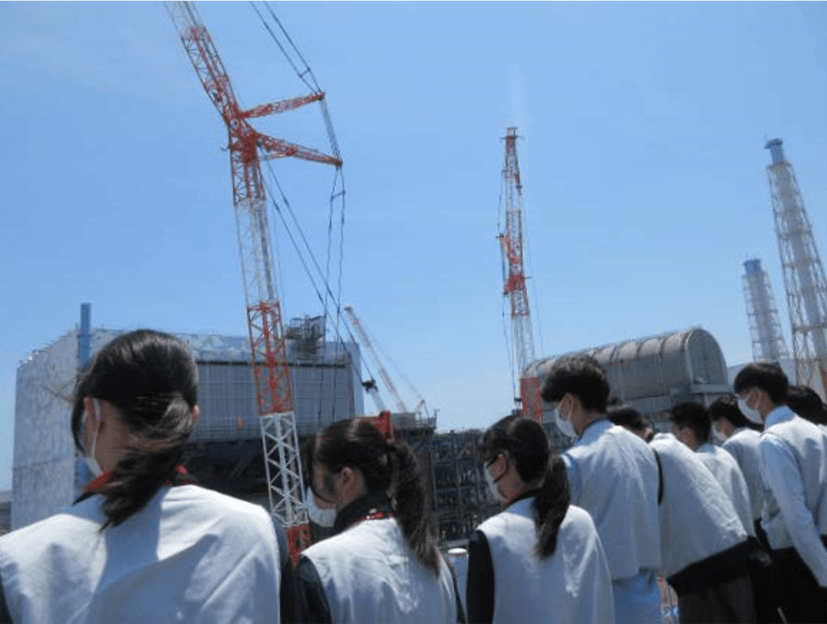

支援学校

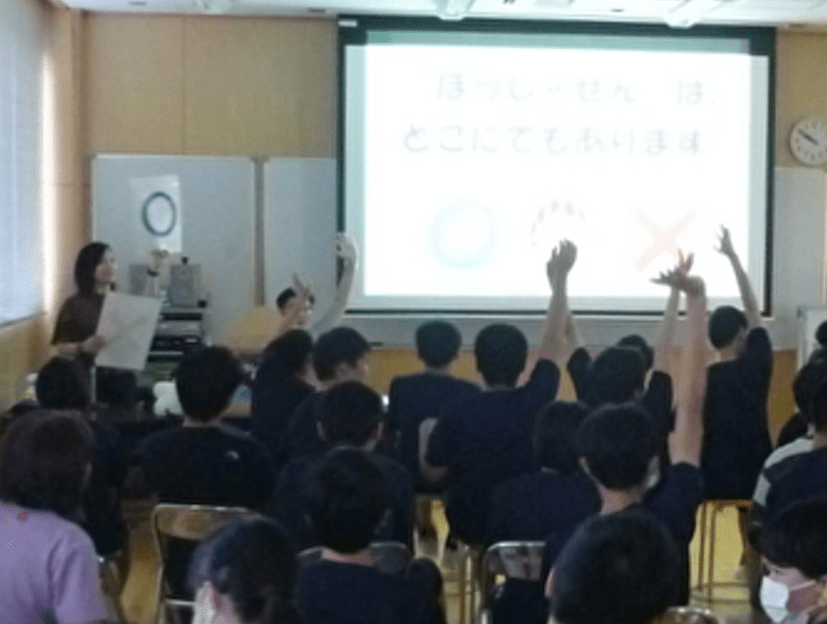
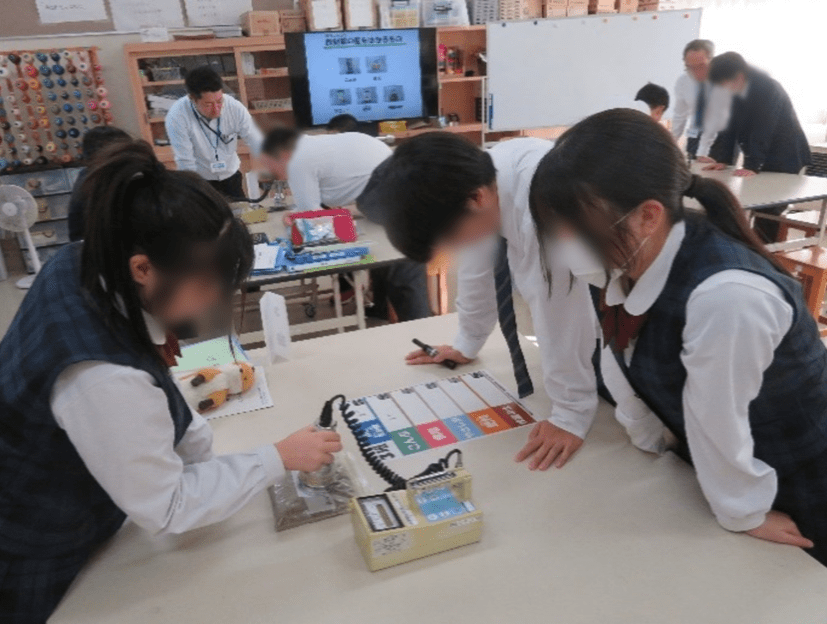
専門学校・大学
放射線教育 支援の流れ
-
対象者や授業内容、
時期等、
ご要望を
お知らせください -
ご要望に沿った
プログラムを、
ご提案します -
授業の準備や、
講師、会場等を
手配します -
授業のアンケート結果と
開催概要をまとめ、
ご報告します
支援に関する 以下の準備や手配等は弊センターにお任せください。支援に関する費用負担は一切ありません。
- 授業対象者や内容に適した講師の選定と、授業内容の打合せ
- 授業に必要な資料の作成と、資料の印刷
- 授業で使用する紙芝居や、放射線測定機器、霧箱等の手配
- 会場の状況に合わせたスクリーンや映写機等の手配
- 施設見学の段取りやバスの手配
※支援の内容により、準備や調整に、1ヶ月程のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。
ご連絡先
放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター
0120-478-100
フリーダイヤル
9:00~17:00(土日・祝日を除く)
F-sodan@nsra.or.jp
恐れ入ります。ウィルス、迷惑メール対策のためメールへのリンクは設定しておりません。お手数ですが、上記アドレスを半角で入力してください。コピーされる場合は@マークを半角にしてください。よろしくお願いいたします。
本ウェブサイトではGoogle アナリティクスを使用しています。
Google アナリティクスからの情報取得については、プライバシーポリシー追記事項をご覧ください。