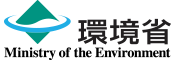放射線教育 専門学校・大学
訪問予定の事前学習
新潟薬科大学附属医療技術専門学校
▮令和5年6月18日(日) 13:00~14:00(オンライン開催)
受講希望者:看護学科2年生18名、保護者9名、教員7名 計34名
看護実習で福島県浜通り地域を訪問予定している、受講希望の学生とその保護者を対象に、放射線の基礎や健康影響等に関する講義を通して、放射線の正しい知識を身に着けることで、放射線や福島の現状に対する理解を深める。講義では、放射線の単位をはじめ、身近なものにも放射性物質が含まれていることや、放射線は人から人へはうつらないこと、第一原発の事故による健康影響は確認されてないことについて学んだ。併せて、日本や世界各国の空間線量率に触れながら放射線は身の回りにあること、量が大切であることについて理解を深めた。
▮令和5年9月4日(月) 14:00~15:00(オンライン開催)
看護学科2年生60名
放射線の正しい知識を身につけ、看護実習で訪れる福島への理解を深めたいとの要望により、今回は看護学部2年生全員を対象に、オンラインでの講義を行った。講義「福島での生活と放射線による影響」では、放射線の基礎知識や放射線は身の回りにあること、看護学科の学生が対象のため、医療分野での放射線被ばく線量等について学んだ。また、実習で福島へ訪問するにあたり、ホールボディ・カウンタ検査の概要や、福島県「県民健康調査」について理解を深めた。
-
6月18日のオンライン講義の様子
-
9月4日のオンライン受講の様子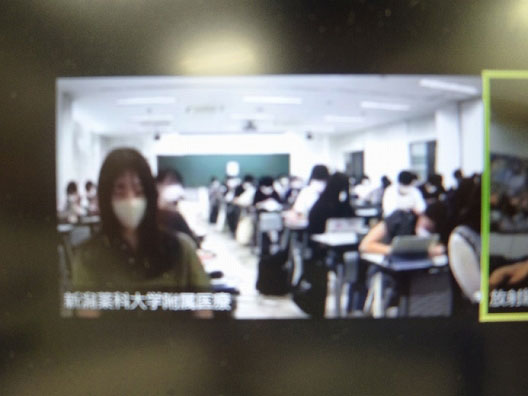
-
9月4日のオンライン講義の様子
施設見学
国際情報工科自動車大学校 学生8名
令和6年1月12日(金) 9:00~18:15
廃炉資料館、福島第一原子力発電所の見学を通じて、福島第一原子力発電所事故の概要や教訓、廃炉事業の全容等について理解を深めた。
福島第一原子力発電所では、原子炉建屋やALPS処理水の貯蔵タンク等の見学を通して廃炉の現状について理解を深めた。廃炉資料館では、展示等の見学を通じて事故当時の状況や廃炉に向けた取り組み等について学んだ。その後、印象に残ったことの発表や福島第一原子力発電所の取り組み等に関する質疑応答を行った。
-
福島第一原発見学の様子
-
福島第一原発見学の様子
-
廃炉資料館見学の様子
国際情報工科自動車大学校 1年生4名、2年生5名 計9名
令和5年1月20日(金) 8:00~18:30
中間貯蔵工事情報センター及び中間貯蔵施設では、施設の見学を通じて中間貯蔵工事を中心とする福島の環境再生に向けた取組や工事の進捗状況等について学んだ。福島第二原子力発電所の見学では、震災当時の状況とその後の対応、廃止措置計画の概要等について学んだ。その後、見学を通して印象に残ったことや新しい発見等について意見交換を行うとともに、放射線や福島第二原子力発電所の取組等に関する質疑応答を行った。
-
福島第二原発見学の様子
-
中間貯蔵施設見学の様子
-
意見交換の様子
講義
会津大学短期大学部食物栄養学科 2年生29名
令和5年12月22日(金) 10:10~11:40
栄養士やフードスペシャリスト等、食のエキスパートを目指す学生が、放射線について正しい知識を身に付け、将来においても生かすことができるよう学習した。福島県立医科大学の講師による講義「放射線の基礎と健康影響」では、福島の原子力災害や放射線による健康影響について、現在の除染状況、福島の食に関する取組等を学んだ。次に、農業・食品産業技術総合研究機構の講師による講義「食品中に含まれる放射性セシウムについて」では、調理過程における食品の放射能の低減について、また国内流通食品に対する流通前の対策と現状等を学んだ。
-
講義の様子
-
講義の様子
福島大学1年生(むらの大学受講生)と学内の希望者 計68名
令和4年10月14日(金) 16:20~17:50
講演「科学的知見の信頼性~楽しく触れる学術論文~」では、どんな情報源であっても(科学論文であっても)多角的に物事を捉え、内容を見極めることの必要性について理解を深めた。講演「デマやフェイクニュースは何をもたらすのか~原発から23㎞での医療支援現場で起こっていること~」では、福島第一原子力発電所事故から11年経過して分かってきたこととして、放射線による健康影響よりも、無理な避難や避難生活により健康状態が悪化した人が多かったこと等について紹介し、問題の大元だけでなく、その周辺で二次的に起きていることにも目を向ける必要があり、自分たちが普段接している情報は、全体のごく一側面でしかないことについて説明した。
-
講義の様子
-
講義の様子
放射線教育 支援の流れ
-
対象者や授業内容、
時期等、
ご要望を
お知らせください -
ご要望に沿った
プログラムを、
ご提案します -
授業の準備や、
講師、会場等を
手配します -
授業のアンケート結果と
開催概要をまとめ、
ご報告します
支援に関する 以下の準備や手配等は弊センターにお任せください。支援に関する費用負担は一切ありません。
- 授業対象者や内容に適した講師の選定と、授業内容の打合せ
- 授業に必要な資料の作成と、資料の印刷
- 授業で使用する紙芝居や、放射線測定機器、霧箱等の手配
- 会場の状況に合わせたスクリーンや映写機等の手配
- 施設見学の段取りやバスの手配
※支援の内容により、準備や調整に、1ヶ月程のお時間をいただきます。余裕をもってお問い合わせください。
ご連絡先
放射線リスクコミュニケーション相談員支援センター
0120-478-100
フリーダイヤル
9:00~17:00(土日・祝日を除く)
F-sodan@nsra.or.jp
恐れ入ります。ウィルス、迷惑メール対策のためメールへのリンクは設定しておりません。お手数ですが、上記アドレスを半角で入力してください。コピーされる場合は@マークを半角にしてください。よろしくお願いいたします。
本ウェブサイトではGoogle アナリティクスを使用しています。
Google アナリティクスからの情報取得については、プライバシーポリシー追記事項をご覧ください。