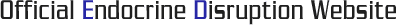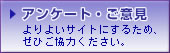対談・コラム
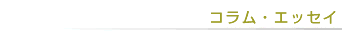
4. 世紀末現象
- 小出
- このころ、まさに雨後のたけのこのごとく、電磁波、化学物質などのリスクを大きく取り上げた、いわゆる恐怖本がいっぱい出るわけですね。
- 安井
- ええ、私の認識では、恐怖本のこの中で社会的な効果が最も大きかったのが、ジャーナリスト、立花隆さんの書いた「環境ホルモン入門」です。これは立花さんらしいセンセーショナリズムを含んだ本で、しかも東大の立花ゼミで学生に調べさせてつくった本なんですが、これがインパクトがあった。優れたジャーナリストの代表である立花さんが言ってるんだから、きっとうそじゃなかろう、みたいな受け止められ方をしていました。
- 小出
- そうですね。特に学生、研究者、その周辺の理解力のある人たちに、より大きなインパクトがあった。
- 安井
- ええ、そのような気がしますね。
- 留意しなければならないことは、科学には「無罪」を立証することが極めて困難だ、という性格があることです。この物質には健康リスクがあるかもしれない、という指摘があったとします。リスクがあるという疑いはあるけれども、本当は因果関係がまったくない――という例もある。ところが、これを確かめることは難しい、大量の実験を繰り返し、追試し、あいている穴を全部塞がなければならない、時には、それが不可能なケースも多いのです。
- このとき、因果関係を冷静に評価しなければならないのですが、「安全が立証されていないものはみんな黒だ」と声高に言われてしまうと、科学者はこれをひっくり返すことがとても難しい、時間を必要とする、ということです。環境ホルモン騒動は、学術のフィールドに近い文献で、そこを巧みに突かれたようなところがあった。これは、防衛のしようがないですね。
- 小出
- 逆に言えば、サイエンス・リテラシーというか、本来、科学者がちゃんと伝えなければいけなかった作業をサボっていた、その間隙を突かれたような面もあったのではないですか?
- 安井
- サイエンスはそれまでサボっていたわけではないと思います。ただ全く新しい毒性の指摘であったということが問題なのであって、新しいという意味ではデータの積み上げがない。従って、否定する材料がないという状況で、いろんな仮説を立てられてしまうと、すぐにはどれも否定できない。という状況のなかで、とうとう立花さんに、子供がキレル原因まで環境ホルモンのせいにされてしまった……。
- 小出
- われわれも読んでインパクトを受けたのは、『中央公論』98年の4月号に掲載された、立花隆さんと、日本テレビのプロデューサー、笹尾敬子さんの対談でした。「環境ホルモンは人類を滅ぼす」という記事の中で、これらの化学物質の中には、動物実験で神経系の発育が遅れたり、行動機能の障害が観察された物質があった、という報告を基に、「現代の少年に多発するキレル現象、その結果発生する事件の原因が環境ホルモンである」という指摘をされています。
- 安井
- そういうことで、結局いかなる仮説が出ても、誰も反論できない状況という状況の下にあったのが、この98年でした。
- 小出
- そこまで広がった背景には、合成化学、化学工業に対しての何となく潜在的な不安感、不信感があったと思います。こうした不安感に訴えるように、週刊誌の見出しはエスカレートしてゆきます。見出しの例を拾ってみますと、98年4月25日の『週刊現代』は「虫歯の詰め物に“猛毒”環境ホルモンが使われている」。ここで「猛毒」という言葉が出ています。それから、『フライデー』の4月24日号では、「環境ホルモン汚染の恐怖」。続いて「忍び寄る環境ホルモンの恐怖 精子激減」(週刊読売5月3日号)、「見えない猛毒 環境ホルモン汚染の恐怖」(女性自身5月5日)、「いわく史上最悪の猛毒、人類絶滅の危機」(週刊文春5月28日号)……。
- 安井
- これを書いた記者が今、どう感じているのか聞いてみたいですね。(笑)
- 今おっしゃったようなある意味の化学工業に対する不安と同時に、ダイオキシン全体へのリスク感があって、その当時、もう1つ世紀末恐怖現象というのがあったのです。98年は、ノストラダムスの1999年人類滅亡予言、そして2000年のコンピューター・クライシスに向かって、何となく世の中が浮き足立っていた時期でもあるのです。最後に何かが起きる、コンピューター社会が壊滅する、という、そういう予言めいた恐怖本が大量に出版された年でもありました。
- 小出
- そうですね。確かに世紀末はそういう世相でした。
- 安井
- 例えばこの時期の私のホームページの記述などを見ると、98年の12月には、今はもうない『サイアス』という雑誌が「世紀末人類絶滅の道」なんていう企画を掲載していますが、こうした記事を書くのがはやる時代だったのですね、このころは。
- 小出
- 待ち構えていたマスコミに、すごく良い素材を提供してしまった。(笑)
- 安井
- そこに実に手ごろな恐怖話を提供してしまったというところでしょう。振り返ってみれば、この時期はかなり特殊だったのですね。例えば、遺伝子組み換え作物をめぐる混乱なども、この時期に盛り上がりを示していて、この時世を反映しているような気がします。
- 結局、ダイオキシン騒ぎというものが収まるきっかけとなったのは、日垣隆さんが『文藝春秋』98年の10月号に書いた「ダイオキシン猛毒説の虚構」という記事でした。これは、ダイオキシン騒ぎが終息に向かう、最初のターニングポイントだったと思います。この後、世の中のさまざまな混乱が終息に向かったような気がします。
- 小出
- この年の12月に、環境省主催の最初の環境ホルモン国際シンポジウム(内分泌攪乱化学物質問に関する国際シンポジウム)会議が京都国際会館で開催され、そこである程度この問題の全容のようなもの、相場観が得られた印象があります。もちろん「ごく微量でも生殖機能に悪影響を与える」という意見、指摘もありました。でも、危ないといってもどの程度のものなのか、少し冷静に見る機会が出てきようですね?
- 安井
- そうですね。データベースをみると、私も98年10月に、「多少落ち着きを見せてきた環境ホルモン問題」なんていう記事を書いています。このころから環境ホルモン問題も、新聞記事への出現頻度が下がってきています。
- 小出
- 大手5紙の関連記事の合計数を見ると、この年の10月、11月には、5-6月ころの半分以下に落ちていますね。毎月800件ぐらいあった記事が400以下になっている。12月に増えているのは、環境省の環境ホルモン国際シンポジウムがあって、そのために記述が増えているわけですが、それを除けばその後はずっと下がって行きました。
- 安井
- 社会全体の恐怖のごとき恐怖報道は、その辺で一応収束していったのでしょう。そのあとは、問題が専門家、研究者らプロの話題に徐々に切り替わって行くことになった。その流れ、理解が、現在の評価につながってきています。
つづく