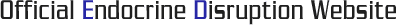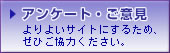対談・コラム
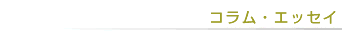
コラム・エッセイ
「“環境ホルモン騒動”を検証する Part 1」

2. 事実と乖離してゆくメディア
- 小出
- 当時の報道の推移を追ってみます。
- 問題になった環境ホルモンと呼ばれた物質の最初の正確な事実認識は「環境ホルモンの疑いがある物質」だったはずでした。討論のきっかけとなったのは、「世界自然保護基金(WWF)」がこしらえた化学物質のリストです。WWFは、環境ホルモンの疑いのある物質のリストをつくり、公表していました。そのリストの中に含まれていたのは、ノニルフェノール、ビスフェノールA、PCBなど、67種類の化合物でしたが、その評価はあくまでも「疑いがある物質」でした。ところが、この「内分泌かく乱の疑いがある物質」がメディアの中で、いつの間にか「内分泌かく乱作用のある物質」という表現に置き換わってくる。新聞の見出しでもそのような形に移っていった。こうしてメディアの伝える事実と、実際の現場、環境化学の事実との乖離が始まったのです。さらに「完全に環境ホルモンである」と断定したような形で記事が書かれてゆきました。今、振り返って当時の記事を見直してみると、明らかに「行き過ぎ」の表現、誤った記事が、各新聞に見られます。
- 安井
- 確かに、そうだと思います。環境省が環境ホルモン・ダイオキシン対策の一環として98年末に急きょスタートさせた「SPEED '98」、これをあまり批判すると怒られちゃうのかもしれないけど、「SPEED '98」に盛り込まれたリストは本来「可能性のある物質のリスト」だった。けれどもメディアは、国が提示したリストにあるものを「環境ホルモン」と呼びならわすという、すり替えを行ってしまった。だから、あくまで可能性のある物質でありながら、リストに載ったら犯罪人みたいな運命にね(笑)。それが現在のメディアをめぐる、ある種の社会的メカニズムなんです。ですから科学の側も、それをわきまえて、もう少しまじめにメディア対策を考えなければいけなかったのかもしれないですね。
- 小出
- 科学的解明には、まず候補物質のリストをつくることが大変重要です。科学者はそこからスタートしたのですが、これが誤解と騒動の手がかりにもなってしまった……
- 安井
- そうだと思います。ただ、書く側(メディア)は、そこに載っている物質を環境ホルモンと呼びならわしても、それほどの違和感はない、と受け止めてしまう。読者や社会はそのあたりの事情を知らないから、メディアの表現を信じるというか、多少踊った表現でも、その言葉どおり受け止めてしまった、という状況があったのだと思います。
- 小出
- 同時に、消費者の受け止め方も、メディアの「事実」から、さらにずれて行きました。典型的な例として「カップ麺問題」というのがありました。これは、カップ麺のポリスチレンの容器に関して、発ガン性が疑われるスチレンモノマーが溶け出す――環境団体の「日本子孫基金」が98年2月、こう指摘したことから始まったものです。また、国立医薬品食品衛生研究所も、環境ホルモンと疑われるスチレンダイマー、スチレントリマーが、有機溶媒を使うとカップ麺容器から溶け出すと指摘しました。ところがこれに対抗して、カップ麺メーカーの団体である「日本即席食品工業協会」が、「カップ麺の容器は、環境ホルモンなど出しません」という全面広告を98年5月15日の全国紙朝刊に掲載して、話題になったのです。
- しかし、国立医薬品食品衛生研究所の追跡調査で、通常の麺を食べる状態でも、スチレントリマーが溶出することを確認。世論は一斉にカップ麺離れに傾いたのです。
- このとき、スチレンダイマー・スチレントリマーは「疑いのある物質」だったはずなんですけれども、メディアでの扱われ方は、完全に「犯人」扱いでした。
- 他の例にはビスフェノールAがあります。当時「日本子孫基金」は、横浜国大に依頼したほ乳瓶の検査で、ビスフェノールAが溶け出すという結果が得られたことを報告しました。こうしたことがきっかけとなって、さまざまなポリマー、特に塩素を含む高分子化合物について、いろいろと健康影響への疑惑が出た。そのころ私たちが見ていて疑問を感じたことは、健康リスクをどう受け止めるか、その物差しがおかしいなと、ということでした。
- ポリカーボネートの容器からビスフェノールAが出るとわかったため、各地の小・中学校の給食容器に異変が起きました。ポリカーボネートの食器が、ほかの容器に置き換えられ始めたのです。全国各地の病院や老人ホームでも、ポリカーボネート容器を外して陶器やガラスの器に置き換えられました。これは適切な判断だったのでしょうか。リスクとベネフィットを考えてみると、高齢者が環境ホルモンを摂取して、その先どの程度の影響があるのか。必ずしもその影響は大きいとは考えられない。一方で、ガラスや陶器の容器を使えば、落として割ったりすれば、けがをするリスクが出てくる。どちらのリスクが大きいのか、もう少し冷静な判断があっても良いと感じました。
- 安井
- 今のカップ麺の例などがそうですけれども、このころになると雑誌メディアがこの騒動に参画してきました。例えば『週刊宝石』、『週刊文春』など、さまざまな週刊誌がカップ麺と環境ホルモンの記事を大量に書き始めた。週刊誌が悪いとは申しませんが、やはり普通の新聞報道よりもよりセンセーショナルな伝えられ方をする、これがさらにテレビ番組に拡大する、というように、多種多様なメディアがこの問題を取り上げていったという経緯があって、社会、世相への拡大効果が生まれたと思います。