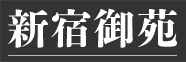菊花壇展
★菊花壇の歴史
日本に園芸品種の菊が渡来したのは、奈良時代末から平安時代はじめといわれています。その後、室町、江戸時代と発達をとげ、明治元(1868)年に菊が皇室の紋章に定められました。
明治11(1878)年、宮内省は皇室を中心として菊を鑑賞する初めての『菊花拝観』を赤坂の仮皇居で催しました。展示用の菊は、当初は赤坂離宮内で栽培されていましたが、明治37(1904)年より新宿御苑でも菊の栽培が始まりました。そして昭和4(1929)年からは、観菊会の会場も新宿御苑となり、戦後昭和24(1949)年、新宿御苑が国民公園として開放されたことを機に、菊花壇も一般公開されるようになりました。
大正から昭和にかけては、観菊会の展示の規模、技術、デザインなどがもっとも充実した時期で、これらによって新宿御苑はパレスガーデンとして、広く海外に知られるようになりました。
★展示鉢の命名方法
展示鉢には、菊の品種名が付けられています。新宿御苑では、主に古今和歌集に由来した命名台帳があり、その中から主として名付けられています。
*露地花壇、懸崖菊花壇、伊勢菊・嵯峨菊・丁子菊花壇、肥後菊花壇には名札はありません。
★鑑賞のポイント
日本庭園内に、モミジとの調和が最も美しい位置に上家(花壇)が配置されており、晩秋の日本庭園を回遊しながら全体の雰囲気を楽しむ、皇室ゆかりの展示方法です。(近年は、温暖化で紅葉の時期が遅くなる傾向があり、菊花壇展開催中は、まだ紅葉の見頃には至っていません。)いずれの花壇も、順路に従って歩くと最も美しく見えるように配置されています。

懸崖作り花壇(けんがいづくりかだん)
野菊が断崖の岩間から垂れ下がって咲いている姿を模しています。一般の花壇展では花持ちの良い八重咲きの品種を使う場合が多いのですが、新宿御苑では、清楚な一重咲きの小菊を使用し、1本の菊から分枝させてあまり整形せず、自然体に飾り付けます。なお、上家は竹とよしずで作る竹木軸上家で、上家の前には水の流れが引かれています。


伊勢菊、丁子菊、嵯峨菊花壇(いせぎく、ちょうじぎく、さがぎくかだん)
地域独特の発展を遂げた菊の品種をまとめて「古典菊」と称しますが、そのうち3種の菊を同時に見ることができる花壇です。伊勢菊は花びらが垂れ下がって咲く品種で、座敷に座して鑑賞したときに美しく見えるようにと伊勢地方で発達した菊です。丁子菊は花の中心部が盛り上がって咲く菊で、その花容はアネモネ咲きとも呼ばれています。嵯峨菊は花びらがまっすぐ上がって咲く菊で、寺社の回廊から立って見下ろしたときに美しく見えるようにと京都の嵯峨地方で発達した菊です。上家は、木材を組み立てて作る木軸上家で、越屋根造りです。




大作り花壇(おおづくりかだん)
新宿御苑の大作りは、全国で見られる千輪作りの先駆けとなったものです。注目いただきたいのは地際の茎の部分。接ぎ木はせず、前年の冬から1年以上かけて枝数を増やし、1株から500輪前後の花を咲かせています。栽培には非常に高度な技術が必要で、菊花壇の中の白眉とも云われています。上家は、木材を組み立てて作る木軸上家で、ひときわ目を引く大きな花壇です。


江戸菊花壇(えどぎくかだん)
江戸菊は江戸(東京)で発達した古典菊で、満開後の花弁の変化を楽しむ品種です。開花後の花形の変化は品種によって異なり、様々に変化する花びらと色彩が魅力です。上家は木材を組み立てて作る木軸上家で、展示中に開花が進むように太陽光のよく当たる南向きに設置されています。


一文字菊、管物菊花壇(いちもんじぎく、くだものぎくかだん)
一文字菊は花びらの数が16枚前後の一重咲きの大輪菊です。花の形が天皇家の御紋章に似ているので、別名「御紋章菊」と呼ばれています。管物菊は筒状に伸びた花びらが放射状に咲く大輪菊で、別名「糸菊」・「細菊」とも呼ばれています。上家は、木材を組み立てて作る木軸上家で、越屋根造りです。



肥後菊花壇(ひごぎくかだん)
肥後菊は一重咲きの古典菊で、熊本地方で発達しました。 武士の精神修養の一環として発達した一重咲きの古典菊で、花びらと花びらの間に隙間があるのが特徴です。上家は竹とよしずで作る竹木軸上家で、一番小さな花壇ではあるものの、黒土に敷かれた苔など、細部にこだわりが見られます。


大菊花壇(おおぎくかだん)
大菊は菊の代表的な品種ですが、新宿御苑では、神馬の手綱模様に見立てた「手綱植え」と呼ばれる独自の様式で展示しています。39品種311株の大菊を、黄・白・紅の順に植え、全体の花が揃って咲く美しさを鑑賞する花壇です。
同じく「手綱植え」の花壇に「一文字菊・管物菊花壇」がありますが、こちらに比べ大菊花壇は屋根の形がシンプルです。これは花にボリュームがある大菊に合わせた上家が設計されているためで、上家は日本庭園の風景だけでなく、展示菊それぞれの花容にも調和するようデザインされていることが分かります。