Branchiostoma belcheri Gray
ナメクジウオ綱ナメクジウオ目ナメクジウオ科ナメクジウオ属
1.分類
ナメクジウオ類は1綱1科1目にまとめられており、日本には2属3種が生息しています。ナメクジウオ属の種類はナメクジウオだけです。もう一つのカタナメクジウオ属にはカタナメクジウオ、オナガナメクジウオの2種類がいます。
ナメクジウオ
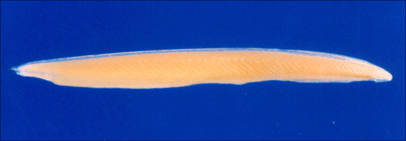
2.分布
日本では、房総半島から九州までの太平洋岸(瀬戸内海を含む)と丹後半島以南の日本海側に分布しており、日本以外では、インド洋や西太平洋の暖水域、東シナ海沿岸などに広く分布しています。潮間帯から水深約75mまでの浅海の荒い砂でできた海底にもぐって生息します。
日本では、愛知県蒲郡市大島と広島県三原市有竜島の2か所が、ナメクジウオ生息地として国の天然記念物に指定されています。しかし、それらの生息地を始めとして、かつてナメクジウオのたくさん見られた地方の環境が悪化していることから、現在では生息数が激減しており、潮間帯では見つけることができなくなってしまいました。
日本沿岸におけるナメクジウオの分布記録
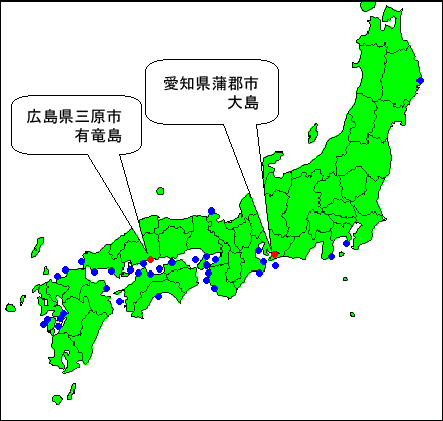
●印で示した場所は、ナメクジウオの生息場所として天然記念物に指定されている場所
3.形態
ナメクジウオは体全体が扁平で細長く、体の両端がとがっていて、柳の葉のような形をしています。体長は通常4~5cmです。表皮が無色透明で、脊索や神経管、内臓などが透けて見えます。体色は薄いピンク色です。
ナメクジウオには眼がありません。その代わりに、神経管のあちこちに光を感じる構造が散らばっています。
口は体前部の腹側にあり、触手によって常にふたをされた状態になっています。餌を食べるときには、この触手によって異物を取り除いています。咽頭は広く、その壁には鰓裂(さいれつ)とよばれる多数の穴がぎっしりと並んでいます。この構造は鰓嚢(さいのう)と呼ばれます。ナメクジウオは、鰓裂の縁に密生した繊毛で水流を起こし、植物プランクトンなどの小さな餌を水流によって取り込んでいます。余分な水は出水孔から外界に出されますが、餌は腸に取り込まれた後、肛門から排泄されます。
出水孔から肛門にかけて肛前鰭室(こうぜんきしつ)と呼ばれる直方体の構造が並んでおり、この数の違いは種類を分ける決め手になります。
ナメクジウオの内部形態
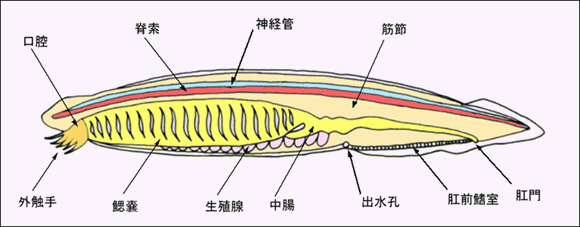
4.生殖と幼生の成長
ナメクジウオは雌雄異体で、体外受精を行います。ふ化した幼生は1.5~4か月の浮遊期間の後、砂底にもぐるようになります。適当な着底場所がない場合には、浮遊期間は延びます。着底後は、一時的に水中に泳ぎ出ることもありますが、砂底に浅くもぐって口だけを出す、といった定着的な生活を送ります。
5.人間との関係
中国福建省廈門(あもい)では、生のナメクジウオを水洗いして塩分を落とした後、鶏肉や牛肉、卵と炒めて食べたり、油で煎って食べたりします。しかし、かつて食用として大量に漁獲されていた廈門でも、近年乱獲や干拓、水質汚濁のために激減しています。
日本ではナメクジウオを食べることはありませんが、実験材料として利用しています。現在では、環境悪化によりナメクジウオが激減しているため、研究者たちは中国産のナメクジウオを使って実験をしています。 ナメクジウオがすめるような清浄な海辺を取り戻すことは非常に重要であると考えられます。
【参考文献】
- 西川輝昭:頭索動物(ナメクジウオ類).日高敏隆監修,日本動物大百科-7.無脊椎動物,平凡社,東京,190(1997).
- 西川輝昭:ホヤ・ナメクジウオ類.奥谷喬司編著,山渓フィールドブックス[8].海辺の生き物,株式会社山と渓谷社,東京,330(1994).
- 西川輝昭:1.ナメクジウオ.社団法人日本水産資源保護協会発行,日本の希少な野生水生生物に関するデータブック(水産庁編).

