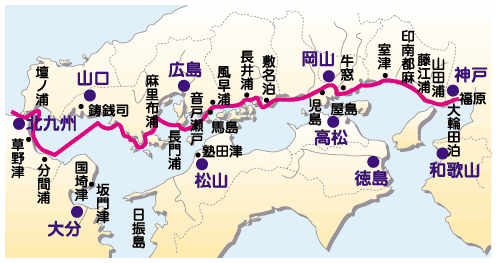
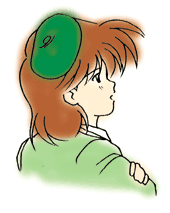
瀬戸内海地域は、昔から我が国の政治・経済・社会・文化のいろいろな分野にわたって、いつも先進的な歩みを進めてきました。 この大きな要因としては、大陸の中国などの文化が主として北九州から瀬戸内海を通って、大和(今の奈良)の方面へと伝えられてきたことが挙げられます。瀬戸内海地域は文化の大動脈として、絶えずこの橋渡しの役割を果たしてきました。
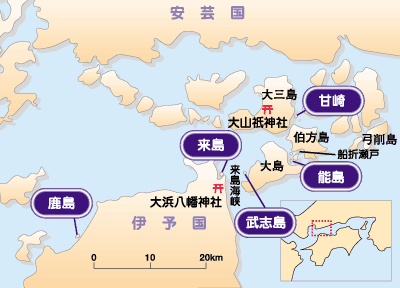
| B.C 6000年ごろ | ほぼ、現在の瀬戸内海の海域が形成される |
| 4000年ごろ | 縄文海進。現在より約3m高い所まで海だった |
| 3000年ごろ | ほぼ現在の海面の高さとなる |
| 300年ごろ | 弥生文化の時代が始まる |
| A.D 57年 | 倭の奴国の王が後漢に使者を派遣し、光武帝から印綬を受ける |
| 147年 | 倭国大乱。このころ、瀬戸内海の沿岸、島嶼部の山頂などに高地性集落が作られる |
| 188年 | 女王卑弥呼の邪馬台国が成立 |
| 290年ごろ | 古墳文化の時代始まる |
| 350年ごろ | 大和政権が成立する |
| 396年 | 日本が朝鮮出兵。高句麗の好太王軍に破られる |
| 538年 | 仏教伝来。百済の聖明王が仏像・経巻を我が国に献ずる |
| 607年 | 遣隋使の派遣始まる |
| 630年 | 遣唐使の派遣始まる |
| 645年 | 大化の改新 |
| 804年 | 遣唐使船で空海、最澄が唐へ |
| 867年 | 伊予の海賊、宮崎付近に集まって掠奪を行う |
| 894年 | 菅原道真が遣唐使の中止を建議 |
| 934年 | 海賊が瀬戸内海などに横行したため、朝廷が追捕海賊使を任命する |
| 935年 | 紀貫之の「土佐日記」が出来上がる |
| 939年 | 藤原純友が伊予国日振島を拠点に反乱を起こす |
| 940年 | 平将門の乱が終結 |
| 1152年 | 平清盛が安芸、厳島神社の社殿を修復 |
| 1167年 | 平清盛が太政大臣となる |
| 1168年 | 尾道が備後大田庄の倉敷地に認定される |
| 1172年 | 宋の明州刺史が後白河法皇・平清盛に物を献上。このころ清盛が大輪田泊の築港や音戸瀬戸の修理などして日宋貿易を振興 |
| 1185年 | 屋島の合戦。壇ノ浦の戦い、平家滅亡。河野通信、兵船を率いて源義経軍に加わる |
| 1192年 | 鎌倉幕府が成立 |
| 1281年 | 元寇-弘安の役。伊予の河野通有、博多へ出陣して奮戦 |
| 1308年 | 幕府、河野通有に西国と能野浦の海賊を追捕させる |
| 1324年 | 弓削島荘の住民、小山弁房承誉の非法を訴える |
| 1338年 | 足利尊氏、征夷大将軍になる。懐良親王、西国へ |
| 1371年 | 今川了俊が九州探題として現地赴任 |
| 1404年 | 足利義満、明との勘合貿易を開始 |
| 1434年 | 室町幕府、大島村上氏に遣明船の海上警固を命じる |
| 1450年 | 村上吉資の級官宮地氏ら、因島に金蓮寺を造営 |
| 1462年 | 能島村上氏が小早川一族の小泉氏らと弓削島荘を押領する |
| 1483年 | 室町幕府、大内氏に貿易の全権を委任する |
| 1489年 | このころ、今治的場の海賊が厳島神社から太刀・鎧を盗むが、河野氏が取り戻す |
| 1552年 | 陶氏、厳島での村上氏の関銭徴収権を停止させる |
| 1555年 | 厳島の戦い。毛利元就が村上水軍の来援を得て、陶晴賢を厳島で討つ |
| 1581年 | ルイス・フロイスが瀬戸内海を航行 |
| 1588年 | 豊臣秀吉、海賊禁止令を出す |
| 1592年 | 秀吉、朝鮮侵攻を始める |
| 1600年 | 関ヶ原の戦い |
| 1604年 | 村上武吉が周防大島で死去。藤堂高虎が今治城を築城 |
| 1607年 | 朝鮮通信使が初めて来日 |
| 1672年 | 河村瑞賢が西廻り航路を開く |
| 1762年 | このころから瀬戸内の塩田で石炭の使用が始まる |
| 1853年 | ペリー艦隊が浦賀に人港 |
| 1868年 | 明治維新 |
| 1886年 | このころ、石炭使用量の51%を塩田で占める |

