森・川・海はつながっている
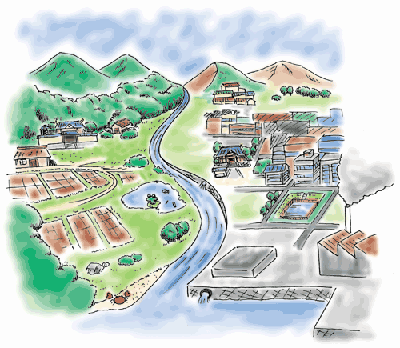
台所から出る油や食べ残しはどこに行くのでしょうか?
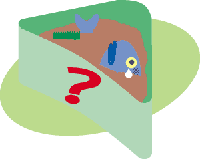
台所から出る油や食べ残し等の有機物は、下水処理施設などで処理され、川に流されます。そして川にすんでいるバクテリアに分解され、栄養分へと姿を変え、海へ流れて行きます。
この栄養分を使って、植物プランクトンや海藻は光合成をし、次の生きものの餌となります。それがまた次の生きものの餌となり、最終的には、私たちの食卓に戻って来る魚などに姿を変えます。中には鳥が餌として食べたり、太平洋へ行ったりする場合もあります。このように、物質はいろいろな生きものの中を変化しながら循環しています。
有機物の中には、海底に堆積し、長い時間をかけて地上に再び戻って来るものもあります。畑にまく肥料にはこのような形で地上へ帰って来た栄養分を利用している場合もあります。これもひとつの循環の形と言えるでしょう。
なぜこんなに多くの生きものが川や海にすんでいるのでしょうか?
瀬戸内海で確認された魚類は約430種です。魚類以外にも、鳥や貝、カニなど本当に多くの生きものが瀬戸内海にはすんでいます。
また、瀬戸内海をとりまく陸の森や川にも多くの生きものがすんでいます。なぜこのように多くの生きものが生きているのでしょうか。私たち人間も魚、鳥、虫なども同じ生きものです。おのおのの生きものは、それぞれが尊く、お互いがささえ合っています。すべての生きものには同じ命が与えられ、おのおのが大切な働きをしています。
いろいろな生きものが川や海にすんでいるおかげで栄養分などの物質はいろいろなところにいきわたります。多くの生きものがいるからこそ山は緑におおわれ、水はきれいになり畑の野菜は成長し、私たちも生きることができます。この循環がなくなったら、山は荒れて、海は汚れたままでしょう。
たとえ一種類の生きものでもいなくなっていいのでしょうか?
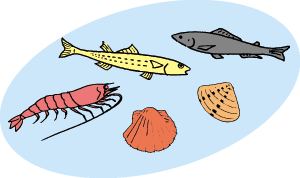
一種類の生物がいなくなっても、生きものの世界のバランスがくずれるかもしれません。 多くの生きものは互いに影響し合いながら、ともに生きるための世界を作っています。しかし、私たち人間は、このような複雑なシステムをまだ良く理解していません。ましてや10種、20種がいなくなるとどうなるか、予想はつきません。
私たちの都合だけで、他の生きもの(種)の命をうばうことは許されないことです。私たちが今できることは、すべての生きものを大切にし次の世代に伝えて行くことではないでしょうか。
なぜこのように多様な場が世の中にあるのでしょうか?
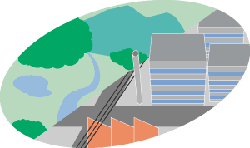
海や川には実にいろいろな場があります。流れがゆるい場所、速い場所、草が生えている場所、砂利だけがある場所、浅い場所、深い場所など、いろいろな場所が思い浮かぶことでしょう。
このように多くの場所をよく見ると、その場所に応じて異なる生きものが見られます。森にすむ生きもの、川にすむ生きもの、そして海にすむ生きものは違います。同じ森や川、海でも、場所によって生きている生きものは異なっています。
いろいろな生きものが生きていることが大切だと説明しましたが、生きものが生きるためには、いろいろな場所が必要になります。私たちの周りはあまりにもコンクリートやアスファルトで固められ、単調な場になっていないでしょうか。
海岸に流れついたごみはどうなるのでしょうか?

海岸に多くのごみが流れ着いています。有機物のごみは生きものが分解します。
しかし、ナイロン袋やビンなどのように生きものが分解しにくいものはどのようになるでしょうか。海へ沈むのでしょうか。鳥やウミガメが誤って食べてしまうこともあります。太平洋へ流れ出てオットセイなどにからまってしまうこともあります。
日本のごみが外国に流れ着いたり、海へ沈むこともあります。このように、いつまでも消えず、どこかに残っていることでしょう。
なぜ瀬戸内海で赤潮が発生するのでしょうか?
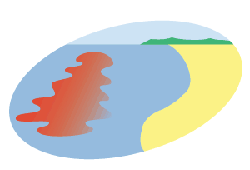
あまりにも多くの栄養分が海へ流れ込んで来ると、プランクトンが異常に発生します。これが赤潮です。
自然な海域にもこのような現象が見られます。しかし瀬戸内海に発生する赤潮の原因のひとつは、私たちの家庭から流れ出た排水が原因と考えられます。
赤潮が発生すると、海の生きものの多くが死にます。養殖していた魚が赤潮の影響で全滅したニュースがたまにテレビなどで報道されます。実際にはテレビに出てくる以上に赤潮が発生しています。
瀬戸内海での赤潮の発生状況についてはこちらから「赤潮の発生状況」のページへ

