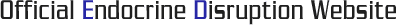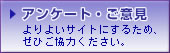「内分泌かく乱作用とは」
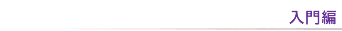
「入門編」
内分泌かく乱作用をもつ物質は複数あります。
まずは、女性ホルモンで、これは、まさに生体内で合成され、体内でホルモンとして働く物質ですから、当然、作用は強いといえます。例えば、ヒトの生体内で合成された女性ホルモンは、ヒトの内分泌系にとってはなくてはならないものです。しかし、これが、環境中に出て、他の生物の内分泌系に作用した場合、その生物にとっては不必要な外からの作用ですから、 "内分泌かく乱作用"となります。
女性ホルモンに似ていますが、医薬品として、ホルモン作用をもつよう合成された、合成女性ホルモンがあります。例えば、経口避妊薬や、更年期障害の治療薬、流産防止薬として使用されたDES(ジエチルスチルベストロール)などです。
また、植物エストロジェンは、一部の植物の中に含まれるホルモン様作用をもつ物質です。例えば、大豆の中に含まれるイソフラボノイド類などで、食べ物として、ヒトが摂りこむものです。
さらに、化学品の一部が、内分泌かく乱作用をもつ可能性があることが分かってきました。ただし、Q1の図に表現されているように、内分泌かく乱作用をもつ物質は、内分泌かく乱作用以外にも様々な作用を持っていることも多くあります。例えば、殺虫剤として用いられたDDT (1971年に使用禁止)、耐熱絶縁体として用いられたPCB(ポリ塩化ビフェニル:1972年に製造禁止)等は、すでに毒性が明らかな物質ですが、それに加えて、内分泌かく乱という作用も持つのではないかという可能性がでてきました。また、船底塗料(船底への貝付着防止のため)として用いられていた TBT(トリブチルスズ:1990年より禁止:化審法)により海にすむ他の巻貝類が影響を受けることが知られており、これは、"内分泌かく乱作用"によると推察されています。界面活性剤の原料(アルキルフェノール類)、プラスチック製品の原料樹脂(ビスフェノールA)などの一部も、弱いながら、野生生物(とくに水の中にすむ生き物)の内分泌系に影響を与えることが示唆されています。