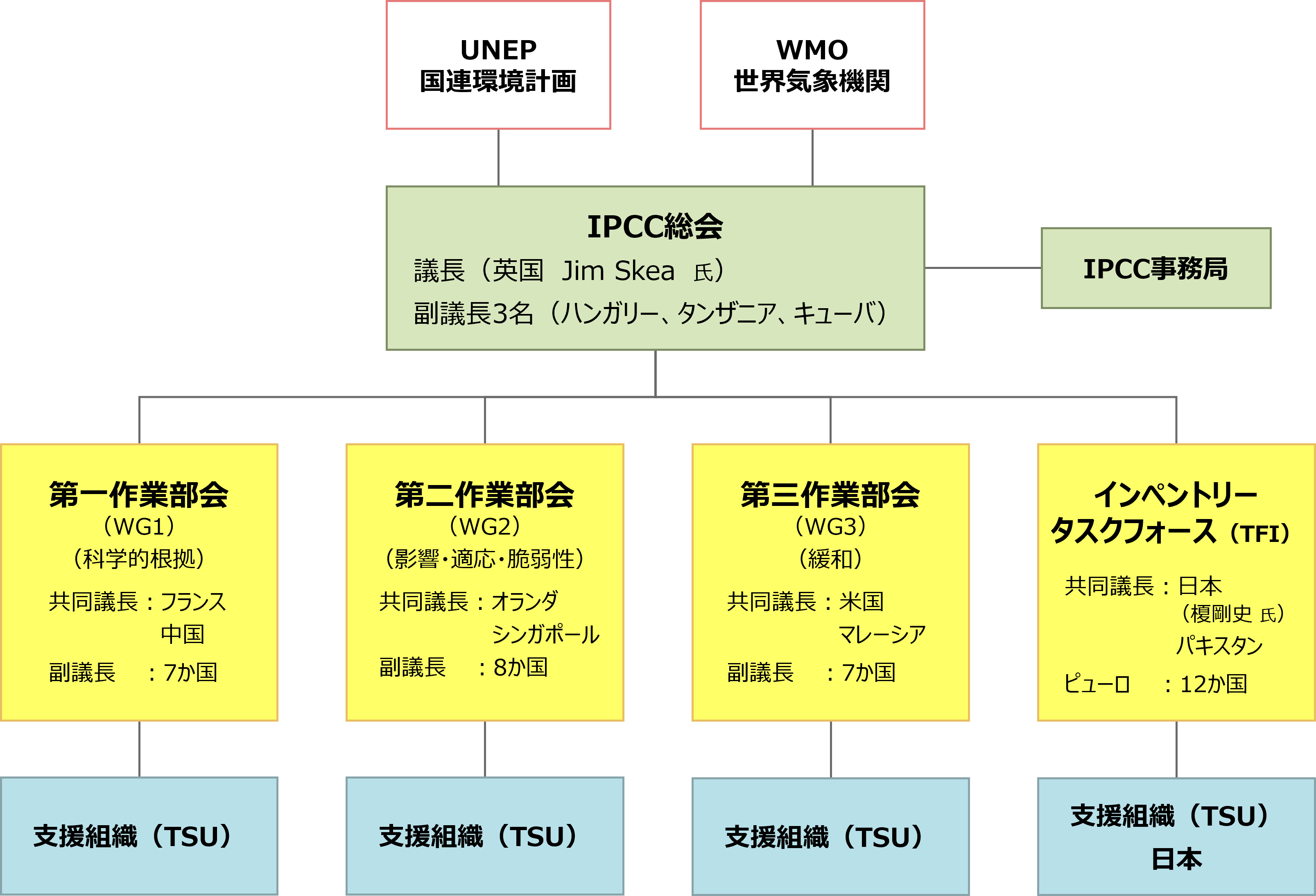地球環境・国際環境協力
気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第7次評価報告書(AR7)サイクル
第7次評価報告書(AR7)サイクルにおける各報告書
IPCC第59回総会(令和5年7月)において、IPCC第7次評価報告書(AR7)の作成プロセスでIPCCを率いるビューロー(議長団)メンバー等が選出され、AR7プロセスが開始されました。IPCC議長には Jim Skea氏(英国)、我が国からはインベントリータスクフォース(TFI)共同議長に榎剛史氏が就任しました。
AR7に関する情報について、当ページで順次公開していきます。
作業部会
IPCCは評価対象により分けられた3つの作業部会から構成されてます。
- 第1作業部会(WG1)- 自然科学的根拠
- 第2作業部会(WG2)- 影響・適応・脆弱性 (影響と適応に関する1994 年IPCC テクニカルガイドラインの改訂と更新を含む)
- 第3作業部会(WG3)- 気候変動の緩和
特別報告書等
現在、作成が決定されている特別報告書等は以下の通りです。
- 気候変動と都市に関する特別報告書
- [短寿命気候強制力因子(SLCF)インベントリに関する]2027年IPCC方法論報告書
- [国家温室効果ガスインベントリのための二酸化炭素除去(CDR)技術・炭素回収利用及び貯留(CCUS)に関する]2027年IPCC方法論報告書(追加ガイダンス)
報告書ごとの情報
評価報告書
■令和7年2月 IPCC第62回総会にてWG1・WG2・WG3のアウトラインが決定
アウトライン:Decision-8-Working-Group-Outlines.pdf (外部へのリンク)
■令和7年3月 主執筆者等の参加意向調査 ※令和7年3月28日に締め切りました
■令和7年12月 第1回WG1・WG2・WG3合同主執筆者会合(パリ・フランス)
『AR7 第1作業部会の報告 『気候変動 - 自然科学的根拠』』
『AR7 第2作業部会の報告 『気候変動 - 影響・適応・脆弱性』』
『AR7 第3作業部会の報告『気候変動 - 気候変動の緩和』』
『気候変動と都市に関する特別報告書』
■令和6年7月 IPCC第61回総会にてアウトラインが決定
アウトライン:Outline-of-Special-Report-on-Climate-Change-and-Cities.pdf (ipcc.ch)(外部へのリンク)
■令和6年9月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和6年9月1日に締め切りました
■令和7年3月 第1回主執筆者会合開催(大阪・日本)
■令和7年7月 第2回主執筆者会合開催(モンバサ・ナイロビ)
■令和7年10月~12月 First Order Draftの査読(専門家)
査読者登録:Review Comments (ipcc.ch)(外部へのリンク)(9月17日~11月30日)
短寿命気候強制力因子(SLCF)インベントリに関する『2027年IPCC方法論報告書』
■令和6年7月 IPCC第61回総会にてアウトラインが決定
アウトライン:Outline-of-Methodology-report-on-SLCF.pdf (ipcc.ch)(外部へのリンク)
■令和6年9月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和6年9月1日に締め切りました
■令和7年3月 第1回主執筆者会合開催(ビルバオ・スペイン)
■令和7年10月 第2回主執筆者会合開催(イスタンブール・トルコ)
国家温室効果ガスインベントリのための二酸化炭素除去(CDR)技術・炭素回収利用及び貯留(CCUS)に関する『2027年IPCC方法論報告書』(追加ガイダンス)
■令和7年10月 IPCC第63回総会にてアウトラインが決定
アウトライン:Decision-6-MR-CDR.pdf(外部へのリンク)
■令和7年11月 執筆者の推薦・IPCCによる選定 ※推薦者の公募は令和7年12月1日に締め切りました
環境省の取り組み
国際応用システム分析研究所(IIASA)と都市の変容に関する共同研究プロジェクトを令和5年9月に立ち上げました。
普及啓発:令和6年3月 国際シンポジウム「IPCC第7次評価サイクルへの日本の貢献と「気候変動と都市」に関するIIASAとの連携」を開催
令和7年3月 「日本-IIASA ジョイントセミナー in 横浜:日本の経験は、IPCC 気候変動と都市報告書にどのように貢献できるか?」を開催
AR7サイクルにおける体制
IPCC組織図
国内連絡会
IPCCの活動は、日本国政府にとって、気候変動に関する科学的知見の集積を行うという観点から、また、国連気候変動枠組条約の動向との関係性からも、非常に重要であると認識されています。
そこで、関係省庁では互いに連携・協力しながら、IPCC活動に参画する研究者への支援を積極的に行っており、関連4省庁(環境省・文部科学省・気象庁・経済産業省)のもとに、「IPCC国内連絡会」を開催しています。同連絡会は、IPCC活動全般についての進捗状況把握、AR7作成に関する情報の共有化とそれに関する意見交換等を図るべく、年1~2回程度、開催しています。
日本からの執筆者等
CLA:統括執筆責任者、LA:主執筆者、RE:査読編集者
2024年2月時点、敬称略、章・五十音順
第1作業部会報告書
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
スコーピング会合 |
大島 長 |
気象庁気象研究所 主任研究官 |
|
スコーピング会合 |
平林 由希子 |
国芝浦工業大学大学院 理工学研究科 教授 |
- 第2作業部会報告書
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
スコーピング会合 |
栗原 晴子 |
琉球大学 理学部 教授 |
|
スコーピング会合 |
森 信人 |
京都大学防災研究所 気象・水象災害研究部門 教授 |
- 第3作業部会報告書
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
スコーピング会合 |
飯山 みゆき |
国際農林水産業研究センター プログラムディレクター |
|
スコーピング会合 |
杉山 昌広 |
東京大学 未来ビジョン研究センター 教授 |
|
スコーピング会合 |
長谷川 知子 |
立命館大学 総合科学技術研究機構 教授 |
|
スコーピング会合 |
森田 香菜子 |
慶応義塾大学 経済学部 准教授 |
- 気候変動と都市に関する特別報告書
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
第2章LA |
橋爪 真弘 |
東京大学 大学院医学系研究科 教授 |
|
第5章LA |
伊東 瑠衣 |
海洋研究開発機構(JAMSTEC) 付加価値情報創生部門 |
|
第5章LA |
ESTOQUE Ronald C. |
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 |
|
第5章RE |
SHAW Rajib |
慶應義塾大学 政策・メディア研究科 教授 |
|
スコーピング会合 |
足立 宗喜 |
環境省 地球環境局 総務課 気候変動科学室 室長補佐 |
|
スコーピング会合 |
ESTOQUE Ronald C. |
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 |
|
スコーピング会合 |
沖 大幹 |
東京大学大学院 工学系研究科 教授 |
|
スコーピング会合 |
吉田 有紀 |
国立環境研究所 気候変動適応センター アジア太平洋気候変動適応研究室 研究員 |
- SLCFインベントリに関する『2027年IPCC方法論報告書』
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
Vol1-第1章LA |
大原 利眞 |
日本環境衛生センター アジア大気汚染研究センター センター長 |
|
Vo1-第2章LA |
金谷 有剛 |
海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球環境部門 |
|
Vol1-第6章LA |
小田 知宏 |
Universities Space Research Association (USRA) Senior Scientist |
|
Vol1 General RE |
田辺 清人 |
公益財団法人 地球環境戦略研究機関(IGES) 上席研究員 |
|
Vol2-第1章LA |
黒川 純一 |
⼀般財団法⼈ ⽇本環境衛⽣センター アジア大気汚染研究センター |
|
Vol2-第2章LA |
藤森 俊郎 |
IHI 事業開発統括本部 技監 / 東北大学流体科学研究所 特任教授 |
|
Vol2-第3章LA |
森川 多津子 |
一般財団法人日本自動車研究所 環境研究部 主任研究員 |
|
Vol4-第4章LA |
森下 智陽 |
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 東北支所 主任研究員 |
|
Vol5 Waste RE |
山地 一代 |
神戸大学大学院 海事科学研究科 准教授 |
|
スコーピング会合 |
金谷 有剛 |
海洋研究開発機構(JAMSTEC)地球環境部門 |
|
スコーピング会合 |
黒川 純一 |
⼀般財団法⼈ ⽇本環境衛⽣センター アジア大気汚染研究センター |
|
スコーピング会合 |
竹村 俊彦 |
九州大学 応用力学研究所 大気海洋環境研究センター 所長 |
|
スコーピング会合 |
谷本 浩志 |
国立環境研究所 地球システム領域 副領域長 |
- CDR・CCUSに関する『方法論報告書』
|
|
氏名 |
所属・役職 |
|
スコーピング会合 |
岸本 文紅 |
国立研究開発法人 農業・食品産業総合技術研究所 グループ長補佐 |
|
スコーピング会合 |
中垣 隆雄 |
早稲田大学 理工学術院 創造理工学部 総合機械工学科 教授 |
AR7関連会議結果(2023年~)
- 第59回 総会 環境省報道発表<2023年7月>:AR7議長団選挙
- 第60回 総会 環境省報道発表<2024年1月>
- 第61回 総会 環境省報道発表<2024年8月>:特別報告書/方法論報告書(SLCF)のアウトライン決定
- 第62回 総会 環境省報道発表<2025年3月>:WG1~3のアウトライン決定
- 第63回 総会 環境省報道発表<2025年11月>:方法論報告書(CDR・CCUS)のアウトライン決定
リンク集
- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)など:最新の評価報告書や普及啓発(シンポジウム)関連情報を掲載