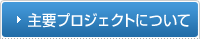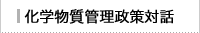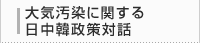日中韓環境教育ネットワーク(TEEN)
TEENの成り立ちと活動について
平成12年に北京で開催された第2回日中韓三カ国環境大臣会合(以下、TEMM:Tripartite Environment Ministers Meeting)において、「環境共同体意識の向上」を図るための三カ国協力プロジェクトを形成・推進していくことが決定されました。そして、同年6月の日中韓三カ国実務者会合において、TEENをプロジェクトの一つとして構築することが合意され、平成12年以降は三カ国が交替でTEENシンポジウム及びワークショップを開催しています。本会合では、環境教育の専門家や教育者、NGO代表等が三カ国から集まり、環境教育のイニシアティブについて議論や意見交換などを行っています。今年(令和6年)は、25回目の開催となりました。
第25回シンポジウム・ワークショップ
2024.10.26~30(日本・京都)
令和6年10月26日(土)~30日(火)の日程で、「第25回日中韓環境教育ネットワーク(The 25th Tripartite Environmental Education Network : 以下、TEEN25)シンポジウム及びワークショップ」が開催されました。

三カ国からのTEEN25参加者
テーマと目的
2050年カーボンニュートラルの実現をはじめとした持続可能な社会への変革が求められている中、本年は「過去から現在、未来をつなぐ~脱炭素社会実現へのロードマップ~」をテーマとして、日中韓における脱炭素社会の実現に向けた取り組みに関して発表や意見交換が行われました。
内容報告
- 一日目
-
午前は、政府円卓会議並びに京都国際会館への視察が行われました。京都議定書締結の地である京都国際会館のスタッフの案内のもと、1997年に地球温暖化防止のための国際会議(COP3)が開催された会議場や日本庭園などを視察しました。
午後からは、「過去から現在、未来をつなぐ~脱炭素社会実現へのロードマップ~」をテーマとしたシンポジウムが行われました。シンポジウムは一般にも公開され、基調講演の他、日中韓三カ国の代表者からの報告とパネルディスカッションが行われました。
基調講演
講演者:江守正多氏(東京大学未来ビジョン研究センター 教授)
タイトル:気候の危機にどう向き合うか政策報告
- (1) 日本
-
- 発表者:黒部一隆氏 (環境省 環境教育推進室 室長)
- タイトル:カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリション ~環境省・文部科学省・経済産業省連携プロジェクト~
- 概要:2050年のカーボン・ニュートラル実現のために期待されている、大学が国、自治体、企業等と連携強化を行う大学等コアリションの各地での実践例や効果についての発表が行われました。
- (2) 中国
-
- 発表者:YU Wei氏 (中国計量大学 カーボンニュートラル・グリーン開発センター エグゼクティブ・ディレクター)
- タイトル:中国の低炭素・気候変動教育政策と展望
- 概要:中国の学校教育における低炭素・気候変動教育の特徴について、また国家レベルでの長期目標や行動計画及び地方レベルでの規制や条例の紹介、今後の展望について発表が行われました。
- (3) 韓国
-
- 発表者:KIM Chankook氏 (韓国国立教育大学 環境教育学部 教授)
- タイトル:カーボン・ニュートラルに向けた教育の事例~気候危機時代における環境市民意識~
- 概要:韓国の環境教育の背景や歴史についての紹介および以前の法体制や改正後の内容、また市民の取り組みや2022年に改訂された国家カリキュラムについての発表が行われました。
実践報告
- (1) 日本
-
- 発表者:中島恵理氏 (同志社大学政策学部 教授)
- タイトル:地域循環共生圏&ソーシャル・イノベーションを担う人づくり
- 概要:環境政策の革新的な課題解決策である「地域循環共生圏」についての説明、また信州大学と同志社大学で行われたプロジェクトの実践例について発表が行われた。
- (2) 中国
-
- 発表者:SUN Liqiu氏(深圳市福田区教育科学アカデミー 科学労働者教育部門 ディレクター)
- タイトル:SUN Liqiu氏(深圳市福田区教育科学アカデミー 科学労働者教育部門 ディレクター)
- 概要:再生可能資源を重視したグリーンビルディングや、深圳市福田区の学校で毎年実施されている「低炭素アクション」といった、深圳市福田区内で実践されている6つのプロジェクトについての発表が行われました。
- (3) 韓国
-
- 発表者:LEE Soree氏 (ソウル特別市教育庁 初等教育 学校検査官)
- タイトル:ネットゼロスクール~生態転換教育の事例から~
- 概要:ネットゼロを学校でも推進すべく、ソウル市内の小中学校10校を対象に炭素データの分析から排出量を削減するための標準モデルの開発を行うプロジェクトについての発表が行われました。
また、日中韓三カ国の代表者からの報告後はパネルディスカッションが行われ、
モデレーターの近藤順子氏(京都外国語大学 非常勤講師)の進行のもと、脱炭素社会を目指していく上で環境教育において必要とされることについて意見交換が行われました。パネルティスカッションには日本から中島恵理氏の他、中国からLIU Jian氏(人民教育出版社 シニアエディター)、韓国からLEE Sun-Kyung氏(清州教育大学科学教育学部 教授)が登壇されました。最後に、京都府立大学学生サークル「森なかま」より、活動紹介及びTEEN25開催期間中のプログラムを環境に配慮したものにするためのアイディア紹介が行われました。

京都国際会館

シンポジウム
- 二日目
-
午前は桂離宮を訪問しました。庭園内の石材や材木の加工は最小限に抑え、自然のあるべき姿をそのまま活用している様子など、参加者は長い歴史の中で培われてきたと自然との共生の仕 組みに強く関心を抱いている様子で、積極的に質問をする姿が見られました。
午後は、けいはんな学研都市および積水ハウス総合住宅研究所を訪問し、参加者は施設見学や体験を通して各企業の環境に関する取組みについて学びました。
最後に国際高等研究所に会場を移し、ワークショップを実施しました。まず、「これからの環境教育に求められる企業の役割について」というテーマで寺西一浩氏(積水ハウス総合住宅研究所環境推進部)よりワークショップの導入となるプレゼンテーションが行われました。その後、参加者は2グループに分かれて企業に求められる環境教育について自由に意見を述べ合い、各グループのファシリテーターがその内容を取りまとめて全体で報告を行いました。

桂離宮

ワークショップ