bar
3R容器包装リサイクル法
- ホーム
- レジ袋に係る調査(平成20年度)
- 調査結果の詳細
3. 調査結果の詳細
1.平成20年11月1日現在、都道府県の約8割、市町村の約4割が何らかの方法でレジ袋削減の取組を実施しており、今後こうした取組みはさらに広がっていくことが見込まれます。
平成20年11月1日現在、47都道府県のうち38道府県(全体の81%)では、既に何らかの方式でレジ袋削減の取組が実施されており、現在取組を行っていない9都県についても、3県(同6%)では平成21年度中にも実施する具体的な計画があり、5県(同11%)では取組を検討する予定と回答されています。このように、都道府県レベルでは、今後ほとんど全国各地で何らかの取組が行われると見込まれます(図1、図2)。
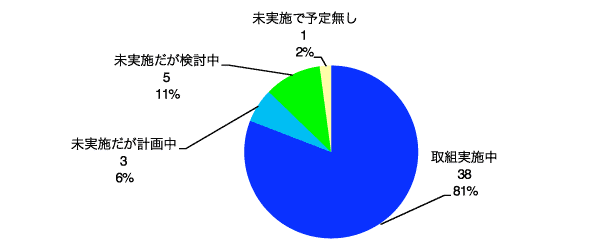
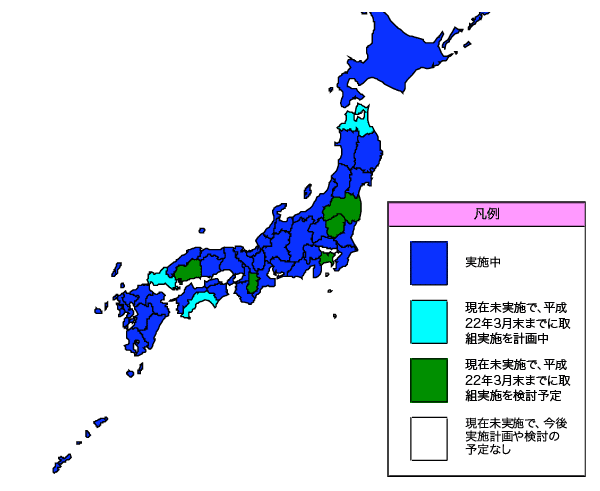
市町村レベルでの取組の実施状況をみると、回答のあった1,754市町村のうち、685市町村(全市町村の39%)では、現在、何らかの削減の取組が実施されています。また現在、取組を実施していない市町村のうち、97市町村(同6%)では、平成22年3月末までに取り組む具体的な計画があり、230市町村(同13%)では同様に取組を検討する予定である等、都道府県と同様、市町村レベルでも今後削減の取組が大きく広がっていくことが見込まれます。
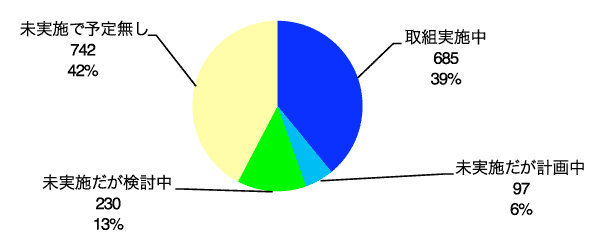
市町村レベルでの取組状況の広がりを都道府県別にみると、半数以上の市町村が取り組む都道府県は、平成20年11月1日現在、13都道府県であるのに対して、平成22年3月末までに17都道府県へと増加するものと見込まれます(図4、図5)。
(注) 図4及び図5は、市町村から寄せられた回答を都道府県ごとにまとめて作成したもので、未回答の市町村については、未実施として取り扱いました。
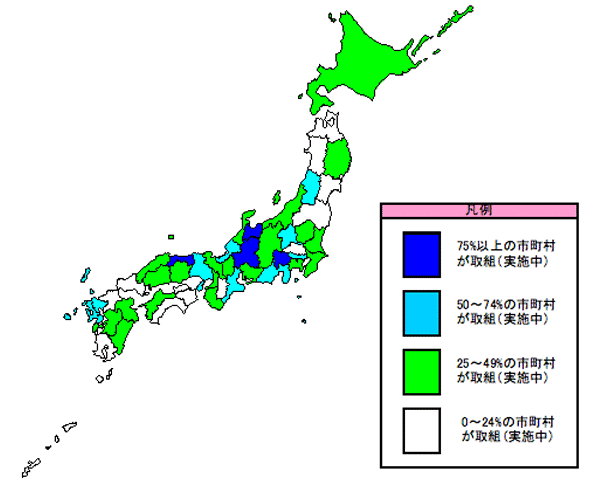
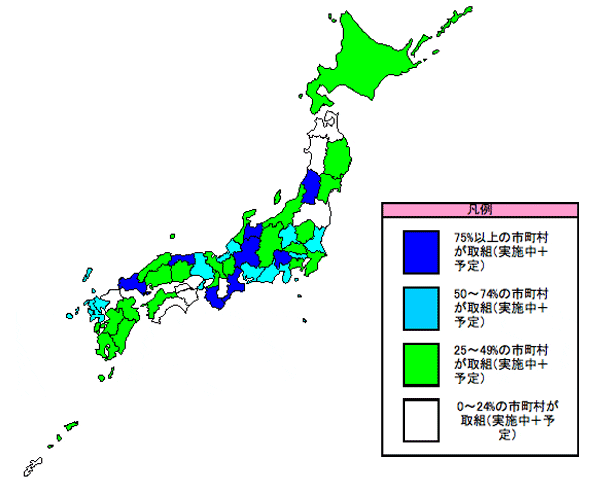
2.レジ袋削減の具体的な取組手法としては、(a)全廃・有料化手法、(b)全廃・有料化以外の手法、(c)有料化・有料化以外を問わず事業者に削減手法の選択を委ねる手法等があり、全国で地域特性を反映して、様々な手法が実施されています。
地方自治体における取組の概要
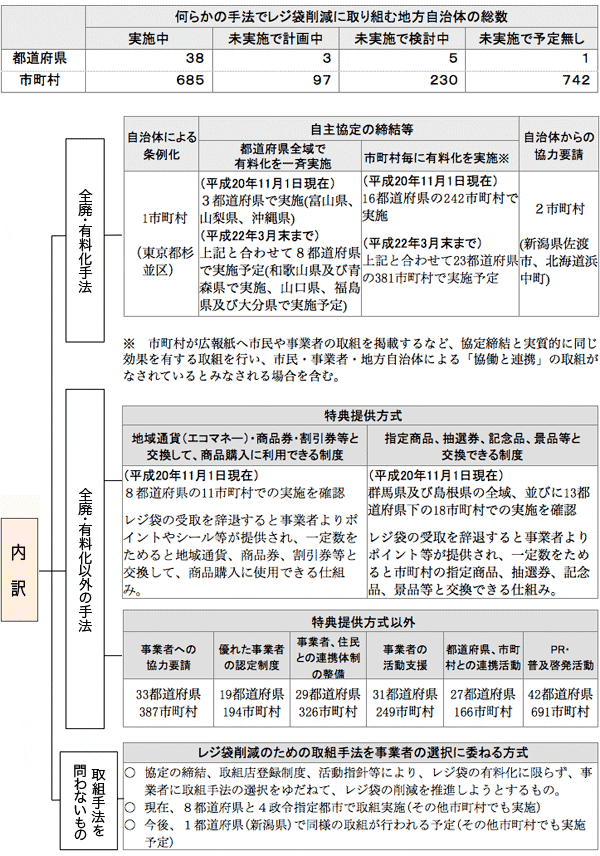
3.レジ袋の有料化については、平成20年11月1日現在、都道府県の主導により、都道府県全域で有料化の一斉実施が3県において行われています。さらに、平成22年3月末までに、新たに5県において同様の取組が行われる予定など、有料化の取組が広がる見込みです。
平成20年11月1日現在、3都道府県において、レジ袋の有料化を全域で一斉実施(図7、資料1)
◆富山県:平成20年4月1日から開始、21年3月現在43事業者399店舗で有料化実施
◆山梨県:平成20年6月30日から開始、21年3月現在26事業者116店舗で有料化実施
◆沖縄県:平成20年10月1日から開始、21年3月現在11事業者252店舗で有料化実施
平成22年3月末までに、5都道府県において、レジ袋の有料化を全域で一斉実施及び実施予定(平成21年3月6日現在)
◆和歌山県:平成21年1月23日から主要スーパー31事業者192店舗で実施
◆青森県:平成21年2月2日から主要なスーパー、総合スーパー、百貨店、ホームセンター、クリーニング店24事業者231店舗で実施
◆山口県:平成21年4月1日から主要スーパー41事業者298店舗で実施予定
◆福島県:平成21年6月1日から主要スーパー11事業者214店舗で実施予定
◆大分県:平成21年6月1日から主要スーパー21事業者201店舗で実施予定
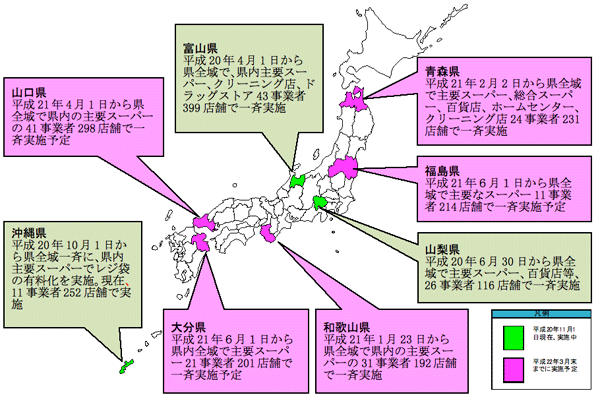
(注) 本項は、都道府県の主導により、都道府県全域でレジ袋有料化の一斉実施を行っている事例を集約したものであり、市町村の取組により都道府県内でレジ袋有料化の拡大が図られている事例については、次の(4)に集計しました。
4.市町村レベルでみると、平成20年11月1日現在、16都道府県の245市町村で、市町村が主体となってレジ袋の有料化に取り組んでおり、さらに平成22年3月末までに、23都道府県の384市町村で有料化が実施される予定です。
平成20年11月1日現在、16都道府県の245市町村で有料化が実施されています。このうち条例化しているものが1特別区(東京都杉並区)、市民・事業者及び地方自治体と自主協定を締結しているものや、協定締結と実質的に同じ効果を有する取組を行っているとみなされるものが16都道府県の242市町村、自治体からの協力要請により事業者が有料化を実施しているものが2市町(新潟県佐渡市、北海道浜中町)という状況です。
今後、平成22年3月末までに、19都道府県の139市町村で新たに有料化が実施され、合計23都道府県の384市町村で有料化が実施される予定であり(表1)、実施手法として、自主協定の締結に基づく取組が増加するものと見込まれます。
表1 都道府県別にみた有料化実施及び実施予定の市町村数(現在、将来)
| 都道府県 | 有料化実施の市町村数 (H20年11月1日現在) |
増減 | 有料化実施予定の 市町村数 (平成22年3月末まで) |
| 北海道 | 131 | 10 | 141 |
| 宮城県 | 1 | 9 | 10 |
| 山形県 | 14 | 7 | 21 |
| 茨城県 | 5 | 12 | 17 |
| 埼玉県 | 0 | 1 | 1 |
| 東京都 | 2 | 0 | 2 |
| 神奈川県 | 1 | 0 | 1 |
| 新潟県 | 1 | 1 | 2 |
| 福井県 | 1 | 3 | 4 |
| 石川県 | 0 | 5 | 5 |
| 長野県 | 0 | 15 | 15 |
| 岐阜県 | 32 | 10 | 42 |
| 静岡県 | 13 | 3 | 16 |
| 愛知県 | 16 | 36 | 52 |
| 三重県 | 9 | 15 | 24 |
| 京都府 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫県 | 14 | 5 | 19 |
| 島根県 | 0 | 1 | 1 |
| 岡山県 | 0 | 1 | 1 |
| 広島県 | 1 | 2 | 3 |
| 徳島県 | 3 | 0 | 3 |
| 高知県 | 0 | 1 | 1 |
| 鹿児島県 | 0 | 2 | 2 |
| 合計 | 245 | 139 | 384 |
都道府県別にみた市町村レベルでの有料化実施率(有料化実施市町村数÷都道府県内の市町村数×100)について、現在(平成20年11月1日)と将来(平成22年3月末)を比較すると、有料化実施の市町村がない都道府県が28から16へと減少する一方で、全体として有料化実施率が高くなる傾向が見られ、全国的に有料化に取り組む市町村が増える傾向が認められました(表2)。
表2 市町村の有料化実施率別にみた都道府県数の推移(都道府県主導の一斉実施データを併記)
| 現在 (H20年11月1日現在) |
将来 (H22年3月末まで) |
増減 (将来 - 現在) |
|
| 有料化実施市町村なし | 28 | 16 | △12 |
| 有料化実施(予定)率 1~19% |
9 | 12 | 3 |
| 有料化実施(予定)率 20~39% |
4 | 4 | 0 |
| 有料化実施(予定)率 40~59% |
1 | 2 | 1 |
| 有料化実施(予定)率 60~79% |
2 | 2 | 0 |
| 有料化実施(予定)率 80~99% |
0 | 2 | 2 |
| 有料化実施(予定)率 100% |
0 | 1 | 1 |
| 全域で有料化を一斉実施 | 3 | 8 | 5 |
| 合計 | 47 | 47 | 0 |
特に都道府県別に市町村レベルの取組状況を見た場合、平成22年3月末までに、岐阜県では県内の全ての市町村で有料化が実施される全国初の事例となる予定です。都道府県レベルでの有料化実施予定率をみると、平成22年3月末までに、岐阜県で100%に達する予定に次いで、愛知県で85%、三重県で83%、北海道で78%、山形県で60%と、これらの都道府県では過半数の市町村において有料化が実施される見込みです(図7、図8)。
レジ袋の有料化を行っている店舗数の多い市町村をみると、平成20年11月1日現在では、愛知県名古屋市の635店が最も多く、次いで新潟県佐渡市(195店)、山形県鶴岡市(194店)、北海道札幌市(161店)、岐阜県岐阜市(107店)となっています。名古屋市の場合は、平成21年4月より、スーパーマーケット、ドラッグストア、薬店・薬局、クリーニング店など79社3組合の1,296店舗が有料化の取組に参加予定です。
この他、コンビニエンスストアにおいても、三重県津市の大学内の店舗で平成21年6月から有料化が実施される予定であるなど、取組が広がりつつあります。
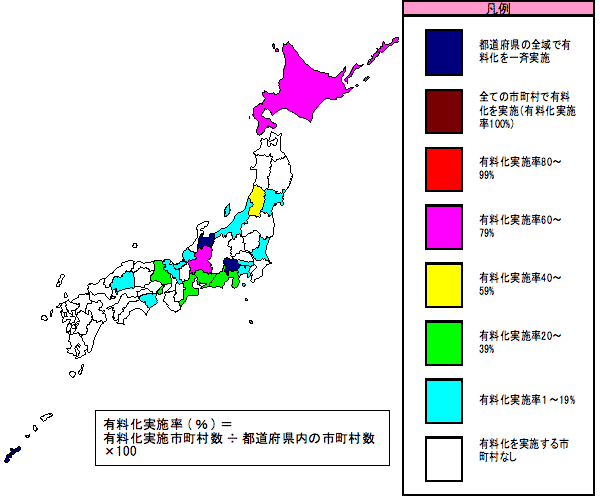
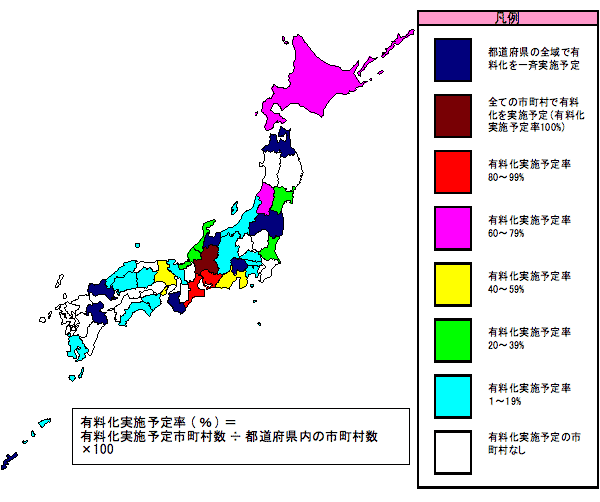
5.有料化の実施に伴い、レジ袋辞退率やマイバッグ持参率が80%を越える等、レジ袋の高い削減効果が確認されました。
有料化を実施した市町村を対象に、有料化実施による効果をどう評価しているかを集計したところ、レジ袋辞退率、マイバッグ持参率いずれの評価項目ともに、“随分向上した”と評価する市町村が7割以上ありました。さらに、やや向上したとする自治体が16~18%で、両者を合わせると、8割以上の市町村で有料化実施による効果を高く評価していました。逆に、取組が低下したと評価する市町村はありませんでした(図9、図10)
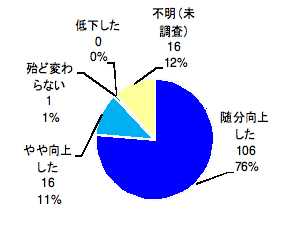 |
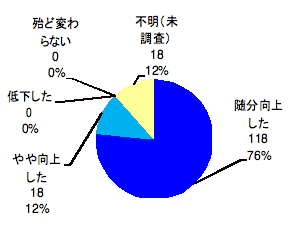 |
(図9)レジ袋辞退率からみた有料化実施による効果(平成20年11月1日現在、実施している139市町村の評価) |
(図10)マイバッグ持参率からみた有料化実施による効果(平成20年11月1日現在、実施している154市町村の評価) |
有料化を実施した市町村のうち、有料化の実施前後に、レジ袋辞退率又はマイバッグ持参率を調査した市町村の回答を集計すると、レジ袋辞退率では実施前が28%であったものが実施後は87%に、マイバッグ持参率では実施前が41%であったものが実施後は83%へと大幅に改善しており、有料化の実施がレジ袋削減に大きな効果があることが確認されました(図11)。
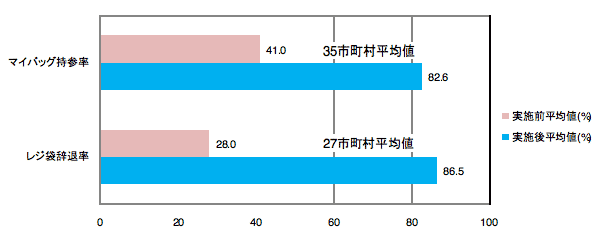
注:図11は平成20年11月1日現在、有料化を実施している市町村からの回答のうち、有料化実施の前後に調査が実施され、調査結果(数値)が回答されたものから平均値を算定した。
6.レジ袋削減の手段として、地域通貨(エコマネー)や商品券・割引券等の提供を受けて買い物に使用したり、市町村が指定する商品や抽選券、景品等を提供することにより、レジ袋の受取辞退を促そうという「特典提供方法」が18都道府県の29市町村で実施され、相当の削減効果をあげていることが確認されました。
レジ袋の受取を辞退すると、事業者よりポイントやシール等が提供され、一定数をためると地域通貨、商品券、割引券等と交換され、商品購入に使用できる仕組みが、平成20年11月1日現在、8都道府県の11市町村で実施されていることが確認できました。(図12、資料2)。
同様に、ポイントやシール等で指定ごみ袋、再生紙トイレットペーパー、環境配慮商品等の市町村指定商品、記念品、景品等と交換できる仕組みが、平成20年11月1日現在、群馬県及び島根県の全域、並びに13都道府県の18市町村で実施されていることが確認できました。
特典提供方法への参加店舗数の多い市町村等は、広島県福山市、同県三次市、群馬県(全域)、福岡県北九州市、島根県(全域)等です。なお、有料化を実施した市町村等では、特典提供方法事業の中止、縮小、見直し等が行われている場合がありました。
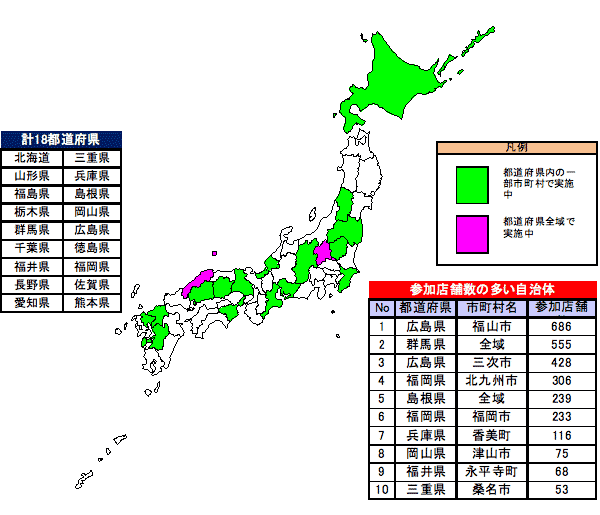
「特典提供方法」を実施した市町村が、実施前と実施後を比較して評価した結果を見ると、レジ袋辞退率、マイバッグ持参率いずれの評価項目ともに、“随分向上した”との評価が21~22%、“やや向上した”との評価が30~36%と、両者を合わせると過半数となり、取組効果が高く評価されていました(図13、図14)。
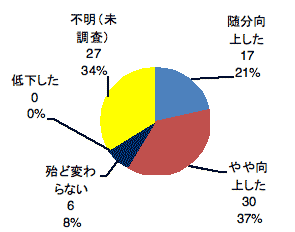 |
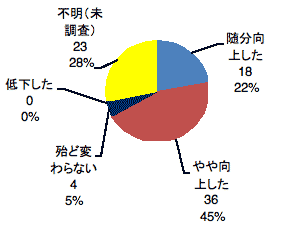 |
(図13) 特典提供方式による効果(レジ袋辞退率、感覚評価、回答:80市町村) |
(図14) 特典提供方式による効果(マイバッグ持参率、感覚評価、回答:81市町村) |
さらに、取組実施の前後に、レジ袋辞退率又はマイバッグ持参率を調査した市町村の回答を集計すると、レジ袋辞退率、マイバッグ持参率ともに実施前が21%であったものが、実施後は38~47%と、有料化手法ほど大幅ではないものの、相当程度の改善が図られていることが確認されました(図15)。
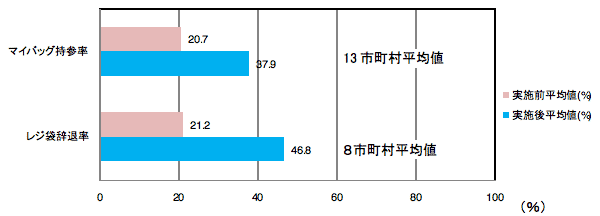
注:図15は、平成20年11月1日現在、特典提供方式を実施している市町村からの回答のうち、有料化実施の前後に調査が実施され、前後の調査結果(数値)が回答されたものから平均値を算定した。
7.特典提供方式以外にも、事業者への協力要請、優れた事業者の認定制度、事業者・住民との連携体制の整備、事業者の活動支援、都道府県・市町村との連携活動、PR・普及啓発活動など、都道府県や市町村が様々な方法で取り組んでいます。
都道府県の取組内容をみると、PR・普及啓発活動に取り組む都道府県が最も多く、次いで、事業者への協力要請、事業者の活動支援、事業者・住民との連携体制の整備の順で、それぞれ過半数の都道府県が取り組んでいました。今後は、市町村との連携活動、事業者の活動支援、事業者・住民との連携体制の整備等に取り組む予定の都道府県がそれぞれ4以上あり、取組の充実が図られるものと見込まれます(図16)。
市町村も都道府県と同様の傾向であり、PR・普及啓発活動に取り組む市町村が約4割と最も多く、次いで、事業者への協力要請、事業者・住民との連携体制の整備、事業者の活動支援の順でした。今後、PR・普及啓発活動や事業者への協力要請などに新たに取り組む市町村が90~100程度あると見込まれ、都道府県と同様、取組の充実が図られるものと見込まれます(図17)。
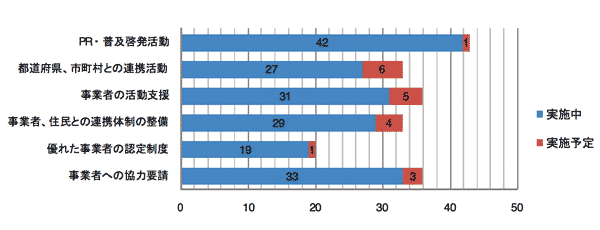
都道府県における特典提供方式以外の実施状況
(平成20年11月1日現在実施中+22年3月末までに実施予定の都道府県数)
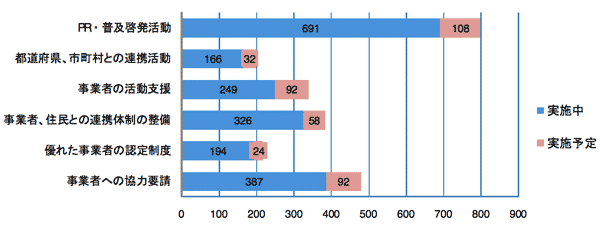
市町村における特典提供方式以外の実施状況
(平成20年11月1日現在実施中+22年3月末までに実施予定の市町村数)
8.レジ袋の有料化や特典提供方式等を問わず、事業者にレジ袋削減手法の選択を委ねる手法も全国に広がっています。
平成20年11月1日現在、8都道府県と4政令指定都市において、協定の締結、取組店登録制度の創設、活動指針の策定等に基づき、事業者が有料化に限らず、自ら削減手法を選択することを通じて、レジ袋使用量の削減を推進しようとする取組が行われています(図18)。
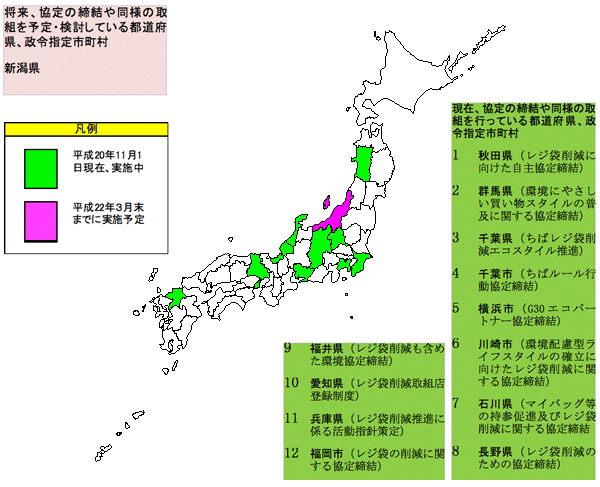
事業者に取組手法の選択を委ねる協定の締結等を通じて、
レジ袋の削減を推進する都道府県及び政令指定都市の事例
bar