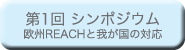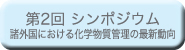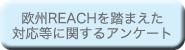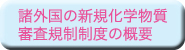| 1 |
年間100kg以下で製造/輸入される物質 |
| 2 |
開発・工程改善の目的の場所で、調査・研究者に限って使用される物質 |
| 3 |
機械/装置に内蔵しているか、又は試運転用に機械/装置類とともに輸入される物質 |
| 4 |
特定の固体形態で一定の機能を発揮する製品に含有され、使用過程で流出のない物質 |
| 5 |
全量輸出のために年間10トン以下で製造/輸入される物質又は全量輸出のための化学物質を製造するために年間10トン以下で製造/輸入される物質
|
| 6 |
2重量%以下の単量体を除外した単量体で構成された高分子が、既存化学物質目録に収載されている高分子化合物 |
| 7 |
すべてのブロックが既存化学物質目録に収載されているブロック高分子化合物 |
| 8 |
幹および枝部分がすべて既存化学物質目録に収載されているグラフト高分子化合物 |
| 9 |
数平均分子量が10,000以上の非イオン性高分子化合物 |
| 10 |
| 数平均分子量が1,000以上で、次の規定をいずれも満たす物質 |
| イ. |
高分子単量体が有毒物、観察物質、新規化学物質及びエポキシ化合物に該当しない |
| ロ. |
水溶解度がpH 2、7及び9で5mg/g以下 |
|
| 11 |
1991年2月2日以前に製造/輸入された事実が証明される化学物質(1991年2月2日以前に外国で国内に輸出した事実が証明される化学物質を包含する。) |