公害の防止や自然環境の保護を扱う機関として誕生した環境省にとって、人の命と環境を守る基盤的な取組は、原点であり使命です。その原点は変わらず、時代や社会の変化と人々のライフスタイルに応じた政策に取り組んでいます。
水俣病対策については、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)(及びその前身である公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法(昭和44年法律第90号))に基づく認定・補償や1995年及び2009年の二度の政治解決による救済が行われるとともに、医療・福祉の充実や地域づくりの取組も進められてきたものの、現在もなお認定申請や訴訟は継続しており、水俣病問題は終わっていません。「水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法」(平成21年法律第81号。以下「水俣病被害者救済特措法」という。)等を踏まえ、全ての被害者の方々や地域の方々が安心して暮らしていけるよう、関係地方公共団体等と協力して、補償や医療・福祉対策、地域の再生・融和等を進めていきます。
医療・福祉対策については、患者やその介護者等の高齢化に伴う日常生活能力の低下、介護能力の低下に対応するための胎児性患者等の地域生活支援(デイサービス、在宅支援)や離島等における介護予防事業等の保健福祉の取組を実施していきます。また、水俣病被害者救済特措法第37条において、政府は健康に係る調査研究を行うこと、及びこのための手法の開発を図ることが規定されています。これを踏まえ、環境省では、これまでメチル水銀による脳への影響を客観的に評価するための手法の開発に取り組んできたところ、一定の精度に達したこと等から、2024年12月に外部有識者で構成する検討会を設置し、水俣病被害者救済特措法に基づくメチル水銀による健康影響に係る疫学調査の在り方について議論を行いました。本検討会で検討いただいた結果も踏まえつつ、2026年度をめどに健康調査を開始できるよう必要な検討・準備を進めていきます。
地域の再生・融和については、水俣病発生地域における「もやい直し」は、地域の環境再生と復興、そしてその先にある「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現、また、それらの過程における「参加」の重要性や、さらには地域の土台としてのコミュニティが果たす役割の大きさ、政府(国、地方公共団体等)、市場(企業等)、国民(市民社会、地域コミュニティを含む。)の共進化の重要性などについて、今日の我々に重要な示唆をしており、引き続き水俣病発生地域における地域循環共生圏の実現を支援するとともに、他地域への参考としていくことが必要です。
また、我が国の水俣病の経験と教訓を活かした国際的な取組も進めています。例えば、水銀に関する水俣条約においては、条約の有効性評価(条約に基づく措置が条約の目的の達成に効果を上げているかを評価)を実施しており、2025年3月には科学者からなる専門家グループ(OESG:Open-Ended Scientific Group)の会合を熊本県水俣市で開催しました。我が国は、OESGを構成する1チームの代表を務めるとともに、OESGの分析結果に基づき有効性を評価する作業グループ(EEG:Effective Evaluation Group)の共同議長を務めるなどして、本取組に貢献しました。また、水俣市の中学生による水銀対策技術を紹介する動画制作や、水俣と世界の高校生がオンラインで交流する「水銀に関するユースダイアログ」を開催するなど、次世代の水俣条約への理解の促進と行動の強化につなげる環境学習の支援を行いました。
近年、“暑い夏”が続いています。2024年の夏は、全国的に気温の高い日が多く、特に6~8月の平均気温は、西日本と沖縄・奄美では1位、東日本では、2023年の夏と並ぶ1位タイの高温となりました。こうした状況の中、熱中症の死亡者数や救急搬送人員も多くなっています。
さらに今後、気候変動の影響によって、極端な高温の発生リスクが増加することが見込まれており、我が国における熱中症対策は喫緊の課題といえます。(図3-3-1、図3-3-2)
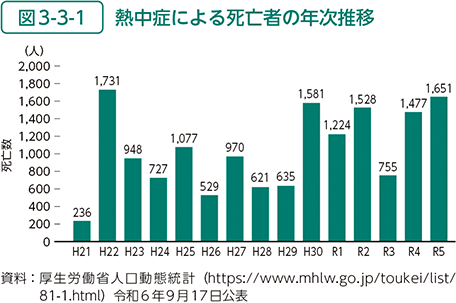
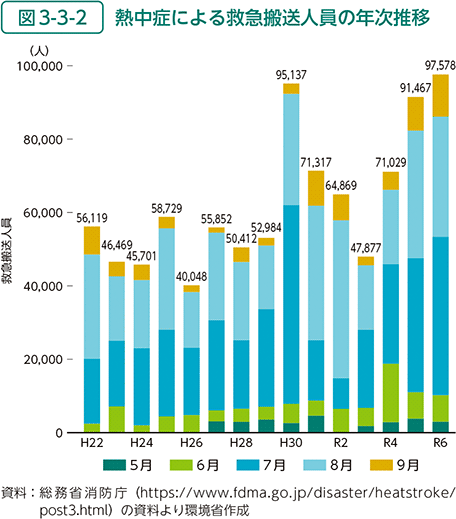
熱中症対策の更なる推進を図るため、2024年4月に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号。以下「改正法」という。)が施行されました。また、関係府省庁及び地方公共団体等は、改正法に基づく「熱中症対策実行計画」(令和5年5月閣議決定)の下、連携を強化しながら、熱中症と予防行動に関する理解の醸成等を進めています。環境省では、熱中症特別警戒アラートや熱中症警戒アラートの運用、暑さ指数情報等の提供、市町村が指定する指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)の増加に向けた支援、熱中症予防に関する各種の普及・啓発等を行っています。(図3-3-3、図3-3-4)
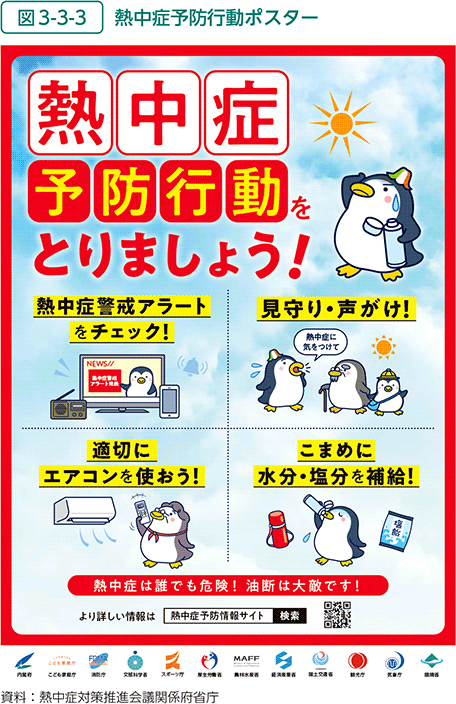
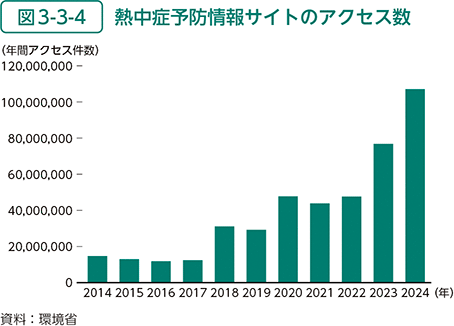
[![]() Excel]
Excel]
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)、PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)については、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)で廃絶等の対象とされたことを受け、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)の第一種特定化学物質に指定し、その製造・輸入等を原則禁止しています。また、過去に製造・輸入されたPFOS等を含有する泡消火薬剤については、関係省庁・関係団体と協力して、代替と処分に向けた取組を進めるとともに、4年ごとにPFOS等を含有する泡消火薬剤の全国の在庫量を調査しており、2024年度の調査結果によると、前回の2020年度の調査と比べて、PFOSを含有する泡消火薬剤は約45%減少、泡消火薬剤中のPFOS含有量は約36%減少しました。
環境中のPFOS及びPFOAについては、化学物質環境実態調査における2009年以降の継続的なモニタリングの結果によると、水質(河川等の公共用水域)や底質及び大気中では統計的に有意な減少傾向が確認されています。河川や地下水等については、2020年に要監視項目に指定し、地方公共団体が地域の実情に応じてモニタリングを実施することで測定地点の拡大を図っています。2020年に設定した指針値(暫定)を超過した地点では、地方公共団体において、「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」に基づき飲用摂取防止のための取組が行われており、2024年11月には、同手引きを改定し、水道水源や飲用井戸等の存在状況を踏まえた調査を行うなどの内容を新たに反映しました。さらに環境省では、環境中のPFOS及びPFOAの濃度を効果的・効率的に低減する対策技術の実証にも着手します。
また、国民の健康リスクの低減が最も重要であることから、飲み水からの摂取を防止することを第一に、2024年6月に内閣府食品安全委員会がまとめた「有機フッ素化合物(PFAS)に関する食品健康影響評価」等を踏まえて、環境省では、水質の目標値等の取扱いについて検討を進めています。また、2024年5月から9月にかけて、国土交通省と環境省の共同で、水道におけるPFOS及びPFOAに関する全国調査を実施し、全国の水道における検出状況等を把握するとともに、11月及び12月には取りまとめ結果を公表しました。同調査結果も活用しつつ、環境省では、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準への引上げを含めた対応を進めていきます。また、国土交通省では、水道水において暫定目標値を超過した場合に水道事業者等が実施した主な対応を整理し、11月に公表しました。
さらに、環境省では、PFASと健康影響の関連性を明らかにするため、環境研究総合推進費を活用して疫学調査や研究を支援するとともに、PFASに関する総合研究、子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)、化学物質の人へのばく露量モニタリング調査等、科学的に評価可能な疫学調査や研究を進めています。エコチル調査では、2010年度から約10万組の親子を対象に、血液等を採取し化学分析を実施するほか、健康状態等の追跡調査を実施しており、化学物質(PFASを含む。)等が子どもの健康に与える影響を明らかにするための調査研究を実施しています。また、化学物質の人へのばく露量モニタリング調査では、人への化学物質(PFASを含む。)の平均的なばく露の状況を把握するために、対象規模を拡大して血液等の生体試料中の化学物質濃度調査を実施します。
加えて、「PFOS、PFOAに関するQ&A集」やリーフレット、ポータルサイト等を通じて、PFASのリスクコミュニケーションも促進していきます。
中山間地域における人口減少・高齢化による人間活動の低下に伴い、耕作放棄地や利用されない里山林等が鳥獣の生息にとって好ましい環境となることなどにより、ニホンジカ、イノシシ、クマ類等の分布域が拡大し、生態系や農林業、生活環境に深刻な被害を及ぼしています。
環境省と農林水産省は、ニホンジカとイノシシについて、2023年度までに2011年度の個体数から半減させることを目標として捕獲対策を強化してきました。その結果、特にニホンジカの個体数については、未だ高い水準にあることから、目標の期限を2028年度まで延長し、ニホンジカの集中的な捕獲対策等の取組を進めています。
クマ類については、秋の堅果類の結実量の影響等もあり、数年おきに人里への大量出没を繰り返していましたが、特に2023年度は統計のある2006年度以降最も多い人身被害件数を記録しました。人の日常生活圏にクマ類が侵入し、国民の安全・安心を脅かす事態を受け、環境省ではクマ類の専門家による検討会を設置し、科学的知見に基づき、クマ類の出没や被害の発生要因を分析するとともに、被害防止に向けた総合的な対策の方針を取りまとめました。本方針では、クマ類の地域個体群を維持しつつ、人の日常生活圏への出没防止によって人とクマ類の空間的なすみ分けを図るため、「ゾーニング管理」、「広域的な管理」、「順応的な管理」の3つの管理を推進する方向性が示されました。本方針を受けて、2024年4月に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護管理法」とする。)に基づく指定管理鳥獣に、絶滅のおそれのある四国の個体群を除いたクマ類を指定し、関係省庁と共に「クマ被害対策施策パッケージ」を策定しました。また、人の日常生活圏にクマ等が出没した場合に、地域住民等の安全の確保の下で銃猟を可能とする改正鳥獣保護管理法が2025年4月に公布され、新たに創設された緊急銃猟制度について公布後6か月以内に施行することとしています。今後、制度整備を着実に進めるとともに、クマ類の地域個体群を維持しながら、捕獲に偏らない総合的かつ効果的な被害防止策を推進していきます。