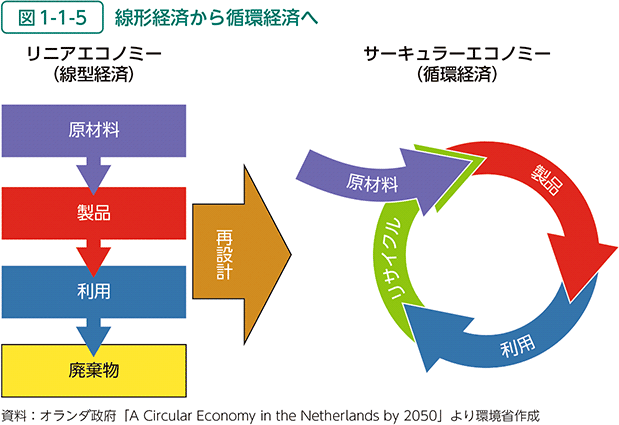人類の活動は地球の環境収容力を超えつつあり、環境や自然資本の安定性は脅かされ、気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの世界的危機に直面しています。経済社会活動は、自然資本(環境)という基盤の上に成り立っており、これらの危機の克服は最重要課題の一つです。持続可能な社会に向けては、経済社会システムをネット・ゼロ(脱炭素)で、循環型で、ネイチャーポジティブ(自然再興)なものへと転換する統合的アプローチが必要です。昨年5月に閣議決定した第六次環境基本計画では、環境政策が目指すべき社会の姿として、「循環共生型社会」の構築を掲げ、現在のみならず、将来にわたって「ウェルビーイング/高い生活の質」をもたらす「新たな成長」の実現を目指すこととしています。
第1章では、「新たな成長」を導く経済活動について、持続可能な生産と消費を実現するグリーンな経済システムを構築し、環境価値への適切な評価や、自然資本及び自然資本を維持・回復・充実させる資本システムへの長期的な視野に基づく投資を促していく取り組みについて、世界、我が国の環境問題や気象災害、それがもたらす経済的影響等も踏まえながら解説します。
世界の平均気温は上昇傾向にあり、1970年以降、過去2000年間のどの50年間よりも気温上昇は加速しています。世界の平均気温の上昇は、我が国も含め、極端な高温、海洋熱波、大雨の頻度と強度の増加を更に拡大させ、それに伴って、洪水、干ばつ、暴風雨による被害が更に深刻化することが懸念されています。まさに人類は深刻な環境危機に直面しているといえます。
国連環境計画(UNEP)は、「早急に行動を起こさなければ、世界全体の気温上昇は間もなく1.5℃を超え、今世紀末までに産業革命以前と比べて2.6℃から3.1℃という破滅的な上昇に達する可能性がある」と強調しました。また、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)総会第11回会合では「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価(ネクサス・アセスメント)」にて、「世界は、生物多様性の損失、水と食料の不安、健康、気候変動という相互に関連し、増大する危機に直面している。それぞれの危機に、個別に単独で対応するという現状の取組は非効果的かつ非生産的である。」と述べられています。第1節では、我々が直面する環境問題とその経済的影響等について概観します。
気象庁の報告によれば、2024年も世界各地で様々な気象災害が見られました。また、世界気象機関(WMO)は、2024年が観測史上最も暑い年となり、世界の平均気温が工業化前と比べて約1.55℃上昇と、単年ではあるが初めて1.5℃を超えたことを発表しました。
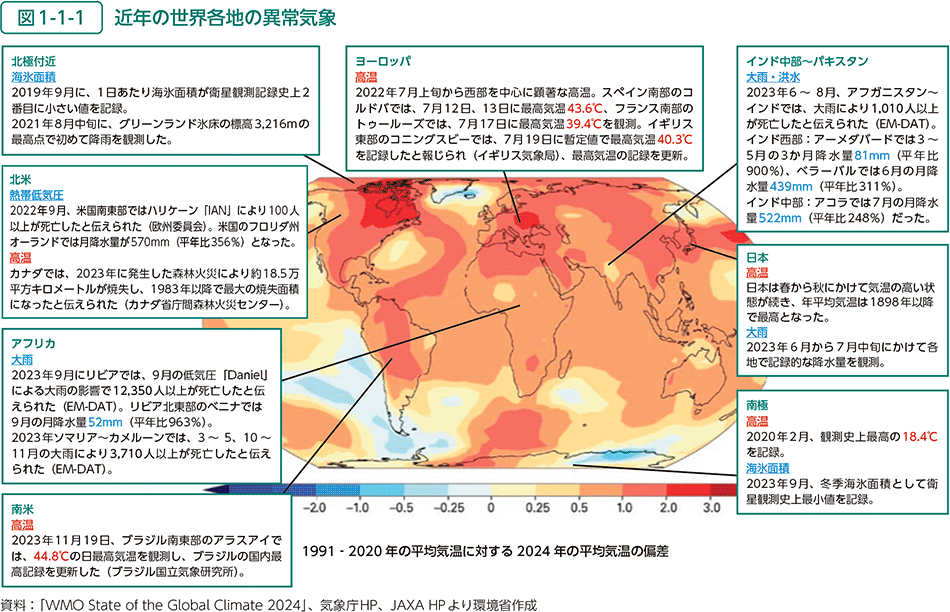
例えば、サウジアラビアでは、リヤド国際空港において6~8月の3か月平均気温37.6℃(平年差+1.8℃)を記録しました。また、6月の熱波により1,300人以上が死亡したと伝えられました。アメリカ南西部の夏(6~8月)の3か月平均気温は、夏としては1895年以降で最も高くなりました。また、中国南部~東南アジアでは、7月の台風第3号、9月の台風第11号、10月の台風第20号や大雨の影響により合計で1,240人以上が死亡したと伝えられました(写真1-1-1)。スペイン東部では、10月の大雨により230人以上が死亡、東アフリカ北部~西アフリカでは、3~9月の大雨により合計で2,900人以上が死亡したと伝えられました(写真1-1-2)。我が国においては、夏(6~8月)の平均気温平年差は東日本で+1.7℃、西日本で+1.4℃、沖縄・奄美で+0.9℃となり、1946年の統計開始以降、夏として西日本と沖縄・奄美では1位、東日本では1位タイの高温となりました。5月から9月の全国における熱中症救急搬送人員の累計は97,578人となり、昨年度同期間と比べると6,111人増加しており、2008年の調査開始以降、最も多い搬送人数でした。また、夏の降水量は、6~7月の梅雨前線と8月の台風第10号などの影響を受けた東日本太平洋側でかなり多く、低気圧や前線の影響を受けやすかった北日本日本海側と7月の台風第3号の影響で大雨となった沖縄・奄美でも多くなりました。このほか、台風の影響では、台風第5号は、岩手県に上陸した後、ゆっくりした速度で東北北部を横断し、岩手県では記録的な大雨となりました。台風が東北地方の太平洋側から上陸したのは1951年の統計開始以降3回目です。また、台風第10号は、日本付近で動きが遅くなり、非常に強い勢力で奄美地方、九州南部に接近し、強い勢力で鹿児島県に上陸した後、西日本を横断しました(写真1-1-3)。日本付近で台風の動きが遅かったため、台風本体の雨雲や暖かく湿った空気の影響が長く続き、西日本から東日本の太平洋側を中心に記録的な大雨となりました。



コラム:気候変動に関する政府間パネル(IPCC)「気候変動と都市に関する特別報告書」第1回主執筆者会合
IPCCの第6次評価報告書において、世界の人口の55%が暮らしている都市は、地球温暖化の影響をより強く受ける地域とされています。IPCCは、7回目の評価報告書の一つとして、「気候変動と都市に関する特別報告書」の作成を進めています。その第1回主執筆者会合が、環境省の支援により、2025年3月10日から14日にかけて大阪にて開催されました。この会合は、特別報告書を執筆する日本を含む世界各国の専門家が集まり、執筆内容を検討するもので、全4回の会合のうち1回目のものです。今後、2027年の特別報告書の公開に向けて、専門家等による執筆・査読が行われます。

国連防災機関(UNDRR)は、1998年~2017年の20年間に自然災害によって世界全体で130万人が死亡し、経済損失額は2兆9,080億ドルに上るとの報告書をまとめました。このうち大半の77%の2兆2,450億ドルは気象災害で、その前の20年間と比べると、2.5倍に増加しています。国別の経済損失では米国の9,448億ドルが最大であり、これは2005年のハリケーン・カトリーナや2017年のハーベイ、イルマなどの大型ハリケーンによる被害が大きかったためです。次いで、大洪水や四川大地震などに見舞われた中国(4,922億ドル)が2位、東日本大震災などで大きな被害を受けた日本(3,763億ドル)は3位となっています(図1-1-2)。
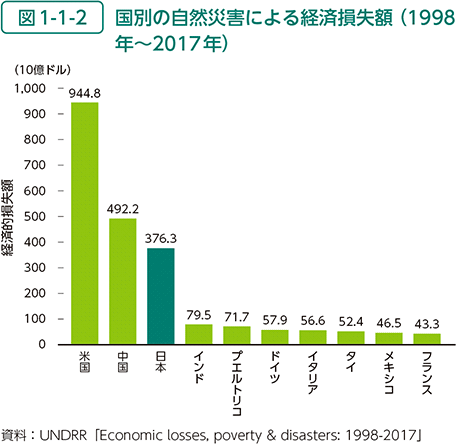
1998年~2017年の20年間の世界全体における自然災害発生件数は7,255件であり、このうち、洪水、暴風雨、干害、熱波などの気象災害が多くなっています。特に、洪水と暴風雨による被害が多く、その件数は前20年間に比べて2.2倍に増加しました(図1-1-3)。
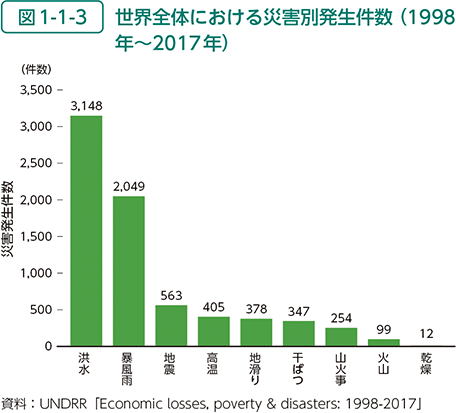
WMOによると、1970年から2019年までの50年間で1万1,000件以上の気象災害が発生し、200万人以上が死亡、経済損失は3兆6,400億ドルに達しています。2023年の我が国においては、「令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号」や「令和5年6月29日からの大雨」、「令和5年7月15日からの大雨」、「令和5年台風第7号」等により、広範囲で河川の氾濫等による被害が発生し、これらの災害による農林水産関係の被害額は1,928億円でした。
2023年に公表されたIPCC第6次評価報告書(AR6)統合報告書では、人為的な影響は1950年以降、熱波と干ばつが同時発生する頻度の増加を含む、複合的な極端現象の発生確率を高めている可能性が高いとしており、気象と気候の極端現象の増加によって、何百万人もの人々が急性の食料不安にさらされるとともに、世界の人口の約半分が現在、少なくとも1年の一部の期間、気候駆動要因及び非気候駆動要因に起因する深刻な水不足に陥っているとしています。また、約33~36億人が生活している気候変動に対する脆弱性が高い地域では、2010~2020年の洪水、干ばつ、暴風雨による人間の死亡率は、脆弱性が非常に低い地域と比べて15倍高かったと報告しています。さらに、人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことは疑う余地がないこと、継続的な温室効果ガスの排出は更なる地球温暖化をもたらし、考慮されたシナリオ及びモデル化された経路において最良推定値が短期のうちに1.5℃に達する、との見通しが示され、この10年間に行う選択や実施する対策は現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いことも指摘されました。
国立研究開発法人国立環境研究所らの研究グループは、パリ協定で定めた2℃目標を含む複数の異なる温室効果ガス排出の将来シナリオ、並びに異なる人口やGDPといった社会経済の将来状況の仮定の下での大規模なシミュレーションを実施し、地球温暖化によって生じる経済的な被害額の推計を行い、成果を公表しました。21世紀末における全世界での地球温暖化による被害額は、最も悲観的なシナリオ(SSP3-RCP8.5)において世界全体のGDPと比較して3.9~8.6%に相当するものであると推計されました。一方で、パリ協定の2℃目標を達成し、かつ、地域間の経済的な格差等が改善されるシナリオ(SSP1-RCP2.6もしくはSSP2-RCP2.6)においては、被害額は世界全体のGDPの0.4~1.2%相当に抑えられるという結果になっています。
温室効果ガスの排出削減や社会経済状況の改善といった人為的な要因と気候予測の不確実性が被害額の推計結果の差に対して寄与する割合についても明らかになっています。比較的近い将来(2020~2039年)においては、気候予測の不確実性が大きな割合を占めています。すなわち、仮に温室効果ガス排出削減等の地球温暖化対策を取ったとしても、その効果よりも、気候予測の不確実性の方が大きく、対策の効果は必ずしも明確ではないことを意味しています。しかし、この関係は21世紀の中盤には逆転し、人為的な要因の占める割合が大きくなっています(2050~2069年においては63%、2080~2099年においては78%)。これらの結果は、中長期的には、気候モデルの違いによる結果の不確実性を考慮してもなお、人為的な温室効果ガスの排出削減や社会経済状況の改善は、地球温暖化による被害を大きく軽減させる効果があることを示しています(図1-1-4)。
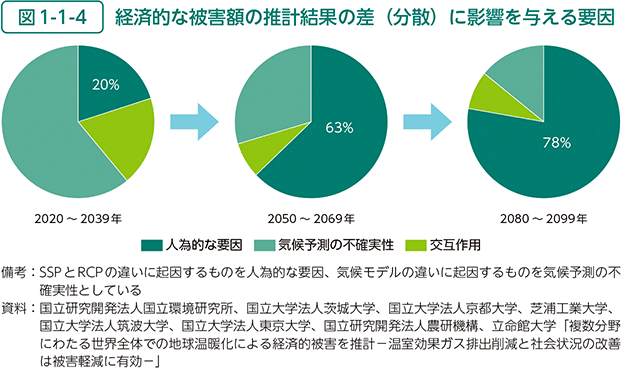
IPBESが2019年に公表した「生物多様性と生態系サービスに関する地球規模評価報告書」では全陸地面積のうち、人間活動による影響が最小限であり生態的及び進化的プロセスが機能している面積は25%程度に過ぎず、全世界の海洋のうち、人間活動の影響を全く受けていない面積はわずか3%であるとされています。また、過去50年間の地球上の種の絶滅は、過去1,000万年の平均の少なくとも数十倍、あるいは数百倍の速度で進んでいるとしており、地球全体の自然は人類史上かつてない速度で変化していると指摘しています。国際自然保護連合(IUCN)が2024年に公表した絶滅のおそれのある世界の野生生物のリスト、いわゆる「レッドリスト」の最新版では、絶滅危惧種の数は1年前と比較して約2,300種増え、合計で4万6,337種に上っています。
近年、このような生物多様性の損失は、自然資本の劣化とともに、社会経済的なリスクとして認識されており、2025年1月に世界経済フォーラム(WEF)が発表した「グローバルリスク報告書2025」では、向こう10年間で世界のGDPや人口、天然資源に甚大な影響を及ぼし得るリスクとして、生物多様性の損失及び生態系の崩壊が、異常気象に次いで第2位に位置付けられています。
コラム:様々な生態系における気候変動の影響
全国の約1,000か所の自然環境を毎年調査している「モニタリングサイト1000」事業では、日本を代表する生態系の変化状況を把握(モニタリング)しており、2024年10月には、これまでの20年間の調査で明らかになった日本の自然の変化・異変などの概要をまとめた「モニタリングサイト1000第4期とりまとめ報告書概要版」を公表しました。気候変動の影響として、陸域では、高山帯でのハイマツの生長量の増加、森林での暖かい気候を好む樹種の増加および寒い気候を好む樹種の減少、里地での南方系チョウ類の増加等の傾向が見られます。海域では、各地のアマモ場・藻場の衰退・消失が見られ、サンゴ礁では夏期の高水温が原因とみられる白化現象が頻繁に見られるようになっています。
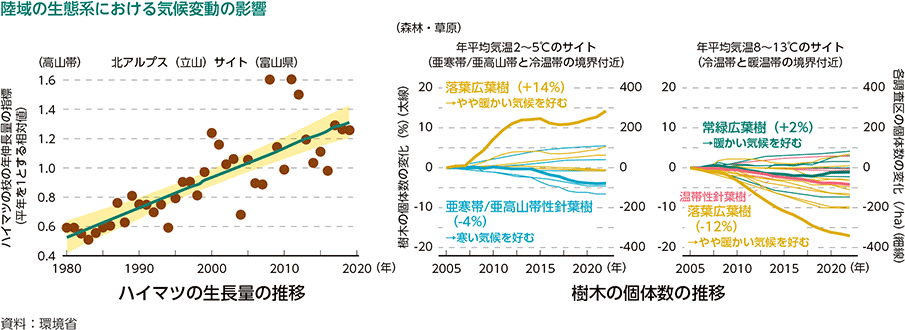
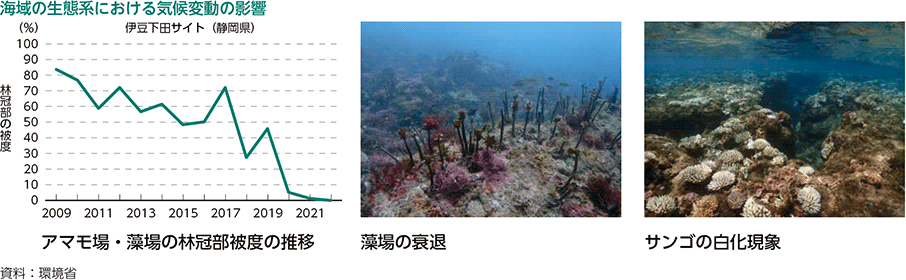
使い捨てを基本とする大量生産・大量消費型の経済社会活動は、大量廃棄型の社会を形成し、天然資源の消費を抑制し環境への負荷ができる限り低減される健全な物質循環を阻害するほか、気候変動問題、天然資源の枯渇、大規模な資源採取による生物多様性の損失など様々な環境問題にも密接に関係しています。例えば、国連環境計画国際資源パネル(UNEP IRP)の「世界資源アウトルック2024」では、世界の天然資源の採取と加工が、地球全体の温室効果ガス排出量の要因の55%以上、陸域の生物多様性の損失と水ストレスの要因の90%以上、粒子状物質による健康影響の要因の最大40%を占めており、これら採取・加工による気候及び生物多様性への影響は、気候変動を1.5℃未満に抑制し生物多様性の損失を防ぐための目標をはるかに超過していると指摘されており、資源効率性・循環性を向上させ天然資源利用の削減を進める取組は気候変動対策や生物多様性保全を始めとする環境負荷削減策としても極めて重要です。
循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、従来の延長線上の取組を強化するのではなく、経済社会システムそのものを循環型に変えていくことが必要です。具体的には、大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済・社会様式につながる一方通行型の線形経済から、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を推進することが鍵となります(図1-1-5)。環境制約に加え、産業競争力強化、経済安全保障、地方創生、そして、質の高い暮らしの実現によるウェルビーイングの向上にも資する循環経済への移行を進めることは、関係者が一丸となって取り組むべき重要な政策課題であり、バリューチェーン全体での徹底的な資源循環を促進する必要があります。