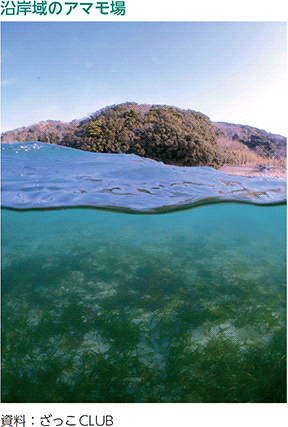私たちの暮らしは、森里川海からもたらされる自然の恵み(生態系サービス)に支えられています。かつて我が国では、自然から得られる資源が地域の衣・食・住を支え、資源は循環して利用されていました。それぞれの地域では、地形や気候、歴史や文化を反映した、多様で個性豊かな風土が形成されてきました。そして、地域の暮らしが持続可能であるために、森里川海を利用しながら管理する知恵や技術が受け継がれ、自然と共生する暮らしが営まれてきました。我が国の文化は、自然との調和を基調とし、自然とのつきあいの中で日本人の自然への感受性が培われ、伝統的な芸術文化や高度なものづくり文化が生まれてきました。しかし、戦後のエネルギー革命、工業化の進展、流通のグローバル化により、地域の自然の恵みにあまり頼らなくても済む暮らしに変化していく中で、私たちの暮らしは物質的な豊かさと便利さを手に入れ、生活水準が向上した一方で、人口の都市部への集中、開発や環境汚染、里地里山の管理不足による荒廃、海洋プラスチックごみ、気候変動問題等の形で持続可能性を失ってしまいました。さらに、海外への資源依存や急速な都市化の進展、人口減少・高齢化等によって、人と自然、人と人とのつながりが希薄化し、従来のコミュニティが失われつつあります。
国全体で持続可能な社会を構築するためには、各々の地域が持続可能であることが必要です。第六次環境基本計画においては、コミュニティの基盤である地域について、地域資源を活用した持続可能な地域づくりを通じて地域の経済・社会的課題の解決に結びつけ、環境・経済・社会の統合的向上を実践・実装していくことを重点戦略の一つに位置付けました。
私たちの消費行動を含むライフスタイルやワークスタイルにおいても、限られた資源を有効活用することで、天然資源の利用及び加工による環境負荷の削減を実現し、大量生産・大量消費・大量廃棄型の生産や消費に代わる、持続可能で健康的な食生活やサステナブルファッションなど持続可能な消費に基づくライフスタイル、ウェルビーイングの在り方を示すことが重要です。また、地域ならではの自然とそこに息づく文化・産業を活かした持続的な地域づくり等を推進する中で、各地域の自然が有する価値を再認識し、人と自然のつながりの再構築、人間性及び感受性の回復、健康増進、子どもの健全な発育等を推進することも重要です。そして、地域脱炭素の推進や循環経済への移行、地域の自然資本を活用したネイチャーポジティブの達成等の地域の環境課題と経済・社会的課題の同時解決に向けた取組は、地域コミュニティの再生、雇用の創出、地場産業の振興や高齢化への対応、生態系保全等地域課題の解決や地方創生の実現にもつながります。
第3章では、地域やそこに住んでいる人々の暮らしを、環境をきっかけとして豊かさやウェルビーイングにもつなげ得る取組を紹介します。
地域循環共生圏は、地域資源を持続的に活用して環境・経済・社会を統合的に良くしていく事業(ローカルSDGs事業)を生み出し続けることで地域課題を解決し続ける「自立した地域」を作るとともに、それぞれの地域の個性を活かして地域同士が支え合うネットワークを形成する「自立・分散型社会」を示す考え方です。例えば、再生可能エネルギーや里地里山からもたらされるバイオマス等の自然の恵みを始めとする地域の資源を持続的に活用し、地域の防災力の向上といった社会課題の解決や、地域の経済循環を強くし、雇用や所得を向上させることを通じて、脱炭素や資源循環、自然再興の取組と地域の経済・社会課題の同時解決を進めることで、持続可能な地域づくりを目指します。地域の主体性を基本として、パートナーシップの下で、地域が抱える環境・社会・経済課題を統合的に解決していくことから、ローカルSDGsともいいます(図3-1-1)。
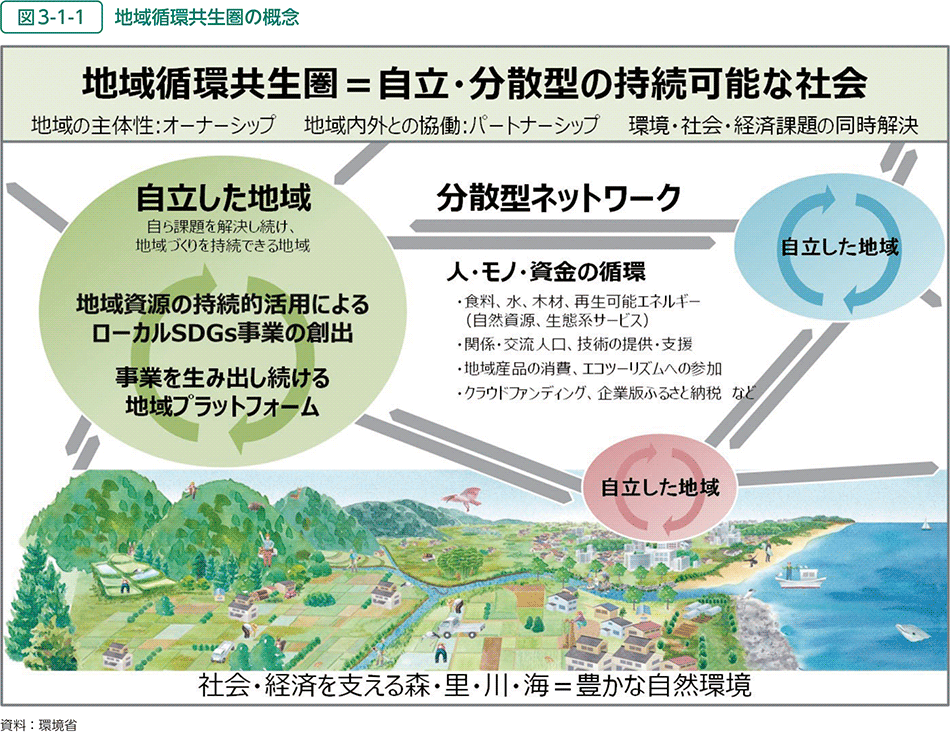
地域循環共生圏を創造していくためには、地域のステークホルダーが有機的に連携し、環境・社会・経済の統合的向上を実現する事業を生み出し続ける必要があります。環境省は2019年度から2023年度にかけて、「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業」を行い、ステークホルダーの組織化と、事業の構想作成を支援してきました。2024年度からは、「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業」を開始し、各地域での地域循環共生圏の創造に加え、地域循環共生圏づくりの支援ができる担い手の支援・創出を図っています。さらにこの事業の中で、地域循環共生圏に係るポータルサイトの運用も行っており、「しる」「まなぶ」「つくる」「つながる」機会等を提供することで、全国各地におけるローカルSDGsの実践を一層加速させています。
事例:NIIGATA MUSIC LABORATORY・社会事業化団体SHE『クロスオーバー』
NIIGATA MUSIC LABORATORYは「新潟を音楽の街に!」をテーマに、音楽を愛する人々が集まるコミュニティづくりを目指している団体です。地域循環共生圏づくりとして、「誰かのやりたいが希望になる」をテーマに、音楽や文化に対する一人一人の「やりたい」という思いが地域の新しい可能性となり、次の世代の希望となることを目指し、NEW HOPEプロジェクトを立ち上げています。このプロジェクトでは、新潟に暮らす様々な人が集い、コーヒー片手に地域について語り合う場「Coffee House」や、そこで出た課題について、自分たちで何ができるか語り合う場「アーダーコーダー」を開催しています。また、対面の場でのつながりをオンライン上でも続けられる場として、Slackも運用しています。こうした取組の中で、未利用魚の活用プロジェクトや、部活動の地域移行の受け皿づくりなどといった、地域課題・社会課題を解決する取組が次々と生まれてきています。
社会事業化団体SHEは、こうした取組を俯瞰で捉えながら、行政・地域・企業など様々な要素をつなぐ役割を担い、持続可能な地域づくりのために、例えば、「Coffee House」で参加者が活発に話せるような場づくりや、参加者から出てきた課題の整理・地域課題との結び付けへの支援等を行っています。こうした体制で、音楽や文化と環境づくりの融合を図り、共感のカルチャーをベースとして新しいライフスタイルと地域の活性化に取り組んでいます。


事例:一般社団法人フウド・一般社団法人HLL『21世紀型“さとうみエコシステム”』
一般社団法人フウドは、瀬戸内海広島湾の中心に位置する広島県江田島市において、人の暮らしが自然と共生していた時代に習いつつ、里海環境の保全を進め、その活動を支える経済システムを確立する仕組み、環境×社会×経済の循環による「21世紀型さとうみエコシステム」の構築に取り組んでいます。ブルーカーボンクレジット及びふるさと納税制度を活用したエコシステムの構築による豊かな海づくりや、島の資源を活用したアドベンチャーツーリズム、企業・団体向けの研修事業等を行い、域外からの資金獲得、人づくりと仕事づくりの好循環、自然にとっても人にとっても幸福度の高い島を目指しています。
こうした取組に対して、一般社団法人HLLは、地域マンダラを用いた意見交換等を通じて、地域の関係者の巻き込み・地域のビジョンづくり、事業アイデア・やりたいことの整理等を支援し、一般社団法人フウドの「風土の再生・再編集」というコンセプトの下、暮らしの中で大切にされている個人の感覚や感情に根差しながら、民間主体が単体では難しい事業活動や仕組みづくりを共に実現することを目指しています。
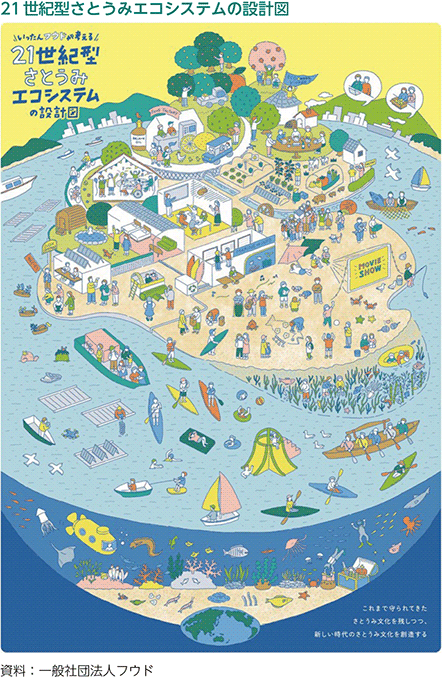

事例:佐賀県唐津市・GBPラボラトリーズ『唐津市版地域循環共生圏の実現』
唐津市は、地域ごとの特性を活かした新たな取組が創造されていくエコシステムを構築し、外部環境の変化に対応しながら地域が発展していく持続可能な社会の実現を目指しています。具体的には、多様な主体が積極的に連携・協力し自然資本と調和した多様なビジネスが創出/共創される街づくりを目指して、ブルーカーボン、ネイチャーポジティブ、海洋プラスチック、資源循環、再生可能エネルギー等のテーマで地域の関係者間で集まり、ありたい姿の共有、その実現に当たって不足している要素等の意見交換を深めています。こうしたプラットフォームでの議論から、プロジェクトの立案・事業化を行い、市域内外の企業や研究機関等との連携を強化し唐津市版地域循環共生圏の実現を目指しています。
こうした取組に対して、一般社団法人GBPラボラトリーズは、社会の動向や国の政策等の大きな流れを汲んだ唐津市の目指す姿の整理、関係者との協力体制の築き方・運営の継続方法等のプラットフォームの仕組みづくりに関する助言・支援、具体のプロジェクトに対する同時解決・協働の視点のインプット、地域外の人やリソースとの連結等の支援を実施し、中長期的視点での課題解決を目指しています。


環境省が主催するグッドライフアワードは、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」に関わる取組を表彰することによって、SDGsを体現する取組を応援するとともに、広く社会に発信するプロジェクトです。企業・学校・NPO・地方公共団体・地域・個人など多くの応募の中から、毎年「環境大臣賞」と「実行委員会特別賞」が決定され、これまで表彰された取組は400件を超えます。地域循環共生圏の「見本市」として様々な場面で発信するとともに、関係者のパートナーシップを強化することでグッドライフの輪を広げ、地域循環共生圏の創造につなげていきます。
事例:環境循環型農業を実践し、育てる人、作る人、食べる人の顔が見える関係を目指す取組(ヤマキ醸造)
農業生産法人を組織し、有機栽培・特別栽培など環境循環型の栽培方法にこだわり、自社で生産した原料を用いて昔ながらの方法で味噌・醤油・豆腐・漬物を製造し、既存品を活かしたアップサイクル商品の商品開発、そして製造の過程で発生する副産物を有効活用して廃棄ゼロを達成しました。
自社にて太陽光発電からエネルギーを作り、工場稼働などに使用しています。また地元の生協組織と大豆トラスト運動やNPO法人と共に水を育む森林保全の活動などを行っています。

事例:「終わらない服をつくろう。」お客様と共に歩むグッドライフなエコ活動の取組(青山商事)
大量生産・大量廃棄への対応として、1998年から始まった不要衣類の回収と資源循環の取り組みを進化させ「WEAR SHiFT」リサイクリングBOXを全国の店舗に設置し、顧客と共に歩むエコ活動を推進するとともに、服から服へ、循環型リサイクルにもチャレンジしています。また、回収衣類の一部を用いて災害支援用リサイクル毛布を作製し大規模災害に見舞われた自治体へ寄贈、衣料の回収量に応じた森林保全活動への寄付を通して「AOYAMAの森」づくりに取り組んでいます。

事例:びっくりドンキーの生きものにも優しいお米~契約産地での生きもの調査実施率100%!~の取組(アレフ)
ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」で提供するお米は全量契約栽培を行い、農薬使用は除草剤1回以下で畔を含め殺虫剤の使用は禁止という独自の厳しい基準に加え、生産者自身の水田の「生きもの調査」を義務化しています。
この調査を通して、カエルやトンボ等の水生の幼生が成体になるまで水田の中干し開始時期を延期したり、水生生物が行き来することができるよう排水路と水田をつなぐ魚道を設置したりするなど、生物多様性に配慮した取組を契約産地で推進しています。

事例:里山再生「我田の森」プロジェクトの取組(里山クラブ可児)
岐阜県可児市東部の里山で活動する「里山クラブ可児」は、2000年4月に発足し、同市久々利地区にある「我田の森」を拠点として、四半世紀にわたり里山の再生・維持・保全等の活動を行っています。
耕作されなくなった棚田を、田んぼビオトープとして再生させ、一年中水を張りながら、耕さず農薬を使わない米作りを行います。ここでは、田植え・稲刈り・餅つきと一連の作業を体験するワークショップを地域の親子に提供しています。
また、里山を維持する活動も活発です。森の整備により出た木材を用い、原木椎茸作りなどを行い、畑ではオーガニックな野菜を栽培し、季節の恵みを分かち合います。
協賛団体は、企業から行政、大学から幼稚園までと幅広く、多様なパートナーと連携して共に活動を行っています。

事例:再生可能エネルギーで輝く「おおなん成長戦略」(島根県邑南町)
2030年度までにネット・ゼロ実現を目指す脱炭素先行地域の一つ島根県邑南町では、地域新電力「おおなんきらりエネルギー株式会社」が、住宅や民間事業者等に太陽光発電・蓄電池を設置し自家消費を進めています。加えて、オフサイト太陽光発電の再エネ電力を地域内に供給することにより、地域外へ流出していた電気料金の地域内循環を目指しています。さらに、スマート農業を推進すると同時に、ビニールハウスのエネルギー源や農耕具の電化、省エネ性能の優れた道の駅の建設など、CO2排出削減と農業振興を同時に進めています。
また、ふるさと納税・企業版ふるさと納税の使途に「エネルギーの地産地消による環境と経済を両立したまちづくり」を設け、脱炭素先行地域エリア外でのPPA希望者の財源確保を図っています。

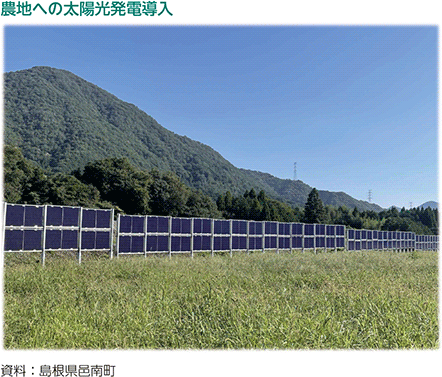
コラム:「環境教育・ESD 実践動画100選」
持続可能な社会を実現するためには、現代社会における様々な問題を、自らの問題として主体的に捉え、取り組むことが求められます。そのような問題の解決につながる新たな価値観や行動等の変容をもたらす社会づくりを目指して行われる教育が、環境教育・持続可能な開発のための教育(ESD)であり、その実践を社会に広げていくことが重要です。環境省では、現場での実践や学びのヒントになるよう、環境教育・ESD 実践の優良事例の動画を「環境教育・ESD 実践動画100選」として選定し、優良事例のショーケースとして広く発信しています。
2024年度の社会教育部門に選定された「ハーベスト」を制作した加山興業では、廃棄物処理事業を行う同社が、環境に悪影響を与えていないか確認をするため、環境指標生物としてミツバチを飼育しています。選定された動画では、飼育するミツバチの観察や採蜜体験を通じて、地域の方々も巻き込みながら活動している様子を紹介しています。
同社は、「生物多様性のための30by30アライアンス」への参加や、環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成15年法律第130号)第20条に基づく認定「体験の機会の場」での体験の機会を提供しており、廃棄物の適正処理と生物多様性をつなげ、環境教育・ESDの推進に向けて取り組んでいます。
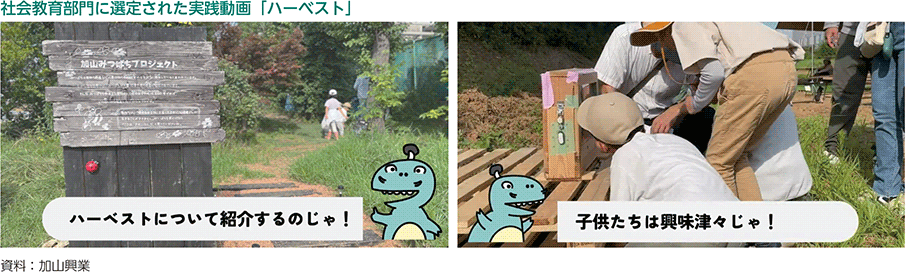
持続可能な社会を構築し次世代に引き継ぐためには、良好な環境を目指すとともに、人々がその良好な環境とふれあい、持続可能な形で利用することにより、地域のウェルビーイングや地域の魅力度の向上、持続可能な観光等の地域活性化の実現など、地域に具体的なメリットを創出することが重要です。この実現のため、豊かな水辺、星空、音の風景等、地域特有の自然や文化を保全・再生・創出するとともに持続的な利用を促進する取組や、水道水源となる森や川から海に至るまで、良好な環境の創出に取り組む地域を連結した流域一体的な保全のモデルの構築、藻場・干潟の保全・再生・創出の促進と地域資源としての利活用との好循環を目指す里海づくりなどを実施しています。
コラム:良好な環境の創出活動
環境省では、規制等による施策と並行して、これまで「名水百選」や「平成の名水百選」、「残したい“日本の音風景百選”」等により、健全な水循環の維持・回復についての理解醸成や、豊かな水辺や星空、音の風景など地域特有の五感で感じる自然や文化といった「良好な環境」の保全にも取り組んできました。「良好な環境」は、きれいな水を活用したそば、わさび、酒づくり等の地場産業や観光の振興など、地方創生の重要な要素にもなっています。
しかし、近年、「良好な環境」が荒廃しつつある地域や、良好な環境の保全活動の継続が資金不足や担い手不足等により困難となる地域も見られます。
このような状況の中、地域における「良好な環境」を保全するだけでなく、積極的に再生・創出し、持続可能な形で利活用することにより、地域課題の解決への貢献とともに、人々のウェルビーイングや地域の魅力度の向上、地域活性化の実現が期待されています。


コラム:令和の里海づくり
瀬戸内海を始めとした閉鎖性海域及び、各地の沿岸域では、高度経済成長期における産業の近代化、都市化に伴い、藻場・干潟の埋め立て、河川や沿岸海域における水質汚濁が急速に進行し、「瀕死の海」とも呼ばれる状況にまで悪化してしまう海域もありました。そのため、環境省では排水規制等に取り組んできたところ、現在では、一定の水質改善が達成されています。一方で、豊かな海を実現するには、生物の生息場になる環境の保全等の取組が重要になりますが、「瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)」の基本理念では、豊かな海を目指していくことが明記されました。瀬戸内海を豊かな海とするために、2022年度から地域の里海づくりを支援することで好事例モデルを創出することを目的に「令和の里海づくり」モデル事業を実施しています。
当モデル事業は、気候変動の影響による水温上昇等による海域環境の変化も著しい中、現在では、瀬戸内海のみならず全国の沿岸域等で行われる里海づくりが、地域の様々な課題の同時解決を図り、かつ持続可能な取組となることを目指すものです。具体的には、藻場・干潟の保全・再生・創出と、地域資源の利活用の好循環を生み出すことを目的とした里海づくりを通じて、依然として発生する赤潮、資源の枯渇、人口減少、地域への理解増進、海洋人材の育成といった、沿岸域の環境を取り巻く様々な課題を解決していく好事例を創出していきます。