我が国は2050年ネット・ゼロの実現という目標を掲げていますが、我が国の温室効果ガス排出量を消費ベースで見ると、全体の約6割が家計によるものという報告があり、私たち一人一人が温室効果ガスの削減に取り組んでいく必要があります(図3-2-1)。そのためには、「住まい」「移動」「食」「ファッション」の側面から、温室効果ガスの排出量を減らし、廃棄物を減らして3R+Renewableによる資源循環や自然資源を大事にする視点でライフスタイルを変えていくほか、私たち全員が自らの課題として身近なところから行動することを目指すとともに、私たち一人一人の行動変容から社会や組織の変革を連動的に促すことで、持続可能な社会への転換を実現することが必要です。
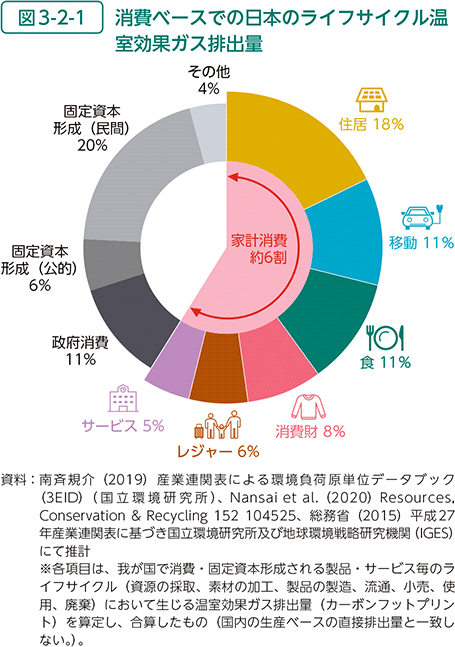
2050年ネット・ゼロの実現に向けては、暮らし、ライフスタイル分野でも大幅なCO2削減が求められます。そこで、環境省では、国民・消費者の行動変容、ライフスタイル転換を促すため、2022年10月に新しい国民運動(脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動)を開始し、2023年7月に「デコ活」を愛称として決定しました。
「デコ活」では、衣食住・職・移動・買い物など、生活全般にわたる国民の将来の暮らしの全体像「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしの10年後」を提案し、自治体・企業・団体等とも連携しながら、国民の脱炭素につながる豊かな暮らし創りに向けた取組を展開しています(図3-2-2)。
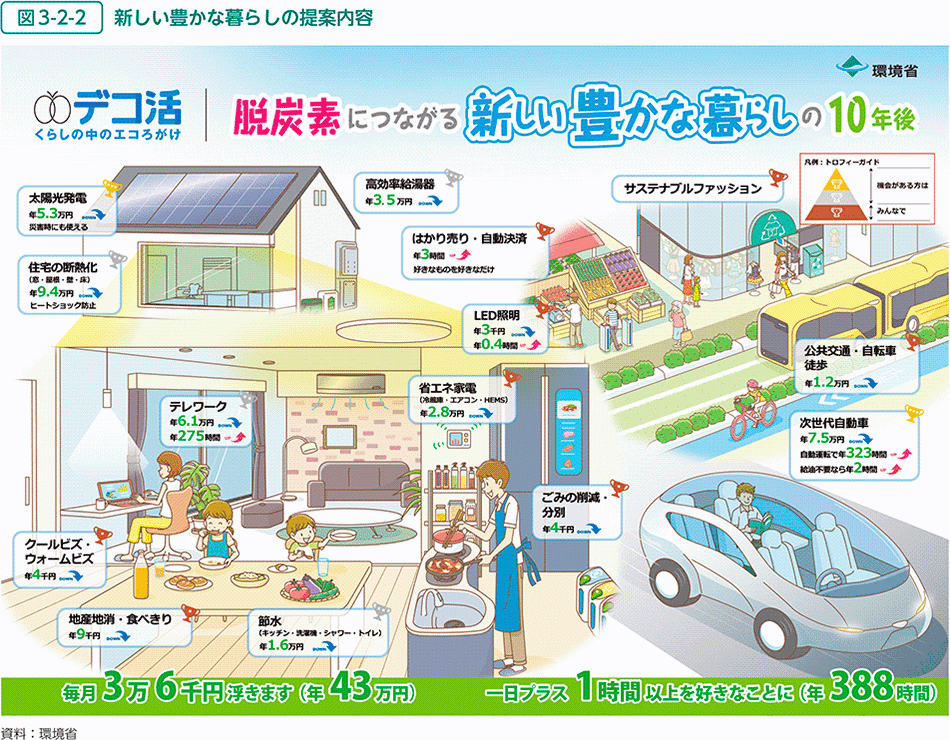
また、「デコ活」の開始と同時に発足した官民連携協議会(デコ活応援団)に参画している自治体・企業・団体等とも連携しながら、国民の豊かな暮らし創りを後押しすることで、ライフスタイル転換と併せて新たな消費・行動の喚起と国内外での製品・サービスの需要創出を推進しており、2024年には連携協働型の社会実装プロジェクトであって、需要サイドのボトルネックを構造的に解消する仕掛けを国民に提供する事業に対する補助制度を創設しました。
デコ活の具体的な取組の一つとして、WEBサイトにおいて、自治体・企業・団体等より登録いただいた情報を以下の4つの切り口で発信することにより、国民の豊かな暮らし創りを後押ししています。
[1]デジタルも駆使した、多様で快適な働き方・暮らし方の後押し(テレワーク、地方移住、ワーケーション等)
[2]脱炭素につながる新たな豊かな暮らしを支える製品・サービスの提供・提案
[3]インセンティブや効果的な情報発信(気づき、ナッジ。消費者からの発信も含め)を通じた行動変容の後押し
[4]地域独自の(気候、文化等に応じた)暮らし方の提案、支援
(2025年3月時点の掲載数:[1]デジタル関係:62件、[2]製品・サービス関係:266件、[3]インセンティブ関係:167件、[4]地域関係:48件、計543件(複数カテゴリにまたがるものも有))
さらに、国民の暮らしを豊かにより良くする取組として、[1]デ・コ・カ・ツにちなんだ“まずはここから”4アクションを筆頭に、[2]“ひとりでにCO2が下がる”3アクション、[3]“みんなで実践”する6アクションの計13アクションを決定し、日常における一人ひとりのデコ活の実践の呼びかけを行っています(図3-2-3)。
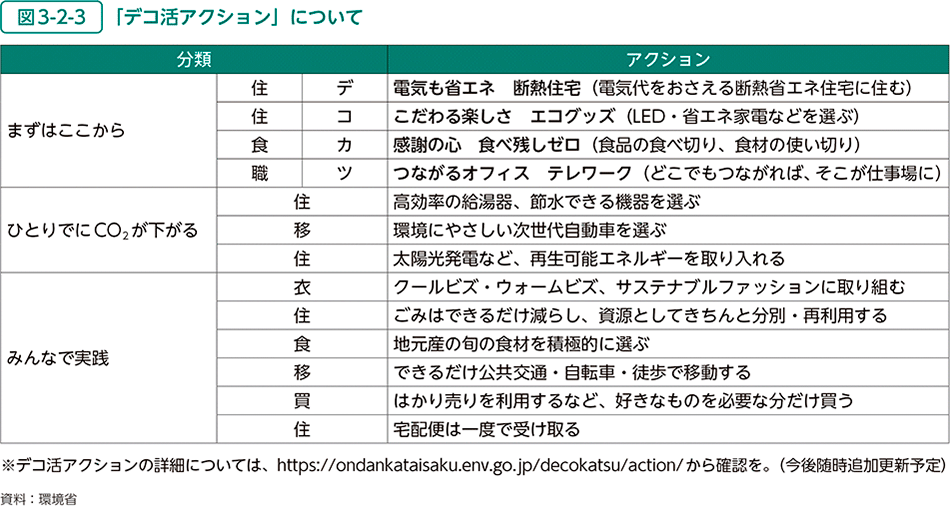
このほか、「デコ活」の普及浸透のため、組織(自治体・企業・団体)、個人単位で「デコ活宣言」を呼びかけるとともに、日々のデコ活の取組を「#デコ活」としてSNS等で発信し、広めていただくこともお願いしているほか、従業員・職員含む個人・自治体・企業・団体の方から「私の/私たちの/我が社の/我が町のデコ活アクション」標語を考えていただき、各部門の中から環境大臣賞を選定・表彰する「デコ活アクション大喜利大会」を開催するなど、様々な施策を展開しています(図3-2-4)。
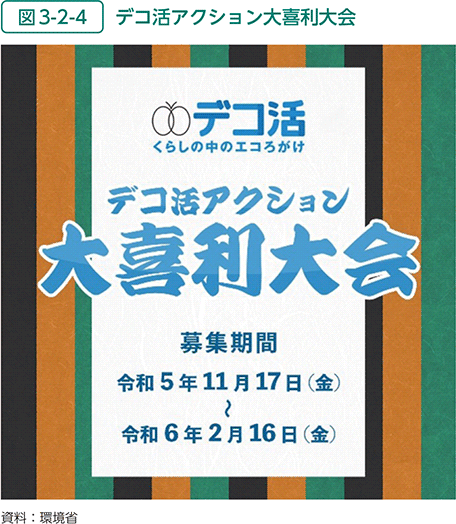
今後は、2024年2月に公表した「くらしの10年ロードマップ」の進捗把握のため、取組状況に関する消費者アンケート調査を実施し、国民の生活全般における行動変容・ライフスタイル転換に向けた課題・ボトルネックの構造的な解消のため、「デコ活関係予算」等も活用しながら、官民連携の取組を効果的に促進するなど、あらゆる機会を捉えてデコ活を推進していきます。
事例:昼の再エネ余剰電力を活用した便利・快適・お得な暮らしの実現に向けて~「デコ活」における実証事業~
近年、再エネの導入拡大により出力制御エリアは全国に拡大し、電力需要の減少等の影響により、足元の出力制御量は増加傾向にあります。この状況を改善する方策の一つとしては、昼間の電力需要を創出することが効果的です。このため、デコ活では、昼の余剰電力を有効活用する新しい暮らしのあり方の絵姿を描いた上で、昼の電力利用への行動変容と、それによる生活者の利益・利便性を訴求すべく、昼間の電力需要の創出に向けて、ディマンド・リスポンス(Demand Response:DR)(消費者が賢く電力使用量を制御することで電力需要パターンを変化させること)のうち、「上げDR」を促し、昼の電力利用へのシフトに向けた効果や消費者の利益について検証するため、2つの実証事業を実施しました。
〔1〕IoT機器を活用し、蓄電池・エコキュート・EV等を所有する家庭を対象にしたHEMS機器等を用いた機器制御型DRと、手動で制御する行動変容型DRの実証事業を実施しました。HEMSを活用した住宅用エネルギー機器(蓄電池・エコキュート・EV)の自動制御により平均0.759kWh/回の電力需要創出が達成され、手動制御(0.437kWh/回)と比較して高い上げDRの効果を持つことが確認されました。また、自動制御による経済便益が最も大きくなる場合において、実証期間中に世帯あたり最大約2,400円程度の消費者便益を得られる可能性があることが確認されました。一方、機器登録設定の煩雑さや、電力会社提供の報酬とユーザーの期待値の乖離など、社会実装に向けた課題も明らかになりました。
〔2〕市場連動型電気料金プランを活用した行動変容型DR、蓄電池・洗濯乾燥機等をIoT機器を活用して自動制御する機器制御型DRの実証事業を実施しました。市場連動型電気料金プランを活用した行動変容型DRの実証では、秋の平均上げDR量は0.04kWh/30分~0.51kWh/30分、冬では0.04kWh/30分~0.48kWh/30分の範囲でDR効果が確認されました。家庭用蓄電池を活用した機器制御型DRの実証では、太陽光発電の売電価格が高い時間に蓄電し安い時間に消費する蓄電池の導入により、太陽光発電の自家消費を最大化する蓄電池を導入した場合と比べ、月平均400円程度の追加的な電気代削減が可能であることが示されました。一方、アンケート等において、「自分で制御できない」、「経済メリットが分からない」、「停電時の残量不足」といった市場連動制御に対する不安が多く挙げられました。今後の普及に向けては、対象者自身での操作や選択を可能にすること、アプリ等での経済メリットの提示、一定の蓄電池残量を残す等の方法が有効であると考えられます。洗濯乾燥機等を活用した機器制御型DRの実証では、指ロボットによる家電の遠隔制御を行い食器洗い乾燥機は0.46円~1.27円/回、浴室乾燥機は1.77円~3.29円/回、洗濯乾燥機は0.55円~6.78円/回で変動することが確認されました。対象者が希望する電気代削減額はインタビュー結果によれば月平均551円であり、実証結果と大きな乖離が見られるが、電気代削減額が少額でも、家電の遠隔制御等の利便性向上があれば、サービス受容度が向上する可能性が示唆されています。指ロボットの取付けは、家電により設置が難しいものや複数必要になる場合があり、指ロボットを使用せずに遠隔制御が可能な仕組みの構築が必要であると考えられます。
本実証結果をもとに国民・消費者に対して昼の電力利用へのシフトの利益やメリットを提示し、脱炭素につながる豊かな暮らしの実現と2050年ネット・ゼロの実現に向けた取り組みを推進していきます。
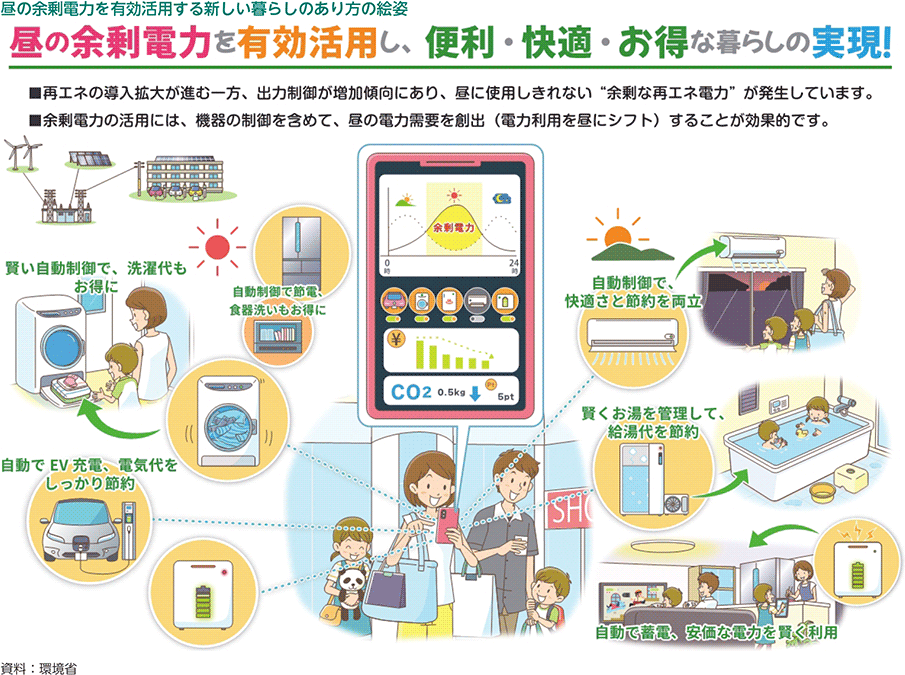
消費ベースで見た我が国の温室効果ガスの排出量において、生活者の住まいからの排出は全体の18%を占め(図3-2-1)、民間の固定資本形成に次いで高いとの報告があり、2050年ネット・ゼロを目指す上で生活者の住まい、中でもエネルギーの利用の見直しは必要です。
2050年ネット・ゼロの実現に向けて、経済産業省、国土交通省及び環境省は連携して省エネ性能に優れた住宅に対する補助を実施しています。特に数の多い既存住宅について、断熱性能の高い窓への改修等による省エネ化を進めるとともに、2024年度からはZEH(ゼッチ)基準の水準を大きく上回る省エネルギー性能を有する住宅の新築に対する補助事業を創設するなど、取組を強化しています。
「省エネライフ」とは、太陽光発電設備、断熱リフォーム、高効率給湯器、省エネ家電、節水機器を設置・工事をすることで、自宅の住環境を快適にするだけでなく、月々の光熱費を削減することができ、さらにはCO2排出削減にも貢献できる暮らしのことです。
環境省では、2023年10月から「省エネライフキャンペーン」を展開しています。本キャンペーンでは、デコ活アクションの中でも、家庭の省エネ対策としてインパクトの大きい、ZEH(ゼッチ)化・断熱リフォーム、省エネ家電への買換え等を補助金情報やデコ活に賛同する企業等の情報と併せて呼び掛け、国民一人一人の行動変容を促していくことにより、脱炭素で快適、健康、お得な新しいライフスタイルを提案しています。
家庭での脱炭素電力使用には、太陽光発電設備等を自宅に設置する以外にも、家庭で使用する電力を脱炭素電源由来のものにする方法があります。
現在、全国では、複数の小売電気事業者が太陽光や風力等の再生可能エネルギー由来の電力メニュー等を一般家庭向けに提供しています。また、電力需要が比較的少なくなる季節の昼間に太陽光等の再生可能エネルギーの出力が抑制される問題が各地で次第に顕在化する中、一部の小売電気事業者では、昼間に電力需要のピークをシフトする世帯に料金割引やポイント等のインセンティブを付与する取組を開始しています。脱炭素電源由来の電力メニューを選択する家庭が増えることにより、家庭部門からの排出削減に加え、脱炭素電力に対する需要が高まり、市場の拡大を通じて脱炭素電源の更なる普及拡大につながることが期待されます。
脱炭素電力を選択する家庭を増やすための地方公共団体による支援も広がっています。電力切替え希望者を広く募ってまとめて発注したり、競り下げ方式の入札で契約事業者を決定したりすることで、個別の契約よりも安い料金で契約できる取組等も行われています。
消費ベースで見た我が国の温室効果ガス排出量において、生活者の移動時に伴う温室効果ガスの排出は我が国全体の11%を占めるとの報告があり(図3-2-1)、グリーン社会を目指す上で住まいと同様、対策が必要な分野と言えます。世界ではガソリン車の販売禁止が加速しており、脱炭素社会に向けた新たな競争が始まっています。このような、世界的な電動化の流れに乗り遅れることがないよう、我が国でも自動車産業の電動化を後押しするとともに、私たち一人一人のライフスタイルの転換を進めていくことが大切です。日常生活を送る上で必ず伴う移動手段はとかく習慣・固定化しがちです。中でも乗物の利用時にはCO2排出度合いを考慮することも重要です。
再生可能エネルギー電力と電気自動車(EV)等を活用したドライブを「ゼロカーボン・ドライブ(ゼロドラ)」と名付け、家庭や地域、企業におけるゼロドラの取組を応援しています(図3-2-5)。
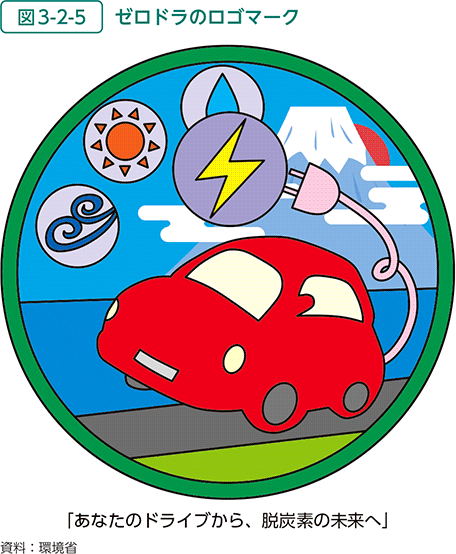
私たちが毎日口にしている食べ物は自然の恵みで作られており、私たちは「食」のために自然資源を毎日消費しているともいえます。限りある自然資源を未来につなげるために、毎日自分が消費する食べ物がどのように作られたのか、食した後の結果等にも関心を払い、食べ物の選択や食べ残しを減らすライフスタイルを意識することが重要です。
「第2次食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」(令和7年3月閣議決定)においては、更なる食品ロス削減の取組が進むよう「食べ残し持ち帰りガイドライン」に基づく消費者の自己責任を前提とした持ち帰りの周知、納品期限等の商慣習の見直し、食品寄附活動の社会的信頼の向上と活動定着のための「食品寄附ガイドライン」の普及啓発などの具体的な施策が取りまとめられました(図3-2-6)。
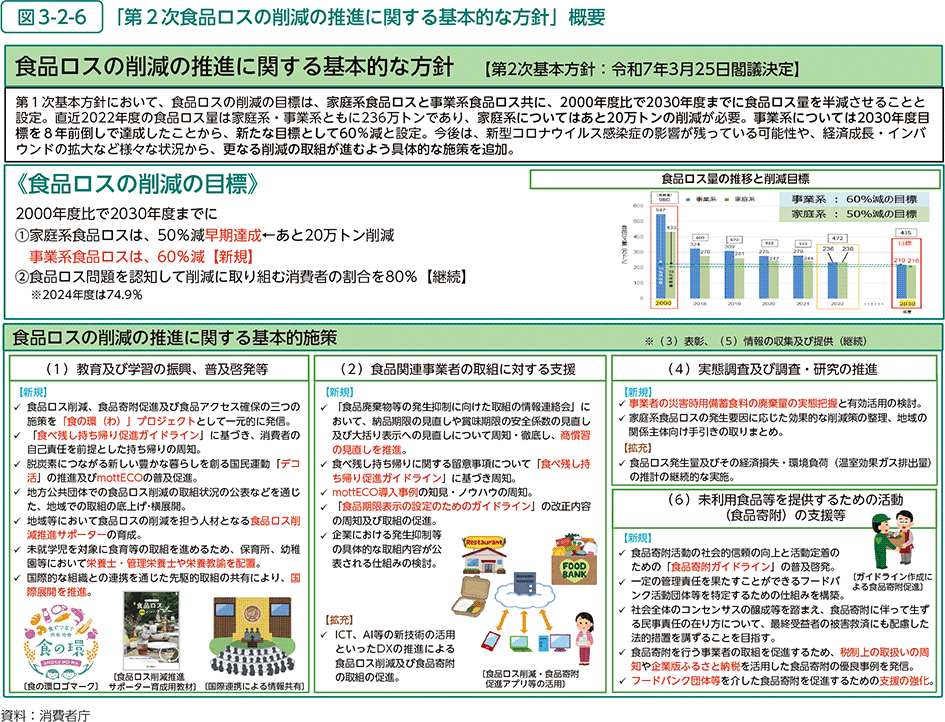
また、「食品ロス削減」や「食品寄附促進」に加え、「食品アクセスの確保」に向けた取組を、関係府省庁や地方公共団体が一体的に取り組めるように、三つの施策を包括する概念を「食の環(わ)」と呼ぶことについて2024年6月に関係府省庁で申合せをし、共通のロゴマークを使用して、一元的に発信していくこととしました(図3-2-7)。

食品産業から発生する食品ロスを削減するためには、食品事業者における取組のみならず、消費者による食品ロス削減への理解と協力が不可欠です。消費者が買い物をする際、購入してすぐに食べる場合などは、商品棚の手前にある商品等、販売期限の迫った商品を選ぶ「てまえどり」をすることは、販売期限が過ぎて廃棄される食品ロスを削減する効果が期待できます。
環境省は、消費者庁、農林水産省、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会と連携して、食品ロス削減月間(10月)に合わせて「てまえどり」の呼びかけを行いました(図3-2-8)。また、2022年12月にはユーキャン新語・流行語大賞トップ10に選出されるなど「てまえどり」の普及・認知が進んでいます。

本来食べられるにもかかわらず廃棄されている食品、いわゆる「食品ロス」の量は2022年度で約472万トンでした。食品ロス削減のため、環境省は、消費者庁、農林水産省及び全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会と共に、2024年12月から2025年1月まで、「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施し、食品ロス削減の普及啓発を行いました。外食時には、残さず食べきることが大切ですが、どうしても食べきれない場合には自己責任の範囲で持ち帰る「mottECO(モッテコ)」に取り組む活動の普及啓発を実施しています(図3-2-9)。
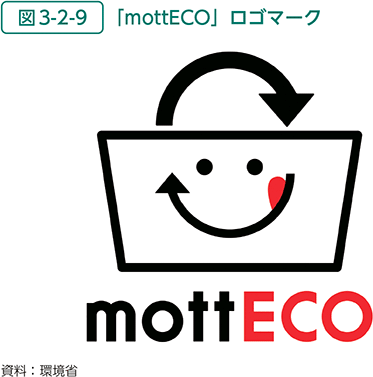
また、環境省、消費者庁では、食品ロスの削減に先駆的に取り組み、国民運動をけん引する団体等を対象に「令和6年度食品ロス削減推進表彰」を実施しました。企業、団体、学校、個人など様々な主体から計81件の応募があり、環境大臣賞には味の素による「フードロス削減プロジェクト『TOO GOOD TO WASTE~捨てたもんじゃない!~™』を通じた生活者の行動変容の促進と協業によるローカルなエコシステム構築への貢献」、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)賞には一般社団法人全国フードバンク推進協議会による「全国のフードバンクと連携した食品寄附促進・食品ロス削減推進事業」が選ばれました。
ファッション産業は、世界全体で水を大量に消費し、温室効果ガスを大量に排出するなど、近年、環境負荷が大きい産業と指摘されるようになりました。
また、生産過程における労働環境の不透明性も課題とされています。経済産業省の「2030年に向けた繊維産業の展望(繊維ビジョン)」によると、我が国の衣料品の約98%が輸入であり、このような環境負荷と労働問題の大部分が海外で発生しています。2022年度に環境省が実施した調査では、1年間に新たに国内に供給される量の約92%が使用後に手放され、約64%はリユースもリサイクルもされずに廃棄されています。このような現状を変革するため、サステナブルファッションの推進が求められています。我が国においても、適正な在庫管理とリペア・アップサイクル等による廃棄の削減、回収から製品化までのリサイクルの仕組みづくり等の企業の取組が進んでいます。2021年8月に消費者庁、経済産業省、環境省による「サステナブルファッションの推進に向けた関係省庁連携会議」を立ち上げ、政府一丸となって取り組む体制を構築、連携をしています。消費者庁は消費者向けの啓発及び人材育成、経済産業省は繊維リサイクル等の技術開発の支援及び環境配慮設計の在り方の検討、環境省は企業と家庭から排出される衣類の量及び回収方法の現状把握、使用済み衣類回収のシステム構築に関するモデル実証事業の実施等、各省庁の視点から関連する取組を進めています。
さらに、経済産業省と環境省は、2023年1月に「繊維製品における資源循環システム検討会」を立ち上げ、「回収」「分別・再生」「設計・製造」「販売」の4つのフェーズにおける、繊維製品の資源循環システムの構築に向けた課題の整理と取組の方向性を議論し、同年9月にその報告書を取りまとめました。これを受け、経済産業省では、産業構造審議会 繊維産業小委員会において取り組むべき具体的な政策について議論を行い、2024年6月に、「繊維産業におけるサステナビリティ推進等に関する議論の中間とりまとめ」、「繊維製品における資源循環ロードマップ」を公表・策定しました。また、2024年3月には「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」、同年6月に「繊維・アパレル産業における環境配慮情報開示ガイドライン」をそれぞれ策定し、ガイドラインの普及に向けた取組を推進しています。
我が国で売られている衣料品の約98%は海外からの輸入品です。海外で作られた衣料品は我が国に輸送され、販売・利用されて、回収・廃棄されます。こうした原材料の調達、生地・衣服の製造、そして輸送から廃棄に至るまで、それぞれの段階で環境に負荷が生じています。海外における生産は、数多くの工場や企業によって分業されているため、環境負荷の実態や全容の把握が困難な状態となっています。
私たちが店頭で手に取る一着一着の洋服、これら服の製造プロセスではCO2が排出されます。また、原料となる植物の栽培や染色等で大量の水が使われ、生産過程で余った生地等の廃棄物も出ます。服一着を作るにも多くの資源が必要となりますが、大量に衣服が生産されている昨今、その環境負荷は大きくなっています。
手放す枚数よりも購入枚数の方が多く、一年間一回も着られていない服が1人当たり35着もあります。
生活者が手放した服がリユース・リサイクルを通じて再活用される割合の合計は約34%となっており、年々その割合は高まってきていますが、更にリユース・リサイクルを推進する必要があります。
家庭から服がごみとして廃棄された場合、再資源化される割合は5%ほどでほとんどはそのまま焼却・埋め立て処分されます。その量は年間で約44.5万トン。この数値を換算すると大型トラック約120台分を毎日焼却・埋め立てしていることになります。
サステナブルファッションを実現していくためには、環境配慮製品の生産者を積極的に支援するとともに、生活者も一緒になって、「適量生産・適量購入・循環利用」へ転換させていくことが大切です(図3-2-10)。具体的には、以下の5つのアクションが挙げられます。まずはできることからアクションを起こしていくことが大切です。
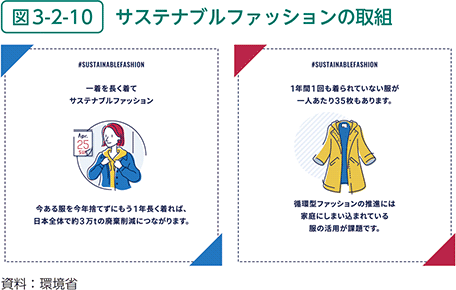
[1]服を大切に扱い、リペアをして長く着る
[2]おさがりや古着販売・購入などのリユースでファッションを楽しむ
[3]可能な限り長く着用できるものを選ぶ
[4]環境に配慮された素材で作られた服を選ぶ
[5]店頭回収や資源回収に出して、資源として再利用する