気候変動問題は世界全体で取り組むべき喫緊の課題です。我が国は、世界全体での1.5℃目標と整合的な形で、「2050年ネット・ゼロの実現」という目標を掲げ、この実現に向けて、「2030年度46%削減、さらに50%の高みに向けた挑戦の継続」、「2035年度60%削減」、「2040年度73%削減」という目標を掲げており、2023年度時点で2013年度比27.1%削減と着実に実績を積み重ねてきています。目標の実現に向けて、2025年2月に改定された地球温暖化対策計画及びエネルギー基本計画、さらには同月GX推進戦略を改訂する形で新たに策定されたGX2040ビジョン等に基づき、徹底した省エネルギーの推進に加え、再生可能エネルギーや原子力等の脱炭素電源を最大限活用するとともに、脱炭素成長型経済構造移行債を活用した20兆円規模の先行投資支援や、排出量取引制度の2026年度からの本格稼働等を始めとする成長志向型カーボンプライシング構想の速やかな実現・実行等、引き続きあらゆる施策を総動員していきます。
一方、2050年ネット・ゼロ実現に向け、気候変動対策が世界全体として着実に実施され、世界の気温上昇が1.5℃程度に抑えられたとしても、熱波のような極端現象や大雨等の変化は避けられないことから、現在生じている、又は将来予測される被害を回避・軽減するため、気候変動への適応や気候変動の悪影響に伴う損失及び損害(ロス&ダメージ)への対応についても、緩和策と同様に喫緊の課題として取り組むことが必要です。このため、多様な関係者の連携・協働の下、気候変動適応法及び気候変動適応計画を礎として気候変動適応策を着実に推進していきます。
我が国が有する技術・ノウハウを活用し、官民で連携しながら、世界規模でのネット・ゼロの実現に貢献するとともに、新たな市場・需要を創出し、我が国の産業競争力を強化することを通じて、経済を再び成長軌道に乗せ、将来の経済成長や雇用・所得の拡大につなげることが求められています。
2050年ネット・ゼロの実現に向けて、特に地域の取組と密接に関わる「暮らし」や「社会」分野での施策を中心に取りまとめた「地域脱炭素ロードマップ」(2021年6月国・地方脱炭素実現会議決定)に基づき、脱炭素先行地域等の実現を進めています。脱炭素先行地域とは、民生部門(家庭部門及び業務その他部門)の電力消費に伴うCO2排出の実質ゼロを実現し、運輸部門や熱利用等も含めてそのほかの温室効果ガス排出削減についても、我が国全体の2030年度目標と整合する削減を地域特性に応じて実現する地域であり、全国で脱炭素の取組を展開していくためのモデルとなる地域です。2025年度までに少なくとも100か所選定し、脱炭素に向かう地域特性等に応じた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度までに取組を実行します。これにより、農村・漁村・山村、離島、都市部の街区など多様な地域において、地域課題を同時解決し、地方創生に貢献します。2024年度までに5回の募集により81の脱炭素先行地域を選定しています(写真2-4-1、写真2-4-2、図2-4-1)。
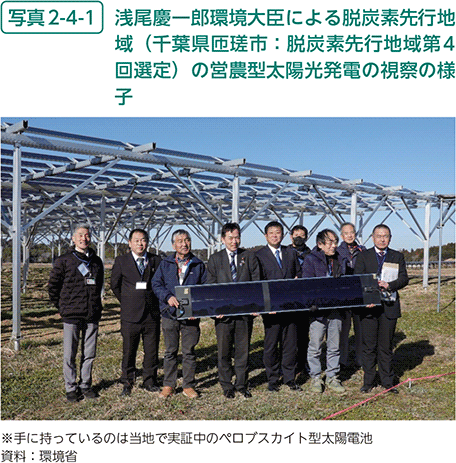

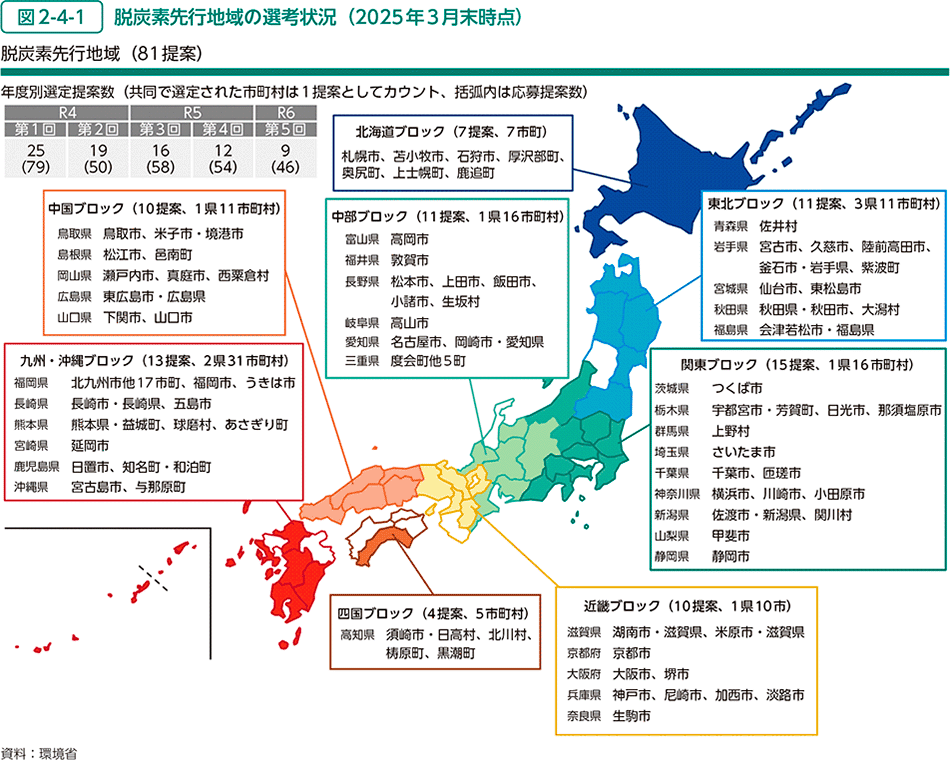
「地域脱炭素ロードマップ」に基づくもう一つの施策の柱が、脱炭素の基盤となる重点対策加速化事業の全国展開です。2030年度目標及び2050年ネット・ゼロの実現に向けては、脱炭素先行地域だけでなく、全国各地で、地方公共団体・企業・住民が主体となって、排出削減の取組を進めることが必要です。あらゆる対策・施策を脱炭素の視点をもって取り組むことが肝要ですが、特に、屋根置きなど自家消費型の太陽光発電の導入、住宅・建築物の省エネルギー性能の向上、ゼロカーボン・ドライブの普及等の脱炭素の基盤となる重点対策の複合実施について、国も複数年度にわたって包括的に支援しながら各地の創意工夫を凝らした取組を横展開し、全国津々浦々で実施していくことにしています。2024年度までに、「地域脱炭素推進交付金」にて、148の地方公共団体における脱炭素の基盤となる重点対策の加速化を支援しています。
地域の脱炭素化に向けて、国は、人材、情報・技術、資金の面から積極的に支援していく方針です。
人材面では、環境省において、地域の脱炭素化を進める人材育成のための研修を行っているほか、地方公共団体と企業のネットワークを構築するためのマッチングイベントの開催、地方公共団体への「脱炭素まちづくりアドバイザー」の派遣を行っています。また、内閣府において、地方創生人材支援制度によりグリーン専門人材の派遣を行うほか、総務省と環境省において、自治大学校の協力を得て地方公共団体職員向けの地域脱炭素に係る研修を行うなど、関係省庁と連携して、人的な支援を行っています。
情報・技術面では、再生可能エネルギー情報提供システム(REPOS)により、地域再生可能エネルギーの案件形成の基盤として、自治体支援のためのサイトを改修するとともに、地域経済循環分析ツール等を提供し、再生可能エネルギーなど地域資源を活用し、地域のお金がどうすれば地域で循環するかという地域経済循環の考え方を普及させ、地方公共団体による地域に貢献する脱炭素事業の計画を促進しています。
資金面では、2022年度当初予算に創設した脱炭素先行地域づくりや脱炭素の基盤となる重点対策加速化事業を支援する「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を拡充し、「地域脱炭素推進交付金」として2024年度当初予算に計上しており、民間と共同して意欲的に脱炭素に取り組む地方公共団体を支援していきます。また、総務省において2023年度に創設した脱炭素化推進事業債について、再生可能エネルギーの地産地消を一層推進するため、2024年度から地域内消費を主たる目的とする場合、第三セクター等に対する補助金を対象に追加することとしました。加えて、地域における再エネの最大限の導入を促進するため、地方公共団体による脱炭素社会を見据えた計画の策定等を補助する「地域脱炭素実現に向けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援事業」を実施しています。
国の積極支援に当たっては、地域の実施体制に近い立場にある国の地方支分部局(地方農政局、森林管理局、経済産業局、地方整備局、地方運輸局、地方環境事務所等)が水平連携し、各地域の強み・課題・ニーズを丁寧に吸い上げて機動的に支援を実施します。具体的には、各府省庁が持つ支援ツールと支援実績・実例等の情報を共有し、協同で情報発信や地方公共団体等への働きかけを行います。また、複数の主体・分野が関わる複合的な取組に対しては各府省庁の支援ツールを組み合わせて支援等に取り組みます。さらに、2022年度から、地方環境事務所に地域脱炭素創生室を創設することで、こうした関係府省庁との連携も通じた脱炭素先行地域づくりについて、地方公共団体が身近に相談できる窓口体制を確保し、相談対応や案件の進捗状況を地方支分部局間で共有しながら連携して対応しています。
さらに、これらの取組を始めとする地域脱炭素政策の今後については、2024年12月に「地域脱炭素政策の今後の在り方に関する検討会」の報告書が取りまとめられ、今後の地域脱炭素政策の方向性が示されています。これらに基づき、引き続き地域脱炭素の取組の加速化・全国展開を図っていきます。
地域の脱炭素化を進めていく上では、再生可能エネルギーの利用の促進が重要ですが、一部の再エネ事業では環境への適正な配慮がなされず、また、地域との合意形成が十分に図られていないことなどに起因した地域トラブルが発生し、地域社会との共生が課題となっています。脱炭素社会に必要な水準の再エネ導入を確保するためには、再エネ事業について適正に環境に配慮し地域における合意形成を促進することが必要です。
このため、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第54号)により、再エネの利用と地域の脱炭素化の取組を一体的に行うプロジェクトである地域脱炭素化促進事業が円滑に推進されるよう、市町村が再エネ促進区域の設定や、再エネ事業に求める環境保全・地域貢献の取組を自らの地方公共団体実行計画に位置付け、適合する事業計画を認定する仕組みが2022年4月に施行されました。また、地域共生型再エネの導入促進に向けて、都道府県の関与強化による地域脱炭素化促進事業制度の拡充を含む「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)」が2025年4月に施行されました。2025年3月末時点で全国56か所の市町村で促進区域が設定されるとともに、環境保全と地域経済への発展等を考慮した地域脱炭素化促進事業計画の認定も始まるなど、広がりを見せつつあります。国は今後も、地方公共団体における再生可能エネルギーの導入計画の策定や、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニング等を行う取組への支援等とともに促進事業認定に向けた事業者の支援を行い、地域共生型・地域裨益型再エネ導入を促進していきます。
地球温暖化対策計画の中では、2030年度において、家庭部門は2013年度比で66%、業務その他部門では2013年度比で51%のエネルギー起源CO2を削減する野心的な目標が設定されています。住宅・建築物は一度建築されるとストックとして長期にわたりCO2排出に影響することから、2050年ネット・ゼロに向けて、今から住宅・建築物の脱炭素化に取り組むことが不可欠です。
新築の住宅及び建築物に関しては、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)を改正し、省エネルギー基準適合義務の対象外である住宅及び小規模建築物の省エネルギー基準への適合を2025年度から義務化するとともに、2030年度以降新築される住宅及び建築物についてZEH(ゼッチ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)・ZEB(ゼブ)(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)基準の水準の省エネルギー性能の確保を目指し、整合的な誘導基準の引上げや、省エネルギー基準の段階的な水準の引上げを遅くとも2030年度までに実施することとしています。これらの制度的措置に加え、新築される住宅及び建築物のZEH(ゼッチ)・ZEB(ゼブ)化への支援や、国土交通省とも連携し、ZEH(ゼッチ)基準の水準を大きく上回る省エネルギー性能を有する住宅に対する補助事業を実施しています。
また、全国に既に存在する住宅の約8割、ビルや学校等の建築物の約6割が現行の省エネルギー基準を満たしていません。これら膨大な数の住宅・建築物ストックの脱炭素化改修への投資は、新たな市場を創出し、経済成長にも資するものです。このため、経済産業省、国土交通省及び環境省では、GX予算も一部活用しつつ、既存の住宅及び建築物の省エネ性能向上のための補助事業を実施しています。特に既存住宅に関しては、経済産業省、国土交通省及び環境省の住宅の省エネリフォームのための補助事業をワンストップで利用可能とし、より一層の省エネリフォームの促進を図っています。
我が国全体の二酸化炭素排出量の約2割は運輸部門から、3割以上は産業部門から排出されており、それらの部門からの排出量削減につながるモビリティの脱炭素化は、2050年ネット・ゼロ実現のために非常に重要です。
ネット・ゼロ実現に向けて、トラック・バス等の商用車については、8トン以下の車両は2030年までに新車販売に占める電動車(EV、PHEV、FCV等)の割合を20~30%とする、8トン超の車両は2030年までに電動車を5,000台先行導入するなどという目標を設定し、電動化を進めています。また、GX建設機械認定制度も活用しつつ、電動建設機械の導入・普及を促進しています。
船舶については、水素・アンモニア燃料等を使用するゼロエミッション船等の導入の促進に向けて、国内生産体制の整備支援に取り組んでいます。
2050年ネット・ゼロや2025年2月に閣議決定された地球温暖化対策計画に示される我が国の温室効果ガス削減目標の実現に向けては、公共部門の率先した取組が重要です。特に太陽光発電については、2025年2月に改定した「政府実行計画」において、2030年度までに設置可能な政府保有の建築物等の約50%以上に、2040年度までに100%設置することを目指しており、各府省庁において導入に向けた取組を進めています。地方公共団体についても、地球温暖化対策推進法に基づき、地球温暖化対策計画に即した「地方公共団体実行計画」を策定した上で、政府実行計画に準じた取組を進めることとされており、こうした取組を促進するために、建築物のZEB(ゼブ)化に資するシステム・設備機器や公共施設への太陽光発電設備・蓄電池等の導入支援等を行っています。また、自治体職員向けに、初期費用及びメンテナンスが不要であり、設備設計も民間提案とすることが可能である「第三者所有モデル」による導入についての手引きや事例集、公募要領のひな型等を公表しています。
これらの取組を円滑に進めるため、「公共部門等の脱炭素化に関する関係府省庁連絡会議」を2023年9月に設置しました。連絡会議を通じ、公共部門における太陽光発電の導入容量に関する目標の設定、各府省庁の太陽光発電整備計画の策定、地方公共団体への支援策等の周知等を実施しました。
再生可能エネルギーの最大限導入に当たっては、環境に適正に配慮し、地域に貢献する、地域共生型の再エネ事業を進めることが重要です。そのため、脱炭素と地域課題解決の同時実現を目指す脱炭素先行地域、重点対策加速化事業を始めとした地域主導の脱炭素の取組を、財政・人材・情報等の面から支援します。また、地域脱炭素化促進事業制度も活用しながら、地域共生型・地域裨益型の再生可能エネルギー導入を促進し、地域企業の脱炭素化支援を含めて地域共生型再エネの利活用を促進します(「1.地域の脱炭素移行、建築物・モビリティの脱炭素移行」参照)。発電と営農が両立する営農型太陽光発電については、事業規律や適切な営農の確保を前提として、地方公共団体の関与等により適正性が確保される事業の導入の拡大を進めていきます。さらに、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度の運用を通じて、事業者による適正な環境配慮が確保されるよう取り組んでいきます。
日本発の技術として開発の進むペロブスカイト太陽電池は、軽量・柔軟という特徴を有し、耐荷重性の低い屋根や建物壁面等、従来の太陽電池では設置が困難だった場所への導入を可能とする次世代技術です。この技術の活用により、太陽光発電が直面する様々な課題を乗り越えながら、再生可能エネルギーの更なる導入拡大につながることが期待されています。ペロブスカイト太陽電池の社会実装に向け、次世代型太陽電池の導入拡大及び産業競争力の強化に向けた官民協議会において、2024年11月に「次世代型太陽電池戦略」が取りまとめられました。本戦略に基づき、ペロブスカイト太陽電池の継続的な需要の創出に取り組み、量産化による価格低減、更なる導入拡大につながる好循環を目指します。2025年2月には、政府実行計画を改定し、政府施設への率先導入を位置付けました。また、地方公共団体を含む需要家への導入支援を実施し、導入初期におけるコスト低減と継続的な需要拡大に資する社会実装モデルの創出に取り組んでいきます。
初期費用ゼロでの自家消費型の太陽光発電設備・蓄電池の導入支援等を通じて、太陽光発電設備・蓄電池の価格低減を促進しながら、太陽光発電設備の導入に際して、蓄電池を導入しないよりも蓄電池を導入した方が経済的メリットがある状態(ストレージパリティ)の達成を目指します。また、窓・壁等の設置場所の特性に応じた太陽光発電設備の導入を促進していきます。
太陽光パネルについては、2030年代後半以降に排出量が顕著に増加すると見込まれており、脱炭素化と循環経済への移行を共に進めていくためにも、リサイクルを促進することが重要です。2024年9月から、「中央環境審議会循環型社会部会太陽光発電設備リサイクル制度小委員会」と「産業構造審議会イノベーション・環境分科会資源循環経済小委員会太陽光発電設備リサイクルワーキンググループ」の合同会議において、太陽光パネルの廃棄・リサイクルを確実に行うための仕組みについて議論し、2025年3月に「太陽光発電設備のリサイクル制度のあり方について」が取りまとめられました。この報告書を踏まえ、具体的な制度設計について検討を進めるとともに、リサイクルを促進するための環境整備を進めていきます。
遠浅の海域の少ない我が国では、水深の深い海域に適した浮体式洋上風力の導入拡大が重要です。長崎県五島市の実証事業において風水害にも耐え得る浮体式洋上風力が実用化されたことを活かし、確立した係留技術・施工方法等を基に普及啓発を進めています。浮体式洋上風力の導入に当たっては、環境保全・社会受容性の確保や、維持管理や使用後の破棄など多様な観点からの検討が不可欠です。今後も、脱炭素化と共に自立的なビジネス形成が効果的に推進されるよう、エネルギーの地産地消を目指す地域における浮体式洋上風力発電の導入計画策定の支援や漁業関係者等の理解醸成に資する海洋生態系観測システムの実証に取り組みます。
事例:既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築実証事業
「既存のインフラを活用した水素供給低コスト化に向けたモデル構築実証事業」では、地域資源である再エネ等を活用し、水素供給に必要なコストを低減することで、地産地消型の水素サプライチェーンモデルを構築することを目指しており、現在、北海道苫小牧市、室蘭市、福島県浪江町、大阪府大阪市の4地域で実証事業を行っています。
そのうち、浪江町では、太陽光発電を利用した水素製造施設である「福島水素エネルギー研究フィールド」より出荷されたグリーン水素を、町内に設置した燃料電池やFCV等の水素を利活用できる設備の燃料として利用するほか、水素需給量・搬送状況を考慮した最適搬送管理システムを町の水素利用プラットフォームとして構築し、サプライチェーンの全体管理・最適化を目指す実証を行っています。また、室蘭市では、市が所有する風力発電所の電力を活用して製造した水素を、既存のLPガス配送トラック車に混載可能な円筒型水素吸蔵合金タンク(MHタンク)に充填し、高圧ガス関係法令に抵触しない低圧で配送し、大学職員宿舎に設置された燃料電池、小規模食堂や宿泊施設における水素ボイラー等において利用するサプライチェーン構築の実証を行っています。


再生可能エネルギーの最大限の導入拡大に当たっては、地域における合意形成を図り、環境への適正な配慮を確保することが重要であり、環境影響評価制度の重要性はますます高まっています。
とりわけ風力発電については、今後も更なる導入拡大が期待されている一方で、地域によっては、環境影響等への懸念が高まっている状況にあります。
このような中、中央環境審議会「風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」における審議を経て、2024年3月、「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(一次答申)」が取りまとめられ、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)(平成30年法律第89号)に基づき実施される洋上風力発電に関し、より適正に環境配慮を確保する観点から、国が海洋環境等に関する調査を行った上で促進区域等を指定するとともに、これに相当する事業者の環境影響評価手続の一部を適用除外とする仕組みの必要性などが示されました。この結論を踏まえ、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を2025年3月に閣議決定し、第217回国会に提出しました。
また、陸上風力発電に係る環境影響評価制度を含む今後の環境影響評価制度全体の在り方に対する結論を得るため、中央環境審議会「風力発電に係る環境影響評価制度の在り方に関する小委員会」及び「環境影響評価制度小委員会」における審議を経て、2025年3月、「風力発電事業に係る環境影響評価の在り方について(二次答申)」と「今後の環境影響評価制度の在り方について(答申)」が取りまとめられ、陸上風力発電を含む、工作物の建替事業に係る配慮書手続の見直しや、環境影響評価図書の制度的な継続公開などの必要性が示されました。この結論を踏まえ、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」を2025年3月に閣議決定し、第217回国会に提出しました。
地熱発電は、発電量が天候等に左右されないベースロード電源となり得る再生可能エネルギーであり、我が国は世界第3位の地熱資源量を有すると言われていることなどから、積極的な導入拡大が期待されています。しかし、地下資源の開発はリスクやコストが高いこと、地熱資源が火山地帯に偏在しており適地が限定的であること、自然環境や温泉資源等への影響懸念等の課題もあります。このような状況を踏まえて、守るべき自然は守りつつ、地域での合意形成を図りながら、自然環境と調和した地域共生型の地熱利活用を促進する観点から、環境省は2021年4月に「地熱開発加速化プラン」を発表し、9月に自然公園法及び温泉法の運用見直しを行いました。引き続き同プランに基づき、地球温暖化対策推進法に基づく促進区域の設定の促進、温泉モニタリング等の科学的データの収集・調査を行うことによって、地域調整を円滑化し、全国の地熱発電施設数の2030年までの倍増と最大2年程度のリードタイムの短縮を目指しています。
電力部門におけるCO2排出係数が大きくなることは、産業部門や業務その他部門、家庭部門における省エネの取組(電力消費量の削減)による削減効果に大きく影響を与えます。このため、電力部門の取組は、脱炭素化に向けて非常に重要です。
再生可能エネルギー、原子力等の脱炭素電源を最大限活用するとともに、2050年ネット・ゼロ実現に向けて、火力発電から大気中に排出されるCO2を実質ゼロにしていくことが必要です。特に、石炭火力発電は安定供給性と経済性に優れていますが、CO2排出係数は最新鋭のものでも天然ガス火力発電の約2倍となっています。一方で、火力発電は、東日本大震災以降の電力の安定供給や電力レジリエンスを支えてきた重要な供給力であるとともに、現時点の技術を前提とすれば、再生可能エネルギーを最大限導入する中で、再生可能エネルギーの変動性を補う調整力としての機能も期待されることを踏まえ、安定供給を確保しつつ、その機能をいかにして脱炭素電源に置き換えていくかが鍵となります。
このため、2025年2月に閣議決定された地球温暖化対策計画に示される温室効果ガス削減目標の実現に向けては、火力全体で安定供給に必要な発電容量(kW)を維持・確保しつつ、非効率な石炭火力発電を中心に発電量(kWh)を減らしていくことが重要です。G7では、各国のネット・ゼロの道筋に沿って、2030年代前半、または、気温上昇を1.5度に抑えることを射程に入れ続けることと整合的なタイムラインで、排出削減対策が講じられていない既存の石炭火力発電をフェーズアウトすることで一致しました。
電力部門の脱炭素化に向けた取組として、具体的には、非効率な石炭火力発電について、省エネ法の規制強化により最新鋭のUSC(超々臨界)並みの発電効率(事業者単位)をベンチマーク目標として設定するとともに、バイオマス等について、発電効率の算定時に混焼分の控除を認めることで、脱炭素化に向けた技術導入の促進につなげていくほか、容量市場においては、2025年度オークションから、一定の稼働率を超える非効率な石炭火力発電に対して、容量市場からの受取額を減額する措置を導入するなど、規制と誘導の両面から措置を講じることにより非効率な石炭火力発電のフェードアウトを着実に推進していきます。また、大手電力等は火力の脱炭素化計画を毎年度作成するとともに、経済産業省は全事業者を統合した形で2030年に向けたフェードアウトの絵姿を公表することとしています。
さらに、2050年ネット・ゼロに向けては、グリーンイノベーション基金等も活用して、水素・アンモニアの混焼・専焼化やCO2回収・有効利用・貯留(CCUS/カーボンリサイクル)の技術開発・実装を加速化し、脱炭素型の火力発電に置き換える取組を推進していくこととしています。
中でも、我が国では、2023年3月に取りまとめられた「CCS長期ロードマップ」において、2030年までに事業開始に向けた事業環境を整備し、2030年以降に本格的にCCS事業を展開することを目標としています。また、2023年6月に取りまとめられた「カーボンリサイクルロードマップ」において、化石燃料等の燃焼に伴う排ガス中のCO2を資源として捉え、化学品や燃料、鉱物といった新たな有価物に転換して社会で活用することでカーボンニュートラル社会の実現に貢献することとしており、CCUS/カーボンリサイクルの早期社会実装のため、モデル事業等を通じ、商用化規模の早期の技術確立を目指し、普及に向けた取組を加速化していきます。環境省では、商用規模の火力発電所におけるCO2分離回収設備の建設・実証により、CO2を分離回収する場合のコストや課題の整理、環境影響の評価等を実施するほか、カーボンリサイクル技術を地域社会で活用するモデル構築等の検討を実施しています。
我が国は、グローバルサウス等のパートナー国で、日本の企業や政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、得られるGHG削減・吸収の効果を、両国の貢献度合いに応じて配分する仕組み(二国間クレジット制度:JCM)を展開しており、これまで270件以上のプロジェクトを実施しています。2024年10月にラオス・ビエンチャンで開催された第2回アジア・ゼロエミッション共同体(AZEC)首脳会合において採択された「今後10年のためのアクションプラン」でも、AZEC内でのJCMパートナー国の拡大を含めた質の高い炭素市場に関する協力が盛り込まれました。また、こうしたJCMの活用促進に向けて、クレジットの発行手続き等を法定化する「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)」が2024年6月に成立し、2025年4月1日に同法に基づく指定実施機関「日本政府指定JCM実施機構」(英名:The Joint Crediting Mechanism Implementation Agency, designated by the Government of Japan)が発足しました。
また、パリ協定第6条に沿ったJCMを含む市場メカニズムの構築のため、COP27において我が国が主導して立ち上げた「パリ協定6条実施パートナーシップ」(2025年1月末時点、86か国、200以上の機関が参加)による各国の実施体制の構築支援等を行っています。世界各国でJCMを含む市場メカニズムの活用と炭素市場がますます拡大していくことが期待され、今後も国際的な連携を更に強化しながら、各国の6条実施に対する支援を拡大していきます。
また、官民連携の枠組みとして、2020年9月に設立した環境インフラ海外展開プラットフォーム(JPRSI)を活用し、環境インフラの海外展開に積極的に取り組む民間企業の活動を後押ししていきます。具体的な活動として、セミナーや展示等を一体的に開催する「環境ウィーク」の開催、現地情報へのアクセス支援、日本企業が有する環境技術等の海外発信、タスクフォース・相談窓口の運営等を通じた個別案件形成・受注獲得支援を行っています。
さらに、環境省水素等新技術導入事業では2023年度から、これまでJCMを通じた事業化の実績のない先進的な技術導入を目的とした実証事業として、モンゴルにおけるグリーン水素の実証事業やタイにおけるペロブスカイト太陽電池の実証事業を実施しています。また、水田から排出されるメタン削減に資する水管理技術とJCMとを組み合わせるための具体的手法(方法論)をフィリピンと共同で開発し、現地でプロジェクトが開始されました。加えて、2025年度より、脱炭素だけでなく他の環境課題・社会課題等を相乗的に解決するためのJCM事業の案件形成に向けた実証事業を開始しました。
これらの取組を通じて、「脱炭素、経済成長、エネルギー安全保障の同時実現」及び「多様な道筋によるネット・ゼロ実現」との「アジア・ゼロエミッション共同体」(AZEC)原則の下でのAZECの取組にも貢献するなど、世界全体、とりわけアジアの脱炭素化に貢献し、気温上昇を1.5℃に抑制するために、できるだけ早く、できるだけ大きな削減を実現できるよう貢献していきます。
事例:神奈川県横浜市とタイ・バンコク都による脱炭素社会実現のための都市間連携事業
環境省では、我が国と海外の自治体が連携し、脱炭素プロジェクトの形成や制度構築支援等をパッケージで展開する「脱炭素社会実現のための都市間連携事業」を2013年度から実施しています。2022年度に開始した横浜市とバンコク都の都市間連携事業では、現在、バンコク都のエネルギーアクションプランを策定し、[1]エネルギー効率の改善、[2]再生可能エネルギーへの移行、[3]持続可能な交通の促進、という3つの戦略の下、バンコク都保有施設及びバンコク都内の民間企業における対策を進めています。これまでには、民間企業交流のプラットフォームの提供、「タイのアルミインゴット生産工場への高効率システム導入による生産性改善」、「亜熱帯地域におけるペロブスカイト太陽電池システムの実証事業」といったJCM事業の実現など協力の成果を上げています。
なお、横浜市は、2013年にバンコク都と環境分野の技術協力に係る覚書に署名して以来、JICAと連携した技術研修や気候変動マスタープラン策定に係る協力を行ってきたほか、アジア・スマートシティ会議を主催しており、2024年10月に横浜で開催された第13回目となる会議には2,200人以上が出席し、39の海外都市・政府機関等が賛同するアジアのグリーン社会の実現に向けた横浜宣言が行われました。