「ネイチャーポジティブ:自然再興」とは、「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させる」ことです(図2-3-1)。これは、いわゆる従来の自然保護だけを行うものではなく、気候変動対策や資源循環等の様々な分野の施策と連携して社会・経済全体を生物多様性の保全に貢献するよう変革させていく考え方であり、愛知目標を始めとするこれまでの目標が目指してきた生物多様性の損失を止めることから一歩前進させ、損失を止めるだけではなく回復に転じさせるという強い決意が込められています。「ネイチャーポジティブ」という言葉は、2021年にイギリスで開催されたG7コーンウォール・サミットの首脳コミュニケの附属文書である「G7・2030年自然協約」において用いられたことから、国際的にも認知され始めました。なお、2022年12月にCBD-COP15で採択されたGBFの2030年ミッションにも、この考え方が反映されています。
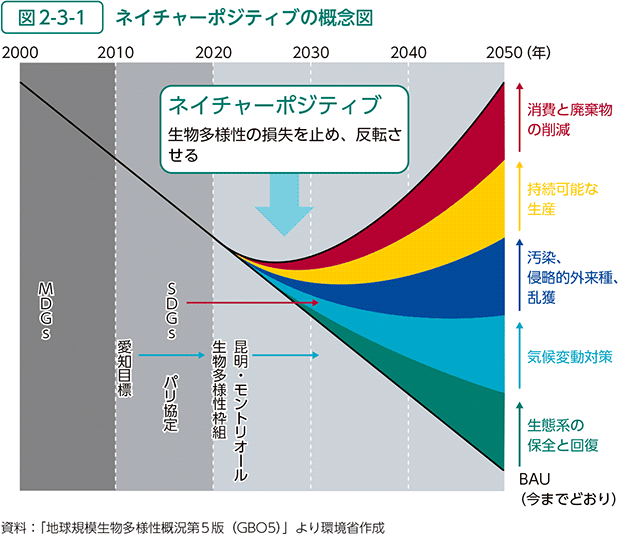
「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021(JBO3)」によれば、我が国の生物多様性は、過去50年間損失し続けています。劣化しつつある生物多様性を改善していくために、生物多様性国家戦略2023-2030では2030年ネイチャーポジティブ実現を掲げ、各種取組を推進することとしています。例えば、次節で取り上げる30by30目標に向けた取組もその一つです。
国全体での生物多様性保全の取組と並んで、地域でも多様な主体により様々な取組が行われています。奄美大島では、関係者が一丸となって特定外来生物であるマングースの防除に長年取り組んだ結果、同種の根絶に至り、在来種がより多く観察されるようになりました。他の地域でも、外来種の防除活動等の成果により、沖縄県やんばるの森のヤンバルクイナ、福岡県小屋島のヒメクロウミツバメ、埼玉県天覧山・多峯主山周辺のヤマアカガエルなど、危機に陥っていた生き物が回復している状況も捉えられています(図2-3-2)。世界全体、国内全体でのネイチャーポジティブの実現に向けては、このような生物多様性の保全に資する取組が各地域で進められることが不可欠です。
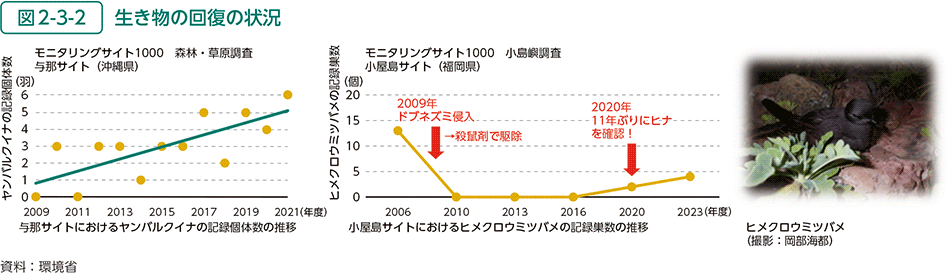
コラム:奄美大島における特定外来生物フイリマングースの根絶
奄美大島では、1979年にハブ対策としてフイリマングース(以下「マングース」という。)が持ち込まれ、2000年には推定1万頭以上まで増加しました。マングースの増加に伴い、マングースの分布地域では在来種の大幅な減少が見られ、またマングースによる農業被害も発生しました。このため、2000年から本格的な防除事業を開始し、2005年からは根絶達成を目的として専門家集団「奄美マングースバスターズ」を結成して計画的な防除を推進しています。その結果、2018年5月以降マングースは捕獲されておらず、2024年9月に奄美大島における特定外来生物マングースの根絶を宣言しました。
本事例は、長期間定着したマングースを計画的な防除によって根絶した事例としては世界最大規模であり、マングースの根絶に伴い多数の在来種において生息状況の回復が確認されました。また、マングースによる農業被害は消失し、野生生物観光と農業の盛んな同島の社会経済への好影響が期待されます。
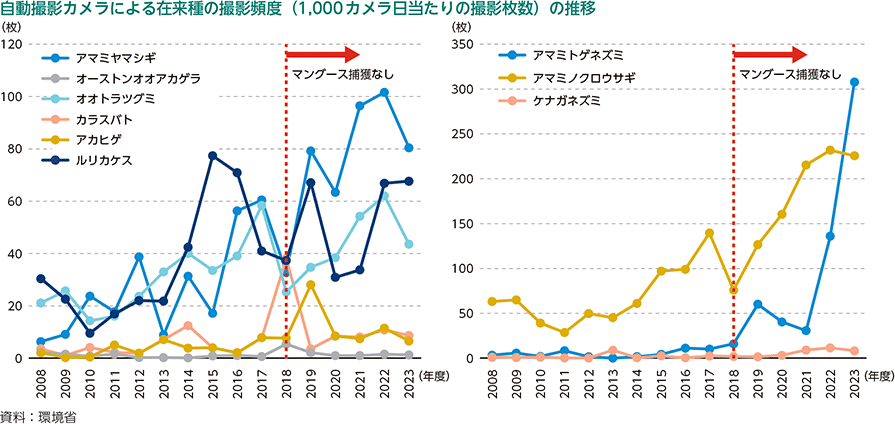
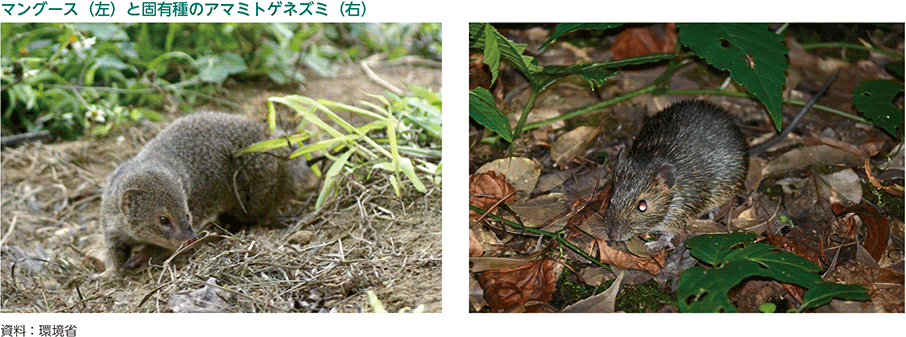
コラム:エコツーリズム大賞
エコツーリズムは、自然環境の保護と利用の好循環の形成や、豊かで活力ある地域づくりの推進に資する取組の一つです。エコツーリズム大賞は、自然環境や歴史文化の保全、自然体験等に関連した観光に取り組む団体又は個人を幅広く表彰しており、第20回となる今回は2024年2月に大賞1点、優秀賞2点、特別賞6点、パートナーシップ賞2点の表彰式を行い、受賞者へ小林史明環境副大臣から表彰状、一般社団法人日本エコツーリズム協会水谷初子事務局長から副賞が授与されました。
今回、大賞を受賞された「支笏ガイドハウス かのあ」は、北海道、支笏洞爺国立公園内の支笏湖をフィールドに、美しい自然環境を水上から体感できる様々なカヌーツアーを提供し、4歳から94歳までの幅広い年齢層、病気や障害を抱える方を積極的にツアーに受け入れていることに加え、清掃活動やフィールドパトロールの実施、環境保全金制度の創設など多岐にわたる環境保全活動を、地域の多様な主体と連携して実施されている点が、高く評価されました。
独自の形状のカヌーを使用するなど、参加者同士のコミュニケーションや自然に対する理解、学びを促す工夫も行っており、当該地域におけるエコツーリズムによる「まちづくり」の牽引役として今後が期待されます。


2030年までに、陸と海の30%以上を健全な生態系として効果的に保全しようとする、いわゆる「30by30目標」は、ネイチャーポジティブ実現のための鍵となる目標の一つです。
この30by30目標は、GBFのターゲット3に位置付けられており、「2020年までに少なくとも陸域の17%、海域の10%を保護地域等により保全すること」を目指した愛知目標「個別目標11」の後継となる目標です。
我が国では、2024年8月時点で、陸地の約20.8%、海洋の約13.3%が国立公園等の保護地域及びOECM(Other Effective area-based Conservation Measures、保護地域以外で生物多様性の保全に資する地域)に指定等されており、目標の達成に向けては、保護地域の拡張と管理の質の向上に加え、OECMの設定・管理を進めることが不可欠です。
目標設定の背景としては、以下の科学的知見があったことが挙げられます。
例えば、国際的な科学的知見の例として、世界の陸棲哺乳類種の多くを守るためには、既存の保護地域を総土地面積の33.8%にまで拡大することが必要であるという指摘があります。また、世界中で両生類・鳥類・哺乳類等を保全しようとした場合に、世界の陸地の26~28%の割合を保全すべきとの研究報告もあります。海洋についても、例えば既往の144の研究をレビューした結果、その過半数は海洋の3割以上を保護すべきとし、平均すると世界の海洋の37%は保護される必要があるとされています。
国内での科学的知見においても、陸域に関して、今後、保護地域を30%まで効果的に拡大すると、生物の絶滅リスクが3割減少する見込みがあるとする研究報告があります。
自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づいて指定される自然公園(国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園)は、国土の約15.2%を占めています。「30by30ロードマップ」を踏まえた「国立・国定公園総点検事業フォローアップ」により、国立・国定公園の新規指定・拡張候補地に選定された14か所の地域において調整が進められてきました。これらの候補地のうち、2024年度においては、日高山脈襟裳十勝国立公園が35か所目の国立公園として新たに指定されました(写真2-3-1)。また、阿蘇周辺の草原を中心に、阿蘇くじゅう国立公園の大規模拡張が行われました。拡張等がまだ行われていない地域において、引き続き調整を図っていきます。

また、保護地域の拡張に加え管理の質の向上も重要であり、国立公園においては、地域の関係者が望ましい保全・利用の目標、ビジョンを共有し、関係者が主体的に国立公園の管理運営に資する取組を実施する協働型管理運営を推進しています。この取組の一環として地域の関係者と丁寧な合意形成を図った上で入域料を収受施設の維持管理に充てたり、ツアー料金等の一部を自然環境の保全に充てたりする利用者負担の取組を進めています。2024年2月時点では、国立公園における入域料の事例は16件であり、それ以外の利用者負担の仕組みの件数は34件となっています。
2024年に瀬戸内海、雲仙天草、霧島錦江湾、阿寒摩周、大雪山、中部山岳、日光、阿蘇くじゅうの8つの国立公園が指定90周年を迎えました(写真2-3-2)。地域の宝である国立公園の自然、その自然と共に生きてきた人々の歴史、文化、ストーリーを見つめなおし、次の世代、次の100年に引き継いでいく必要があります。このため、国立公園制度100周年を迎える2031年までに全ての国立公園において聞き書き集「国立公園ものがたり」を制作することとしており、2024年は釧路湿原、大雪山、西海、雲仙天草の4つの国立公園で制作しました。
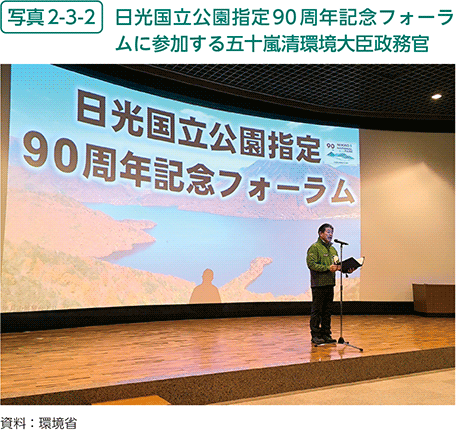
長距離自然歩道の第一号である東海自然歩道が2024年7月に開通50周年を迎えたことを記念して、同月に沿線自治体や関係者を対象に記念式典を開催するとともに、環境省から「東海自然歩道の活性化の方向性」を公表しました。みちのく潮風トレイルは、東日本大震災からの復興に向けた「三陸復興国立公園を核としたグリーン復興プロジェクト」の取組の一つとして、青森県八戸市から福島県相馬市までの4県29市町村にまたがり設定された長距離自然歩道です。2024年度は全線開通から5周年の節目であり、記念式典やウォーキングイベント等を開催し、関係者との連携強化や、同トレイルの更なる盛り上げを図りました。北海道東トレイルは、知床、阿寒摩周、釧路湿原の3つの国立公園を結ぶロングトレイルで、国立公園満喫プロジェクトの一環として地域の関係者と協働で検討し、2024年10月に全線開通しました。
コラム:オフィシャルパートナーの活動事例
近年拡大している国立公園オフィシャルパートナー企業等によるネイチャーポジティブにつながる取組として、特定非営利活動法人Nature Serviceの取組を紹介します。
◯国立公園の認知拡大に向けたPodcast番組
2024年7月より全国の国立公園の魅力を発信するPodcast番組「Sunny Spot」の配信を開始しました。本番組は、各国立公園で実際に働く環境省職員の生の声をお届けすることを特徴とし、毎月1公園、約3年掛けて35公園を順次紹介していく予定です。
各番組では、雄大な自然景観や希少な動植物、地域固有の文化や歴史等、国立公園の多様な魅力を深掘りしています。現地職員ならではの視点や、ガイドブックには載らないような穴場スポットの情報などを盛り込むことで、リスナーが実際に訪れたくなるような臨場感あふれる内容を目指しています。
番組を通して、従来の広報活動では届きにくかった層、特に若い世代や多忙なビジネスパーソンへの情報発信を強化します。「ながら聴き」に適したPodcastの特性を活かし、通勤時間や家事の合間など、様々なシーンで国立公園に触れてもらう機会を創出します。
配信プラットフォームは、Apple Podcast、Spotify、Amazon Music等を網羅し、より多くのリスナーにアプローチできるよう工夫しています。また、SNS等での積極的な情報発信を通して、番組の認知度向上も図っています。
本番組は、環境保全や地域活性化といった社会的課題にも貢献することを目指しています。国立公園の魅力を発信することで、自然環境や生物多様性の保全への関心を高め、地域への観光客誘致を促進し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。
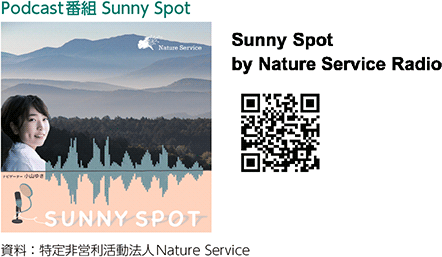
国立公園等の保護地域以外の場所で、生物多様性の保全に貢献している地域を指すOECMは、2010年に日本で開催されたCBD-COP10で採択された愛知目標において盛り込まれた考え方です。里地里山など慣習や生業によって結果として生物多様性が守られている場所も、地球の生態系を守るための場所としてきちんとカウントしていくことができる仕組みとして国際的に注目され、「名古屋のギフト」と言われることもあります。
日本においても、「モニタリングサイト1000」の過去20年にわたる調査結果により、スズメやヒバリ、イチモンジセセリやノウサギ等の身近に見られる生き物の減少傾向が確認されており、保護地域以外の身近な自然環境を保全することが必要だとされています(表2-3-1)。
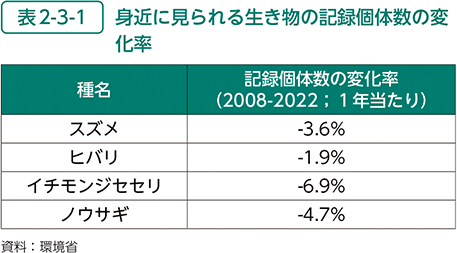
我が国においては、OECMの設定・管理に関する取組として、民間の取組等によって生物多様性の保全が図られている区域を「自然共生サイト」として認定する仕組みを2023年度から開始しています(図2-3-3)。例えば、企業の水源の森や都市の緑地、ナショナルトラストやバードサンクチュアリ、里地里山、里海における藻場、干潟など、企業、団体・個人、地方公共団体が所有又は活動する多様な場所が対象になります。これまで合計4回にわたって認定を行い、2025年3月末時点で合計328か所、9.3万haを認定しました(写真2-3-3、写真2-3-4、写真2-3-5、写真2-3-6)。申請者の半数以上が民間企業であり、特にビジネス界を中心に高い関心が寄せられています。なお、2023年度に認定された184か所については、保護地域との重複を除き、2024年8月に我が国のOECM第1弾として、OECM国際データベースに登録しました。





自然共生サイトに認定されている沿岸域は、わずか10件程度と少なく、現状では陸域中心となっています。そのため、全国各地で実施されている里海づくり等を通じて、更なる海域生物多様性保全の取組が求められています。また、海域環境については、高度経済成長期に著しく汚染が進み、排水規制等の取組により現在、水質は一定程度改善したものの、豊かな海の実現には至っていません。その観点でも、藻場・干潟の保全・再生・創出と地域資源の利活用の好循環を目指す地域の取組を支援し、自然共生サイトへの登録も見据えた好事例を創出する「令和の里海づくり」モデル事業等に取り組んでいます。
現在、企業経営においても、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の流れもあいまって、生物多様性や自然資本の重要性が高まっています。現に、自然共生サイト認定制度に対して、想定を超える多くの申請をいただくなど、我が国においても企業を中心に生物多様性の保全に向けて多くの関心が寄せられており、これまでにない大きなチャンスが到来していると感じています。この勢いを更に加速するためにも、認定制度の安定性・継続性を確保することが必要です。また、自然共生サイトは、既に生物多様性が豊かな場所を対象としていますが、ネイチャーポジティブの実現に向けては、生物多様性の回復や創出を図ることも同様に必要です。
このような背景を踏まえ、企業等の活動を更に促進するため、自然共生サイト認定制度を法制化した、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号)」が第213回国会において成立し、2025年4月に施行されました。本法律は、民間等による自主的な活動を更に促進するため、生物多様性が豊かな場所における活動に加え、管理放棄地等において生態系を回復又は創出する活動も認定対象としています。認定された活動の実施区域を、「自然共生サイト」と呼び、生物多様性が豊かな場所については、保護地域との重複を除き、OECMとして国際データベースに登録することとし、2023年度から開始した自然共生サイトの運用を踏襲しています。なお、生態系の回復・創出を行っている場については、活動の結果として生物多様性が豊かになったことが認められた後で、OECMとして国際データベースに登録されます。
里地里山や身近な自然等は生物多様性の保全上重要な場所ですが、規制を伴う保護地域制度でカバーすることは困難でした。自然共生サイトは、里地里山を始め、従来の手法では保全の機運の醸成が難しかった場所を含め、国土全体における多種多様な場の保全を進めることができる画期的な制度です。今般、この自然共生サイト認定制度が法制化されたことによって、今後より一層、全国各地の多様な自然環境において、企業含む多様なプレイヤーによる活動が促進され、保護地域との連結性も相まって、各地域の生物多様性の保全が進むことが期待されます。そして、企業等による優れた活動を国が認定することを通じて、その価値や信頼性を客観的に担保し、社会・経済の両面で適切な評価がなされることが期待されます。
さらに、より多くの民間資金や人的資源が自然共生サイトにおける活動の質の維持・向上に活用されるよう、2022年度から「支援証明書」制度の検討を行っています。支援証明書は、企業等へのインセンティブとなるようTNFDやIR等の投資家向け情報開示等への活用も念頭に検討し、令和6年度は制度の試行運用を行って支援証明書(試行版)を発行しました。
30by30目標の達成には、自然共生サイトの取組に代表されるように、企業、自治体、地域の活動団体等あらゆる主体との連携が不可欠です。これらの取組を通じ、ネイチャーポジティブの実現のためにも必要な社会変革を目指していきます。
コラム:自然共生サイトにおいて気候変動対策とのシナジーを発揮しているNbSの事例
NbS(自然を活用した解決策)とは、健全な自然生態系が有する機能を活かして社会課題の解決を図る取組です。例えば、森林を健全に管理・保全することで、森林の持つ水源涵養機能が洪水の緩和に寄与するだけでなく、CO2の吸収にもつながります。こうした自然由来の緩和ポテンシャルは、パリ協定の2℃目標の達成のために2030年までに必要な二酸化炭素緩和策の約3分の1に該当し、費用対効果が高いことが指摘されています。生物多様性損失の5大要因のうち3番目に大きな要因が気候変動と言われており、気候変動対策による生物多様性への恩恵も期待されます。その一方で、気候変動対策が結果として生物多様性の損失を引き起こしてしまう、いわゆるトレードオフも懸念されています。NbSはこうした気候変動対策と生物多様性保全のトレードオフを最小限にしつつシナジーを強化し、両課題を統合的に解決するキーワードとして期待されます。
健全な生態系が保全されている自然共生サイトの中には、生態系の有する機能を効果的に活用したNbSの事例が多く見られます。例えば、2023年度に自然共生サイトとして認定された「山川の海のゆりかご」では、山川町漁協組合が中心となって、ワカメやアマモ場造成などに長年取り組むとともに、単年性アマモの再生のために、食害対策ネットの設置や藻場のウニ駆除・モニタリング、海洋ゴミの清掃等の活動を行っています。本サイトでは漁業資源を始めとする生物多様性保全に貢献するだけでなく、アマモ場における炭素固定を通して気候変動対策にも貢献しています。それだけでなく、窒素やリンの吸収源として水の安全保障や子供への課題活動の提供を通じた地域の環境教育への貢献等のコベネフィットを伴い、多くの社会課題への貢献に寄与しています。なお、山川町漁協組合では、自然共生サイトで採れた水産物に自然共生サイト認定マークを貼ることで、生物多様性の保全に貢献する場で採れた水産物であることのPRにも活用しています。
このように、30by30目標の達成を目指すことは、地域の経済・社会・環境問題の同時解決につながるNbSの基盤となる健全な生態系を確保するという観点からも重要であると言えます。
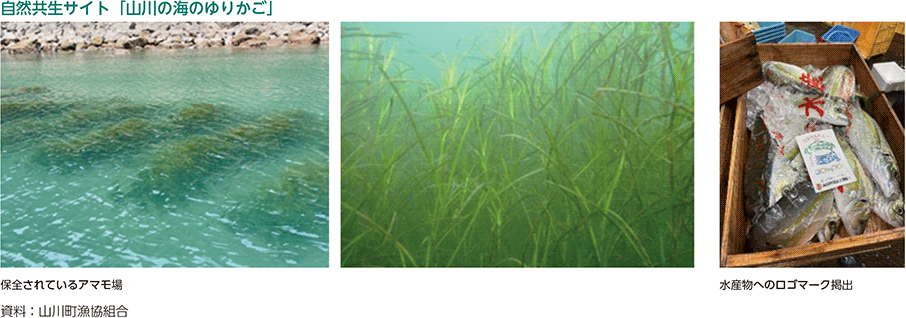
各国もOECMの設定を進めており、現在、OECM国際データベースには、2025年3月末時点で14か国において、砂漠、海洋、自然林等様々なタイプのOECMが登録されています。我が国のOECMは、里地里山里海のように人が手を入れることによって維持されてきた自然環境や、生物多様性に配慮した持続的な産業活動が行われている地域など、人と自然が共生してきた場所に着目し、民間等によるボトムアップの制度を構築していることが特徴的です。GBFの2050年ビジョンは、愛知目標から引き継がれた「自然と共生する世界」です。このような我が国のOECMの制度や考え方を積極的に国際発信することを通して、人が手を入れることによって維持される自然環境の重要性や、自然と共生するOECM制度が国際的なルールでも受け入れられるよう努め、世界における「自然と共生する社会」の実現に貢献していきます。