2024年の世界の年平均気温は、観測史上最高となり、世界規模で異常気象が発生し、大規模な自然災害が増加するなど、気候変動問題は、人類や全ての生き物にとっての生存基盤を揺るがす「気候危機」とも言われる状況です。我が国においても、2024年は史上最高の年平均気温を観測したことに加え、農産物の収量及び品質の低下、熱中症のリスク増加等、気候変動の影響が全国各地で現れています。現下の危機を克服し、循環共生型社会、「新たな成長」を実現していくためには、利用可能な最良の科学的知見に基づいて取組の十全性(スピードとスケール)の確保を図るとともに諸課題をカップリングして解決するための諸政策の統合・シナジー(相乗効果)を推進することが不可欠です。
このような状況認識も踏まえ、第六次環境基本計画では、目指すべき持続可能な社会の姿、循環共生型社会を実現するため、環境・経済・社会の統合的向上の高度化に向け、循環経済(サーキュラーエコノミー)、自然再興(ネイチャーポジティブ)、炭素中立(ネット・ゼロ)等といった個別分野の環境政策を統合的に実施し、シナジーを発揮させ、経済社会の構造的な課題の解決にも結びつけていくため、特定の施策が複数の異なる課題をも統合的に解決するような、横断的に取り組んでいく必要があるとしています。
第2章では、国際的な動向を慨観した後、サーキュラーエコノミー、ネイチャーポジティブ、ネット・ゼロの同時達成に向けたそれぞれの取組を見ていきます。
エネルギー危機、食料危機も相まって、世界は未曾有の複合的な危機に直面しています。国境のない地球規模の環境問題においては、国際社会が誓約した2030年までの目標達成に向け、先進国・途上国の区分を超えて、分断ではなく、共に取り組む「協働」の重要性がかつてなく高まっています。また、経済安全保障の観点からも、厳しい国際情勢を踏まえ、熾(し)烈化する国際競争に対し、環境も踏まえて十全に対処する必要があります。天然資源の争奪を巡っては、世界全体の持続可能性の向上に向けた取組の強化が喫緊の課題です。
現下の国際情勢等も踏まえ、我が国としては「勝負の2030年」まであと5年であることや、ポストSDGsの議論をにらみつつ、シナジーを最大化しながら、これらを実現するための具体的な好事例を示すなどして国際議論を主導していく必要があります。我が国のこれまでの公害問題への対策や、伝統的な自然共生やものを大切にする価値観は、持続可能な経済社会システムの構築に当たって有用で、地域循環共生圏の創造を始めとした環境課題と社会・経済的課題との同時解決を目指し、誰一人取り残さない、「ウェルビーイング/高い生活の質」の向上とパッケージとなった取組を実施するとともに、国際的に発信・展開していくことが重要です。
コラム:世界的危機の課題にシナジーアプローチで挑む
我々の地球は、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの世界的危機に直面しています。そして、これらの課題は相互に関わり合っており、統合的に対処し、相乗効果(シナジー)を活用することの重要性が注目されています。
例えば、国際資源パネル(IRP)が2024年に発行した「世界資源アウトルック2024」報告書では、資源の採取及び加工に関する経済システムが、気候変動、生物多様性の損失、汚染という主要な環境問題と密接に関係していることが示されました。資源効率性・循環性を高める取組が環境負荷削減策として統合的に貢献することが示唆されています。また、生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム(IPBES)が2024年12月に公表した「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価(ネクサス・アセスメント)」においても、生物多様性、気候変動、食料、健康、水資源の1つの要素のみを優先して他の要素を考慮せずに取り組むと、全体としてトレードオフ(相反作用)が発生することが示されました。国連においても、国連経済社会局(UNDESA)と国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は、「パリ協定とSDGsのシナジー強化に関する国際会議」の開催等を通じて、世界の様々な課題に対処するため、気候とSDGsのシナジーを推進する取組を主導してきています。こうした取組には我が国からも複数の専門家が執筆者として参画するなど、課題解決のためのシナジーアプローチの推進に貢献しています。
我が国は、2024年3月に第6回国連環境総会(UNEA6)において「シナジー・協力・連携の国際環境条約及び他の関連環境文書の国内実施における促進に関する決議」を提案し、採択されました(フィジー、カナダ、チリ、スイス、ノルウェー及びペルーも共同提案国)。本決議を踏まえ、各国や国際機関と連携し、シナジーを発揮させることの重要性を発信しつつ、各国において統合的な政策が推進されるよう国際連携を進めていくことが、地球環境課題の解決やSDGsの達成のために重要です。
2025年2月にタイ・バンコクで開催された「第12回持続可能な開発に関するアジア太平洋フォーラム(APFSD)」において、我が国は、公益財団法人地球環境戦略研究機関(IGES)、国連アジア太平洋経済社会委員会(ESCAP)、アジア開発銀行(ADB)と共にイベントを開催し、アジア太平洋地域におけるシナジーアプローチの好事例を幅広く収集し、ノウハウや提言等を取りまとめる「アジア太平洋シナジーレポート」の作成に向けた作業を開始しました。
今、気候変動、生物多様性の損失、汚染という3つの世界的危機への対応に当たって、脱炭素、ネイチャーポジティブ、循環経済等を統合的に実現する経済社会システムの構築が世界的に求められています。我が国としては、ポストSDGsの議論を視野に入れつつ、シナジーを最大化しながら、これらを実現するための具体的な好事例を示すことなどにより、シナジーアプローチの推進を主導していきます。
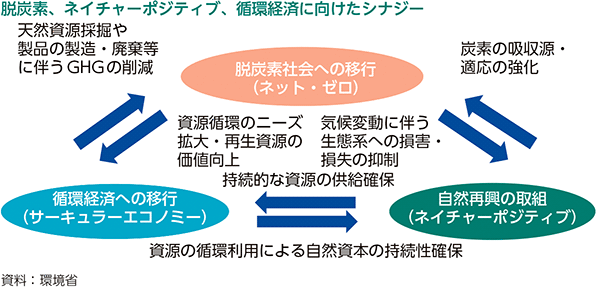
2024年10月にブラジル・リオデジャネイロで開催されたG20環境・気候持続可能性大臣会合では、世界のGDP、人口、温室効果ガス排出量約80%を占めるG20諸国が、気候変動、生物多様性の損失、汚染等の危機に対処するため、G20による緊急行動の強化へのコミットメントを再確認するとともに、議長国ブラジルが設定した4つの優先課題の相互関係を認識し、G20の共同行動の重要性を強調しました。また、1.5度目標達成に向けて気候変動対策を加速させるため、気候変動に対する世界的な資金動員のためのタスクフォース(TF-CLIMA)が、議長国ブラジルのイニシアティブにより設置されました。G20財務トラック及びシェルパトラックが共同して作業する場が設けられたのはこれが初めてであり、TF-CLIMAにおける議論の総括として、2024年10月にアメリカ・ワシントンD.C.でG20財務大臣、気候・環境大臣、外務大臣及び中央銀行総裁合同会合が開催されました。
さらに2024年11月のG20リオデジャネイロ・サミットにおいても、気候変動や生物多様性、循環経済、プラスチック汚染等についての取組の重要性を首脳間で共有しました。
2024年11月、アゼルバイジャン共和国・バクーにて、COP29が開催されました。COP29では、浅尾慶一郎環境大臣から1.5℃目標の実現に向けて世界の排出削減に積極的に貢献することを発信しました(写真2-1-1)。交渉では、気候資金に関する新規合同数値目標(NCQG)について「2035年までに少なくとも年間3,000億ドル」の途上国支援目標が決定され、また、全てのアクターに対し、全ての公的及び民間の資金源からの途上国向けの気候行動に対する資金を2035年までに年間1.3兆ドル以上に拡大するため共に行動することを求める旨が決定されました。加えて、国際的に協力して温室効果ガスの排出削減などを実施するパリ協定第6条の詳細ルールが決定され、完全運用化が実現されました。この機運の高まりを踏まえ、二国間クレジット制度(JCM)を活用したプロジェクトの拡大・加速や、「6条実施パートナーシップ」を通じた6条に基づく取組の世界各国への展開に一層強力に取り組むことで、世界全体の排出削減等に積極的に貢献していきます。

また、2023年に開催されたCOP28において実施された、パリ協定の目標達成に向けた世界全体の進捗を評価する第1回グローバル・ストックテイク(GST)の中で、1.5℃目標達成のための全ての国による緊急的な行動の必要性が強調されました。2025年1月に米国はパリ協定からの脱退を表明しましたが、我が国としては2050年ネット・ゼロの実現に向けた取組を着実に進めるとともに、2050年ネット・ゼロの実現に向け順調な減少傾向にある我が国の温室効果ガス排出・吸収量の実績を世界に示しつつ、パリ協定の運用を通じて、1.5℃目標の達成に向けた世界全体の気候変動対策の野心向上と実施に関する議論に積極的に貢献していきます。
2024年10月、コロンビア共和国・カリにおいて、CBD-COP16が開催されました。この会議は、2030年に向けた生物多様性に関する世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組(GBF)」が、2022年12月にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)第2部において採択されて以来、初めての生物多様性条約締約国会議(CBD-COP)となりました。GBFでは、2050年ビジョンである“自然と共生する世界”の実現に向け、4つのゴールと2030年ミッションである“自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め反転させる”こと、いわゆるネイチャーポジティブの実現に向けた23のターゲットが設定されています。また、GBFの実施には、社会全体の関与や、関連する環境危機への対策との連携が必要であるとされています。CBD-COP16では、GBFの実施状況を評価する仕組みについて具体的な進め方を決定すること等が期待されていました。
CBD-COP16には、CBD-COPとしては過去最多の1万3,000人超が参加しました。締約国以外にも、地方公共団体、研究機関、NGO、先住民グループ、民間企業等も多数参加し、生物多様性に対する関心の高まりを表していました。CBD-COP16では、遺伝資源のデジタル配列情報(DSI)の使用に係る利益配分に関する多国間メカニズムの大枠や、先住民及び地域社会の生物多様性保全への参画を強化・確保するための常設補助機関の設置が決定されました。しかし、GBFの実施のための資源動員等の議題で議論が収束せず、会期末の翌朝まで議論が続けられたものの、定足数不足によりCBD-COP16は中断されました。これを受けて、2025年2月、イタリア・ローマにおいてCBD-COP16再開会合が開催されました。再開会合では、GBFの実施状況を評価する仕組みとして、使用が任意のものを含めて約200の指標が設定され、それら指標を用いて締約国が報告を行うこと、締約国からの報告や科学的なデータを活用してGBFの達成状況に関する地球規模のレビューをCBD-COP17及びCBD-COP19で行うこと等が決定されました。このほか、GBFの実施に必要な資金を動員するためのガイダンスである資源動員戦略フェーズII(2025-2030)が採択されるなど、残されていた全ての議題について決定が採択され、CBD-COP16は正式に閉幕しました。
コラム:IPBESのネクサス(相互関係)及び社会変革アセスメント報告書
2024年12月、ナミビア共和国・ウイントフックでIPBES総会第11回会合(IPBES11)が開催されました。この会合においては、以下の2つのIPBESアセスメント報告書の政策決定者向け要約(SPM)が審議・承認されました。これらの報告書は、それぞれ日本を含む世界各国の専門家170名程度により、2021年から約3年間をかけて執筆されたものです。
「生物多様性、水、食料及び健康の間の相互関係に関するテーマ別評価(ネクサス・アセスメント)」は、生物多様性、水、食料、健康、気候変動といったネクサス(相互関係)の各要素に関する危機の解決のため、対策の選択肢や、各選択肢に関して要素間のシナジー(相乗効果)とトレードオフ(相反作用)について明らかにすることを目的に実施されました。報告書は、各要素が相互に関連しており、それぞれの要素が危機の増大に直面していることを示した上で、要素ごとに別々に対応している現状の取組は、非効果的かつ非生産的であると指摘しています。その解決策として、複数の要素の危機に同時に対応することによりコベネフィット(相乗便益)が生じるような、「ネクサス・アプローチ(相互的アプローチ)」を提示しています。また、ネクサス・アプローチによる71の対応の選択肢について分析を行った結果、慎重に実施しなければ他の要素に非意図的な悪影響を及ぼす場合がある一方で、社会システム全体にわたり持続性を高める変化の機会を生み出し、要素間のシナジーを高めることができる場合があることなどが指摘されています。さらに、様々な主体が協力的、順応的、かつ衡平なかたちで対応に携わることで、更に大きな効果を得ることができるとしています。
「生物多様性の損失の根本的要因、変革の決定要因及び生物多様性2050ビジョン達成のためのオプションに関するテーマ別評価(社会変革アセスメント)」は、GBFにおいて掲げられている生物多様性2050年ビジョン「自然と共生する世界」やSDGsの達成等に寄与する社会変革を加速するため、対応の選択肢、決定要因、課題等を明らかにする目的で実施されました。SPMでは、「社会変革は急務であり困難であるが、可能である」とした上で、生物多様性の損失及び自然衰退に最も寄与するセクターにおける体系的な変革や、自然及び衡平性のための経済システムの変革、人間と自然との基本的な相互の結びつきを認識及び優先した社会的な見方及び価値観へのシフトなど、5つの主要な戦略を提案しています。また、社会変革の実現に向けては、個人を含め、すべての関係者やセクターが重要な役割を有するとして、すべての主体による参画を促しています。
コラム:生物多様性国際ユース会議 横浜2024
GBFでは、ターゲットの一つとして、女性や若者(ユース)、先住民等の多様な主体による政策決定への参画が盛り込まれています。
環境省では、CBD-COP10の開催に併せ、「生物多様性国際ユース会議 in 愛知 2010」を開催するなど、これまでも次世代を担うユースの参画を支援してきました。また、この会議を契機として、国際的なユース組織である「生物多様性グローバルユースネットワーク(GYBN)」が設立されました。GYBNの設立以来、環境省は、生物多様性日本基金を通じて国際的なユースの活動支援を継続して実施してきており、女性や先住民等を含むユースの参画が、様々な条約、国際会議、そして世界各地でも活発化しています。
こうしたユースの活動を更に支援し、国際的な生物多様性に関する意思決定への参画やGBFの実施への貢献を促すことを目的に、2024年8月、「生物多様性国際ユース会議 横浜2024」が神奈川県横浜市内で開催されました。この会議は、生物多様性に関する国際ユース会議としては、前回の愛知での会合から実に14年ぶりの開催となります。会議はGYBNが主催し、横浜市、生物多様性条約事務局及び環境省が共催したほか、公益財団法人 イオン環境財団、2030生物多様性枠組実現日本会議(J-GBF)、国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J)、ソフトバンク等が開催を支援しました。会議には、我が国を含む世界各地域の83か国から計126名のユースが参加し、生物多様性に関するそれぞれの経験を共有するとともに、行動計画の検討等の活発な議論が行われました。また、エクスカーションやイベント等の交流の場を通じて、国や地域の垣根を越えたユース同士の積極的なネットワーキングも行われました。会議の成果は「社会変革のための横浜ユースロードマップ」として取りまとめられ、その成果は、昨年開催されたCBD-COP16の場でも発表されました。今後、GYBNを始めとしたユース団体がロードマップを基に、生物多様性に関する意思決定に対し一層積極的に参画することが期待されます。また、ユース等の多様な主体が生物多様性の保全及び持続可能な利用に貢献していくことができるよう、環境省としても引き続き支援や取組を続けていきます。
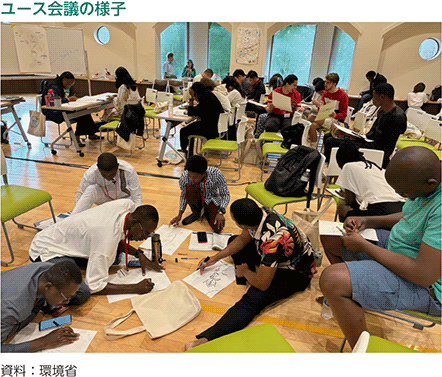

2024年7月、アメリカ合衆国・ニューヨークの国連本部において持続可能な開発のためのハイレベル政治フォーラム(HLPF)閣僚級会合が「2030アジェンダの強化と、複数の危機の時代における貧困の撲滅:持続可能で強靱(じん)かつ革新的な解決策の効果的な提供」をテーマに開催されました。
HLPFは、2015年9月、国連サミットにおいて採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」の実施状況を世界的にレビューする場と位置付けられており、毎年、SDGsの17のゴールから複数の分野を選んで実施状況のフォローアップが行われています。HLPF2024では、SDG1(貧困)、SDG2(飢餓)、SDG13(気候変動)、SDG16(平和)、SDG17(実施手段)についてレビューされ、HLPF及び2024年の国連経済社会理事会ハイレベル・セグメントにおいて閣僚宣言が採択されました。閣僚宣言では、「我々は、国家の気候及び開発政策・行動の効果的な実施に向けたシナジーを強化し、世界の気候目標の達成と2030アジェンダの実現に貢献することを約束する」こと等が盛り込まれました。
環境省からは、滝沢求環境副大臣(当時)が開会式及びスペシャルイベント「気候とSDGsのシナジーを通じて、私たちが望む未来への野心のギャップを埋める」に出席し、UNEA6において日本から提案し採択された「シナジー促進のための決議」を紹介するとともに、シナジーの強化の取組を引き続き推進していく意思を明確にし、アジア太平洋地域各国のシナジーの事例に関するレポートの作成を進める考えを表明しました。また同イベントでは、「気候変動とSDGsのシナジーに関する第2次グローバル・レポート」が公表され、世界的課題解決に向けたシナジーアプローチの重要性が強調されました。