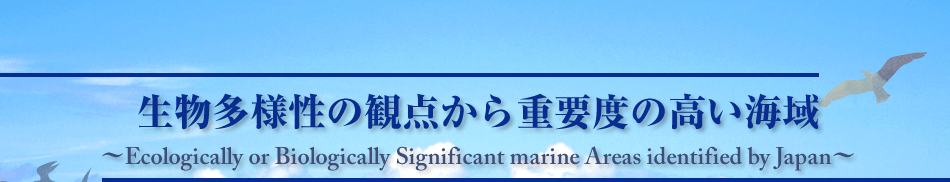環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沿岸域 > 16501 能登半島
沿岸域 16501 能登半島
基本情報  出典
出典
| 該当市区町村 | 石川県羽咋市、志賀町、珠洲市、能登町、輪島市 |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 621 |
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準1、2、5が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
能登半島西岸の羽咋川河口域から半島北部を経て、田ノ浦、宇出津までの海域である。羽咋(はくい)から柴垣にかけて、遠浅の砂浜が続いており、豊かな砂浜の生物相が見られる(加藤, 1999)。これらの砂浜海岸はシギ・チドリ類の春秋の渡り期の種数・個体数も比較的多い(環境省, 2001)。羽咋の海岸には、イカリモンハンミョウの生息地がある。また、志賀町周辺海域には、ここしか記載がない日本固有種のノトカズナギが生息する(Kimura and Sato, 2007)。能登半島には大規模なガラモ場が広がり、西岸は人工的に造成された「のり島」が多いが、ウップルイノリ、クロノリなど含むアマノリ群落もある(環境省, 2001)。増穂浦は、遠浅の内湾の砂浜で、日本海で最も多様な打ち上げ貝群集が見られる場所である。波打ち際には、フジノハナガイやナミノコガイが多く、潮下帯にはカバザクラやベニガイが棲息している。海士崎周辺には、シバナなどの塩性湿地があり、岩礁の生物も豊かである(加藤, 1999)。珠洲岬から飯田湾、宇出津までの海域は海藻藻場とアマモ場が広がる海域で(池森, 2013)、タチアマモ(九十九湾)、スゲアマモ(飯田湾)の生息地は重要である(Nakaoka and Aioi , 2001)。鳳珠郡能登町の地先沿岸はガラモ場があり、種類・希少種が多い(環境省, 2001)。当該海域に含まれる九十九湾には希少種のマシコヒゲムシの生息地がある(金沢大学自然計測応用研究センター, 2005)。
環境情報  出典
出典
| 干潟(平方キロメートル) | |
|---|---|
| 藻場(平方キロメートル) | 96.7 |
| サンゴ(平方キロメートル) | |
| 自然海岸の長さ(キロメートル) | 136.7 |
| 自然海岸の占める割合(パーセント) | 48.5 |
| 砂堆(在情報) | |
| マングローブ |
生物情報の例(※)  出典
出典
| ■基準1 |
| 【維管束植物】 |
| スゲアマモ |
| タチアマモ |
| ■基準2 |
| 【鳥類】 |
| アマツバメ(営) |
| イソヒヨドリ(営) |
| ウミウ |
| ウミウ(営) |
| ウミネコ |
| ウミネコ(営) |
| クロサギ(営) |
| コチドリ(営) |
| シロチドリ(営) |
| ミサゴ(営) |
| 【魚類】 |
| ウルメイワシ(産) |
| キュウリエソ(産) |
| クロソイ(産) |
| サヨリ(産) |
| マアジ(産) |
| マイワシ(産) |
| マダラ(産) |
| 【頭足類】 |
| スルメイカ |
| ホタルイカ |
| マダコ |
| ヤリイカ |
| ■基準3 |
| 【魚類】 |
| シロウオ |
| 【昆虫類】 |
| イカリモンハンミョウ |
| カワラハンミョウ |
| ハラビロハンミョウ |
| 【貝類】 |
| タマキビ |
| 【維管束植物】 |
| タチアマモ |
| 【藻類】 |
| ウミフシナシミドロ |
| ■基準7 |
| 【貝類】 |
| イツマデガイ |
| 【維管束植物】 |
| アマモ |
| ウミヒルモ |
| オオクグ |
| コアマモ |
| シバナ |
※掲載種は抽出基準に合致するとして解析に用いた種のリストであって、当該海域に分布する種全てではない。
生物情報の例の凡例:無印:その種の分布情報あり。(営):営巣地・繁殖地に隣接する海域。(産):産卵海域。(※):解析には用いていないが、種の生息が確認されたとして追加で掲載したもの。(★):解析には生息情報を用いたが、当該海域では近年生息・生育の確認がない、あるいはすでに絶滅した可能性があるもの。