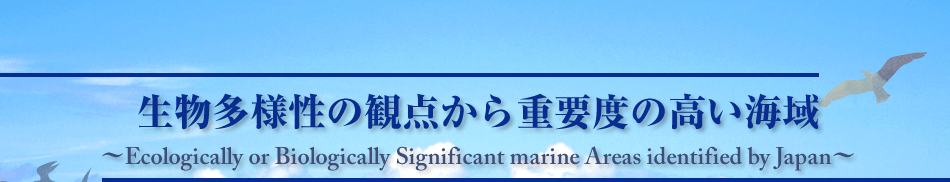環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沿岸域 > 15208 吹上浜
沿岸域 15208 吹上浜
基本情報  出典
出典
| 該当市区町村 | 鹿児島県南さつま市、日置市 |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 106 |
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準2、3、7、8が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
大浦川河口から万之瀬川を経て、江口漁港周辺までの吹上浜を中心とする海域である。大浦川河口にはメヒルギの生育するマングローブ林があり、マングローブ林の地理的希少分布地である(環境省, 2001)。吹上浜は、総延長約30kmの九州で最大規模の砂浜であり、自然の状態が残されている遠浅の海岸には、コタマガイ、ナミノコガイ、チョウセンハマグリ、キンセンガニといった砂浜海岸を代表する生物が豊産する(加藤、私信)。海岸の北側から南側にかけてハビタットのグラデーション(砂浜地形のバラエティ)がみられ、それに応じた生物相が形成されている。吹上浜には、多くの海洋生物が出現することがわかっており、また、多くの沿岸魚類の仔稚魚が保育場として波打ち際を利用していること等が明らかとなっている(中根ら, 2006; 大富ら, 2005; Nonomura et al., 2007; 富岡ら, 2012; Nakane et al., 2013)。また、アカウミガメの重要な繁殖地である(環境省, 2001)。万之瀬川河口には、自然度の高い河口干潟が広がり、そこにハマグリが棲息していることは特筆すべき点であり(加藤、私信)、フタハピンノや河口外側の干潟にはナミノコガイが多産する(環境省, 2001)。河口周辺はシギ・チドリ類の春秋の渡りおよび越冬期の種数・個体数が比較的多く、ミヤコドリでは最小推定個体数の0.25%以上が記録されており、クロツラヘラサギの渡来もある(環境省, 2001)。
環境情報  出典
出典
| 干潟(平方キロメートル) | 0.6 |
|---|---|
| 藻場(平方キロメートル) | |
| サンゴ(平方キロメートル) | |
| 自然海岸の長さ(キロメートル) | 25.6 |
| 自然海岸の占める割合(パーセント) | 81.9 |
| 砂堆(在情報) | |
| マングローブ |
生物情報の例(※)  出典
出典
| ■基準1 |
| 【鳥類】 |
| クロツラヘラサギ |
| 【甲殻類等】 |
| フタハピンノ |
| 【貝類】 |
| オキシジミ |
| クリイロカワザンショウ |
| タケノコカワニナ |
| ハマグリ |
| ■基準2 |
| 【鳥類】 |
| アマツバメ(営) |
| シロチドリ(営) |
| ハヤブサ(営) |
| 【爬虫類】 |
| アカウミガメ |
| 【魚類】 |
| タチウオ(産) |
| ブリ(産) |
| マアジ(産) |
| マイワシ(産) |
| マサバ(産) |
| ■基準3 |
| 【甲殻類等】 |
| アシハラガニ |
| チゴガニ |
| ハクセンシオマネキ |
| フタハピンノ |
| 【貝類】 |
| オキシジミ |
| タケノコカワニナ |
| タマキビ |
| ハマグリ |
| ■基準7 |
| 【爬虫類】 |
| アカウミガメ |
| 【甲殻類等】 |
| オサガニ |
| ハクセンシオマネキ |
| 【貝類】 |
| カノコガイ |
| タケノコカワニナ |
| ハマグリ |
| フトヘナタリ |
| ■基準8 |
| 【天然記念物】 |
| 万之瀬川河口域のハマボウ群落及び干潟生物群集 |
※掲載種は抽出基準に合致するとして解析に用いた種のリストであって、当該海域に分布する種全てではない。
生物情報の例の凡例:無印:その種の分布情報あり。(営):営巣地・繁殖地に隣接する海域。(産):産卵海域。(※):解析には用いていないが、種の生息が確認されたとして追加で掲載したもの。(★):解析には生息情報を用いたが、当該海域では近年生息・生育の確認がない、あるいはすでに絶滅した可能性があるもの。