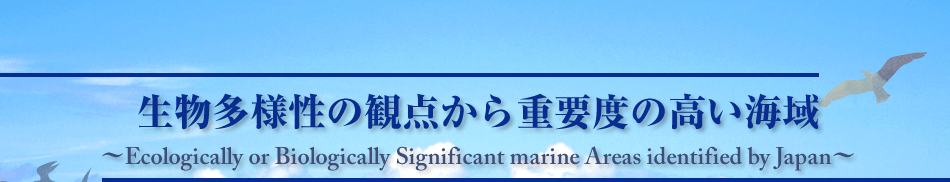環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沿岸域 > 14803 沖縄島中南部
沿岸域 14803 沖縄島中南部
基本情報  出典
出典
| 該当市区町村 | 沖縄県うるま市、沖縄市、糸満市、西原町、中城村、那覇市、南城市、八重瀬町、豊見城市、北中城村 |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 514 |
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準1、2、3、4、7、8が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
沖縄島中南部、勝連半島(平安座島、宮城島、伊計島南部)から沖縄島南端を経て国場川河口(那覇港)までの海域である。藪地島周辺沿岸には藻場が広がり、ホンダワラ属、クビレミドロの最大の生育地である。中城湾には、干潟、藻場、海草藻場が広く見られる。中城湾北部(泡瀬、久場沖など)にはリュウキュウスガモ、リュウキュウアマモ、ベニアマモなど海草8種が生育する。キバナガミズギワゴミムシ、ケシウミアメンボなどが生息するのも特徴である。トカゲハゼ、キララハゼの日本唯一の生息地であり、トビハゼ、マサゴハゼの日本での分布南限地。ナカグスクオサガニの日本唯一の生息地で泡瀬は特に希少貝類が豊富である。中城湾南部の藻場にはヒジキ(南限)、フタエヒイラギモク、ボタンアオサ、ハイテングサなどが生育する。泡瀬干潟、佐敷干潟ともシギ・チドリ類の渡来地であり、春秋の渡り期の種数・個体数が比較的多い。中城湾の南の佐敷町から与那原町にかけての砂泥干潟にはトカゲハゼやシオマネキが生息している(環境省, 2001)。金武湾同様、中城湾もハゼ科魚類を中心に多様で独特な魚類相が形成されていることが判明しつつある(鈴木ら, 1996; 鈴木ら, 1999; 鈴木ら, 2011)。具志干潟もシギ・チドリ類の春秋の渡りおよび越冬期の種数・個体数が比較的多く、キアシシギでは最小推定個体数の0.25%以上が記録されている。具志干潟から大嶺岬の岩礁地帯の潮間帯にはキバナガミズギワゴミムシが生息する。与根干潟にはオオツヤウロコガイ、コハクオカミミガイ、イチョウシラトリなどの希少種が多く生息する(環境省, 2001)。
環境情報  出典
出典
| 干潟(平方キロメートル) | 8.1 |
|---|---|
| 藻場(平方キロメートル) | 5.4 |
| サンゴ(平方キロメートル) | 0.9 |
| 自然海岸の長さ(キロメートル) | 63.1 |
| 自然海岸の占める割合(パーセント) | 31.8 |
| 砂堆(在情報) | |
| マングローブ |
生物情報の例(※)  出典
出典
| ■基準1 |
| 【哺乳類】 |
| ジュゴン |
| 【鳥類】 |
| クロツラヘラサギ |
| 【甲殻類等】 |
| シオマネキ |
| ツノメチゴガニ |
| 【貝類】 |
| オイランカワザンショウ |
| オキシジミ |
| クリイロカワザンショウ |
| ゴマセンベイアワモチ |
| シイノミミミガイ |
| ユンタクシジミ |
| ■基準2 |
| 【哺乳類】 |
| ザトウクジラ |
| ジュゴン |
| 【鳥類】 |
| イソヒヨドリ(営) |
| エリグロアジサシ |
| エリグロアジサシ(営) |
| クロサギ(営) |
| クロハラアジサシ |
| コアジサシ |
| コアジサシ(営) |
| コチドリ(営) |
| シロチドリ(営) |
| ベニアジサシ |
| ベニアジサシ(営) |
| ■基準3 |
| 【哺乳類】 |
| ジュゴン |
| 【鳥類】 |
| エリグロアジサシ |
| コアジサシ |
| ベニアジサシ |
| 【爬虫類】 |
| イイジマウミヘビ |
| エラブウミヘビ |
| ヒロオウミヘビ |
| 【魚類】 |
| Rhincodon typus |
| キララハゼ |
| トカゲハゼ |
| 【甲殻類等】 |
| クシテガニ |
| クメジマハイガザミモドキ |
| シオマネキ |
| ベニシオマネキ |
| ミナミヒライソモドキ |
| 【貝類】 |
| イチョウシラトリ |
| イボウミニナ |
| オウトウハマシイノミガイ |
| オキシジミ |
| カワアイ |
| クリイロコミミガイ |
| コハクオカミミガイ |
| ドロアワモチ |
| フィリピンハナビラガイ |
| ヘラサギガイ |
| ミズゴマツボ |
| 【サンゴ類】 |
| Acropora acuminata |
| Galaxea astreata |
| Heliopora coerulea |
| Montipora cactus |
| Pachyseris rugosa |
| Pavona cactus |
| 【藻類】 |
| イチイズタ |
| ウスガサネ |
| カラクサモク |
| クビレミドロ |
| ホソエガサ |
| ■基準4 |
| 【哺乳類】 |
| ジュゴン |
| 【八放サンゴ類】 |
| Isis hippuris |
| Junceella fragilis |
| Pseudobebryce acanthoides |
| Subergorgia suberosa |
| ■基準7 |
| 【甲殻類等】 |
| シオマネキ |
| 【貝類】 |
| イチョウシラトリ |
| イボウミニナ |
| カブラツキガイ |
| シラオガイ |
| ハボウキガイ |
| ヒロクチカノコ |
| フトヘナタリ |
| ヘナタリ |
| ヤマトクビキレガイ |
| 【維管束植物】 |
| ウミヒルモ |
| コアマモ |
※掲載種は抽出基準に合致するとして解析に用いた種のリストであって、当該海域に分布する種全てではない。
生物情報の例の凡例:無印:その種の分布情報あり。(営):営巣地・繁殖地に隣接する海域。(産):産卵海域。(※):解析には用いていないが、種の生息が確認されたとして追加で掲載したもの。(★):解析には生息情報を用いたが、当該海域では近年生息・生育の確認がない、あるいはすでに絶滅した可能性があるもの。