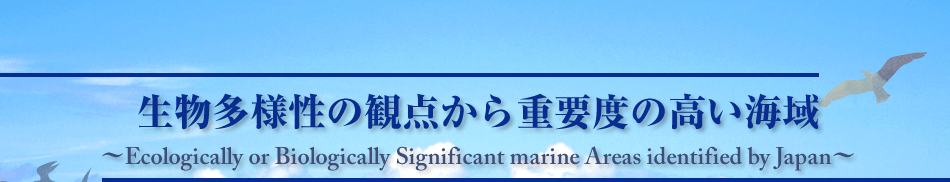環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沿岸域 > 12207 東京湾奥部
沿岸域 12207 東京湾奥部
基本情報  出典
出典
| 該当市区町村 | 神奈川県川崎区、千葉県浦安市、市川市、船橋市、習志野市、千葉市美浜区、東京都江戸川区、江東区、港区、大田区、中央区、品川区 |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 124 |
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準2、3が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
三番瀬、谷津干潟、葛西、東京港野鳥公園、中央海浜公園、森ヶ崎、多摩川河口を含む東京湾の干潟・浅瀬の海域である。東京湾はかつては広大な河口及び干潟が広がっていたが、現在では数カ所を残すのみとなっており、当該海域はそれらのわずかに残された干潟や河口生態系を含む。三番瀬では春秋の鳥類の渡りおよび越冬期の種数・個体数が多く、ハマシギでは最小推定個体数の1%以上、ミヤコドリ、ダイゼン、メダイチドリ、キアシシギ、キョウジョシギ、ミユビシギでは0.25%以上が記録されている。また、アサリなどの二枚貝類ならびにエドガワミズゴマツボが生息し、東京湾水の浄化機能も高い。谷津干潟も春秋の鳥類の渡りおよび越冬期の種数・個体数が多く、ハマシギでは最小推定個体数の1%以上、セイタカシギ、ダイゼン、シロチドリ、メダイチドリ、オオソリハシシギ、チュウシャクシギ、キアシシギ、キョウジョシギ、ミユビシギでは0.25%以上が記録されている。また、ホウロクシギ、アカアシシギが記録されている。 東京湾奥部の河口域はトビハゼ生息地の北限となっている。江戸川放水路では人工放水路であるが砂質から泥干潟そして一部ヨシからなる塩性湿地があり、オキシジミガイなどの閉鎖的な干潟の生物が豊富である。東京港野鳥公園・海浜公園・森ケ崎でも春秋の渡り期の種数・個体数が比較的多く、セイタカシギ、アカアシシギが記録されている。多摩川河口は、東京湾でまとまった規模の塩性湿地を含む河口干潟が残されている唯一の水域であり,56種のベントスが確認されるなど、さまざまな生物相が確認されている(56種のベントスのうち16種が希少種・絶滅危惧種)。同河口域は、東京湾内のいわゆる「干潟ネットワーク」の重要なノード域としてのハビタットの一つとなっている可能性もある。鳥類も春秋の渡り期の種数・個体数が比較的多く、セイタカシギが記録されている。また、ところどころにカキ礁があり、さまざまな生物の生息場所を提供している(環境省,2001; 柚原ら,2013; 風呂田,2007)。
環境情報  出典
出典
| 干潟(平方キロメートル) | 7.9 |
|---|---|
| 藻場(平方キロメートル) | |
| サンゴ(平方キロメートル) | |
| 自然海岸の長さ(キロメートル) | 0.0 |
| 自然海岸の占める割合(パーセント) | 0.0 |
| 砂堆(在情報) | |
| マングローブ |
生物情報の例(※)  出典
出典
| ■基準1 |
| 【貝類】 |
| エドガワミズゴマツボ |
| オキシジミ |
| クリイロカワザンショウ |
| マテガイ |
| ムシヤドリカワザンショウ |
| ヤマトシジミ |
| 【その他無脊椎動物】 |
| ウメタテケヤリムシ |
| ■基準2 |
| 【鳥類】 |
| アジサシ |
| アジサシ(営) |
| ウミネコ |
| ウミネコ(営) |
| オオセグロカモメ |
| オオセグロカモメ(営) |
| カワウ(営) |
| コアジサシ |
| コアジサシ(営) |
| コチドリ(営) |
| シロチドリ(営) |
| セグロカモメ |
| ハジロクロハラアジサシ |
| ユリカモメ |
| 【魚類】 |
| マコガレイ(産) |
| 【頭足類】 |
| イイダコ |
| マダコ |
| ヤリイカ |
| ■基準3 |
| 【鳥類】 |
| コアジサシ |
| 【魚類】 |
| ウナギ |
| エドハゼ |
| 【甲殻類等】 |
| アシハラガニ |
| ウモレベンケイガニ |
| クシテガニ |
| チゴガニ |
| ベンケイガニ |
| ヤマトオサガニ |
| 【貝類】 |
| オキシジミ |
| タマキビ |
| ■基準7 |
| 【甲殻類等】 |
| オサガニ |
| ヤマトオサガニ |
| 【貝類】 |
| ヤマトシジミ |
| 【維管束植物】 |
| ウラギク |
※掲載種は抽出基準に合致するとして解析に用いた種のリストであって、当該海域に分布する種全てではない。
生物情報の例の凡例:無印:その種の分布情報あり。(営):営巣地・繁殖地に隣接する海域。(産):産卵海域。(※):解析には用いていないが、種の生息が確認されたとして追加で掲載したもの。(★):解析には生息情報を用いたが、当該海域では近年生息・生育の確認がない、あるいはすでに絶滅した可能性があるもの。