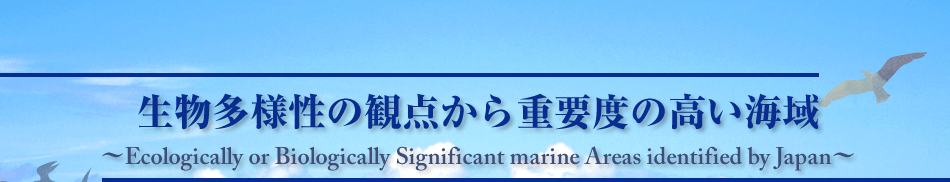環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沿岸域 > 10202 オホーツク沿岸
沿岸域 10202 オホーツク沿岸
基本情報  出典
出典
| 該当市区町村 | 北海道興部町、斜里町、小清水町、北見市、網走市、紋別市、湧別町 |
|---|---|
| 面積(平方キロメートル) | 452 |
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準1、2、5、6が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
オホーツク海沿岸の紋別周辺から知床半島の付け根までの海域である。(能取岬を除く)知床半島までの沿岸は自然の砂浜海岸がよく残っている大規模な砂浜海岸である。また、紋別市から東に、コケム湖、シブノツナイ湖、サロマ湖、能取湖、藻琴湖、濤沸湖などの海跡湖が断続的につながるといった砂浜海岸としての特徴があり、これらの海跡湖沿岸部の多様性は非常に高い(Suda et al., 200; Hiwatari et al., 2003; Suda et al., 2004; Hiwatari et al., 2004; Hiwatari et al., 2005; Suda et al., 2005)。特に、鳥類の多様性が高く、オオセグロカモメやワシカモメ、ミツユビカモメなどのカモメ類、オオワシ、ミサゴ、ハヤブサなどの猛禽類、ショウドツバメなどが多く見られる。コケム湖周辺ではシギ・チドリ類の春秋の渡りの時期には種数・個体数が多く、アカエリヒレアシシギでは最小推定個体数の1%以上、メダイチドリ、チュウシャクシギ、ハマシギでは0.25%以上が記録されている(重要湿地500)。海跡湖周辺海岸にはアッケシソウの群落が見られ、またスゲアマモ、コアマモのアマモ場も見られる。特にサロマ湖は日本最大の潟湖性のアマモ場であり、湖底にはカキ礁遺骸が存在する。ホタテガイ、ホッカイエビ、カキなどの重要な生息地となっている(環境省, 2001)。ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、ゴマフアザラシなどの哺乳類やオショロコマ、(降海型)イトヨなども見られる。冬季には、沿岸部に流氷が接岸し、これにより多くの鰭脚類や猛禽類が見られるようになる。また流氷により非常に高い生産性がもたらされる特異な環境を呈する。沖側はオホーツク中冷水により生産性が高くなる。
環境情報  出典
出典
| 干潟(平方キロメートル) | 4.1 |
|---|---|
| 藻場(平方キロメートル) | 14.1 |
| サンゴ(平方キロメートル) | |
| 自然海岸の長さ(キロメートル) | 121.6 |
| 自然海岸の占める割合(パーセント) | 76.3 |
| 砂堆(在情報) | |
| マングローブ |
生物情報の例(※)  出典
出典
| ■基準1 |
| (哺乳類) |
| ゴマフアザラシ |
| ワモンアザラシ |
| (鳥類) |
| オオワシ |
| ショウドウツバメ |
| (魚類) |
| オショロコマ |
| (維管束植物) |
| スゲアマモ |
| ■基準2 |
| (鳥類) |
| アジサシ |
| アジサシ/営巣地・繁殖地 |
| イソヒヨドリ/営巣地・繁殖地 |
| ウミウ |
| ウミウ/営巣地・繁殖地 |
| ウミネコ |
| ウミネコ/営巣地・繁殖地 |
| オオセグロカモメ |
| オオセグロカモメ/営巣地・繁殖地 |
| カモメ |
| コチドリ/営巣地・繁殖地 |
| ショウドウツバメ/営巣地・繁殖地 |
| シロカモメ |
| シロチドリ/営巣地・繁殖地 |
| セグロカモメ |
| ハヤブサ/営巣地・繁殖地 |
| ミサゴ/営巣地・繁殖地 |
| ミツユビカモメ |
| ユリカモメ |
| ワシカモメ |
| (魚類) |
| イカナゴ/産卵域 |
| クロソイ/産卵域 |
| スケトウダラ/産卵域 |
| ニシン/産卵域 |
| ハタハタ/産卵域 |
| ホッケ/産卵域 |
| マダラ/産卵域 |
| ■基準3 |
| (鳥類) |
| シノリガモ |
| (魚類) |
| オショロコマ |
| カワヤツメ |
| (甲殻類等) |
| アリアケモドキ |
| (維管束植物) |
| アッケシソウ |
| ■基準7 |
| (魚類) |
| カワヤツメ |
| 降海型イトヨ |
| (その他無脊椎動物) |
| ユムシ |
| (維管束植物) |
| アッケシソウ |
| アマモ |
| コアマモ |
※掲載種は抽出基準に合致するとして解析に用いた種のリストであって、当該海域に分布する種全てではない。
生物情報の例の凡例:無印:その種の分布情報あり。(営):営巣地・繁殖地に隣接する海域。(産):産卵海域。(※):解析には用いていないが、種の生息が確認されたとして追加で掲載したもの。(★):解析には生息情報を用いたが、当該海域では近年生息・生育の確認がない、あるいはすでに絶滅した可能性があるもの。