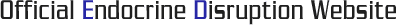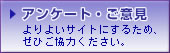「内分泌かく乱作用とは」
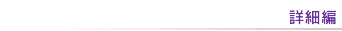
「詳細編」
「内分泌かく乱作用とは」タイトル
ホルモン受容体の標的細胞内での分布
ホルモンは、その化学構造からステロイドホルモン(例えば、エストロジェン、アンドロジェン)、アミノ酸誘導体ホルモン(例えば、甲状腺ホルモン)、及びペプチドホルモン(例えば、性腺刺激ホルモン)に大別されます。一般に脂溶性が高いステロイドホルモン類は、容易に細胞膜を通過して核受容体と結合します。一方、水溶性が高いペプチドホルモン類は、細胞膜を通過できないので,膜受容体と結合します。標的器官に到達したホルモンは、核または細胞膜に存在する特異的な受容体と結合し、標的細胞に対する一連の生理学的変化を引き起こします。
ホルモンと受容体との結合における特異性
ホルモンと受容体との結合には「鍵と鍵穴」といわれるように、一対一の厳密な組み合わせが存在すると考えられてきました。しかし、例えば、エストロジェン受容体に対しては、エストロジェン以外の約200以上の物質が「合い鍵」として作用し、微弱ながらもエストロジェン作用を示すことが判明してきました。逆に、受容体と結合することで、正常は作用が阻害されることもあります。こういった外因性物質による正常なホルモン作用のかく乱は、ホルモンと受容体との結合する段階で最も発生しやすいと考えられています。
しかし、内分泌かく乱作用の作用点は、必ずしもこのホルモンと受容体との結合段階に限定されません。【ホルモン受容体を介在した内分泌かく乱作用の典型的メカニズム】
ホルモンの作用メカニズム(エストロジェンを例として)
エストロジェン-エストロジェン受容体による複合体は、二量体となって核内DNA の上流に存在するエストロジェン応答領域(エストロジェン応答エレメント、ERE)に結合します。この際、共役因子と呼ばれる多様な蛋白質も結合に参加します。その結果生じた巨大分子がRNAポリメラーゼに認識され、ERE下流に存在するDNA配列を雛型としたmRNA更には蛋白質の発現が誘導されることになります。
エストロジェンによって発現が誘導される蛋白質としては、ラクトフェリン、プロジェステロン受容体、ビテロジェニンなどが知られています。
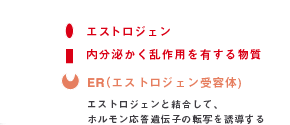
受容体と結合してホルモンに類似した作用を示す例(エストロジェンを例として)
内分泌かく乱作用を有する物質がERと結合する。この物質とERの複合体はエストロジェンと類似の作用をもつため、エストロジェンの作用は増強される。
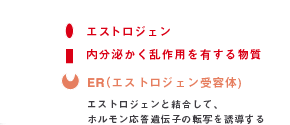
受容体と結合するもののホルモン作用を阻害する例(エストロジェンを例として)
内分泌かく乱作用を有する物質が、ERと結合し、ERを占有する(エストロジェンと競合する)。しかし、この物質とERの複合体はエストロジェンと類似の作用は示さず、結果としてエストロジェン作用は阻害される。

| エストロジェン受容体は、生物進化の初期から存在していたホルモン受容体であるため、進化の過程で多様化し鍵穴としての厳密さが低下したと考えられています。その結果、約200以上の物質と結合し、それらの物質が、微弱ながらもエストロジェン作用を示します。 一方、アンドロジェン受容体に結合することによって体内アンドロジェンの結合及び作用を阻害する例としては約70の化学物質が見出されていますが、受容体に結合しても、実際にアンドロジェン作用を示す化学物質はごく少数です。 |
ヒトやマウスの細胞核に存在するエストロジェン受容体はERαとERβの二種類が存在することが明らかになっています。ERαが機能していなくても、まだエストロジェンを結合する受容体があることから、ERβが見出されました。化学物質によってはERα、ERβそれぞれに結合しやすいものがあることもわかってきました。それぞれの受容体のノックアウトマウスを利用することにより、エストロジェン作用の解析が進んでいます。エストロジェン作用をもつ化学物質の影響を研究するためには、ERα、ERβそれぞれへの結合を介した影響を区別して考察することが必要です。発達中のどの時期に化学物質が受容体に結合し、どのような影響が出てくるのなど、地道な基礎研究が極めて重要です。 |