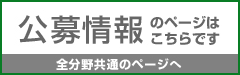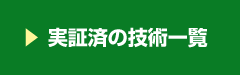対象技術分野
自然地域トイレ し尿処理技術分野
自然地域におけるし尿問題
山岳地などでは一般的に電力供給や給水事情が悪く、従前は穴を掘り、貯留し、浸透させる方法がとられ、また、トイレが設置されていない場所では、屋外排泄も行われてきました。一方で、近年の登山ブームで多くの人が山岳地を訪れ、 し尿による公共用水域の水質への影響、植物への影響等を懸念する声が高まっています。
こうした声の高まりを背景に、山小屋事業者、地方公共団体によるし尿処理に対する改善への取組みが始まり、同時に洗浄水や処理水を放流しないし尿処理装置も急速に開発、商品化されてきました。
インフラが未整備な自然地域におけるし尿の影響を軽減するためには、これらの技術を導入するなどして、自主的な取組が期待されているところです。
 |
 |
自然地域トイレ技術分野に用いられるし尿処理技術の分類】
| 大分類 (水の有無) |
小分類 (処理方式) |
特色 | 前処理の 有無 |
技術説明 |
|---|---|---|---|---|
| 水使用 (水洗) |
生物処理 | 土壌 | 有 | 土壌粒子による吸着・ろ過や土壌微生物を利用して処理する。(簡易水洗) |
| 生物膜および土壌微生物を利用して処理する(簡易水洗) | ||||
| 薬剤添加 | 有 | 生物処理の補助剤として薬剤を添加する。 | ||
| 生物処理の補助剤として酵素剤を添加する。 | ||||
| カキガラ | 有 | 接触剤としてカキガラを使用し、生物膜により処理する。 | ||
| 膜 | 有 | 活性汚泥によって処理した後、膜で固液分解する。 | ||
| 木質 | 有 | 接触剤である木質チップに汚水を散水し、生物膜で処理する。 | ||
| プラスチック | 有 | 接触剤としてプラスチックを使用し、生物膜により処理する。(参考事例として掲載) | ||
| オゾン | 有 | 接触ばっ気で処理した後、オゾンで処理する。 | ||
| - | - | - | ||
| 化学処理 | - | - | - | |
| 物理処理 | 乾燥・焼却 | 無 | 乾燥・焼却して、粉末化する。(参考事例として掲載) | |
| - | - | - | ||
| 水不要 | 生物処理 | 木質 | 無 | 木質系接触剤の中に投入し、撹拌・送気を行い処理する。 |
| - | - | - | ||
| 化学処理 | - | - | - | |
| 物理処理 | 乾燥・焼却 | 無 | 乾燥・焼却して、粉末化する。(参考事例として掲載) | |
| - | - | - |
※本技術分類表は、環境技術実証事業における技術の特色からの分類であり、学問的見地からの分類ではありません。
※前処理とは、あらかじめ固形物を分離したり、微生物が分解しやすくするため液状化するなど、次の処理を行いやすくするための行程を指します。
自然地域トイレし尿処理技術導入事例データベース
<利用上の注意点>この事例データベースは、環境技術実証事業における実証済み技術と自然公園における環境省及び地方公共団体が設置した非放流式し尿処理技術の導入事例を下記のア~キの7つの視点で分類したものです。
なお、本データベースは技術を評価したものではないので、技術選択のための参考情報であることに留意して活用してください。(適切な技術を選択するためには、その他様々な視点から複合的に検討することが必要です。)
<分類>
- ア)全体を見る
- データベース一覧
- イ)電力の必要性で見る
- 商用電源/自家発電設備/自然エネルギー(太陽光、風力、他)/不要
- ウ)水の確保方法で見る
- 公共水道/雨水、雪解け水/井戸等/運搬/不要
- エ)輸送方法で見る
- 自動車/ヘリコプター/人力/左記以外
- オ)最低気温で見る
- -5℃以上/-5℃より低い
- カ)設置エリアで見る
- 山岳/山麓(車両可)/海浜/離島/左記以外
- キ)処理方式で見る
- 下記の「特色」をクリックすると表示されます。
| 処理方式 | 特色 | 技術説明 |
|---|---|---|
| 生物処理 | 土壌 | 土壌粒子による吸着・ろ過や土壌微生物を利用して処理する。 |
| 生物膜および土壌微生物を利用して処理する。 | ||
| 薬剤添加 | 生物処理の補助剤として薬剤、酵素材を添加する。 | |
| カキガラ | 接触材としてカキガラを使用し、生物膜により処理する。 | |
| 膜 | 活性汚泥によって処理した後、膜で固液分解する。 | |
| 木質 | 接触材である木質チップに汚水を散水し、生物膜で処理する。 | |
| 物理処理 | 乾燥・焼却 | 乾燥・焼却して、粉末化する。 |
| 上記以外 | - |
上記の他、自然地域で主に利用されているし尿処理方法
| 技術タイプ | 特徴/留意点 |
| 携帯トイレ | 排泄物をパッキングして持ち帰る。回収・廃棄には、地元自治体との調整が必要。 |
| カードリッジ式 | 汚水をカードリッジ式のタンクに貯留し、ヘリ等によって山麓等に下ろして汲取る。 |
| 浄化槽 | 浄化槽法に基づく点検・管理が必要。処理水の放流先が必要。 環境省浄化槽サイト |
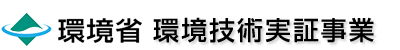

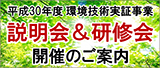
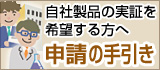










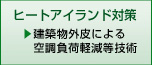
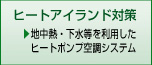

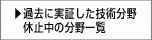





 山岳、海岸、離島などの自然地域
山岳、海岸、離島などの自然地域 自然循環式トイレの設置
自然循環式トイレの設置