環境再生・資源循環
レジ袋に係る調査(平成21年度)
1. 都道府県の取組
1.調査対象
「地方自治体と住民」、「地方自治体と事業者」及び「地方自治体と住民と事業者」という地方自治体(都道府県)が関与する枠組みの中で連携・協働して行われる、レジ袋削減の取組を対象とした。事業者が独自で取り組みを行っている事例は対象外とした。
2.調査方法
47都道府県、18政令市、41中核市、23特別区 計129自治体について、平成22年2月1日現在のレジ袋削減に係る取組状況及び今後の取組予定等(平成23年3月末まで)について、ヒアリング等により取組内容を個別に調査した。
3.回答項目の定義
以下、回答に用いられている用語の定義となる。
| 回答 | 定義 |
|---|---|
| 実施済で継続実施 | 平成22年2月1日までに取組を実施しており、平成22年度も引き続き、取組を継続(拡充を含む)する予定の場合 |
| 実施済で縮小・中止見込 | 平成22年2月1日までに取組を実施しているが、平成22年度以降、取組を縮小又は中止する予定の場合(時期未定) |
| 未実施で実施見込 | 平成22年2月1日までに取組を実施していないが、平成22年度中に、係る取組を実施すると見込まれる場合 |
| 未実施で検討予定 | 平成22年2月1日までに取組を実施していないが、平成22年度中に、具体的な取組を検討する予定がある場合 |
| 未実施で実施検討予定なし | 平成22年2月1日までに取組を実施しておらず、平成22年度中に取組を実施する具体的な計画や検討の予定がない場合 |
| 不明・空欄 | 判断不明の場合 |
※当調査では集計過程で四捨五入を行っているため、各項目の合計が100%にならない場合がある。
4.調査結果の概要
| (1) | 平成22年2月1日現在、全47都道府県で何らかの方法でレジ袋削減の取組が実施されている。政令市・中核市・特別区では同8割超となっており、今後もこうした取組みはさらに広がっていくことが見込まれる。 |
| (2) | レジ袋削減の具体的な取組手法としては、(a)全廃・有料化手法(自治体による条例化、自主協定の締結、自治体からの協力要請等により、レジ袋を全く提供しない又は有料で提供する手法)、(b)全廃・有料化以外の手法(特典提供方式や事業者への協力要請等によりレジ袋の削減を図る手法)、(c)有料化・有料化以外を問わず事業者に削減手法の選択を委ねる手法等があり、全国で地域特性を反映して、様々な手法が実施されている。 |
| (3) | 協定締結によるレジ袋の有料化については、都道府県では平成22年2月1日現在、17自治体において一斉実施が行われている。また10自治体では今後実施見込み、又は検討予定となっている。 さらに、政令市・中核市・特別区では30自治体において協定締結によるレジ袋の有料化が行われている。また、7自治体では今後実施見込み、または検討予定となっている。政令市・中核市・特別区では縮小・中止の動きも見られるが、これは有料化の取組が県レベルの施策へと広がったことによるものであり、全国レベルでは一層の広がりが見込まれる。 こうした有料化の実施に伴い、レジ袋辞退率やマイバッグ持参率が80%を越える等、高い削減効果が確認された。 加えて、「マイバックに係る協定を締結(有料化は任意)」「県内一部のエリア、事業者との間で都道府県もレジ袋有料化協定に関与」、「協定方式に依らない消費者(住民)主導で事業者をレジ袋の有料化に誘導」した事例等も見られた。 |
| (4) | レジ袋削減の手段として、地域通貨(エコマネー)や商品券・割引券等の提供を受けて買い物に使用、市町村が指定する商品や抽選券、景品等を提供することにより、レジ袋の受取辞退を促そうという「特典提供方法」が24都道府県、の23政令市・中核市・特別区で実施され、相当の削減効果をあげていることが確認された。 ただ、特典提供方法については有料化の取組の広がりと共に活動を縮小する動きも見られる。 |
| (5) | 特典提供方式以外にも、事業者への協力要請、優れた事業者の認定制度、事業者・住民との連携体制の整備、事業者の活動支援、都道府県・市町村との連携活動、PR・普及啓発活動など、都道府県や政令市・中核市・特別区が様々な方法に取り組んでいる。 |
| (6) | レジ袋の有料化や特典提供方式等を問わず、事業者に削減手法の選択を委ねる手法も全国に広がっています。 |
2. 都道府県の取組詳細
1.都道府県のレジ袋削減に対する取組状況
| 平成22年2月1日時点で、全47都道府県がレジ袋削減に対して何らかの取組を行っている。 |
|---|
| ○ | 前回調査(平成20年11月1日時点)では38自治体で実施されていたものが、当調査(平成22年2月1日時点)では47全自治体で取組まれるまでに広がっている。 |
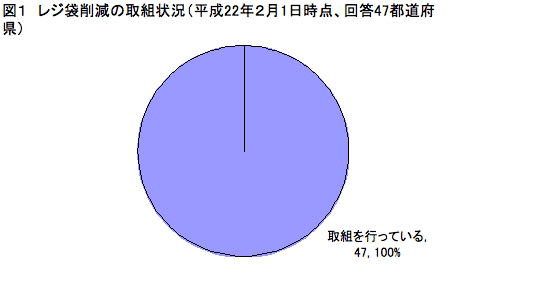
2.都道府県のレジ袋削減に対する今後の取組意向
| 今後の取組意向に関しては、「拡充予定」「継続予定」合わせて9割以上の自治体が継続的な取組の意向を示している。 |
|---|
| ○ | 拡充予定が25自治体(全体の53%)、継続予定が21自治体(全治の45%)、 中止・縮小予定が1自治体(全体の2%)となっている。 |
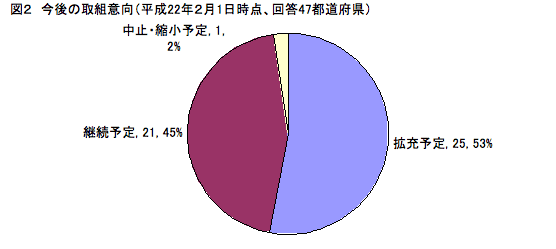
3.都道府県が直接・間接に関与する事業者の取組状況
対象とする事業者の取組の範囲
本調査では、事業者単独の取組を除き、地方自治体が直接的又は間接的に関与して、市民団体、事業者、地方自治体との、"地域の協働と連携"により実施される、レジ袋削減の取組を調査対象とした。
[都道府県が直接・間接に関与する事業者の取組状況の要旨]
- 「レジ袋全廃」については2自治体において取組が見られる。
- 「レジ袋有料化」については8割弱の自治体で実施している。今後取組実施に前向きな意向を示している自治体も多い。
- 「特典提供方式」については4割超の自治体で実施している。一方で3割弱の自治体では今後も取組の意向はない。
- その他の取組としては「マイバッグの無料配布、無料貸出、マイバッグ持参の呼びかけ等」、「レジ袋の要・不要の声掛け」が共に8割以上の自治体で実施されている。また「レジ袋の小型化・薄肉化」も4割超と比較的高い実施率となっている。ただ、「レジ袋無料配布枚数の自主的制限」については2割弱の実施率に留まる。
| (1) |
レジ袋全廃の取組については、2自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で、7割以上の自治体が「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (2) |
レジ袋有料化の取組については、8割弱の自治体が「実施済で継続実施」となっている。また、今後も増加が見込まれる。 |
| (3) |
特典提供方式については4割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」の自治体も3割弱ある。 |
| (4) |
マイバックの無料配布等については8割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (5) |
事業者によるレジ袋の要・不要の声掛けについては8割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (6) |
事業者によるレジ袋無料配布枚数の自主的制限については「実施済で継続実施」の自治体は2割弱に留まる。また、3割弱の自治体は「未実施で実施検討予定なし」となっ ている。 |
| (7) |
事業者によるレジ袋の小型化・薄肉化については、4割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、2割弱の自治体では「未実施で実施検討予定のなし」となっている。 |
| (8) |
事業者によるその他取組については、「実施済で継続実施」の自治体は1割弱に留まる。 |
4.都道府県の取組方針
[政令市・特別区・中核市の取組方針の要旨]
- 基本的な取組方針として「有料化・非有料化を問わず、レジ袋削減の取組そのものを推進する」が最多となっている。
- 条例の制定については実施している自治体は見られない。今後についても殆どの自治体で実施検討予定は無いとしている。
- 協定の締結によるレジ袋有料化については全体の4割弱の自治体で実施済となっている。一方で全体の4割超の自治体では検討予定もなしとなっている。
- 他の具体的な取組としては「事業者への協力要請」、「事業者の活動支援」が全体の8割前後、「組織体制の整備」、「市町村・特別区との連携」が共に全体の7割以上と高い実施率となっている。また、「優れた事業者への認定制度」も全体の3割の実施率となっている。
- 関連調査については「消費者の認知度・意向調査」「レジ袋削減効果調査」が共に全体の4割弱と、「事業者への影響調査」の2割弱と比較して高い実施率となっている。
- PR・普及活動については「テレビ、ラジオ、新聞、広報紙等への取組掲載」、「チラシ、ポスター、リーフレット等の作成・配布」が全体の8割前後、「環境学習、環境教育を通じたPR」は同7割超、「市民独自の普及啓発活動の支援」が同6割超となっている。ただ、「マイバッグの無料配布、コンテストの開催と展示」も同4割弱と比較的高い実施率となっている。
| (1) |
基本的な取組方針としては「都道府県独自の施策により有料化・非有料化を問わず、レジ袋削減の取組そのものを推進する」が最多となっている。 |
| (2) |
条例の制定については1自治体でのみ「未施済で検討予定」となっており、他の自治体では実施検討の予定も無い。 |
| (3) |
協定の締結によるレジ袋の有料化ついては4割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で4割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (4) |
事業者への協力要請については8割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (5) |
優れた事業者への認定制度については、3割の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で6割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (6) |
組織体制の整備については、7割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (7) |
事業者の活動支援については、8割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (8) |
市町村・特別区との連携等については、7割の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で2割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (9) |
消費者の認知度・意向調査については、4割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で4割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (10) |
レジ袋削減効果調査については、4割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (11) |
レジ袋有料化による事業者への影響調査については、2割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で6割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (12) |
マイバッグの無料配布、コンテストの開催と展示については、4割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (13) |
テレビ、ラジオ、新聞、広報紙等への取組掲載については、8割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (14) |
チラシ、ポスター、リーフレット等の作成・配布については、8割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (15) |
市民独自の普及啓発活動の支援については、6割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で3割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (16) |
環境学習、環境教育を通じたPRについては、7割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」も自治体も2割弱ある。 |
| (17) |
レジ袋の全廃、有料化の実施に係る間接的関与については、2割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」の自治体も6割弱になる。 |
| (18) |
その他の取組については、1割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定もない」自治体も4割超になる。 |
5.レジ袋有料化の取組詳細
[レジ袋有料化の取組詳細の要旨]
- 実施地域については、「都道府県での一部地域で実施」が7割超となっている。
- 参加店舗の状況についてはスーパーマーケットでは「殆ど全部が参加」「半数以上が参加」計で5割超、生協・大学生協・農協では同3割超となり、各1割前後である百貨店、ドラッグストア、コンビニと比較して高い参加状況となっている。
- レジ袋削減の評価項目としては「マイバック持参率」、「レジ袋辞退率」を採用している自治体が多い。
- レジ袋辞退率、マイバック持参率の推移共に「随分向上した」「やや向上した」計で8割弱と高い効果を見せている。
| (1) |
実施地域については、「都道府県全域での実施の一環」が3割弱となった。また「都道府県の一部地域で実施」は7割超となっている。 |
| (2) |
スーパーマーケットの参加状況については、「殆ど全部の参加」、「半数以上が参加」計で5割超となっている。 |
| (3) |
生協・大学生協・農協の参加状況については、「殆ど全部の参加」、「半数以上が参加」計で3割超となっている。 |
| (4) |
百貨店の参加状況については、「殆ど全部の参加」が1割超となっている。 |
| (5) |
ドラッグストアの参加状況については、「殆ど全部の参加」、「半数以上が参加」計で1割超となっている。 |
| (6) |
コンビニの参加状況については、「殆ど全部の参加」で1自治体に留まる。 |
| (7) |
その他業種の参加状況については、「半数以上参加」で1自治体に留まる。 |
| (8) |
マイバック持参率、レジ袋持参率を評価項目と設定している自治体が多数となる。 |
| (9) |
レジ袋の辞退率の推移については、8割の自治体で「随分向上した」、もしくは「やや向上した」となっている。 |
| (10) |
マイバック率の推移については、8割弱の自治体で「随分向上した」、もしくは「やや向上した」となっている。 |
| (11) |
レジ袋辞退率、マイバック持参率も有料化前後で50ポイント程度の上昇が見られる。 |
6.レジ袋有料化以外の取組詳細
<レジ袋有料化以外の取組に関する特徴的な事例>
| 宮城県 |
キャッシュバッグ方式:レジ袋を辞退(マイバッグを持参)した顧客に対し、1会計あたり一定の金額をキャッシュバッグする方式。 エコポイント方式:レジ袋を辞退(マイバッグを持参)した客に対し、商店街が独自に発行するポイントカード・スタンプカードに、1会計あたり一定のポイント・スタンプを付与する方式。(ポイント・スタンプは,集めた数に応じた商品又は金券等に交換する。) |
|---|---|
| 埼玉県 | 「埼玉県におけるマイバッグ持参運動とレジ袋削減運動の取組に関する協定」(平成20年9月22日締結)に基づき、レジ袋の削減のための有料化(無料配布中止)はもとより、事業者による特典提供方式等の取組も協定参加事業者・市民団体・埼玉県が協働するとしている。 |
| 千葉県 | レジ袋を配布している小売事業者が、レジ袋辞退に対する値引きやポイントの付与等を例とした「特典提供方式」などレジ袋削減に関し、自由に目標を設定し、宣言を行い、実際に取り組み、年に一度県に報告をするというサインアップ方式を取り入れている。 |
| 徳島県 | 消費者がレジ袋の受取を辞退すると、事業者よりその消費者に対して、ポイントカード等が付与され、一定数が貯まると、一定額を割り引くサービスが提供される。 |
| 香川県 | 事業者ごとに個々のポイント付与、1回2円引きなどを実施しており、実施方法、内容は事業に任せている。 |
3. 政令市・中核市・特別区の取組状況
1.調査対象
「地方自治体と住民」、「地方自治体と事業者」及び「地方自治体と住民と事業者」という地方自治体(政令市・中核市・特別区)が関与する枠組みの中で連携・協働して行われる、レジ袋削減の取組を対象とした。事業者が独自で取り組みを行っている事例は対象外とした。
2.調査方法
47都道府県、18政令市、41中核市、23特別区 計129自治体について、平成22年2月1日現在のレジ袋削減に係る取組状況及び今後の取組予定等(平成23年3月末まで)について、ヒアリング等により取組内容を個別に調査した。
3.回答項目の定義
以下設問への回答に用いられている用語の定義となる。
| 回答 | 定義 |
|---|---|
| 実施済で継続実施 | 平成22年2月1日までに取組を実施しており、平成22度も引き続き、取組を継続(拡充を含む)する予定の場合 |
| 実施済で縮小・中止見込 | 平成22年2月1日までに取組を実施しているが、平成22年度以降、取組を縮小又は中止する予定の場合(時期未定) |
| 未実施で実施見込 | 平成22年2月1日までに取組を実施していないが、平成22年度中に、係る取組を実施すると見込まれる場合 |
| 未実施で検討予定 | 平成22年2月1日までに取組を実施していないが、平成22年度中に、具体的な取組を検討する予定がある場合 |
| 未実施で実施検討予定なし | 平成22年2月1日までに取組を実施しておらず、平成22年度中に取組を実施する具体的な計画や検討の予定がない場合 |
| 不明・空欄 | 判断不明の場合 |
※当調査では集計過程で四捨五入を行っているため、各項目の合計が100%にならない場合がある。
以下調査項目1については、当調査で対象とした82全自治体(政令市・中核市・特別区)を対象に集計
| 平成22年2月1日時点で、約8割超の自治体がレジ袋削減に対して何らかの取組を行っている。 |
|---|
| ○ | 平成22年2月1日時点で、82政令市・中核市・特別区のうち69自治体(全体の84%)ではレジ袋削減に対して何らかの取組を行っている。 |
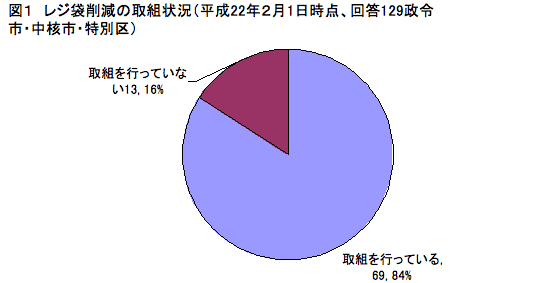
以下調査項目2~6については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていると回答のあった69自治体を対象に集計
2.政令市・中核市・特別区のレジ袋削減に対する今後の取組意向
| 今後の取組意向に関しては、「拡充予定」「継続予定」合わせて9割以上の自治体が継続的な取組の意向を示している。 |
|---|
| ○ | 拡充予定が32自治体(全体の46%)、継続予定が35自治体(全治の51%)、中止・縮小予定が2自治体(全体の3%)となっている。 |
| ○ | 中止・縮小予定の2自治体(青森市・宮崎市)については「政令市・中核市・特別区」レベルでやっていたものを、県レベルの取組に発展させたことが中止・縮小予定の背景と見られる。そのため、全国レベルで見たレジ袋削減の取組は今後より広がっていくことが見込まれる。 |
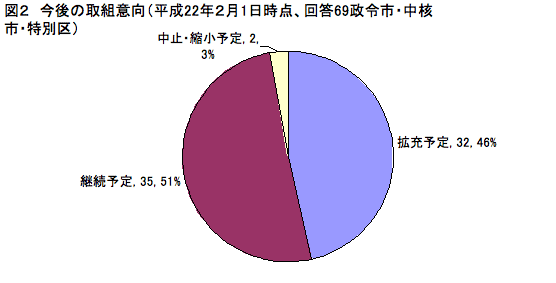
以下調査項目2~6については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていると回答のあった69自治体を対象に集計
3.政令市・中核市・特別区が直接・間接に関与する事業者の取組状況
対象とする事業者の取組の範囲
本調査では、事業者単独の取組を除き、地方自治体が直接的又は間接的に関与して、市民団体、事業者、地方自治体との、"地域の協働と連携"により実施される、レジ袋削減の取組を調査対象とした。
[政令市・中核市・特別区が直接・間接に関与する事業者の取組状況の要旨]
- 「レジ袋全廃」については取組実施の自治体が見られない。
- 「レジ袋有料化」については、5割弱の自治体で実施している。今後取組実施に前向きな意向を示している自治体も多い。
- 「特典提供方式」については3割の自治体で実施している。一方で同程度の自治体では今後も取組の意向はない。
- その他の取組としては「マイバッグの無料配布、無料貸出、マイバッグ持参の呼びかけ等」「レジ袋の要・不要の声掛け」が共に6割以上の自治体で実施されている。また「レジ袋の小型化・薄肉化」も3割弱と比較的高い実施率となっている。ただ、「レジ袋無料配布枚数の自主的制限」については1割弱に留まっている。
| (1) |
レジ袋全廃の取組については、実施している自治体はない。検討予定の自治体も1つに留まる。 |
| (2) |
レジ袋有料化の取組については、5割弱の自治体が「実施済で継続実施」となっている。また、今後も取組に前向きな意向を見せている自治体も多い。 |
| (3) |
特典提供方式については3割の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」の自治体も3割弱ある。 |
| (4) |
マイバックの無料配布等については6割以上の自治体で「実施済で継続実施」となっている。また、今後も増加が見込まれる。 |
| (5) |
事業者によるレジ袋の要・不要の声掛けについては7割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (6) |
事業者によるレジ袋無料配布枚数の自主的制限については「実施済で継続実施」の自治体は1割弱に留まる。 |
| (7) |
事業者によるレジ袋の小型化・薄肉化については、3割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (8) |
事業者によるその他取組については、「実施済で継続実施」の自治体は1割弱に留まる。 |
以下調査項目2~6については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていると回答のあった69自治体を対象に集計
4.政令市・特別区・中核市の取組方針
[政令市・特別区・中核市の取組方針の要旨]
- 基本的な取組方針として「有料化・非有料化を問わず、レジ袋削減の取組そのものを推進する」が最多となっている。
- 条例の制定については1自治体でのみ実施済となっている。他の自治体では実施検討の予定も無い。
- 協定の締結によるレジ袋有料化ついては全体の4割超の自治体で実施済となっている。一方で全体の5割弱の自治体では検討予定もなしとなっている。
- 他の具体的な取組としては「事業者への協力要請」「組織体制の整備」「事業者の活動支援」が全体の6割以上と高い実施率となっている。また、「優れた事業者への認定制度」も全体の4割以上の実施率となっている。ただ、「近隣市町村・特別区との連携」では全体の2割と他の取組と比較して低い実施率となっている。
- 関連調査については「消費者の認知度・意向調査」「レジ袋削減効果調査」が全体の4割前後と、「事業者への影響調査」の1割超と比較して高い実施率となっている。
- PR・普及活動については「環境学習、環境教育を通じたPR」は9割超、「テレビ、ラジオ、新聞、広報紙等への取組掲載」が同8割弱、「チラシ、ポスター、リーフレット等の作成・配布」が全体の7割超、「マイバッグの無料配布、コンテストの開催と展示」が同6割弱、「市民独自の普及啓発活動の支援」が同5割超といずれも高い実施率となっている。
| (1) |
基本的な取組方針としては「政令市・中核市・特別区独自の施策により有料化・非有料化を問わず、レジ袋削減の取組そのものを推進する」が最多となっている。 |
| (2) |
条例の制定については1自治体でのみ「実施済で継続実施」となっており、他の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (3) |
協定の締結によるレジ袋の有料化については4割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (4) |
事業者への協力要請については7割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。また、今後の取組に前向きな意向を示している自治体も多い。 |
| (5) |
優れた事業者への認定制度については、4割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (6) |
組織体制の整備については、6割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。また、今後の取組に前向きな意向を示している自治体も多い。 |
| (7) |
事業者の活動支援については、6割の自治体で「実施済で継続実施」となっている。また、今後の取組に前向きな意向を示している自治体も多い。 |
| (8) |
近隣市町村・特別区との連携等については、2割の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で7割超の自治体では「未実施で実施の検討予定なし」となっている。 |
| (9) |
消費者の認知度・意向調査については、4割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (10) |
レジ袋削減効果調査については、4割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で5割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (11) |
レジ袋有料化による事業者への影響調査については、1割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で7割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (12) |
マイバッグの無料配布、コンテストの開催と展示については、6割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で2割超の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (13) |
テレビ、ラジオ、新聞、広報紙等への取組掲載については、8割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (14) |
チラシ、ポスター、リーフレット等の作成・配布については、7割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。 |
| (15) |
市民独自の普及啓発活動の支援については、5割超の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方で4割弱の自治体では「未実施で実施検討予定なし」となっている。 |
| (16) |
環境学習、環境教育を通じたPRについては、9割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定もない」自治体は1割に満たない。 |
| (17) |
レジ袋の全廃、有料化の実施に係る間接的関与については、2割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」の自治体も8割弱になる。 |
| (18) |
その他の取組については、1割弱の自治体で「実施済で継続実施」となっている。一方、「未実施で実施検討予定なし」の自治体も6割弱になる。 |
以下調査項目2~6については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていると回答のあった69自治体を対象に集計
5.レジ袋有料化の取組詳細
[レジ袋有料化の取組詳細の要旨]
- 実施地域については、「市町村・特別区単独での実施」が6割超となる。また「都道府県全域での実施の一環」も3割超ある。
- 参加店舗の状況についてはスーパーマーケットでは「殆ど全部が参加」「半数以上が参加」計で6割超となり、生協・大学生協・農協では同4割、百貨店の同1割超、ドラッグストアの同2割と比較して高い参加状況となっている。(コンビニにおける同回答はゼロとなった。)
- レジ袋削減の評価項目としては「マイバック持参率」、「レジ袋辞退率」を採用している自治体が多い。
- レジ袋辞退率、マイバック持参率の推移共に「随分向上した」「やや向上した」計で9割弱と高い効果を見せている。
| (1) | 実施地域については、「市町村・特別区単独での実施」が6割超となった。また「都道府県全域での実施の一環」も3割超となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (2) | スーパーマーケットの参加状況については、「殆ど全部の参加」「半数以上が参加」計で6割超となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (3) | 生協・大学生協・農協の参加状況については、「殆ど全部の参加」「半数以上が参加」計で4割となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (4) | 百貨店の参加状況については、1割超の自治体で「殆ど全部の参加」が得られている。一方、「不参加」も7割弱ある。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (5) | ドラッグストアの参加状況については、「殆ど全部の参加」「半数以上が参加」計で2割となっている。一方、「不参加」も7割弱ある。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (6) | コンビニの参加状況については、8割超の自治体で「不参加」となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (7) | その他業種の参加状況については、2割弱の自治体で「不参加」となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (8) | マイバック持参率、レジ袋持参率を評価項目と設定している自治体が多数となる。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (9) | レジ袋の辞退率の推移については、9割弱の自治体で「随分向上した」、もしくは「やや向上した」となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (10) | マイバック率の推移については、9割弱の自治体で「随分向上した」、もしくは「やや向上した」となっている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (11) | レジ袋辞退率、マイバック持参率も有料化前後で50ポイント程度の上昇が見られる。 >> 詳細を見る [PDF 4,768KB] |
以下調査項目2~6については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていると回答のあった69自治体を対象に集計
6.レジ袋有料化以外の取組詳細
<レジ袋有料化以外の取組に関する特徴的な事例>
| 北九州市 | 【北九州市内共通ノーレジ袋ポイント事業「カンパスシール」】 ○参加店での買い物時にレジ袋の受取を辞退すると、ポイントシールが1枚もらえ、シールを20ポイント分集めると、参加店共通の50円割引券として利用できる仕組み。 ○事業開始 平成18年12月 ○参加店舗数 開始時(平成18年12月)147店舗 → 平成22年1月31日現在 300店舗 ○削減効果 [レジ袋辞退率] 開始時(平成18年12月):9.5% → 平成22年1月31日現在 20/7%(目標20%を達成) ・これまでの取組で、レジ袋約5,300万枚を削減(回収されたシール1枚をレジ袋1枚と換算) |
|---|---|
| 福岡市 | ○参加事業者が各事業者の実情に応じた取組(レジでの値引き、ポイントによる値引き券等の進呈など)を実施し,市民団体及び市はその取組を支援する。 |
| 宇都宮市 | ○市から交付されたみやエコファミリー認定証を「みやエコファミリー協力店」に提示し、スタンプカードを受け取る。協力店での買い物にマイバッグを持参し、レジ袋を断ると、スタンプカードに1個押印され、スタンプ50個でエコグッズを贈呈するほか,協力店の買い物券(100円)の進呈または買い物時に100円の値引きがある。認定証の初回の有効期限は3年間で,その後の更新手続きは、5年ごとの更新になる。 |
| 柏市 | ○買い物袋持参協力店制度に登録している各協力店が,レジ袋の受け取りを辞退した消費者に対して、スタンプ、シール、ポイント等の付与又はレジ精算時の商品購入金額からの現金値引きを行っている。 |
| 尼崎市 | ○レジ袋削減に向けた取組については、目標年度を平成22年度とし、ポイント制又は有料化により目標を設定して取組んでいる。 |
| 高松市 | ○レジ袋辞退者またはマイバック持参者に対し、事業者がポイント等を付与している。 |
| 久留米市 | ○特典提供方式は、市民会員が、事業所会員の店舗で「くるめエコ・パートナー」会員証を提示し、マイバッグやマイはしを利用することで特典を受けることができる。特典の内容は、事業所会員それぞれができる範囲で提供してくれており、料金割引や粗品等のプレゼントなどがある。 |
| 品川区 | ○平成14年度より、品川区商店街連合会と連携して、マイバッグ運動を実施。 ○マイバッグ運動に参加する区内の商店街(601店舗:平成21年4月現在)で、バッグ等を持参してレジ袋を断った消費者にコイン1枚を渡している。コインを250枚集めると、品川区内共通商品券(500円相当)と交換できる。 |
| 葛飾区 | ○平成22年度は、かつしかごみ減量・リサイクル推進協議会において商店街においてレジ袋を断った人にスタンプカードに押印を行い、一定のポイントが貯まった時点で景品と交換を行う取り組みを行う予定であり、行政はそのスタンプカードや景品等の支援を行っていく。 |
以下調査項目7については調査対象82自治体(政令市・中核市・特別区)のうち、レジ袋削減に対して何らかの取組を行っていないと回答のあった13自治体を対象に集計
7.政令市・中核市・特別区のレジ袋削減に対する今後の取組意向
| (1) | 今後の取組意向に関しては、「実施予定」「検討予定」合わせて4割弱の自治体が前向きな姿勢を見せている。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (2) | 「今後もレジ袋削減に取組意向が無い」理由として、大きな傾向は見られない。各自治体固有の状況が存在する。 >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
4. 自治体毎のレジ袋削減の取組概要
概要
協定締結方式によるレジ袋有料化については、前回調査(平成20年11月1日時点)では3自治体で実施、5自治体で実施見込みであったものが、当調査(平成22年2月1日時点)では17自治体で取組まれるまでに広がっていることが確認された。
なお、当調査では協定締結方式によるレジ袋有料化として、都道府県が主導的に協定を進めている以外にも、県内市町村と事業者、市民団体が結んでいる協定に広範に参加している自治体も含んでいる。(三重県等)
また、上記17自治体以外でも、秋田県、長野県等が「マイバックに係る協定に係るを締結(有料化は任意)」「県内一部のエリア、事業者との間でもレジ袋有料化協定に関与」の事例も見られた。
更に徳島県では協定方式に依らない、「消費者(住民)主導で事業者をレジ袋の有料化に誘導」した事例等も見られた。
今後は協定を一義的に捉えるのではなく、その内容にまで踏込んだ調査を実施し、自治体毎の特性に合わせたレジ袋削減の取組の波及を図ることが有用と考えられる。
なお、以下ではレジ袋有料化に係る協定に関連する施策以外にも広く各自治体の取組を取上げることとする。
1.都道府県の取組概要
(1)「協定締結方式による全県的なレジ袋有料化実施」自治体の取組概要
| 青森県 | 宮城県 | 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 埼玉県 | 新潟県 |
| 富山県 | 石川県 | 山梨県 | 岐阜県 | 三重県 | 和歌山県 | 広島県 |
| 山口県 | 大分県 | 沖縄県 |
(2)「協定締結方式による全県的なレジ袋有料化実施」以外の自治体の取組概要
| 北海道 | 岩手県 | 秋田県 | 山形県 | 群馬県 | 千葉県 | 東京都 |
| 神奈川県 | 福井県 | 長野県 | 静岡県 | 愛知県 | 滋賀県 | 京都府 |
| 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 徳島県 |
| 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 | 熊本県 |
| 宮崎県 | 鹿児島県 |
2.政令市・中核市・特別区の取組概要<s/trong>
(1)「協定締結方式によるレジ袋有料化実施」自治体の取組概要
| 1.政令市 | ||||||
| 北海道 | 宮城県 | 神奈川県 | 静岡県 | 愛知県 | 京都府 | 大阪府 |
| 兵庫県 | 広島県 | |||||
| 2.中核市 | ||||||
| 北海道 | 青森県 | 福島県 | 栃木県 | 石川県 | 岐阜県 | 愛知県 |
| 兵庫県 | 和歌山県 | 山口県 | 香川県 | 熊本県 | ||
| 3.特別区 | ||||||
| 東京都 | ||||||
(2)「協定締結方式によるレジ袋有料化実施」以外の自治体の取組概要
1.政令市
| 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 新潟県 | 大阪府 | 岡山県 | 福岡県 |
| 2.中核市 | ||||||
| 岩手県 | 秋田県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | 長野県 |
| 愛知県 | 滋賀県 | 大阪府 | 岡山県 | 広島県 | 高知県 | 福岡県 |
| 長崎県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | |||
| 3.特別区 | ||||||
| 中央区 | 港区 | 新宿区 | 文京区 | 品川区 | 目黒区 | 渋谷区 |
| 中野区 | 豊島区 | 北区 | 板橋区 | 足立区 | 葛飾区 | 江戸川区 |
5.レジ袋有料化取組自治体事例
| 青森県 | 福島県 | 茨城県 | 富山県 | 山梨県 | 和歌山県 | 広島県 |
| 山口県 | 大分県 | 沖縄県 |
| 1.青森県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
|---|---|
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●ごみ減量とリサイクルの推進を目的とする「もったいない・あおもり県民運動」の一環として、レジ袋の有料化に取り組む。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●事業者、協力団体及び行政の連携、報道機関、県民等の意識の高まり等により、第1次協定時から県内における主要事業者の参加協力が得られた。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●参加事業者の拡大が課題となる。広報や直接交渉を持続的に実施していく計画。 |
| (5)"レジ袋有料化以外"の 施策への展開状況と課題 |
[ポイント] |
| 2.福島県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●レジ袋削減運動は環境問題に対する象徴的な取組みの一つであることから、広く情報提供しながら県民の環境保全活動を促進していくこととなった。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●協定締結者(事業者、消費者団体、行政(県・市町村))が連携して、住民への広報、PR活動を実施し、周知・普及を図った。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●地球にやさしい"ふくしま"「ストップ・ザ・レジ袋実施店」を募集。 ●協定締結事業者外の事業者にも広く募集を行い、レジ袋削減の輪を広げている。 |
| (5)"レジ袋有料化以外"の 施策への展開状況と課題 |
[ポイント] |
| 3.茨城県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●市町村毎の取組みから、県、事業者、県域団体での協定による締結で県全域への取組みとすることで、レジ袋辞退率は飛躍的に向上。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●消費者への告知活動により、スタートから高い辞退率達成。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●「STOP!地球温暖化」県民宣言。 ●「大好きいばらきエコチャレンジ2009」 |
| 4.富山県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●消費者団体が10年以上にも渡りマイバッグ持参運動に取り組んできたが持参率は20%程度で伸び悩み。 ●こうした中、消費者団体から県に対して消費者団体・事業者・行政がレジ袋削減について議論する場の設置要請があり、平成19年6月に富山県レジ袋削減推進協議会を設立。平成20年4月に無料配布取止めがスタート。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●レジ袋の無料配布取止めにより競合店へ顧客が流れることを懸念する事業者が多かったため、未実施事業者に対して無料配布取止め実施を要請するなど、県内一斉実施に努めた ●県内一斉実施の成功要因は、消費者団体や婦人会の長年に渡る熱心な取組みと、これを受けた事業者の英断と考えられる |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●チラシ、ポスター等で買い物マナーの向上を図っている ●ドラッグストアやホームセンターにも取組の輪を広げている |
| (5)"レジ袋有料化以外"の 施策への展開状況と課題 |
[ポイント] |
| 5.山梨県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●平成19年7月のレジ袋の削減に関するシンポジウムにおいて、「レジ袋の削減について継続的に協議したい」との意見があったことを受け、平成19年8月31日に「山梨県ノーレジ袋推進連絡協議会」が発足。 ●平成20年6月にレジ袋無料配布中止スタート。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●当初から県内大手スーパー等の協力を得られたことからスムーズに活動の輪が広がった。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●個人店舗にレジ袋削減の輪を拡大することが課題。 ●コンビニエンスストア、ホームセンター、ドラッグストアに対しても、レジ袋無料配布の中止を働きかけていく。 |
| 6.和歌山県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●平成22年度末マイバック持参率80%以上に向けて成果を上げており、実施店舗も拡大している |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●県民への周知を目的に、参加事業者の店舗にてキャンペーン等を行った。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●実施店舗拡大によるレジ袋削減の環境への貢献度向上。 |
| (5)"レジ袋有料化以外"の 施策への展開状況と課題 |
[ポイント] |
| 7.広島県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●売場面積が概ね1,000㎡以上を有する事業者及び県内で広範囲に事業展開している事業者を中心に実効果向上を目指す |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●県、市町と事業者区分することで、県内一体となった取組みが可能。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●実施店舗拡大によるレジ袋削減の環境への貢献度向上。 |
| (5)"レジ袋有料化以外"の 施策への展開状況と課題 |
[ポイント] |
| 8.山口県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●消費者団体、事業者、市町村の要望を受け県として取組みを開始した。 ●平成21年4月、レジ袋無料配布中止の取組み開始。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●県等で実施したレジ袋有料化に対するアンケート調査の結果等を用いながら、レジ袋削減の輪を広げた。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●マイバッグ持参運動の継続実施。 ●マイバッグの正しい使い方等の「お買い物エチケット」の啓発。 ●取組店舗や業種の拡大。 |
| 9.大分県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●エコマネー「めじろん」の普及から始まり、この運動の更なる展開を図るため「大分県レジ袋削減検討会議」を設置した。 ●平成21年6月1日からレジ袋無料配布中止を実施。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●エコマネー「めじろん」マイバッグ運動は国体開催が一つの契機。レジ袋有料化の協定に参加する多くの事業者の参加が得られた。レジ袋有料化を進める上で大きな下地になった。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●多くの食品スーパーは協定に参加しているが、他の業種にもレジ袋有料化の輪を拡げることが必要 ●他業種にもレジ袋有料化の輪を広げるために、業種毎に意見交換会を開催 |
| 10.沖縄県 | >> 詳細を見る[PDF 4,768KB] |
| (1)レジ袋削減の取組み経緯と スケジュール |
[ポイント] ●那覇市における実証実験の結果を受けて、平成20年10月1日にレジ袋の有料化がスタート。 |
| (2)レジ袋有料化の効果 | >> 詳細[PDF 4,768KB]をご覧ください |
| (3)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施に至るまでの 課題/対応/解決策 |
[ポイント] ●全県一斉開始には、検討会に県内大手の事業者がすべて参加していることもあり概ね賛成。 ●レジ袋の価格についての協議が難航し、目安3円でスタート。 |
| (4)レジ袋有料化都道府県内 一斉実施後の 課題/対応/解決策 |
[ポイント ] ●マナー啓発ポスターの再掲示、館内放送の強化を図ることで買い物マナーの向上やレジ袋辞退率の伸び悩みに対応している。 ●今後は、沖縄県に多い物産店等をいかに取込むかも課題である |