持続可能な社会を構築していくためには、環境問題を経済の制約要因ではなく新たな成長要因と捉え、環境の保全と経済の活性化とを一体化させていくことが重要であるといった視点から、環境対策に熱心な企業の経営者、環境関連ベンチャー企業の代表者や学識者等をお招きし、平成14年12月に環境大臣主催の「環境と経済活動に関する懇談会」を設置した。
同懇談会では、6回にわたり、企業経営者からの発表や自由討議を行った結果、これからの時代の環境と経済の関係と、その実現に向けた施策の基本的方向について報告を取りまとめたので公表する。
環境省としては、本報告の内容について、平成16年度予算要求をはじめ今後の施策に反映させていく予定である。
-
報告書の概要
| ○ |
環境と経済の直面する状況 |
| |
環境の受容能力の限界が近づき、日本の産業競争力が低下するなかで、環境上の制約を新たな発想や可能性を生み出す原動力として捉え、経済活動の活性化と雇用の創出を実現していくことは十分に可能。
|
| ○ |
これからの時代の基本哲学 |
| |
今日、環境と経済の間に、環境を良くすることが経済を発展させ、経済が活性化することによって環境も良くなっていくような関係(環境と経済の間の好循環)を生み出し、環境と経済が一体となって向上する社会(環境と経済の統合)を実現していくことが重要。これこそ、21世紀の社会のあるべき姿。 |
| 環境と経済の統合のための施策の基本的方向に関する提言 |
環境と経済の統合の実現に向け、必要な法制度の検討も含め施策の検討に早急に着手すべき。(以下、具体的な方向性・施策の例)
| [1] |
各主体による環境行動の推進 |
| |
・ |
企業による環境経営を促進するための仕組みの整備 |
| |
・ |
健全な環境ビジネスを育成し、国民の信頼性を確保 |
| |
・ |
市町村・民間への拡張などによるグリーン購入の充実・強化 |
| |
・ |
「環境ベルマーク」(仮称)制度等による環境情報提供体制等の充実強化 等
|
| [2] |
環境行動が経済的利益につながる基盤の整備 |
| |
・ |
環境保全のメリットを適切に市場の中に反映させる政策手法の充実 |
| |
・ |
融資・保険・投資のグリーン化の促進 等
|
| [3] |
技術革新の促進 |
| |
・ |
バイオマス、ナノテク等、国際競争力を持ち得る分野の技術開発への支援 |
| |
・ |
新しい省エネ技術等の事業化に対する支援、環境技術評価の充実強化 等
|
| [4] |
地域発の環境と経済の好循環の創出 |
| |
・ |
環境ビジネス等の取組を中心とした地域活性化に対する支援 |
| |
・ |
地域住民も主体となって取り組む協働型の地域環境ビジネスの活発化 等
|
| [5] |
環境と経済の好循環の国際的な展開 |
| |
・ |
途上国での人材育成などを通じた国際社会における環境意識の向上 |
| |
・ |
アジア地域への重点的・戦略的な対応 等 |
共通の目標に向かって、国民、企業、行政が環境と経済の統合にそれぞれ取り組んでいくため、中長期的視点に立った国家としての明確なビジョンと工程表が必要。
- 今後の予定
環境省としては、本報告の内容について、平成16年度予算要求をはじめ今後の施策に反映させていく予定である。
【参考】懇談会の構成(50音順、敬称略)
|
| |
天野 明弘 |
財団法人地球環境戦略研究機関関西研究センター所長 |
| |
栗和田 榮一 |
佐川急便株式会社代表取締役会長 |
| |
小林 陽太郎 |
富士ゼロックス株式会社代表取締役会長 |
| |
崎田 裕子 |
ジャーナリスト 環境カウンセラー |
| |
佐々木 元 |
日本電気株式会社代表取締役会長 |
| |
庄子 幹雄 |
鹿島建設株式会社代表取締役副社長 |
| |
手納 美枝 |
株式会社デルタポイントインターナショナル代表取締役 |
| |
半明 正之 |
JFEスチール株式会社代表取締役会長 |
| |
ピーターD・ピーダーセン株式会社 イースクエア代表取締役社長 |
| |
平野 浩志 |
株式会社損害保険ジャパン取締役社長 |
| |
深尾 典男 |
株式会社日経BP日経エコロジー編集長 |
| |
安原 正 |
株式会社サンシャインシティ代表取締役会長 |
| |
八端 憲明 |
株式会社東北エコシステムズ代表取締役社長 |
添付資料
- 連絡先
- 環境省総合環境政策局環境計画課
課長 :鷺坂 長美(6220)
課長補佐:奥山 祐矢(6221)
課長補佐:石川 亨 (6282)
担当 :光地、楠田(6280)
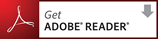
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。