平成13年10月に中央環境審議会に設置された総合政策・地球環境合同部会地球温暖化対策税制専門委員会(委員長:飯野靖四慶應義塾大学教授)は、地球温暖化対策のための税制について、我が国の実情にあった具体的な制度面に関する専門的な検討を行い、「我が国における温暖化対策税制に係る制度面の検討について(これまでの審議の取りまとめ)」を取りまとめました。
記
中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会地球温暖化対策税政専門委員会における審議の経緯及び「我が国における温暖化対策税制に係る制度面の検討について(これまでの審議の取りまとめ)」の概要等は、以下のとおりです。
地球温暖化対策としての税制の検討を行うため、本年10月に中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会の下に「地球温暖化対策税制専門委員会」を設置。関係者からのヒアリングを含め、これまでに6回の会合を開催し、現在までの審議に関して概要以下の取りまとめを行った。
| (1)諸外国の温暖化対策税制 |
|
典型的な「炭素税」を導入したスウェーデン、既存の鉱油税を引き上げたドイツ、自主協定・排出量取引等と組み合わせた「気候変動税」を導入した英国、将来の導入可能性をあらかじめ法定したスイスの4事例を中心に紹介し、以下の諸点等を指摘。 |
|
○ |
各国の対応方法は、新たな税目を複数の化石燃料等を対象に導入するケースと、既存の関連税制を活用して税率引上げ等により対応するケースに大別できる。 |
|
○ |
税率は炭素含有量に必ずしも比例しておらず、エネルギー集約産業への配慮や環境政策上の配慮(再生可能エネルギーの利用促進等)から、各種の減免措置を講じている。 |
|
|
|
| (2)我が国の既存の化石燃料・エネルギー関連税 |
|
○ |
我が国は化石燃料を輸入に依存しているため、既存関連税の課税段階は、化石燃料の輸入・精製前の段階(上流)と精製後・流通の段階(下流)の2つに大別できる。 |
| _ |
○ |
温暖化対策税制を考えるに当たっては、電力や現在課税の対象となっていない石炭等の扱いが課題となること等を指摘。
|
| (3)温暖化対策税制の論点整理 |
|
○ |
税の性格~ |
CO2排出削減という政策目的で課される税であり、税収確保等の従来の課税原則に基づく税とは異なる。 |
|
○ |
課税段階~ |
化石燃料への課税を念頭に、「上流」段階課税は制度的に簡素、「下流」段階課税はCO2排出削減により効果的、という議論があった。 |
|
○ |
課税対象 |
|
|
|
化石燃料~ |
化石燃料全体を対象に包括的に課税するか、個別燃料ごとに課税の要否を検討するか、が論点。個別燃料ごとに検討する場合、既存税制で非課税の石炭や原料として使用される石油等の扱いが問題。 |
| _ |
|
電 力~ |
発電用化石燃料に課税するか、電力そのものに課税するか、が論点。 |
| _ |
○ |
課税標準・税率~ |
従価税ではなく従量税が適当とされ、その場合、化石燃料の炭素含有量に着目するか、燃料種別ごとに税率を設定するか、が論点。 |
|
○ |
既存税制との調整~以下の4つに場合分けができる。 |
|
|
[1] |
化石燃料等に対する包括的な新税を導入し、必要に応じ既存税を調整 |
|
|
[2] |
既存税を活用し、その税率を適切な水準に調整 |
|
|
[3] |
既存税の対象である化石燃料等に新しい税を上乗せして課税 |
|
|
[4] |
既存税の対象外である化石燃料等に課税 |
|
○ |
税による諸影響の緩和~次のような論点について議論が行われた。 |
|
|
・ |
化石燃料の個々の実情に応じて燃料種別等の区分で減免 |
|
|
・ |
マクロ経済への影響に配慮し、他の税目の減税等による税収の中立化 |
|
|
・ |
産業の国際競争力に配慮した国境税調整 |
|
|
・ |
補助金等、税収の民間部門への還元 |
|
|
・ |
環境政策として促進すべき対象(公共交通機関の燃料等の消費)の減免 |
|
○ |
その他~次のような論点についても議論が行われた。 |
|
|
・ |
税制と他の温暖化対策(財政措置、自主協定、排出量取引等)の組合せ |
|
|
・ |
税収の使途や税制導入に当たっての方法論(早期導入か、段階的導入か等) |
| _ |
|
|
|
| (4)税制オプションの提示と比較検討 |
| 化石燃料課税について、上流・下流の2つの課税段階と、新税導入・既存税制活用の2つのアプローチを組み合わせ、次の4つのオプションを提示。 |
|
I |
石炭を含むすべての化石燃料を対象に、その上流で、包括的な新税を導入 |
|
II |
上流課税である既存の石油税の税率を適切な水準にするとともに、既存税の対象外(石炭)への課税を検討 |
|
III |
石炭を含むすべての化石燃料を対象に、その下流で、包括的な新税を導入 |
|
IV |
下流課税である既存のガソリン税、軽油引取税等の税率を適切な水準にするとともに、既存税の対象外(石炭・灯油等)への課税を検討。公平・中立・簡素の課税原則と、政策目標であるCO2削減の観点から、これらを比較検討し、上流課税は制度のわかりやすさ等で優れている一方、下流課税はCO2の効率的な排出削減等において優れていること等を指摘。 |
| _ |
|
|
電力課税については、発電用燃料課税との関係で、[1]発電用燃料のみに課税、[2]電力消費のみに課税、[3]発電用燃料及び電力消費の双方に課税、の3通りに場合分けし、CO2排出の少ない電源構成へのシフトを重視すれば[1]、電力消費者による排出削減策の促進を重視すれば[2]が優れていること等を指摘。
今後さらに、各論点に関する議論の深化、オプションの具体化等が必要であり、来年以降も引き続き、地球温暖化対策税制専門委員会において検討を行うこととしている。
|
|
敬称略:50音順
|
|
浅野 直人 |
福岡大学法学部教授 |
|
天野 明弘 |
関西学院大学総合政策学部長 |
|
飯田 浩史 |
産経新聞社論説顧問 |
| (委員長) |
飯野 靖四 |
慶応義塾大学経済学部教授 |
|
植田 和弘 |
京都大学大学院経済学研究科教授 |
|
大塚 直 |
早稲田大学法学部教授 |
|
奥野 正寛 |
東京大学大学院経済学研究科教授 |
|
小幡 純子 |
上智大学法学部教授 |
|
佐和 隆光 |
京都大学経済研究所教授 |
|
竹内佐和子 |
東京大学大学院工学研究科助教授 |
|
土屋 俊康 |
税理士 |
|
寺西 俊一 |
一橋大学大学院経済学研究科教授 |
|
鳥井 弘之 |
日本経済新聞社論説委員 |
|
中里 実 |
東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
|
本間 正明 |
大阪大学大学院経済学研究科教授 |
|
桝井 成夫 |
読売新聞社論説委員 |
|
水野 忠恒 |
一橋大学大学院法学研究科教授 |
|
森田 恒幸 |
独立行政法人国立環境研究所社会環境システム研究領域領域長 |
|
諸富 徹 |
横浜国立大学経済学部助教授 |
|
安原 正 |
(財)環境情報普及センター顧問 |
|
横山 彰 |
中央大学総合政策学部教授 |
|
横山 裕道 |
毎日新聞社論説委員 |
| |
和気 洋子 |
慶応義塾大学商学部教授 |
「我が国における温暖化対策税制に係る制度面の検討について(これまでの審議の取りまとめ)」本文
| 連絡先) |
環境省総合環境政策局環境経済課内 |
|
中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会事務局 |
|
| 担当 |
: |
西村・古川 |
| TEL |
: |
03-3581-3351(内6269) |
| FAX |
: |
03-3580-9568 |
|
|
添付資料
- 連絡先
- 環境省中央環境審議会総合政策・地球環境合同部会事務局
環境省総合環境政策局総務課
課 長:青山幸恭(内線6210)
調査官:後藤真一(内線6249)
環境省総合環境政策局環境経済課
課 長:三好信俊(内線6260)
補 佐:西村治彦(内線6263)
環境省地球環境局地球温暖化対策課
課 長:竹内恒夫(内線6770)
補 佐:熊倉基之(内線6781)
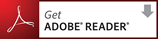
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。