生物多様性国家戦略の長期的目標に掲げられた「代表的な生物地理区分毎に多様な生態系及び動植物が保全されていること」の実現に向け、環境庁では、(財)国立公園協会に委託してその具体化について調査を進めてきたが、今般、委託先に設けられた「生物多様性保全ガイドライン策定検討委員会」が、「生物多様性保全のための国土区分(試案)」(以下「国土区分」という。)及び「区域ごとの重要地域情報(試案)」を取りまとめたので公表する。
国土区分は、多様な自然環境を有する我が国の国土レベルでの適切な生物多様性保全施策の推進を図るため、生物多様性保全の基本単位として生物学的特性から見た地域のまとまりを概括的に把握し、その保全目標と方策を整理しようとするものである。今回の試案では、我が国の生物相を規定する要素として、{1}日本列島の地史的成立経緯、{2}植生に強く影響する気候要素を取り上げ、これにより全国を10に区分した。
この10区分に基づき、各区域の生物学的特性を踏まえた生態系レベルでの生物多様性保全を図るため、植物群集を主な指標として、A:区域の生物学的特性を示す生態系、B:区域内の環境要因により特徴づけられる重要な生態系、C:伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然について、全国の研究者等に対するアンケート調査を行い、区域ごとの重要地域として、A:448件、B:884件、C:154件を抽出した。また、A:について3次メッシュ単位で地図化を行い、国立・国定公園等との重なりの状況にしぼって分析した。
今後の課題として、{1}今回の国土区分(試案)及び区域ごとの重要地域情報(試案)は中間段階のものであり、今後、更に精査するための調査を継続すべきこと、{2}作業途上となっている動物個体群に着目した重要地域についても一覧表作成の作業を進める必要があること、また、施策面で、1)モニタリング・調査研究体制の整備、2)生物多様性保全の観点からの保護地域の体系化、3)重要地域情報の環境アセスへの活用、4)重要地域の自然環境教育の場としての活用等を図るべきことが提言された。
国土区分(試案)では、指標として、ア)大陸島嶼・海洋島嶼、イ)渡瀬線・ブラキストン線(注1)、ウ)気温(温量指数(注2))、エ)年間降水量を用い、全国を、{1}北海道東部区域、{2}北海道西部区域、{3}本州中北部太平洋側区域、{4}本州中北部日本海側区域、{5}北陸・山陰区域、{6}本州中部太平洋側区域、{7}瀬戸内海周辺区域、{8}紀伊半島・四国・九州区域、{9}奄美・琉球諸島区域、{10}小笠原諸島区域に区分した。区分の手順は図1に、区分図については図2に、各区域の特徴は表1に示すとおりである。
| (注1) |
渡瀬線・・・・・・・・・・ |
屋久島・種子島と奄美諸島との間、七島灘(トカラ列島)に東西に引いた生物地理上の境界線。 |
|
ブラキストン線・・・・ |
本州及び北海道の間に引かれた生物境界線で、1880年、T.W.BlakistonとH.Pryrが鳥類の分布から提唱し、J.Milneが命名したもの。 |
| (注2) |
温量指数・・・・・・・・ |
吉良竜夫(1945)の考案による積算温度の一種で、月平均気温5℃を越える期間内の個々の月平均気温から5℃を減じて加算した値。北海道の亜寒帯(北方針葉樹林帯)と冷温帯(夏緑樹林帯)の区分の境となる指数が55、冷温帯と暖温帯(照葉樹林帯)の区分の境となる指数が85とされている。 |
| 2 区域ごとの重要地域<生物群集を対象とする抽出>情報(試案)の概要 |
| (1) |
目的
代表性、典型性、生態系のまとまりの程度等を考慮しつつ、区域ごとの生物学的性を維持していく上でコアとなる生態系を「区域ごとの重要地域」として抽出する。その際、二次的自然についても、生物多様性保全に果たす役割を検討する。
|
| (2) |
抽出対象
植物群集は、土地の気候・地形・土壌・水分条件等を反映して成立し、土地への強い定着性を持ち、動物群集は、その土地の植物群集へ強く依存することから、植物群集を主な指標として、以下の観点により「区域ごとの重要地域<生物群集を対象>」を抽出した。
| A |
: |
区域の生物学的特性を示す生態系 |
|
|
{1} |
区域の特性を示す気候条件によりある程度のまとまりを持って成立している植物群集が見られる地域 |
|
|
{2} |
生物学的特性を示す動物相が存続できるようなまとまりを持つ地域 |
| B |
: |
区域内の環境要因の違いにより特徴づけられる重要な生態系
次に示したような環境要因によりある程度のまとまりを持って成立している植物群集が見られる地域 |
|
|
ア) |
垂直、気候条件 |
|
|
イ) |
地形条件(特異な地形等) |
|
|
ウ) |
水条件(湖沼、湿原、河川等) |
|
|
エ) |
地質、土壌条件(母岩の特性、土壌の物理化学的特性、厚さ等) |
|
|
オ) |
複合条件(複数の環境要因の複合) |
| C |
: |
伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然
二次林(アカマツ林、クヌギ-コナラ林等)、二次草原(山地草原等)、谷津田、ため池など長い年月の継続的な人為の影響下で形成された特色ある生物群集が見られる地域 |
|
| (3) |
区域ごとの重要地域一覧表の作成
地域の自然に詳しい研究者等から情報収集することを目的として、2次にわたるアンケート調査を実施した。1次アンケートでは、(2)の抽出基準に該当する地域のリストアップを、対象者329件に対し依頼し、回答率22%であった。また、2次アンケートは、1次アンケートの結果を整理した一覧表の補完を、対象者432件に対し依頼し、回答率22%であった。
アンケート回答を基に、用語や重複の整理等を行った上で、「区域ごとの重要地域一覧表」を作成した。重要地域として抽出された件数は、表2に示すとおり、A:448件、B:884件、C:154件、計1486件である。各区域ごとの重要地域のうち、主な例を表3に掲載した。なお、「区域ごとの重要地域一覧表」については、環境庁図書館に報告書を備えるほか、環境庁のホームページに掲載することとしている。 |
| (4) |
「A:区域の生物学的特性を示す生態系」の位置図の作成
重要地域の面的広がりについては把握していないため、重要地域の中心と思われる位置を点情報としておさえ、これを3次メッシュ単位で位置情報としてとらえた。この位置情報を基に、国立・国定公園等の保護地域を3次メッシュ単位で重ね合わせ地図化したものが図3である。また、その重複状況を表に示したものが表4である。
なお、今回は3次メッシュ単位で国立・国定公園等との重なりにしぼって分析したものであり、全ての保護地域について調べたものではないことに留意する必要がある。 |
| (1) |
調査の継続
国土区分及び重要地域の意義等について研究者や地方公共団体への浸透が不十分なためアンケートの回答率が悪かった。その意味で、今回の結果は中間段階のものといえるので、今後、更に精査するための調査を継続する必要がある。
また、作業途上である動物個体群に着目した区域ごとの重要地域についても、今後、完成に向けて作業を進めることが必要である。 |
| (2) |
施策面での課題(提言)
| 1) |
モニタリング・調査研究体制の整備
今回抽出された重要地域情報を基礎として、さらに各区域の生物学的特性を保持している代表的な地域を特定し、地球温暖化や酸性雨等の影響を含めて、生物群集の動向やそれを取り巻く環境の変動等に関する長期的なモニタリング・調査研究を行うための体制の整備を検討することが必要である。 |
| 2) |
生物多様性保全の観点からの保護地域の体系化
今回抽出された重要地域情報を基礎として、さらに区域の生物学的特性や生態系レベルの多様性の維持にとって特に重要な地域について特定するとともに、それらを体系的に保護地域として保全を図ることを検討することが必要である。その際、各種保護地域制度について、どの制度を適用することが適切であるか、また、課題は何であるか、さらに知見を集積し、それを踏まえ検討する必要がある。 |
| 3) |
環境アセスメント等への活用
抽出された重要地域については、国土における多様な生態系に関する情報として意義が高いものである。開発の計画段階から環境アセスメントの段階まで、自然環境への配慮を行う際の基礎的情報として適正に活用されることが期待される。 |
| 4) |
自然環境教育の場としての活用
重要地域は、多様な自然生態系の生きたサンプルであり、自然環境教育の場として活用が図られることが望ましい。 |
|
| 4 生物多様性保全ガイドライン策定検討委員会の構成 |
阿部 学 新潟大学農学部教授 (脊椎動物)
(座長) 大島 康行 (財)自然環境研究センター理事長 (生態学)
大場 秀章 東京大学助教授 (植物分類)
奥田 重俊 横浜国立大学教授 (植物生態)
川名 英子 富士総研部長 (農地・都市)
楜沢 能生 早稲田大学教授 (環境法)
椎貝 博美 筑波大学教授 (河川工学)
篠原 修 東京大学教授 (景観)
垰田 宏 森林総合研究所植物生態科長 (植物生態)
谷本 丈夫 宇都宮大学教授 (森林生態)
松本 忠夫 東京大学教授 (無脊椎動物)
吉野 正敏 愛知大学教授 (地理・気候)
添付資料
- 連絡先
- 環境庁自然保護局計画課
課 長 :鹿 野 久 男(内線6430)
補 佐 :上 杉 哲 郎(内線6432)
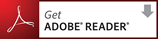
PDF形式のファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です。Adobe Reader(無償)をダウンロードしてご利用ください。