報道発表資料
| [1] | 事業者が悪臭発生の防止に努める責務の明確化 |
| [2] | 悪臭を生ずる物の野外焼却禁止に係る対策の強化 |
| [3] | 事故時に発生する悪臭への対応の強化 |
| [4] | 臭気指数測定体制の充実強化 |
- 1.悪臭問題の現状
-
悪臭に関する苦情件数は、典型7公害の中でも常に上位を占めているが、ここ数年は増 加傾向となっており、特に、平成9年度及び10年度は急激に増加している(図1)。
この原因は、廃棄物の野外焼却の増加とダイオキシン問題等を契機として臭気問題に対 する国民の意識が高まったことによるものと考えられる。
悪臭防止法においては、規制地域内の事業場において発生する悪臭を規制対象としてい るところであるが、平成10年度においては、全国の事業活動に係る悪臭苦情件数のうち、 同法の規制対象外の事業活動に起因するものは約3割を占めていた(表1)。
また、悪臭を生ずる物の野外焼却については、悪臭防止法のほか、全国の 35 の都道府 県等の条例によりその行為を禁止しているところである(表2)が、平成10年度における 野外焼却に係る悪臭苦情件数のうち、同法の当該規定の対象外である住居集合地域以外に おけるものが約2割を占めていた。
さらに、工場等の施設の破損又は故障、野外の中古タイヤ集積場の火災等の悪臭を伴う 事故が各地で発生しているが、このような事故は、一時的に多量の悪臭物質が排出され、 住民の被害が大きくなる傾向にあることや、原因が不明で住民に不安が広がるなどの特性 があり、問題となっている。
このほか、臭気指数規制に関しては、本年2月の中央環境審議会答申に基づき、臭気指 数に係る全ての規制基準が整備される予定であること等から、臭気指数測定体制の充実強 化が求められている。
- 2.悪臭防止対策の強化のため講ずべき方策
(1)事業者が悪臭発生の防止に努める責務の明確化 -
環境基本法の趣旨及び悪臭苦情の現状を踏まえ、事業活動に係る悪臭による住民の生活 環境の支障を防止する観点から、事業者の悪臭発生の防止に努める責務の明確化を図るこ とが必要である。
- (2)悪臭を生ずる物の野外焼却禁止に係る対策の強化
-
野外焼却に係る苦情の状況等に鑑み、現行法では住居が集合している地域に適用が限定 されているものを、当該地域以外でも住民の生活環境が影響を受ける場合には対応ができ るようにすることが必要である。
なお、この場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の不適正処理の防 止対策との関連にも留意することが望ましい。
- (3)事故時に発生する悪臭への対応の強化
-
事業場において発生する事故に伴う住民の悪臭被害を防止するため、当該事故時におい て、事故を起こした事業場の設置者から市町村への通報の義務付けを行うとともに、必要 に応じ、市町村長が当該事業場設置者に対し悪臭原因物の排出の防止のための応急措置命 令を発動することができるよう、新たな仕組みを設けることが必要である。
- (4)臭気指数測定体制の充実強化
-
今後の臭気指数規制基準の整備及び本年4月の地方分権法の施行を踏まえ、国による市 町村職員に対する研修体制の整備、臭気指数測定マニュアルの作成等を行うことが必要で ある。
また、同法施行規則に基づき指定機関で実施されている臭気判定士試験について、平成 8年9月の閣議決定に基づき、今後も臭気判定士を国家資格とし、かつ指定機関制度を維 持するため、法律で試験等実施機関の適切な位置付けを行うことが必要である。
- (5)その他
-
地方自治体が臭気指数規制の導入を行う場合、国は、地方自治体に対し、その導入を円 滑に実施できるよう適切な支援を行う必要がある。また、悪臭苦情の処理には専門的知識 が要求されることから、専門的知識を有する者としての臭気判定士の市町村における積極 的な活用方策について検討していくことが必要である。
近隣型の悪臭苦情は、近年増加傾向にあるため、国及び地方公共団体が悪臭防止対策に 係る知識の普及啓発を推進していく必要がある。
この他、各主体においては、悪臭を防止するだけでなく、地域における快適なにおい環 境の創造に向けた様々な取組を推進していくことが望まれる。
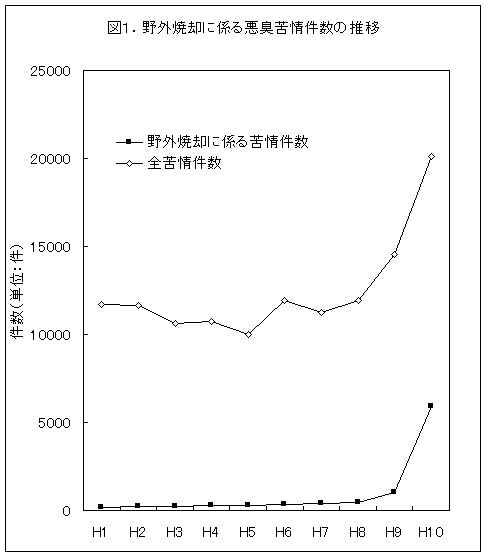
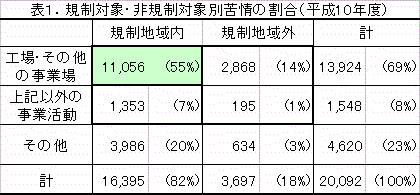
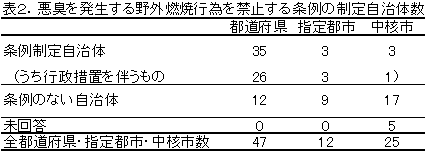
- 連絡先
- 環境庁中央環境審議会第28回大気部会事務局
(環境庁大気保全局大気生活環境室)
室 長 :藤田 八暉(内6540)
室長補佐 :高橋 達男(内6542)
室長補佐 :竹本 明生(内6543)
担 当 :高橋 一彰(内6545)