総説第1章で記載したとおり、循環型社会の形成に向けて資源生産性・循環利用率を高める取組を一段と強化するためには、持続可能な形で資源を効率的・循環的に有効利用する循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行を推進することが重要です(図2-2-1)。
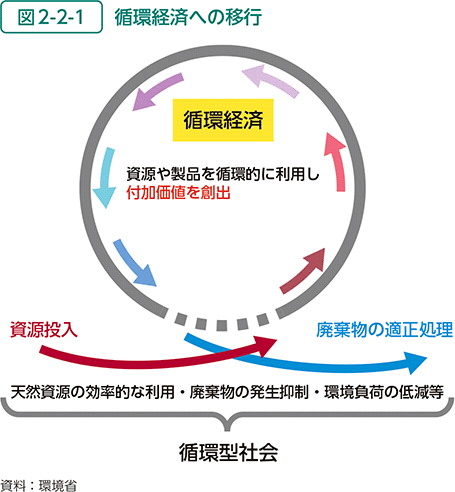
国際的な議論では、循環経済は、資源(再生可能な資源を含む。)や製品の価値を維持、回復又は付加することで、それらを循環的に利用する経済システムであるとされています。この経済システムでは、例えば、環境配慮設計や修理等により製品等の長寿命化、再利用、リサイクル等が促進され、資源が可能な限り効率的かつ循環的に利用され、天然資源利用や廃棄物が減少します。その結果として、資源の採掘、運搬、加工から製品の製造、廃棄、リサイクルに至るライフサイクル全体での環境負荷低減や、世界的な資源需要の増加への対策にもつながります。
資源循環を促進することで、ライフサイクル全体での温室効果ガスの低減につながり、ネット・ゼロに資するだけでなく、生物多様性の損失を止め、反転させ、回復軌道に乗せる「ネイチャーポジティブ」の実現に資するなど、経済・社会・政治・技術の全てにおける横断的な社会変革を実現する上ではネット・ゼロ、循環経済、ネイチャーポジティブ相互の連携が重要となります。
気候変動、生物多様性の損失、汚染という主要な環境問題に加え、欧州等での製品への再生材使用の義務化の動き、少子高齢化に伴う地域経済の縮小は、我が国にとって大きな課題です。これに対し、循環経済への移行を進めることで、輸入した鉱物・食料等の資源の循環利用等を通じた資源確保による経済安全保障の強化、環境配慮設計の推進並びに再生材の質と量の確保及び利用拡大等による企業の国際的な産業競争力の強化や、循環資源等を活用した製品等の製造と廃棄物等の再資源化を通じた地場産業の振興等による地方創生、市民のライフスタイルの転換による質の高い暮らしに貢献できます。
そのため、循環経済への移行等に向けて関係者が一丸となって取組を進めるべく、循環型社会の形成に向けた政府全体の施策を取りまとめた国家戦略として第五次循環型社会形成推進基本計画を2024年8月に策定するとともに、2024年末に循環経済に関する関係閣僚会議で「循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行加速化パッケージ」を取りまとめ、これに基づく取組を進めます。
事例:地域の特性を活かした循環資源や再生可能資源の活用
地域における循環経済の移行を促し、地方創生を実現するための取組として、地域の資源循環や再生可能資源を活用することで新たな付加価値や雇用の創出や地域の経済社会の活性化に資する取組を促進しており、ここではその事例を紹介します。市民、自治体、地域の製造業・小売業や廃棄物処理・リサイクル業といった企業等の各主体が連携し、各地域に特徴的な循環資源や再生可能資源を循環させる取組を創り出し、これが自立して拡大していくことで、雇用の創出や地場産業の振興等により地域経済が活性化し、魅力ある地域づくりや地方創生につながります。
大崎町(おおさきちょう)には、もともと焼却処理場がなく、出たごみは全て埋立処分場で最終処分されていました。焼却炉の新設には毎年莫大な費用がかかり、埋立処分場の建設については周辺住民の理解を得るのが難しかったため、大崎町はごみ減量化による既存埋立処分場の延命化を選択しました。ごみ分別を徹底し、量やコスト、分別手法等を考慮し、品目数を徐々に増やし、令和5年度から新たに「紙おむつ」も加わって、現在では28品目の分別・回収が実施されています。平成18年度からの連続12年間を含む、計16回の資源リサイクル率日本一を達成し、令和5年度実績でリサイクル率は83.0%にのぼりました。大崎リサイクルシステムのメリットとしては、ごみの分別やリサイクルによる1人あたりごみ処理経費の削減、資源ごみ売却による売却益金の発生、リサイクルセンターにおける雇用の増加等が挙げられ、ごみの約59%を占める生ごみ・草木等を全量堆肥化し、その堆肥を農地に還元することで有機農業の推進にもつながっています。
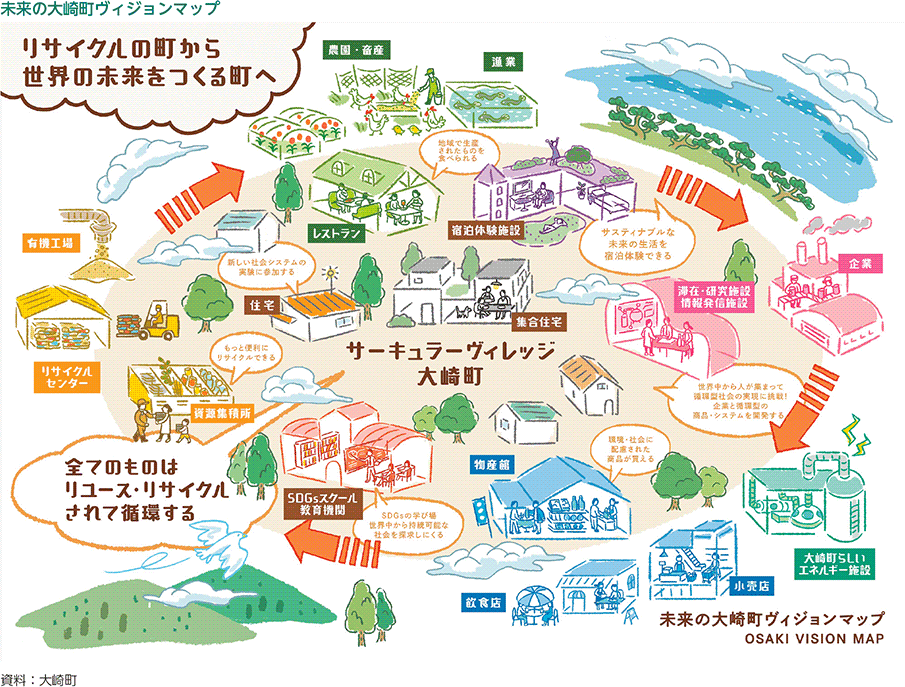
古くから交通の要所・石炭の集散地・鉄鋼のまちとして栄えた北九州市では、高度経済成長により発生した公害の克服に向け、行政と企業が良好な関係を築きつつ、産学官民が一丸となって取り組んできました。公害問題の克服の経験を活かし、循環型社会の先進的な取組を推進しており、日本最大級の「北九州エコタウン事業」として、多くのリサイクル企業が集積(2025年3月時点で25社)し、約1000名の雇用も創出しています。また、2022年には「北九州循環経済ビジョン推進協議会」を設立するとともに、市と企業が連携して、PVパネルや車載用蓄電池、食品資源等のリサイクルシステムを構築するなど、製造業・小売業等を担う動脈産業と廃棄物処理・リサイクル業等を担う静脈産業との連携(いわゆる動静脈連携)による「サーキュラーエコノミーモデル」を推進しています。さらに、公益社団法人福岡県産業資源循環協会北九州支部とも連携しながら産業廃棄物処理業者等の脱炭素経営を促進し、地域全体で脱炭素型資源循環の推進に取り組んでいます。
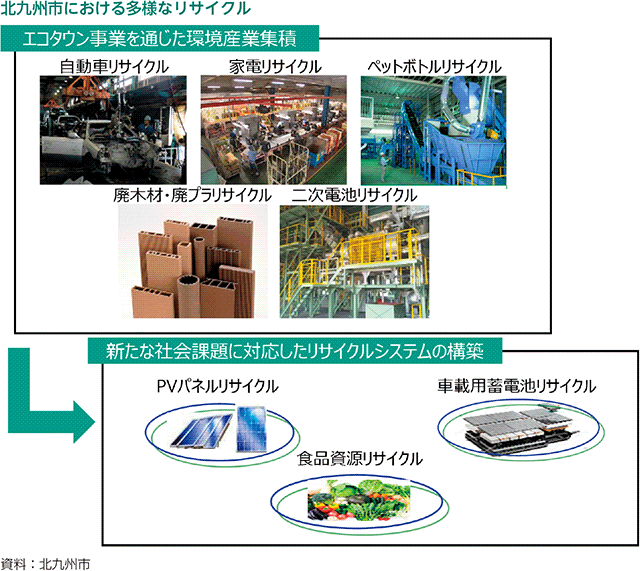
製造業・小売業等を担う動脈産業と廃棄物処理・リサイクル業等を担う静脈産業との連携はますます重要性を増しています。この事業者間の連携(いわゆる動静脈連携)により、日本が長年にわたり培ってきた高い技術力を最大限に活用することで市場に新たな価値を創出することが可能となります。
製造業・小売業等の企業と廃棄物処理・リサイクル業等の企業が連携・協力し、求められる品質や量の再生材を確実に供給できる体制を整えることが重要です。
そのためには、再生材の利用拡大と安定供給、環境配慮設計や再生材利用率の向上、使用済製品等の解体・破砕・選別等のリサイクルの高度化等を推進するとともに、各種リサイクル法に基づく取組を着実に進めることで、素材・製品ごとの中長期的な政策の方向性に基づいて、ライフサイクル全体での徹底的な資源循環を推進します。
地方公共団体は、地域の市民、事業者、NPO・NGO等の各主体間の連携・協働を促進するコーディネーター役として、地域の循環資源や再生可能資源を活用した資源循環システムを構築することが求められています。各資源に応じた最適な規模で地域の資源を効率的に循環させるシステムを構築してリユース・リサイクル・リペア・メンテナンス・シェアリング・サブスクリプション等を推進します。
これらの取組を通じて、地域の循環資源や再生可能資源を活用し、それらを再生材として新たな製品等の原料としたり、肥飼料の原料としたりすることで地域に新たな付加価値や雇用を創出して地域経済を活性化させるとともに、廃棄物として処理する量を減らすことで歳出削減にも貢献することが期待されます。
また、地域において、リユース品や修理サービス、各地域での資源循環の取組により生産された循環資源や再生可能資源を用いた製品等について、環境価値に関する表示等を伴った多様な選択肢の提供を推進し、これにより、消費者がその意識を高め実際の行動に移していけるようライフスタイルの転換を促進し、質の高い暮らしを実現していくことが目指されます。
欧州に端を発した循環経済への移行の流れが世界的な潮流になりつつある一方で、天然資源や域内で発生した使用済製品(資源)を域外に出さないようにする、いわゆる“資源の囲い込み”の動きが一部の国や地域で顕在化しています。こうした政策は、国際市場における日本企業の競争力のみならず、日本市場や資源調達、貿易にも影響を及ぼす可能性があり、天然資源を輸入に頼る我が国において、資源の効率的・循環的な利用を促進し循環経済への移行を進めるためには、資源循環に関する国際的なルール形成をリードして国際的な資源循環を進めることが不可欠です。
我が国が3Rを含む循環経済・資源効率性の施策や資源循環に関する国際合意、再資源化可能な廃棄物等の適正な輸出入、プラスチック汚染対策に関する議論及び国際的な資源循環に関する議論をリードするとともに、国際機関や民間企業等と連携して国際的なルール形成をリードすることで、国内外一体的な資源循環施策を促進します。また、日ASEANのパートナーシップやG7で合意された重要鉱物等の国内及び国際的な回収・リサイクルの強化等に基づき、国際的な資源循環体制を構築することが重要です。さらに、我が国の優れた制度・人材育成・システム・技術等をパッケージとしてASEANを始めとする途上国等へ海外展開することで、適正な廃棄物管理及び資源循環の強化を図ります。これらの取組は、環境汚染等の低減に貢献し、世界の資源制約を緩和するものです。
循環経済への移行は、ネット・ゼロのみならず、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決に貢献でき、あらゆる分野で実現する必要があります。また、欧州を中心に、世界では再生材の利用を求める動きが拡大しており、対応が遅れれば成長機会を逸失する可能性が高く、我が国としても、再生材の質と量の確保を通じて資源循環による産業競争力を強化することが重要です。
こうした背景を踏まえ、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和6年法律第41号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)が2024年5月に第213回国会で成立し、同月に公布されました。再資源化事業等高度化法は、脱炭素化と再生材の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するために、基本方針の策定、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項の策定、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずることとしています。これらの施策のうち、基本方針、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項等の一部の規定については、2025年2月に施行されました。
今後、再資源化事業等高度化法の施策により、先進的な資源循環の取組を行う廃棄物処分業者を後押ししていくとともに、事例を積み重ね、そこから得られた知見を国が展開していくことで、産業全体での再資源化の取組を促進していきます。
2022年4月に施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)」は、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般にわたって、3R+Renewableの原則にのっとり、あらゆる主体におけるプラスチック資源循環の取組を促進するための措置を講じています。2025年3月時点までに、市区町村による再商品化計画は31件の認定を行ったほか、製造・販売事業者等による自主回収・再資源化事業計画について5件、及び排出事業者による再資源化事業計画について計6件の認定を行いました。
我が国は2019年のG20大阪サミットにおいて「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」を提唱し、2023年のG7広島サミットにおいてプラスチック汚染対策に関する野心へのコミットメントを主導するなどプラスチック汚染対策に積極的に取り組んできました。こうした中、2022年2月から3月に開催された国連環境総会において、海洋環境等におけるプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書(条約)の策定に向けた政府間交渉委員会(INC:Intergovernmental Negotiating Committee)を立ち上げる決議が採択されました。同決議が2024年末までに作業を完了する野心を持って2022年後半からINCを開始することを求めたことを受けて、2022年5月から6月のセネガルにおける公開作業部会を経て、2022年11月から12月にウルグアイにおいて第1回政府間交渉委員会が開催され、正式に条約交渉が開始されました。その後、条約の要素等について議論を行った2023年5月から6月のフランスにおける第2回会合、条約の素案(ゼロドラフト)等について議論を行った2023年11月のケニアにおける第3回会合、条文案の改定版を基に交渉等を行った2024年4月のカナダにおける第4回会合を経て、2024年11月から12月に第5回会合が韓国において開催されました。交渉開始当初に予定されていた最後の交渉会合であった第5回会合では、各条文案に関する議論が進展し、それを踏まえて議長から新たな条文案が提示されるなど一定の進展がありましたが、プラスチックの生産、特定のプラスチック製品や化学物質等の規制、条約実施のための資金協力等では引き続き各国の意見に隔たりが残り、条文案の実質合意には至りませんでした。そのため、条文案全体が引き続き交渉対象であることを確認しつつ、再開会合において引き続き交渉することが決定されました。その後、再開会合は2025年8月にスイスにおいて開催されることとなりました。プラスチックの大量消費国・排出国を含む多くの国が参画する実効的かつ進歩的な条約を目指し、早期の交渉妥結に向け、引き続き積極的に議論に貢献していきます。