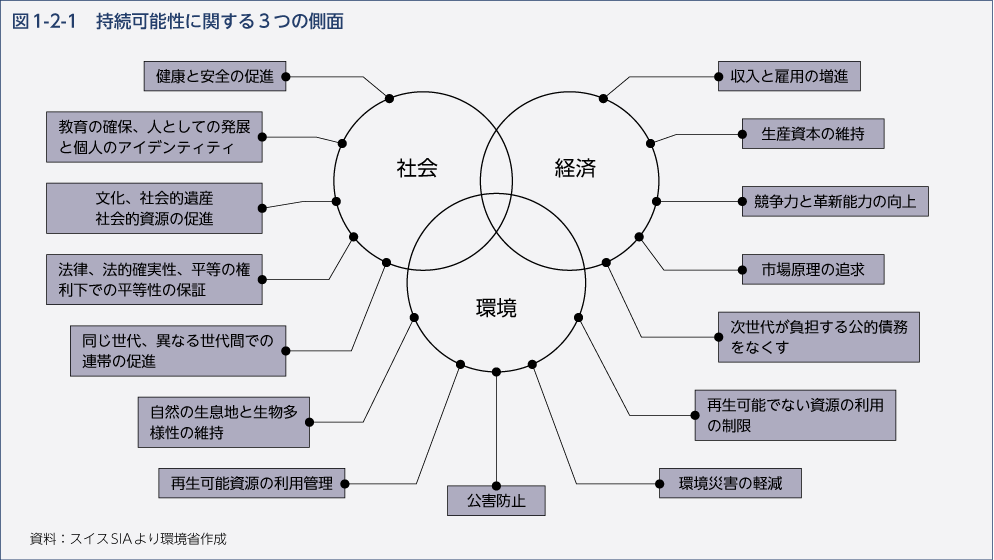
前節で見たように、私たちが望む豊かな暮らしは、主に持続可能な環境と経済と社会の3つの側面の安定の上に成り立っていると考えることもできます。その私たちの暮らしが持続可能なものであるのかを検証するためには、地球が生み出す資源を地球環境が許容できる範囲で利活用できる環境保全システムが構築・維持されているかどうか(環境の持続可能性)、公正かつ適正な経済活動を可能とする経済システムが構築・維持されているかどうか(経済の持続可能性)、人間の基本的権利や文化的社会的多様性を確保できる社会システムが構築・維持されているかどうか(社会の持続可能性)のそれぞれを考慮する必要があります(図1-2-1)。
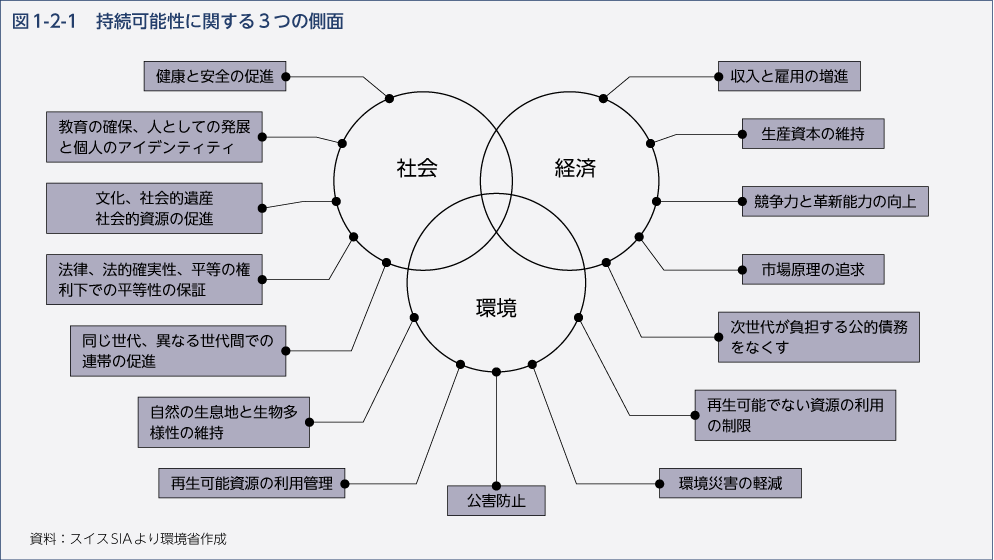
ここで、環境の側面の持続可能性が損なわれれば生活環境の悪化等によって社会の側面の持続可能性に影響を及ぼし、また、自然資源の劣化や枯渇によって経済の側面の持続可能性にも影響を及ぼしうるといったように、環境は、社会と経済の基盤であると考えることができます。
一方で、社会と経済の変化は環境にも影響を及ぼします。たとえば、近年の世界的に重要な社会変化として、人口動態をあげることができます。1970年には37億人であった世界人口は2009年に68億人と急増しました。国連人口部の推計によると、これまで、中国をはじめとする東アジアやインドをはじめとする中央・南アジアの人口増加に牽引される形で世界の人口増加が進み、今後2050年までは、東アジアの人口増加傾向が緩やかになりつつあるものの中央・南アジアでの人口増加が依然として顕著で、また、アフリカでの人口増加傾向が加速するとされています(図1-2-2)。
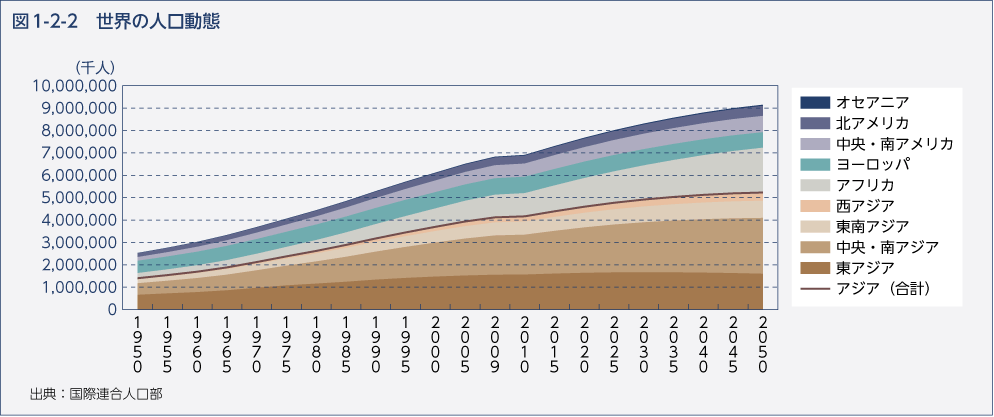
1970年(昭和45年)から2009年(平成21年)までの経済動向としては、特に中国におけるGDP成長が顕著で、東アジアを中心とするアジア経済の伸びがみられます(図1-2-3)。一方で、アフリカでは、人口増加の傾向に比してGDPの伸びが見られず、1日1.25ドル以下で生活をする貧困層の割合が1980年代から2005年まで5割を超えており、地球規模での社会経済的な格差は拡大しつつあると考えられます(図1-2-4)。
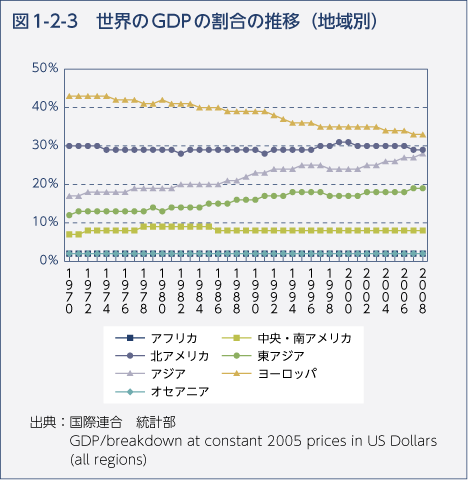
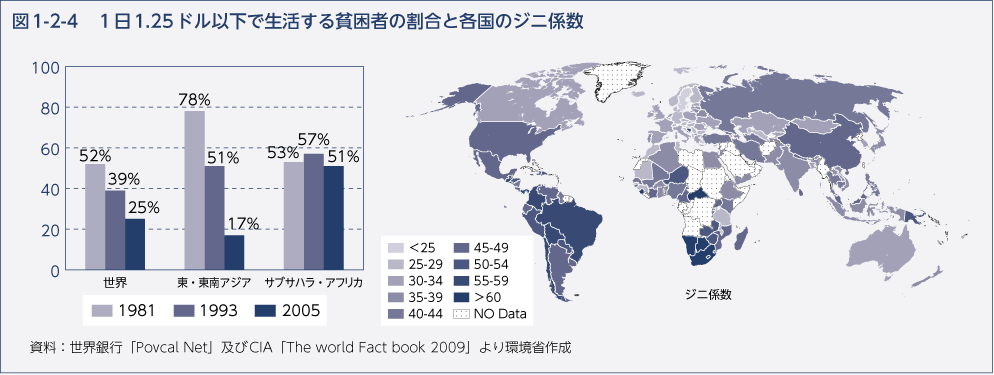
ここでは、このような社会経済的な状況の変化が、環境の側面にどのような影響を与えるのかに注目しながら、環境の側面の持続可能性について考察します。
人口増加及び経済成長に伴うエネルギー供給量の増加といった社会経済の変化が、地球環境に負荷を与えている例として、地球温暖化について考えてみます。
1971年(昭和46年)から2008年(平成20年)までの間に世界のエネルギー供給量は約2.2倍に増加しました。また、これをエネルギー源別に見ると、石炭・石油・天然ガスの占める割合は、1970年代から現在に至るまで8割以上を占めています(図1-2-5)。また、アジアを中心に、新興国のエネルギーの供給量は増加傾向にあります(図1-2-6)。
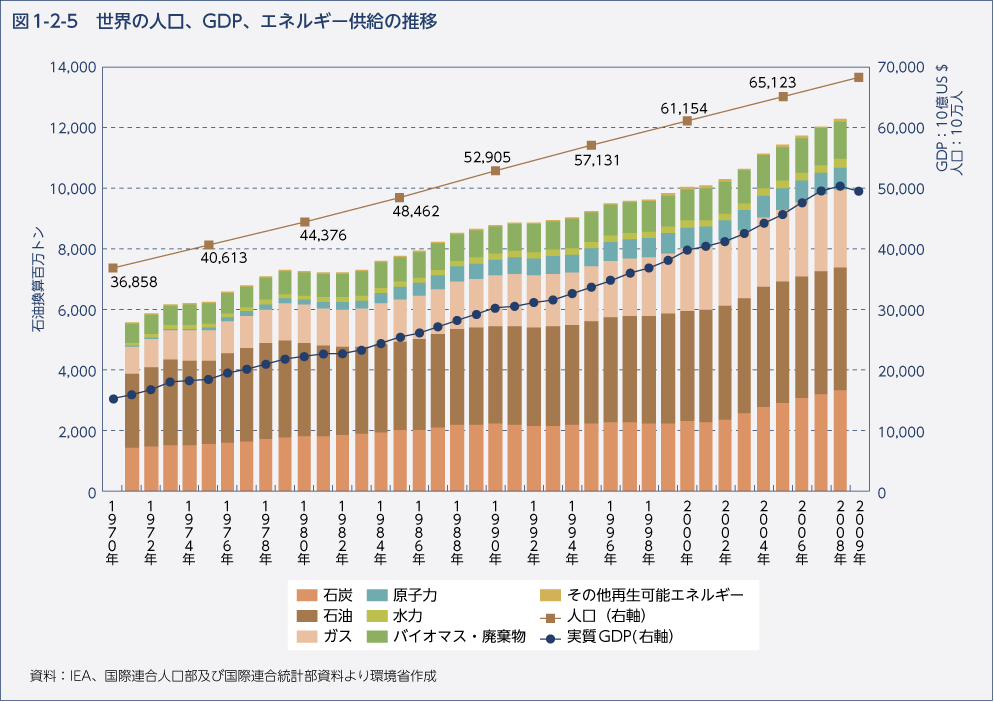
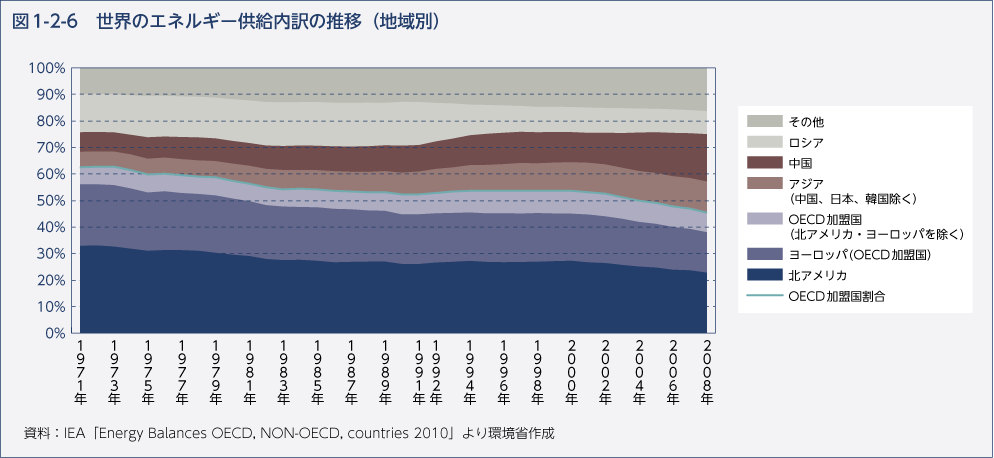
これらのことから、今後も新興国を中心に経済成長が見込まれる中で、エネルギー需要量の増加と化石燃料への高い依存傾向は続くと考えられます。これまでの人口増加や経済の成長は、エネルギー消費の増加に結びついており、IEAの見通しでは、各国政府が既存の政策や対策を全く変えなかった場合、2030年まで化石燃料が依然として世界の一次エネルギー源の大部分を占めるものと予測しています。
地球温暖化の原因となる温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)について見てみると、エネルギー起源の二酸化炭素の排出量は概ね一貫して増加傾向にあります。1971年(昭和46年)から2008年(平成20年)まででエネルギー起源の二酸化炭素排出量は約2倍に増加しており、それに伴って地球上のCO2濃度も増加しています(図1-2-7)。また、世界の二酸化炭素濃度の測定結果に基づき我が国が推定している二酸化炭素分布情報によると、2009年の大気中の二酸化炭素の全球平均濃度は、過去最高水準となっていることがわかりました。これを地域別に見ると、排出量の多いヨーロッパ、東アジア及び北アメリカの東部を中心に年平均濃度が高いことがわかります(図1-2-8)。
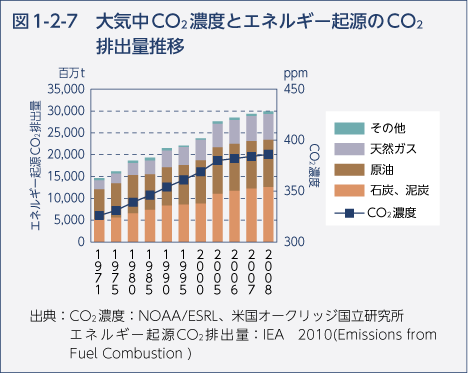
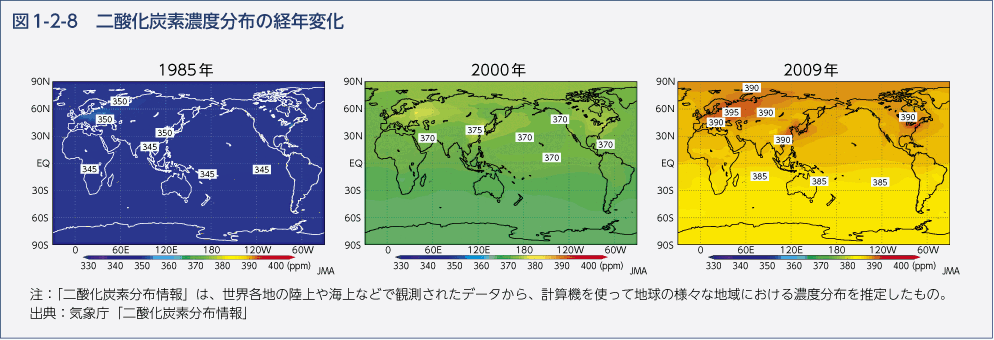
このようなCO2濃度の増加は、世界の気温上昇の一因となっていると考えられます。世界の年平均気温は、長期的には100年あたり約0.68℃の割合で上昇しており、特に1990年代半ば以降、高温となる年が多くなっています。2010年(平成22年)の世界の陸域における地表付近の気温と海面水温の平均である年平均気温の平年差(平均気温から平年値(1971年~2000年の30年平均値)を差し引いたもの)は+0.34℃で、1891年(明治24年)の統計開始以降、2番目に高い値となりました(図1-2-9)。また、平成22年夏期の日本の平均気温は、統計を開始した1898年(明治31年)以降の113年間で第1位の高い記録となりましたが、これは、冷涼なオホーツク海高気圧や寒気の影響を期間中ほとんど受けなかったこと、梅雨明け以降、勢力の強い太平洋高気圧に覆われたこと及びエルニーニョ現象の影響があったこと等に加え、背景として二酸化炭素などの温室効果ガスの増加に伴う地球温暖化の影響があったものと考えられます。
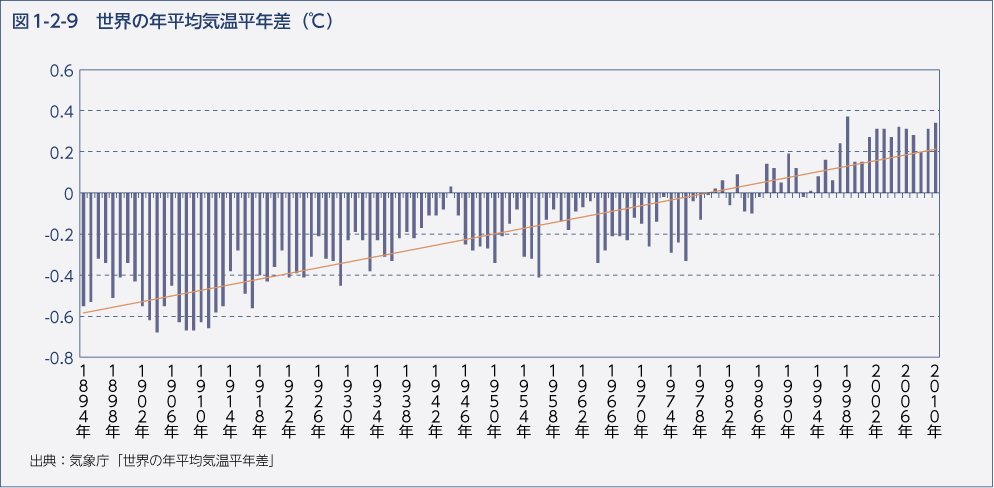
このように、人口増加及び経済の成長は、社会経済におけるエネルギー消費の増加を伴い、そのエネルギー消費の増加に伴う二酸化炭素濃度の増加は、地球温暖化という形で地球に対し環境負荷を与えている要因の一つとなると考えられています。
森林資源は、古くから、材木等の商用伐採の他、薪炭材として消費されて人々の生活のためのエネルギーとなってきました。また、近年、石油などの枯渇性資源の代替エネルギーとして、バイオマス資源の利活用が着目されています。世界では、これまで糖質の割合が高い穀物やパーム油脂などの植物由来の油脂から精製して得られるバイオ燃料を中心に導入が進められてきました。
森林の薪炭材としての利用については、世界全体で毎年伐採されている34億m3の森林資源の内、その約半分が薪炭材として消費されています。これは、我が国の天然林の森林蓄積量18億m3にほぼ匹敵する森林の材積量であり、森林資源に地球規模での大きな負荷を与えています。特に、アフリカ、アジア、南アメリカで薪炭材としての利用割合が高く、ヨーロッパや北・中央アメリカにおいてはそれが1~2割程度であるのに対し、これらの地域では5~9割程度となっています(図1-2-10)。特に、アフリカでは貧困を背景とした森林の薪炭林としての過剰利用や農地開拓による森林伐採が顕著に進んでいると考えることができます。
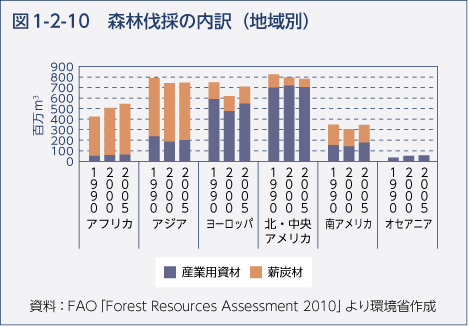
また、世界のバイオエタノールについては、2009年(平成21年)でブラジル・アメリカを中心に年間740億リットル生産されており、その多くは、トウモロコシ又はサトウキビを原料としています。バイオディーゼルについては、EUを中心に年間150億リットル生産されており、その多くは、菜種等が使われています。また、近年、バイオディーゼルの原料として注目されているパームヤシの生産量が、マレーシアやインドネシアを中心に増加しています。パーム油の原料となるヤシの生産面積は、熱帯林を転換する形で1970年(昭和45年)の326万haから2008年(平成20年)には1,462万haまで増加しています(図1-2-11)。
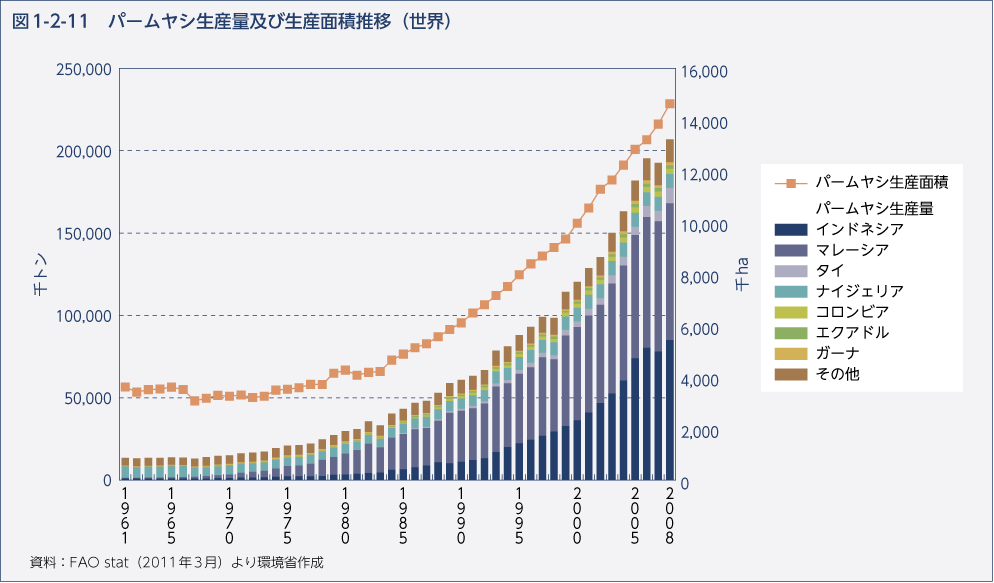
また、これに加えて、食料需要の増加等の背景もあって、近年、アフリカ、南アメリカ、東南アジアの熱帯地域を中心に農地面積が拡大して森林面積は減少する傾向にあります(図1-2-12)。森林蓄積量(樹皮を含む生木の体積の総量)についてみてみると、1990年(平成2年)から2010年(平成22年)にかけて、北・中央アメリカ及びヨーロッパでは森林蓄積量は増加する一方で、アフリカでは830億m3から770億m3に、南アメリカでは1,915億m3から1,772億m3に、東南アジアでは1990年の324億m3から2010年の290億m3に減少するなど、熱帯地域の森林を中心に森林蓄積量の減少傾向が続いています(図1-2-13)。さらに、違法伐採又は公的な機関の把握できない森林伐採は、公的な統計データに反映されないため実際の森林伐採量は公表されている数値より高いことが懸念されています。
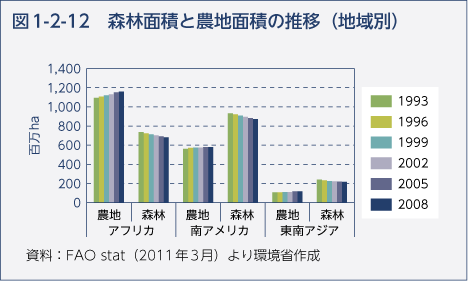
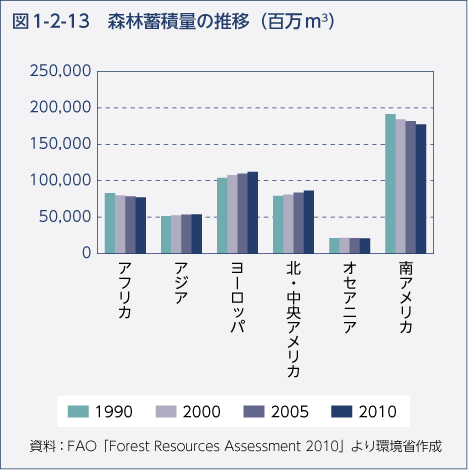
これらの森林資源の減少が見られる地域においては、森林資源管理に関する貧困対策などを含む森林ガバナンスの強化が求められます。また、バイオエタノール・バイオディーゼルといったバイオ燃料については、トウモロコシ、サトウキビ、パームヤシ等を原料とする場合には食料との競合等が懸念されることから、食料と競合しない廃棄物系バイオマスや、未利用バイオマスの導入が重要であり、これらに関する技術開発が求められています。
経済成長が社会の資源消費のあり方を変え、環境負荷を増加させる可能性がある例として、食生活と食料需給の構造変化があります。経済成長とともに、穀物等の植物由来の食料を中心とした食生活から畜産等の動物由来の食料に嗜好が変化する傾向が指摘されています。
食料の生産量は人口増による需要量の増大に伴って1970年頃から2007年までの間に約2倍になり、その一方で耕作地面積の拡大をもたらしました。1990年代に入ってからは、耕作地面積の拡大傾向は止まっているものの、単位面積あたりの穀物の収穫量が増えたため、穀物の生産量は増加し続けています(図1-2-14)。
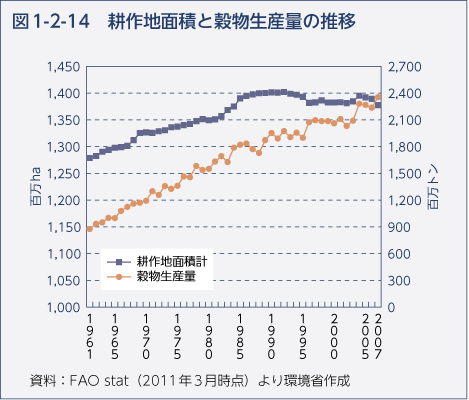
また、世界の人口一人当たりのカロリー供給量は1961年(昭和36年)の約2,200kcal/人から2007年(平成19年)の約2,800kcal/人まで増加しており、世界全体としての栄養供給状態は改善されつつあると考えられます。ただし、この点については、世界的に栄養不足の人口が依然として高い水準にあることから、食料の偏在性が問題とされています。
この間のカロリー供給の構造の変化については、動物由来の食料によるカロリー供給の割合が1961年(昭和36年)の15.4%から2007年(平成19年)の17.2%までやや増加しているものの、全体としては、穀物等の植物由来の食料生産の増加によるものと考えられます(図1-2-15)。
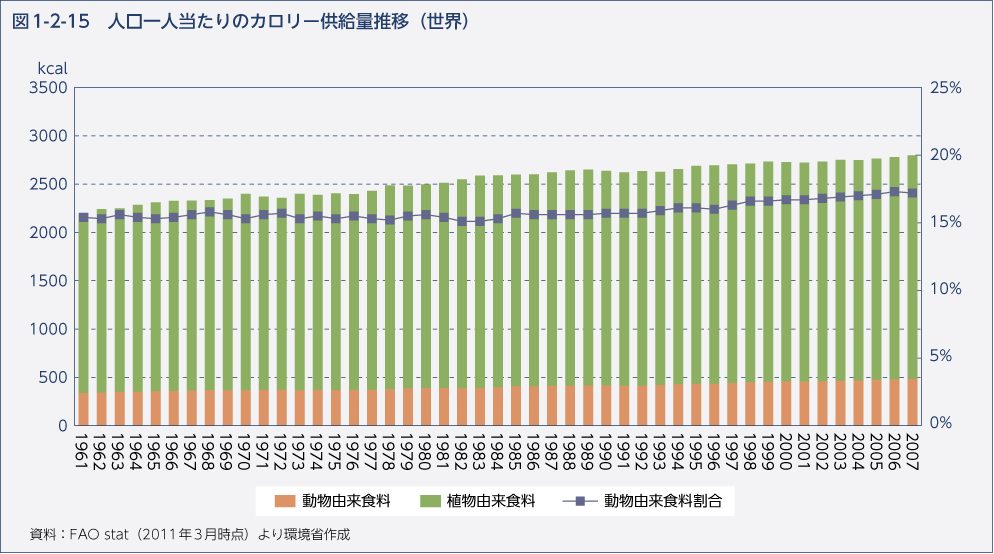
一方で、近年経済成長の著しいアジア地域においては、これとは異なる傾向を見ることができます。近年、アジアのGDPが世界のGDPに占める割合は、1970年代には17%程度であったのが、2009年(平成21年)には28%まで上昇しています。この間のアジアにおけるカロリー供給の構造の変化を見てみると、1960年頃から2007年にかけてカロリー供給総量が約1.5倍に増加し栄養状態が改善される傾向にある一方で、1970年(昭和45年)に動物由来の食料によるカロリー供給の割合は7%程度であったものが、2007年には15%まで上昇しています。この傾向は東アジアにおいて顕著であり、カロリー供給の総量は約2倍、動物由来の食料によるカロリー供給の割合は1970年の7%から2007年の21%まで3倍に上昇しています(図1-2-16)。
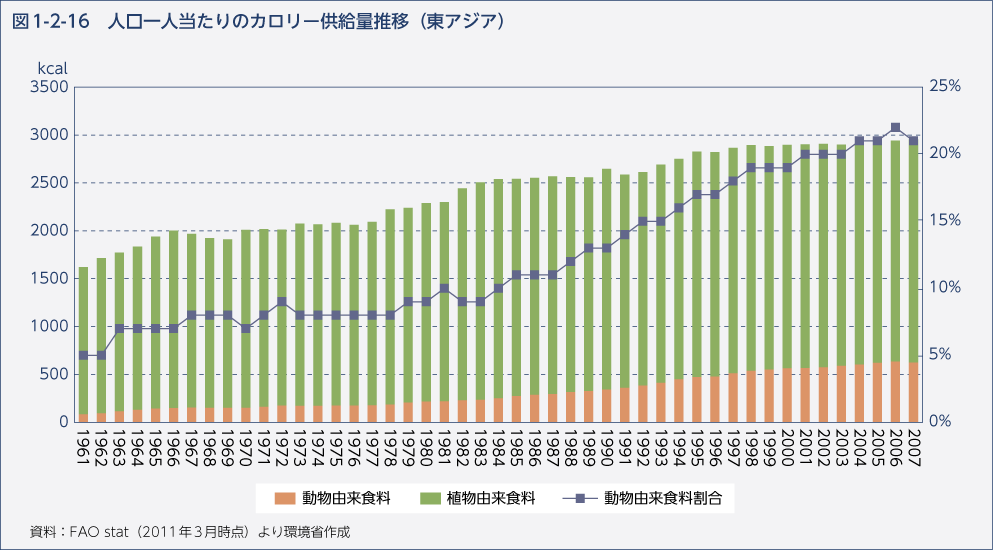
国連世界水資源評価及び計画(WWAP)のレポートによると、一般に、同じ水量を用いて畜産物と穀物を生産した場合、畜産物の方が非効率的であるとされており、水1m3で生産できる小麦が0.2~1.2kg、トウモロコシが0.3~2.0kgであるのに対して、牛肉は0.03~0.1kgとなっています。今後、2050年までの間に、特に東アジアを中心として、飼料穀物の需要増大に由来する穀物需要の増加が見込まれており、これによる水資源の欠乏が懸念されています(図1-2-17)。実際に、南アメリカの西海岸やアフリカ、アジアを中心に水資源が欠乏している地域が広く分布しており、これらの地域において過剰な水利用がなされた結果、水不足による人の生活に重大な影響を与えるだけでなく湖沼などの湿地帯の水位が著しく低下している事例が見られます。
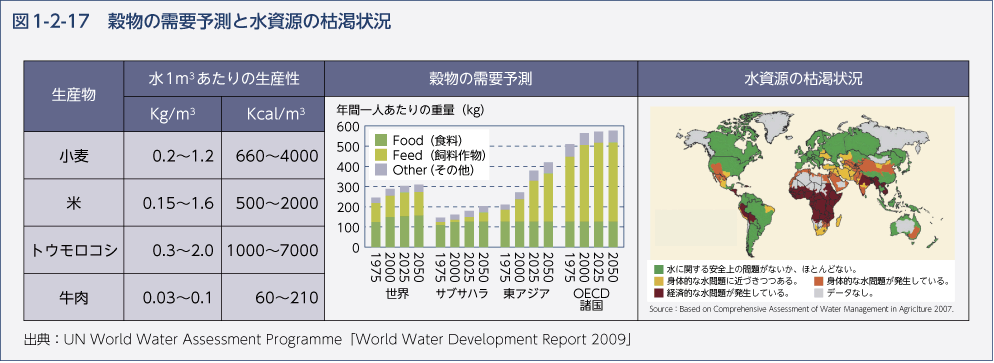
これらのことを考え合わせると、経済成長に伴う食生活の変化が、水資源の需給に影響を与え、結果として環境・経済・社会の広い分野に悪影響を与えるおそれがあると考えることができます。我が国の水資源に関しては、これらの世界的な水資源の状況も踏まえつつ、水資源及び水源の保全を図ることが重要です。
鉱物資源や化石燃料といった地下資源は有限であり、これらの枯渇性資源について、現時点での確認埋蔵量から年間生産量を割った可採掘年数は、鉄鉱石が70年、鉛が20年、銅が35年、金が20年、クロムが15年、石油が46年とされているように、その多くが100年を下回っています(図1-2-18)。現在の生産ペースが続くと、現在の世代に対して地下資源の安定供給が困難となる可能性に加え、将来の世代に資源を残せないという事態が生じる可能性も否定できません。
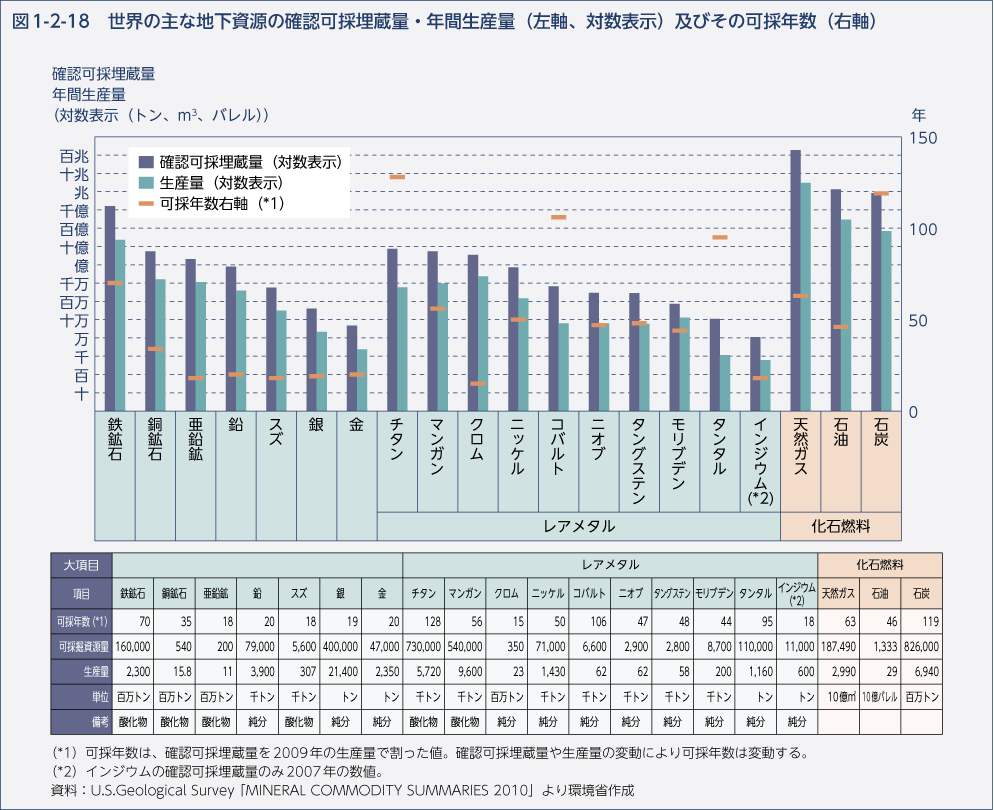
また、地下資源は、生産の過程で多くの資源が投入され、多くの不要物が発生します。技術的に採掘可能な地下資源であっても、採掘が困難な場所にある、又は、有用金属の含有率が低い低品位の地下資源を採取する場合には、生産に必要なエネルギーをより多く要する上、不純物が環境へ大量に廃棄されることから、大きな環境負荷を与えることとなります。これは、隠れたフローとも呼ばれており、地下資源に係る持続可能性を検証するためには、採掘のために投入される中間資源や、廃棄される不純物の量が与える環境負荷についても評価することが重要です。
我が国においては、地下資源の利用に関する技術進歩によって省エネルギー化や省資源化が進展しているものの、依然として様々な枯渇性資源が大量に消費されています。中でも、エネルギーとして消費された後は再利用することができない化石燃料や、人間活動に伴う消費量が非常に多い鉄や銅、有用性が高い一方で希少性も高いレアメタルやレアアースなどの鉱物資源の消費のあり方が、今後、私たちの将来世代に与える影響は大きいと考えられます。
これについて、鉱物資源として銅を例に考察します。銅は電線や伸銅品として、建設・電気機器・工業機械・自動車などの輸送機器・消耗品の分野で利用されており、経済的な発展のための基礎となる鉱物資源として重要な役割を担っています。しかし、世界的に地域偏在性が著しく、上位10鉱山の生産量は世界生産の34%を占めています。たとえば、10百万tを越える埋蔵量を有する8つの銅鉱床の内、6鉱床はチリに集中しており、銅資源の安定的な確保の観点からは、これらの大鉱山による生産量の維持が重要です。
一般に、鉱山から採掘した粗鉱の品位は0.8~3%程度であり、粗鉱を精製した精鉱でも4割程度であると考えられますが、これらの現在操業中の世界の主要な鉱山で銅鉱石の品位低下が指摘されています(図1-2-19)。我が国に輸入される銅鉱石の品位についてみてみると、2001年から2008年までに約32%から約29%まで低下しています(図1-2-20)。これは、地表部の高品位鉱石を掘りつくし、鉱床深部の低品位を採掘する場合が増えていることが原因の一つと考えられています。
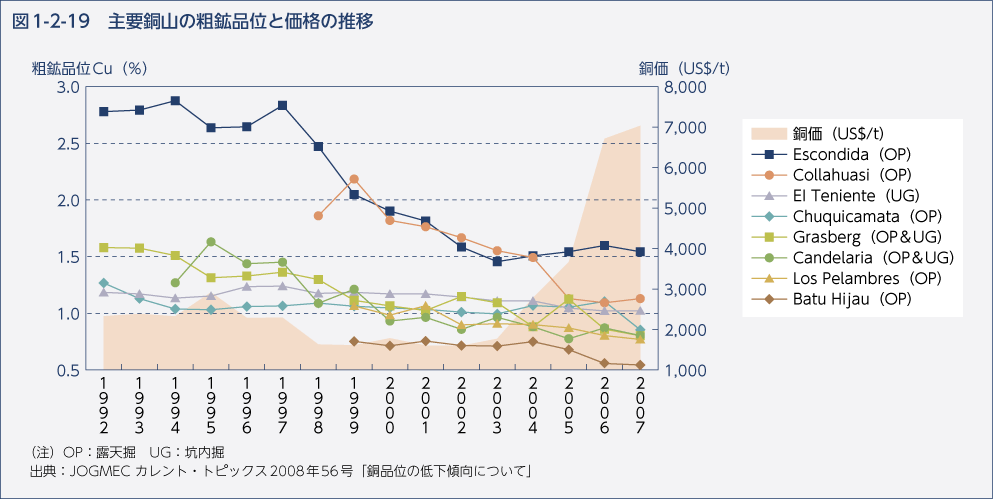
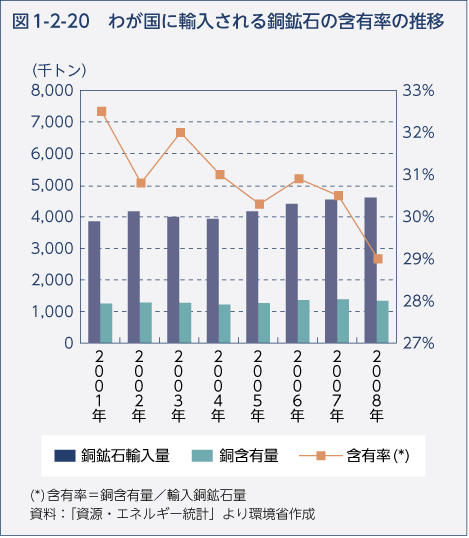
銅鉱石の品位の低下は、銅の単位あたりの生産に伴う廃棄物や銅の精製に必要なエネルギーの増加を意味することから、鉱物資源の採掘に伴う環境負荷を評価するためには、これらの隠れたフローを含めた関与物質総量(TMR:Total Material Requirement)についても考慮する必要があります。TMRの推移を見ると、2001年以降、世界の銅鉱石の生産量に大きな変化はないもののTMRの値は増加していると考えられ、銅鉱石の品位の低下に伴う環境負荷の影響が懸念されます(図1-2-21)。
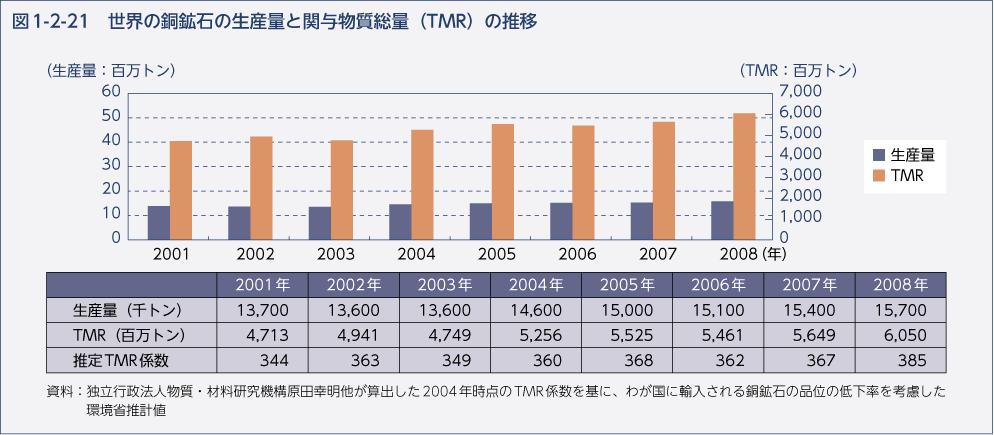
ここまで、個別の人間活動とそれに伴う環境負荷について見てきました。最後に、人間の経済・社会活動と環境負荷を、総合的に見るために、経済成長と、エコロジカルフットプリント及びCO2排出量との関係について見てみましょう。
私たち人間が、持続可能な発展を達成するためには、これまで互いに並行するように増大してきた経済成長と環境負荷を分離すること、つまり、環境負荷の伸び率が経済成長を下回り、経済成長による環境負荷がかかっていないというデカップリング(decoupling)の状況に持っていくことが重要です。
世界のGDPの伸びと世界の二酸化炭素排出量の伸びとの相関を見てみると、GDPの増加に伴って、二酸化炭素の排出量が増加していることがわかります(図1-2-22)。GDPの伸びと二酸化炭素の排出量の増加は、相対的にはデカップリングが進んでいる状況ですが、絶対的なデカップリングが進んでいるとはいえない状況にあります。
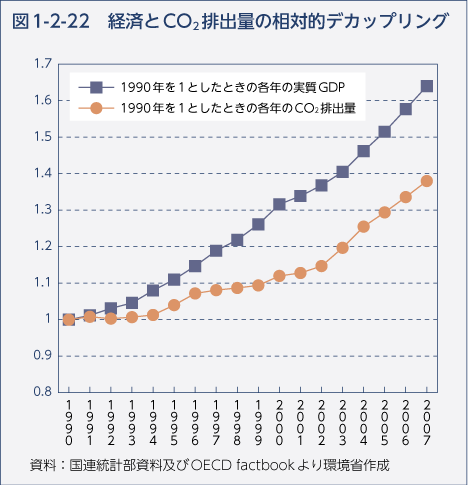
世界約140カ国について、GDPとWWFが2010年(平成22年)に公表したエコロジカルフットプリントの数値との相関を見てみると、一人あたりのGDPが高い国については、エコロジカルフットプリントの値も高い関係にあることがわかります(図1-2-23)。エコロジカルフットプリントは、人々の資源の消費量と自然の生産能力とを比較したもので、人間活動による環境負荷について、資源の再生産および排出物の浄化に必要な面積に換算して示した数値とされており、世界においては依然として経済の成長が自然の再生能力に負荷を与えていることが示唆されます。
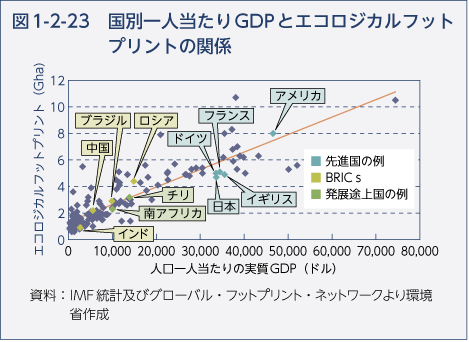
前項で見たように、世界では、環境の側面を中心に持続可能性が懸念される状況にあります。
我が国の社会経済活動は国内のみならず世界の自然資源に依存していることから、地球規模での持続可能性の状況は、我が国にも影響を与えると考えられます。その中にあって、我が国の持続可能性と豊かさはどのような状況にあるのでしょうか。
豊かさと環境の側面の持続可能性とは、密接な関係にあります。EUが2008年に発表した調査結果によると、「生活の質」に影響を与える要素について、EUの人々の84%が経済的な要素が大きな影響を与えるとする一方で、環境の状況が「生活の質」に影響を与えるとする人も80%に上ります(図1-2-24)。
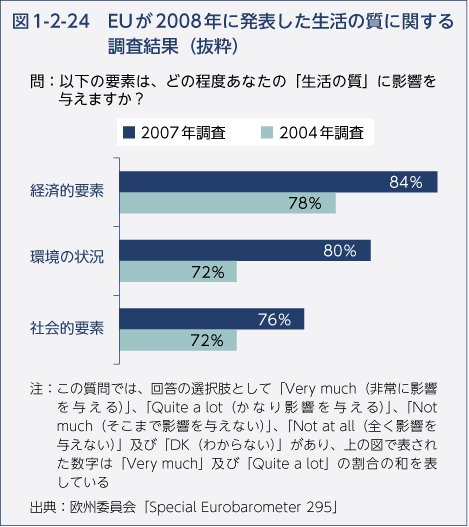
豊かさの測定には様々な課題があり、国内外で様々な研究や試みが行われています。第1節でも触れた、経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に関する委員会報告書(CMEPSP報告書)においては、豊かさは多元的なものとして捉えられ、主な要素として、物的生活水準(所得、消費、富)、健康、教育、安心・安全(物理的・経済的)等が挙げられています。我が国においては、かつて国民純福祉(NNW)算定の取組が行われたほか、現在でも、内閣府において幸福度に関する研究が行われており、今後の知見の充実が期待されます。
ここでは、CMEPSP報告で示された考え方を手がかりにして、主に環境的な側面に関して、我が国の持続可能性と豊かさについて検討したいと思います。まず、我が国の持続可能性について、環境負荷と生物多様性に関わるいくつかの指標を用いて概観した上で、我が国の豊かさについて、その多様な要素との関係に留意しながら、特に環境の側面に焦点をあてて考察していきます。
我が国において、持続可能性はどのような現状にあるのでしょうか。まずは、世界的に持続可能性が懸念されている問題に関わる環境負荷のうち、温室効果ガスと天然資源消費の状況を見てみます。さらに、自然資源のストックという視点から、生物多様性の現状の概況を見てみます。なお、環境の側面における持続可能性の評価に関しては様々な指標が考えられますが、その他の各分野に関する個別の環境の現状については、第2部において言及しています。
国内の非金属鉱物資源の投入量の大きな減少等を背景に、天然資源等の投入量が1990年から2008年にかけて約22億トンから15億トンまで減少しています(図1-2-25)。さらに詳細に見ると、化石資源・製品の輸入量は漸増しているものの、木材等のバイオマス資源投入量(廃棄物を除く)は減少傾向にあります(図1-2-26)。また、これらを背景に、我が国においては、人々の生活や産業における資源の効率的な利用の程度を示す指標である資源生産性(単位GDPあたりの資源投入量)は増加傾向にあり、我が国の社会経済における天然資源の消費のあり方に変化が見られています(図1-2-27)。
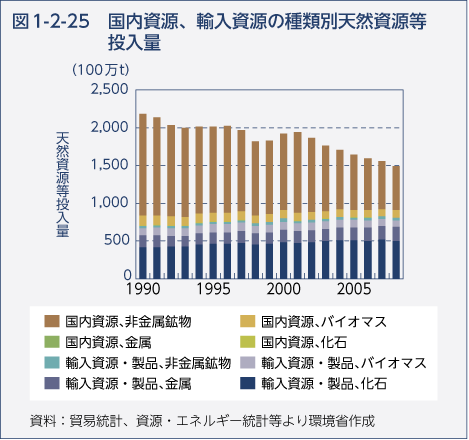
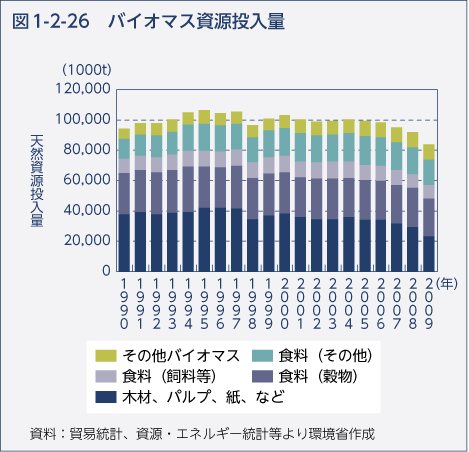
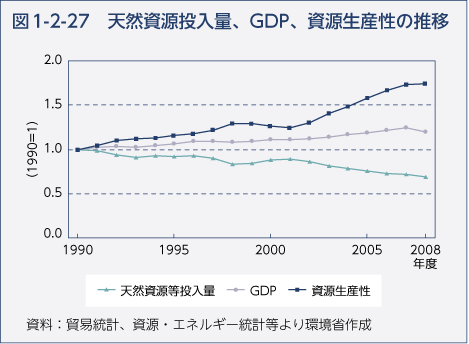
次に、経済活動に伴う環境負荷の例として、温室効果ガスの排出量について見てみましょう。平成21年度の温室効果ガスの総排出量(確定値)は、12億900万トン*(注:以下「*」は二酸化炭素換算)でした。これは、京都議定書の規定による基準年(1990年度。ただし、HFCs、PFCs、SF6については1995年。)の総排出量(12億6,100万トン*)と比べると、4.1%下回っています。平成20年度の総排出量と比べると、産業部門をはじめとする各部門の排出量が減少したことなどにより、5.7%減少しています。平成20年度と比べて平成21年度の排出量が減少した原因としては、平成20年10月に発生した金融危機の影響による景気後退に伴う、産業部門をはじめとする各部門のエネルギー需要の減少が平成21年まで続いたことなどが挙げられます。(図1-2-28)。
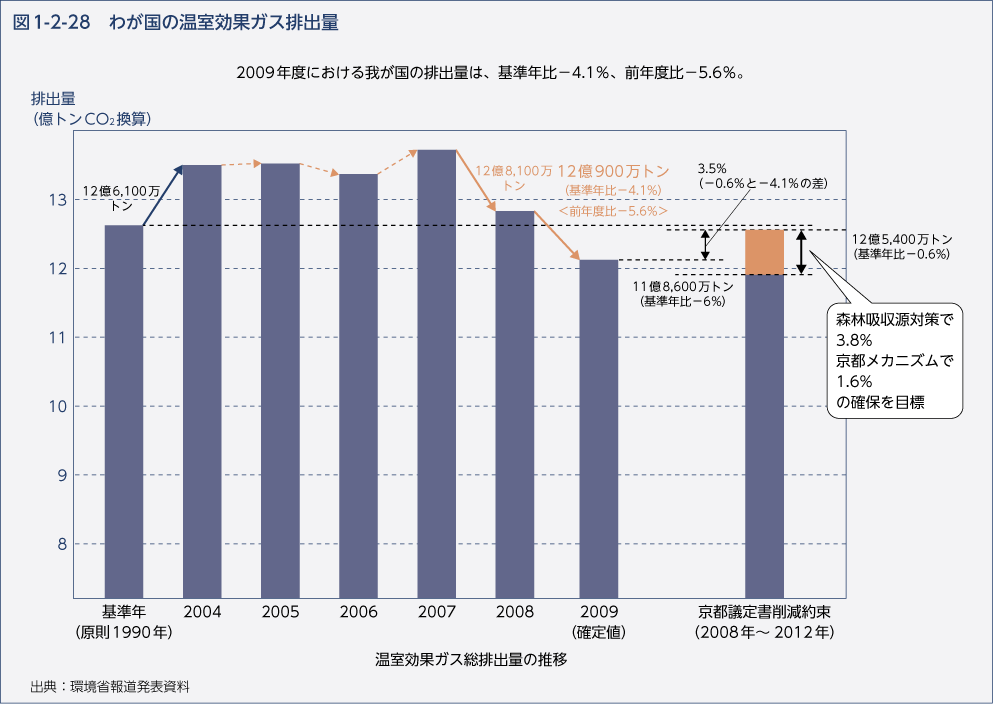
最後に、我が国の自然資源のストックという視点から、生物多様性の状況について見てみましょう。平成22年3月に閣議決定された生物多様性国家戦略2010では、わが国の生物多様性は、以下の「3つの危機」と「地球温暖化による危機」に瀕しているとされています。
第1の危機(人間活動や開発による危機)としては、我が国が経験した戦後の経済成長に伴って、工業地帯の形成や防災などの観点で護岸化の進んだ沿岸域や陸水域における環境変化をあげることができます。例えば干潟については、戦後まもなくの1945年頃に現存していた841km2の干潟が、1978年頃には34%が消滅して553km2となり、1996年頃には496km2まで減少して1945年頃に比べて41%の干潟が消滅しました。陸水域である湿原については、1900年頃から1996年頃の面積を比較すると約61%が消滅しています(図1-2-29)。
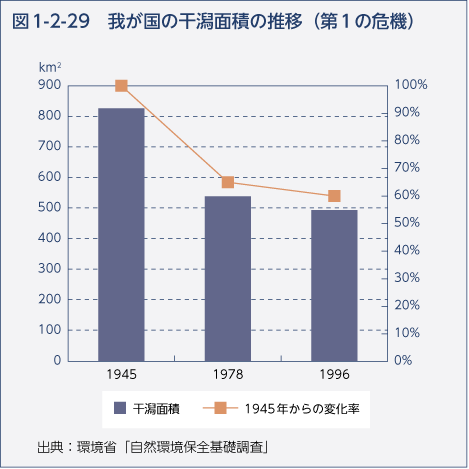
第2の危機(人間活動の縮小による危機)としては、生活様式・産業構造の変化、人口減少など社会経済の変化に伴い、自然に対する人間の働きかけが縮小撤退することによる環境の質の変化や野生生物の生息・生育状況の変化も見られるようになりました。たとえば、耕作放棄地の面積は1985年から2005年にかけて約2.9倍まで増加しています(図1-2-30)。里地里山に代表される自然と人間の関わり合いが深い地域の多くは、人口の減少と高齢化の進行、産業構造の変化によって、里山林や二次的な草原などの利用を通じた自然資源の循環が少なくなることで、大きな環境変化を受けています。
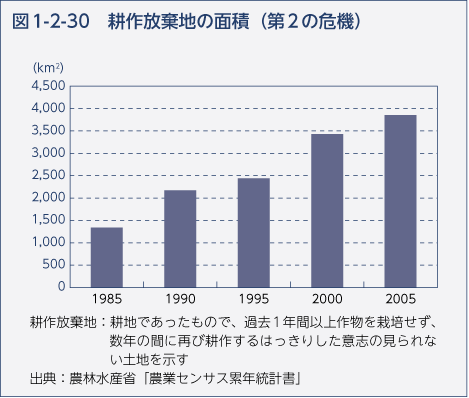
第3の危機(人間により持ち込まれたものによる危機)としての外来生物問題について、近年では、侵略的な外来種が我が国の自然環境の中に定着しつつある状況にあり、我が国固有の生態系への影響の増大も懸念されています(図1-2-31)。
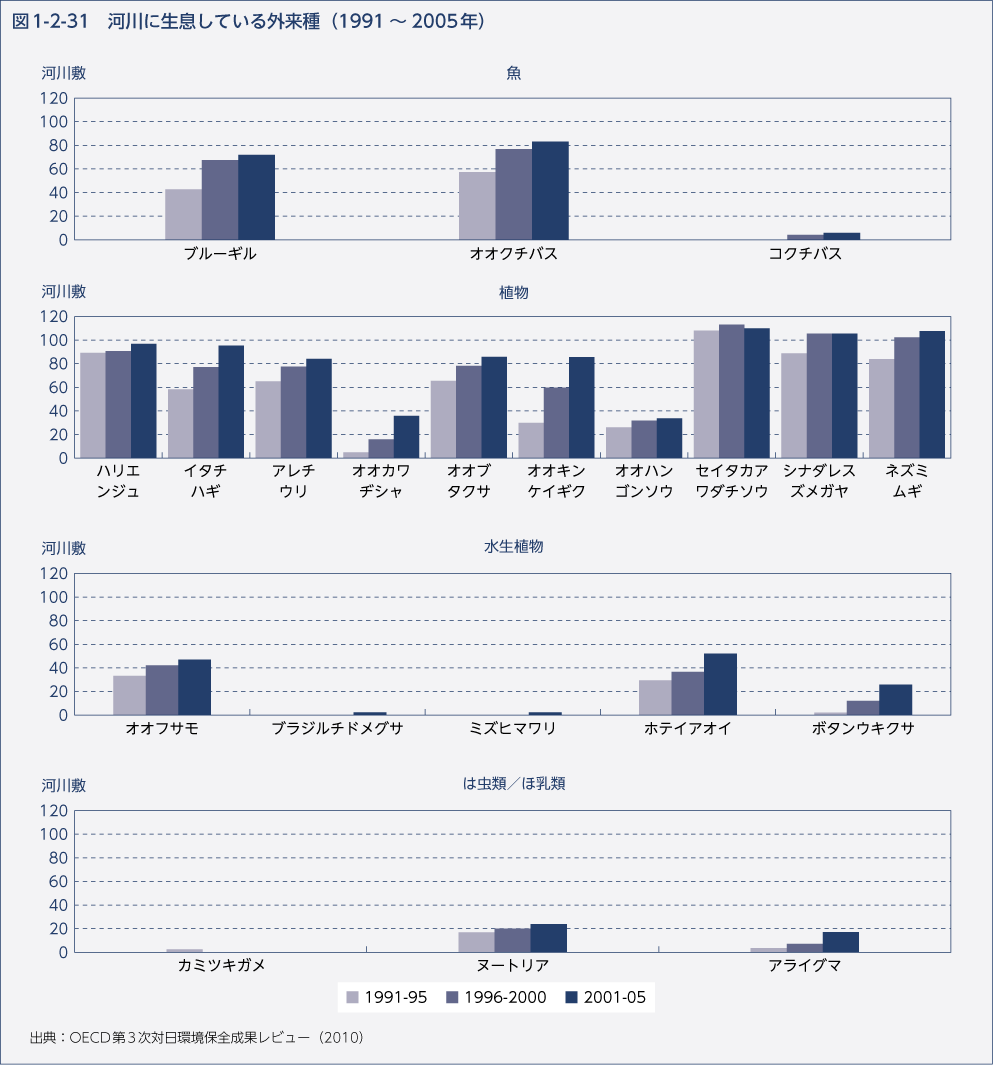
以上、我が国の社会経済活動による環境負荷と生物多様性の現状について、その一部を見てきたところ、天然資源の使用量の減少という改善傾向も見られるものの、全体としては持続可能性が懸念される状態にあり、豊かさを将来にわたって維持し享受するためには、私たちの暮らしの基盤である生物多様性の保全や環境に対する負荷の低減が求められていると考えられます。
汚染のない環境は健康な生活を営むための基盤であり、美しい水、きれいな空気、豊かな緑といった良好な環境は、私たちの生活の質を高めるものであると考えられます。その環境の質を測定することは、環境の側面から見た豊かさの程度を知るための一つの指標となりうると考えられます。
豊かな日常生活を享受するに当たって多くの人が良好な大気環境を求めている中で、我が国の大気中の二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化窒素の濃度は減少しており、我が国の大気汚染の程度は改善に向かっています(図1-2-32)。
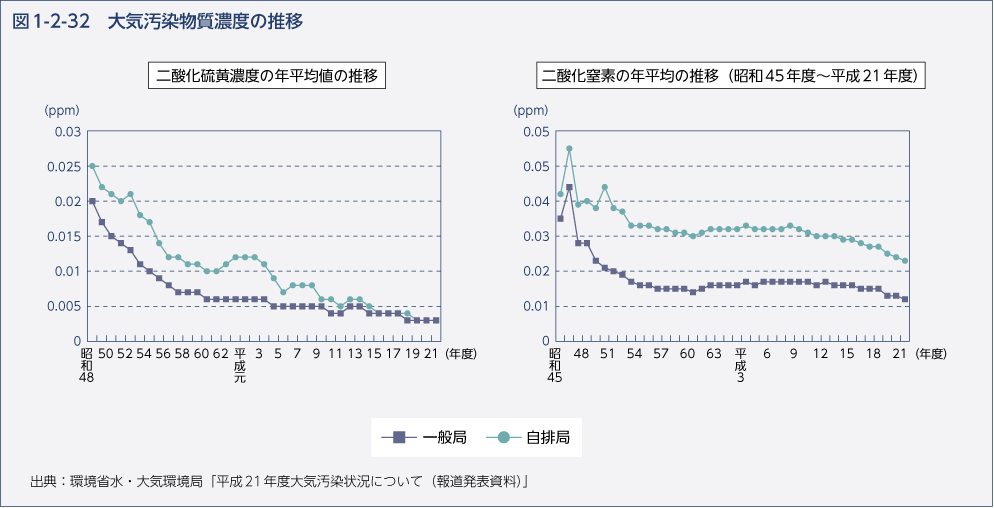
次に、我が国の水質について、水質汚濁に係る環境基準の達成率は、全体で87%と比較的良好な状況にあります。特に河川の水質改善が進んでおり、環境基準の達成率は92%に達しています。一方、内陸の湖沼については環境基準の達成率は53%と低く、有機物が多く富栄養状態にあると考えられます(図1-2-33)。また、地下水の水質については、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が高い状況が続いています(図1-2-34)。このため、硝酸性窒素等による地下水汚染が見られる地域における汚濁負荷削減対策や浄化技術の普及等、効果的な汚染防止対策を促進するための方策を検討しています。
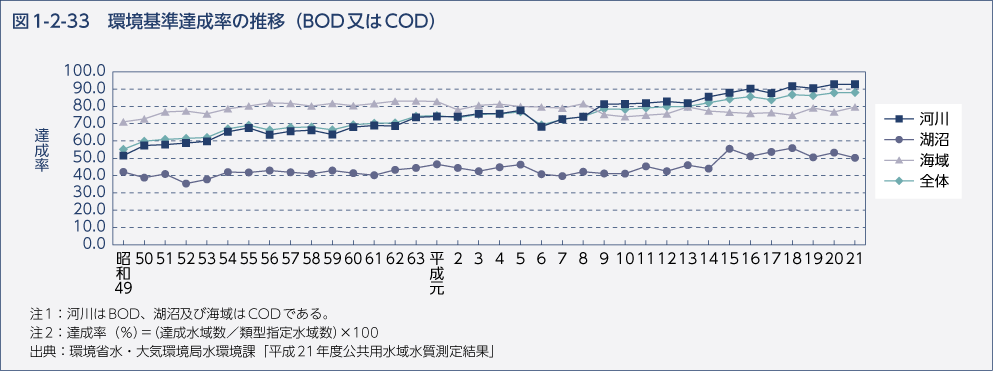
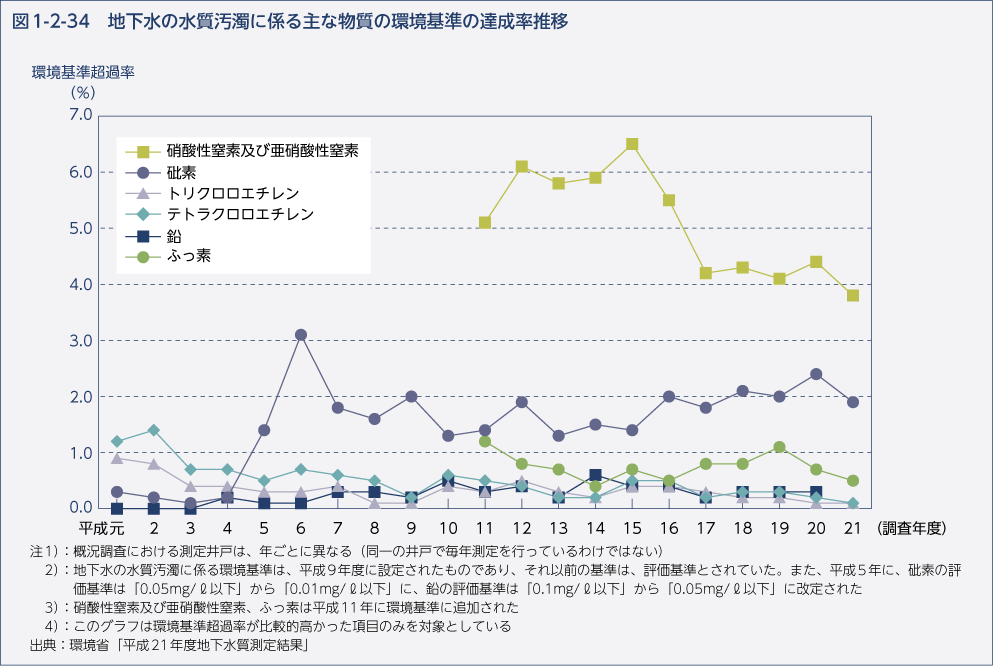
私たちの身の回りにある緑地の状況について見てみましょう。都市域に暮らす人々にとって最も身近な緑地の一つである都市公園等の面積は平成21年度末で全国計約116,667ha(98,568箇所)となっており、一人あたりの面積は約9.7m2/人となっています。また、我が国の森林面積は、国土面積の3分の2を占める約2500万haで推移しており、森林における樹木の幹部分の体積を表す森林蓄積量は人工林を中心に昭和41年から平成19年までの間に2倍以上増加しており森林資源が成熟しつつあると考えられます(図1-2-35,36,37)。
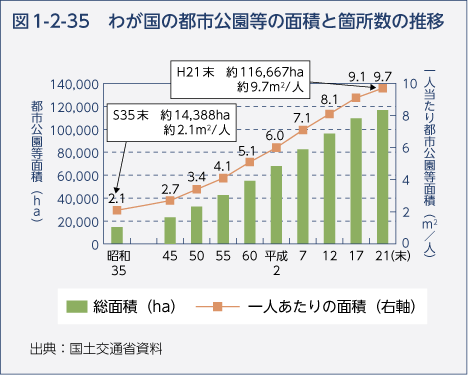
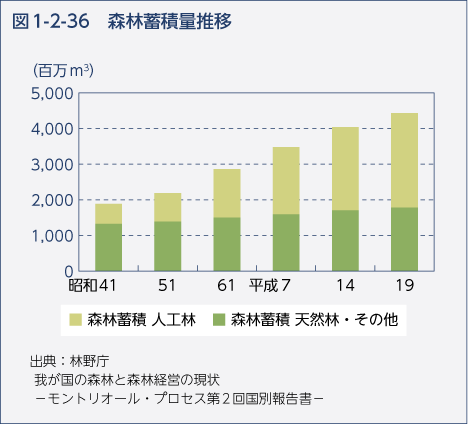
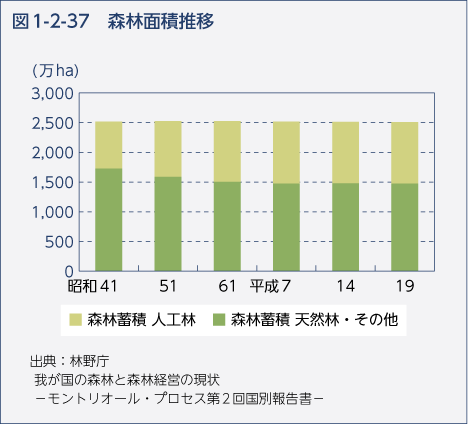
このような環境の改善に向けた取組や、比較的良好な環境の状態も背景にあって、自然とふれあいやすい環境条件が形成されるとともに、人々にも自然とふれあいを求めるような意識も向上しつつあると考えられます。国土交通省が実施している全国一級河川の水質現況調査結果において、多様な視点で河川の環境の現況を総合的に評価する「今後の河川水質管理の指標」では、「川の中に入って遊びやすい」とランクされる河川が全国の一級河川の7割を超えています(図1-2-38)。また、環境省において全国でエコツアー等を実践している団体等を紹介するエコツアー総覧は、平成17年から運用を開始し、平成22年12月現在、登録されている事業者数は、開始当初の1.9倍の728事業者となり、登録されたエコツアーの累計も3.4倍の2,603件となるなど、自然に親しもうとする人々の意識は着実に高まっていると考えられます(図1-2-39)。
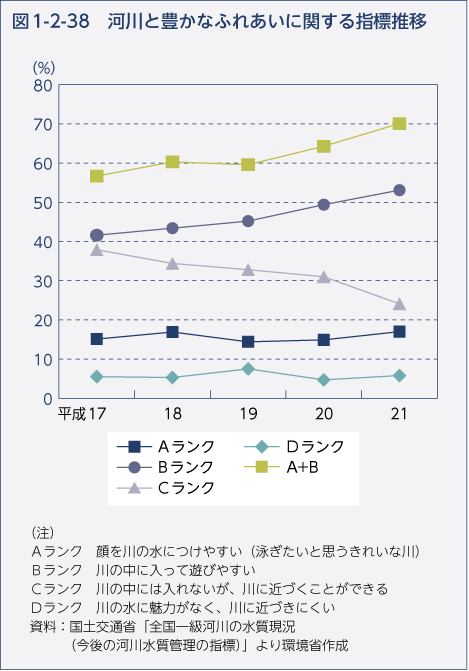
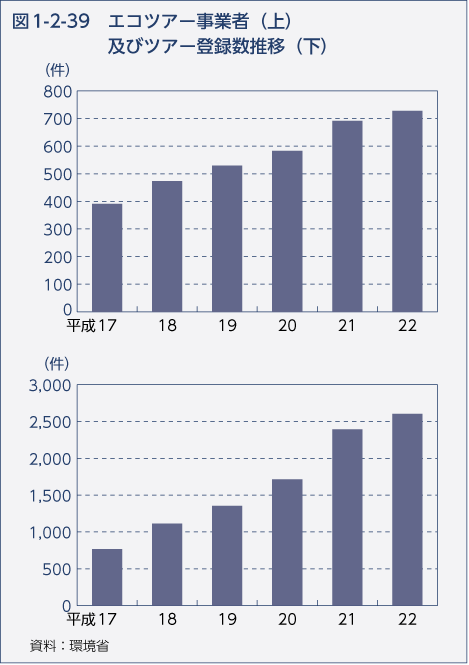
以上、いくつかの主要な側面について環境の質の状況を見てきましたが、全体として比較的良好あるいは改善しつつある状況にあるといえます。これらは健康で豊かな生活を営むための基盤であり引き続きさらなる改善に向けて取り組むことが重要だと考えられます。
豊かさは、環境、経済、社会に関わる多様な要素で構成されると考えられます。その中で、先に取り上げたCMEPSP報告で挙げられている要素から、健康、個人の自由な活動(余暇等)、社会的つながり、消費等の物的生活水準に関する側面について、いくつかの代表的な指標に着目して、我が国の持続可能性と豊かさについて概観しましょう。
健康について平均余命のデータで見てみると、我が国の寿命は戦後延び続け、昭和30年代には男性で65年前後、女性で70年前後であった寿命は、平成21年には男性で79.59年、女性で86.44年まで延びています(図1-2-40)。健康状態によって日常生活への影響がある人の割合は年を重ねるとともに上昇し、65歳以上の高齢者では、平成7年から平成19年までの間、2割前後で推移しています。
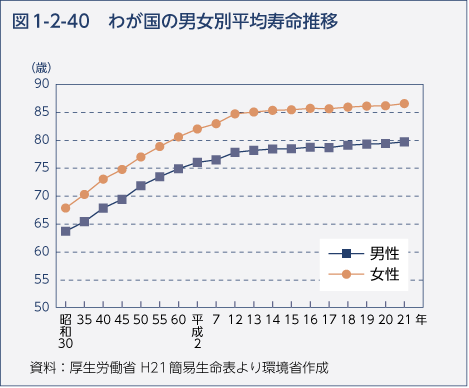
これについて、85歳以上の高齢者においては日常生活への影響がある人の割合は4割前後であり、85歳を超えても半数以上の高齢者が日常生活を営むことができている現状にあると考えられます。また、国民一人あたりのGDPと国民の寿命の関係を測定すると、一般的にはGDPの成長とともに寿命が延びる傾向にあります。一方、我が国においては、他の多くの国々の傾向とは異なり、GDPの成長は見られない時期においても平均寿命が延びています(図1-2-41)。なお、我が国は平均寿命だけでなく、健康寿命(自立して健康に生活できる年齢)も国際的にみて高く、また、健康についての高齢者の意識についても、自分は健康であると考えている人が多いといわれており、我が国では長寿であると同時に健康な生活を営むことができる状況にあると考えられます。
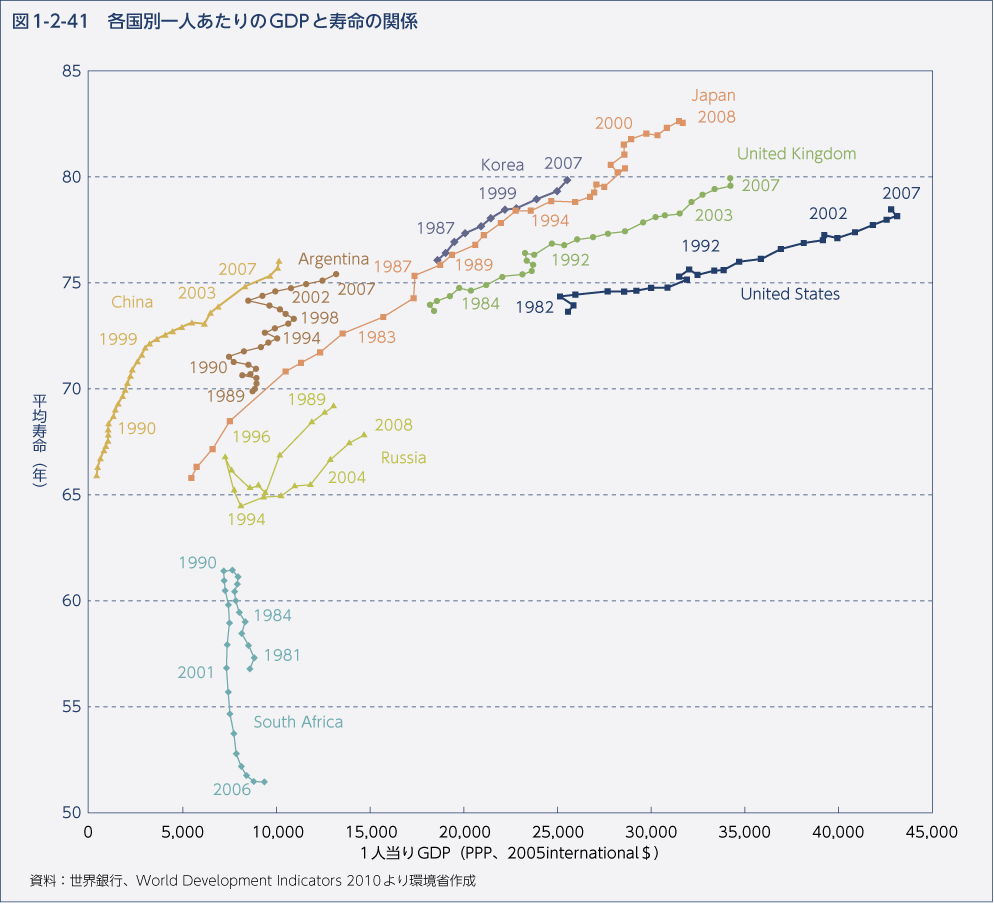
次に、暮らしの中での時間の使い方の変化について見てみると、昭和51年以降、平日の就業時間は8時間前後で推移して大きな変化はありませんが、土曜日・日曜日の就業時間は減少傾向にあり、逆に、昭和51年から平成18年までの間の余暇活動の時間は、土曜日では4.5時間から5.7時間、日曜日で6.3時間から6.8時間まで増加しています(図1-2-42)。このうち、余暇時間の使い方については、平日における高齢者の余暇時間が有業者の余暇時間よりも多く、平成18年度で有業者が3.7時間であるのに対し、65歳以上の高齢者が7.0時間となっています。
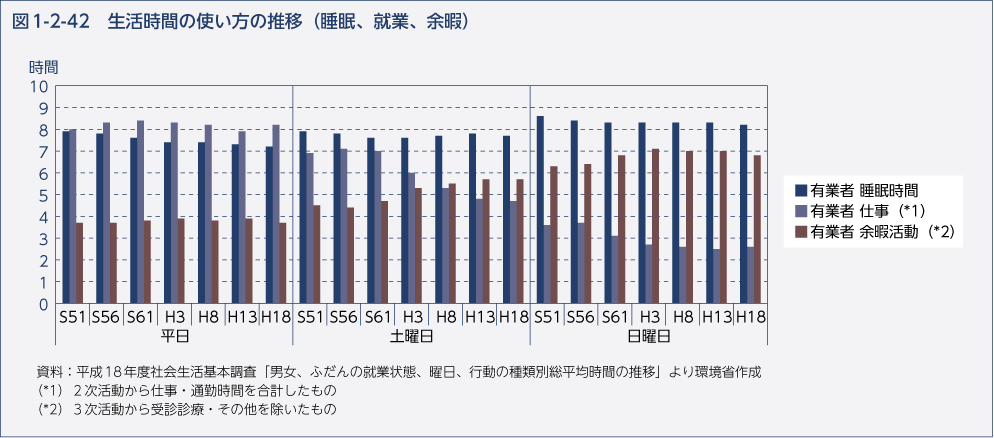
人と社会とのつながりの側面で見てみると、近所づき合いの程度は年を経るごとに低下する傾向にあります(図1-2-43)。内閣府において地域における人のつながりについて調査した結果、我が国の人間関係は難しくなったと感じている人が6割にも上ります。その原因として、54%の人が地域とのつながりの希薄化だと考えており、また、核家族化や親子の関係の希薄化が原因であると考える人も3割を超えている現状にあります(図1-2-44)。
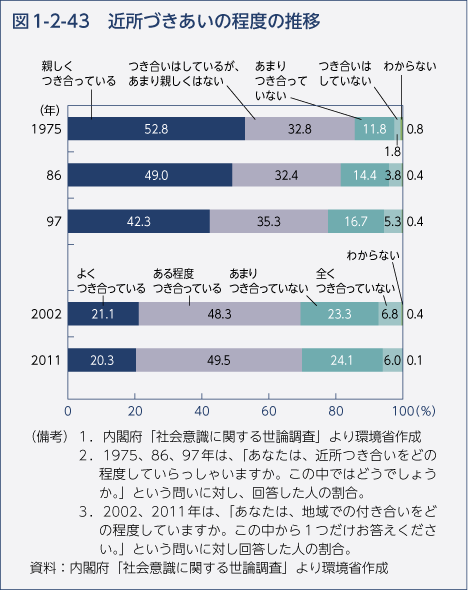
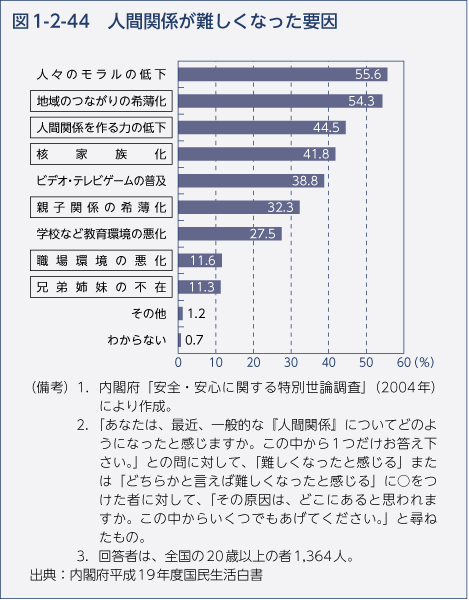
このような中、環境の保全活動を通じて、人と人とが互いに関わり合いを持ちうる傾向を見ることが出来ます。自然や環境を守るためのボランティアをしている人は、地域や学校などの団体や家族と一緒に活動している割合が高く、個人と社会や家族といった人間同士の関わりの中でこれらの活動が行われている様子がうかがえます(図1-2-45)。特に、家族と一緒に自然や環境を守るためのボランティアを行っている人の割合は、他のボランティア活動における割合よりも高く、環境保全活動を通じた家族とのふれあいの場が提供されている側面もあると考えることが出来ます(図1-2-46)。また、環境保全を図る活動をするNPOの団体数は増加する傾向にあります(図1-2-47)。人々は、自らの暮らしに深い関わりを持つ環境という共通の関心事を通じて、社会の中でのつながりを確認することができると考えることが出来ます。
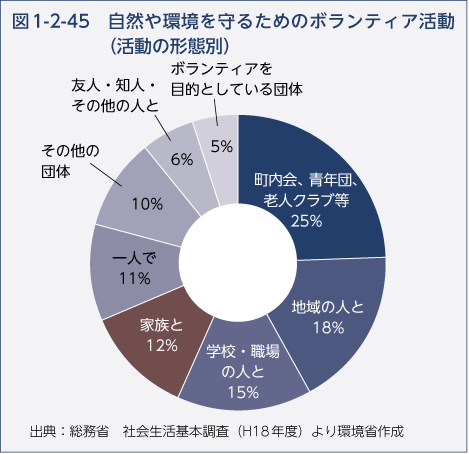
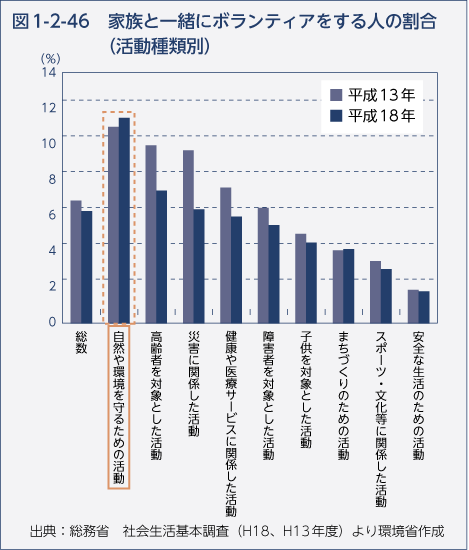
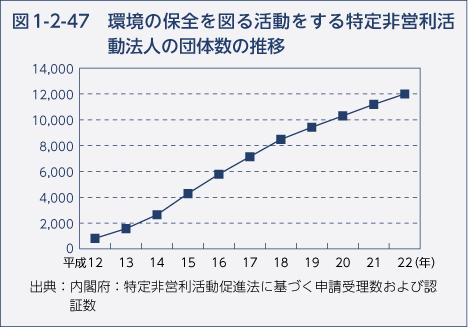
家計消費支出についてみてみると、その変化については、近年、家電製品や自動車などの耐久財は、1990年代に頭打ちになりその後は一貫して減少傾向にあって、平成22年現在においては約15%程度まで減少しました。また、食品や消耗品などといった非耐久財の消費は1980年代以降一貫して減少しており、現在は25%程度まで落ち込んでいます。一方、医療、教育、通信、運輸といったサービス消費が1990年頃に50%を上回り、平成22年現在では6割近くまで割合が高まっており、豊かさを実現する上で、モノの消費以上にサービスの消費の重要性が高まってきていると考えられます(図1-2-48)。
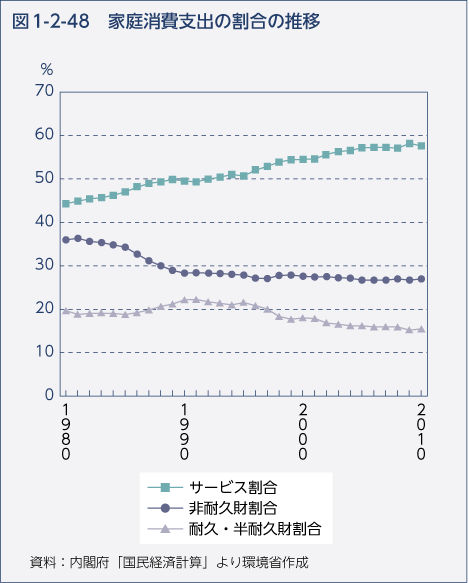
このような社会的、経済的な要素と前述の環境面の要素の上で、総体としての我が国の豊かさはどのような状況にあるのでしょうか。これを考える一つの切り口として、我が国の国民生活選好度調査における「どの程度幸福か」に関する10段階評価の結果を見ると、我が国においては、5点及び7又は8点と答える人が多い傾向を見ることができます。
このような点差のピークが二つに分かれる傾向は、欧州における社会調査におけるイギリスやデンマークのように8点と答える人が最も多い傾向とは異なっており、我が国においては必ずしも多くの人が広く幸福であると感じている状況とはいえないと考えられます(図1-2-49)。
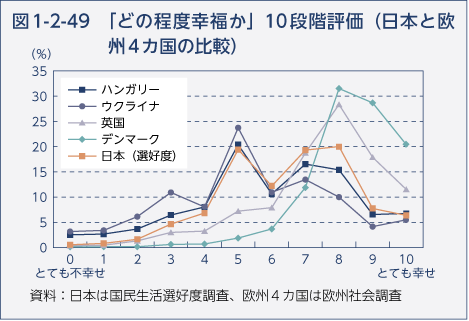
以上のような各要素と全体の傾向は、環境の側面、特に持続可能性の観点から環境負荷の低減が求められていることとの関係で、どのような意味を持つのでしょうか。
まず、ひとつめに、サービスの消費が高まっていること及び天然資源投入量の減少傾向は、サービスの消費を質的に成長させることによって、天然資源やエネルギー消費に伴う環境負荷を増大させることなく、豊かさを向上させることができる可能性を示唆していると考えられます。
次に、人と人、社会と人とのつながりが希薄化している一方で、自然や環境を守るためのボランティア活動が活発となっている傾向は、このような活動を通じて、環境を改善しつつ地域社会とのつながりを強め、豊かな暮らしを実現する足がかりになります。我が国の寿命が延び、余暇の時間が増加傾向を示していることを背景に、これは、今後ますます重要な視点となるものと考えられます。
加えて、安心・安全な社会を構築することは、豊かで持続可能な社会の実現のための最も基本的な要素の一つです。たとえば、環境問題と自然災害には密接な関わりがあります。気候変動による海面上昇や気象災害、森林の過剰伐採に伴う森林の保水機能の低下と洪水の発生等に見られるように、環境の劣化は自然災害による被害を悪化させる場合もあります。他方、ひとたび大規模な自然災害が発生すると、私たちの生活と生産の基盤が破壊され、大量の災害廃棄物の発生などによる環境問題も発生します。
そのため、平常時において自然災害を防ぐためにも良好な環境の保全を進めることは重要であり、また、自然災害が発生した場合にも、復興に向けた歩みを着実に進められるよう災害廃棄物等の環境問題への対処を速やかに行う必要があります。
このように、豊かさの要素を掘り下げて考えると、経済活動の規模や物質的な生活水準だけを重視した考え方を取る場合に比べて、将来に向けた持続可能性と現在の豊かさとを同時に向上させていく可能性が開けてきます。持続可能性や豊かさの評価や測定に向けた取り組みの一層の進展が期待されるとともに、私たち一人一人自らが、望ましい豊かさとは何かについてより深く考えてみることも重要であると考えられます。
以上、第1章では、私たちの暮らしの持続可能性や豊かさについて、これらに影響を与えると考えられる様々なデータに基づいて、環境の側面を中心に見てきました。現在の世代が享受する豊かさを将来世代にも引き継ぎ、持続可能な社会の構築を達成するためには、豊かさの源である自然資源を消費し尽くさずに持続可能な利用を進めること、及び、生存の基盤である地球環境に過大な負荷を与えず健全に保全し続けることが重要な鍵となると考えられます。
豊かな暮らしを営みながら持続可能性を実現するためには、伝統的な知識から新しい科学技術までを含めた様々な知恵を結集するとともに、国内のみならず国際的なルールを確立し、それを確実な行動に移していく必要があります。
この問題に関して環境の側面での考察を深めるため、第2章においては地球の恵みである生態系サービスを持続可能な形で利用するための知恵について考察し、第3章においては、その生態系サービスの基盤となる生物多様性について、生物多様性条約第10回締約国会議で合意された事項を中心に、人と自然と地球が共生するために必要な規範と取るべき行動について提案するとともに、第4章においては、我が国の技術を生かした世界的なグリーン成長と世界的な持続可能性の向上に貢献していくための取組について、特に循環型社会と低炭素社会に着目しながら見ていきます。
なお、今年度については、特に、第5章を設け、平成23年3月11日に発生した、三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の巨大地震に関し、「東日本大震災からの復興に向けて」を記述しています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |