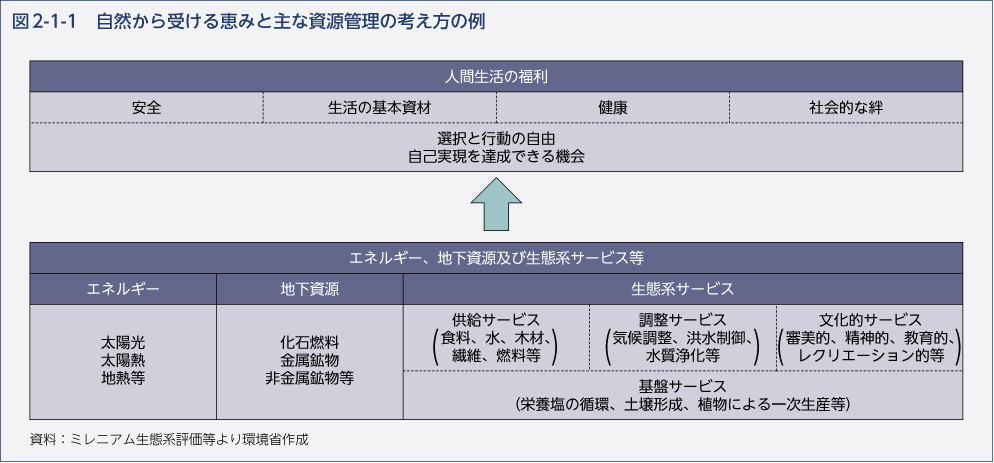
第1章で見たように、私たちの暮らす地球には、化石燃料・鉱物等の有限な地下資源、及び、食料・森林資源等の生物由来の資源や水資源等の再生可能な資源が存在しています。私たちは、地球が提供するこれらの資源をエネルギー・食料・木材・医薬品・その他様々な生活資材などとして利用することによって、生活を成り立たせています。さらに、豊かな森林が台風などの大雨による被害を抑制するなど、私たちの安全な暮らしは健全な生態系に支えられています。この地球の資源に支えられた暮らしの中から、様々な文化が生まれ、今日の地域色豊かな固有の文化が形成されました(図2-1-1)。
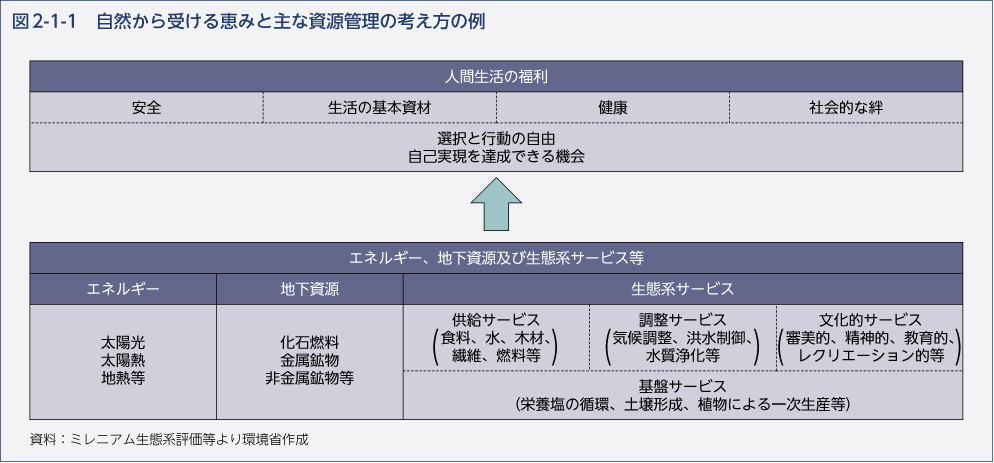
第2章では、特に再生可能な資源である生物由来の資源が提供する恵みの現状に注目して、地域に根ざした私たちの暮らしと地球のつながりを維持し、地球の恵みを保全して、未来に引き継いでいくための知恵について考察したいと思います。
地球上には私たちが認識している種だけで175万種、未知の生物も含めると3000万種ともいわれる野生生物が生息しています。人類は地球上の数多くの種の一つに過ぎず、これら無数の生物との関わりなしには、生存が不可能だと考えられます。人類を含む多様な生物たちは、互いに関係しあい、つながりあって活動しており、この「つながり」を維持していくことが極めて大切な観点になるのです。
生物多様性が提供する生態系サービスと私たちの生活や文化とは、どのように関わっているのでしょうか。私たちの暮らしと生態系サービスとの関わりについて、主として我が国における暮らしの安全、建築物、食文化、医薬品等への利用、文化との関わりのそれぞれの側面から見てみましょう。
健全な生物多様性は、安定した気候の調整や洪水の制御など、環境の激変の緩和や環境の状態を良好な状態に保つ機能を提供します。このような機能を生物多様性の調整サービスといい、そのよく知られた例として、森林の水源涵養機能があります。たとえば、北海道東部の別寒辺牛(べかんべうし)水系の例を見てみましょう。
別寒辺牛川流域のほとんどは人工林や天然林若しくは湿原であり、農地面積の割合は7.6%に過ぎません。一方、別寒辺牛川の支流である大別川流域では農地開発が進み、流域の3分の2が農地となっています。この両河川の流域の降雨後3日間における河川への雨水の流入量を比較すると、別寒辺牛川流域で降った雨で、河川に流入したのは降雨量の約1割だけであったのに対し、大別川においては降雨量の約7割が河川に流入しています。これは、森林が豊富に残っている別寒辺牛川流域では、降った雨水は、降雨後、一定期間流域内にとどまっていることを示していると考えられます(表2-1-1)。
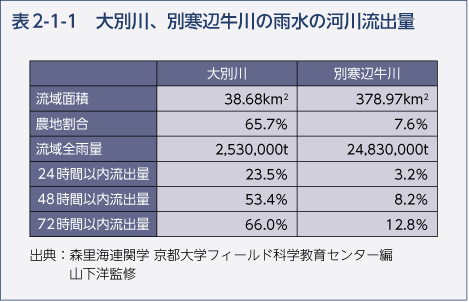
また、森林の大規模な伐採が河川の洪水調整機能に影響を与えたと考えられる過去の例として、静岡県北部地域における、江戸時代の大規模な森林伐採と大井川の洪水の関係に関する報告があります。江戸幕府の御用材採取を目的に、1692年から1700年までの9年間、大井川の上流の森林約3,600haが大規模に伐採されました(図2-1-2)。伐採の始まった1692年以降、それ以前には記録のなかった下流の橋を流出させるような洪水が記録されるようになりました。
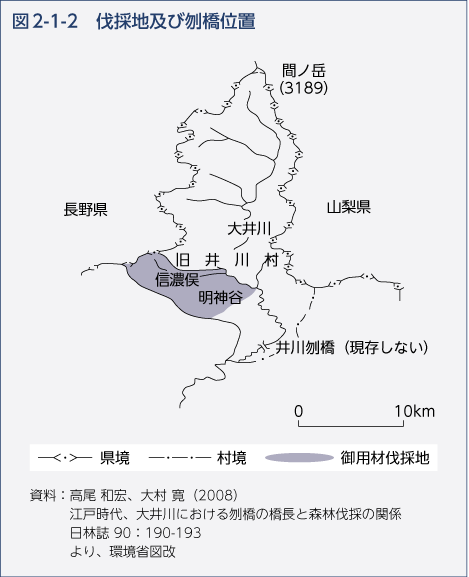
当時の洪水の状況は、伐採地から流れる大井川に架っていた井川刎橋(はねばし)の橋の長さの変化の記録から推定することが出来ます。1600年代始めに約73mの井川刎橋が大井川に架けられて以降、数度の修理を経ても、1600年代終わり頃までの間に橋の長さには変化はありませんでした。ところが、上流域の伐採後の1700年頃から1825年までの間に、橋の長さは約30m長くなっています(図2-1-3)。これは、大井川の上流域の大規模な森林伐採後、森林の保水力が低下したことで河川流量が増し、河床幅が拡大したことによるものと推察されます。
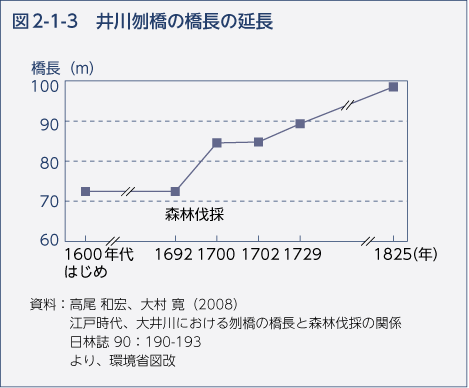
このように、森林をはじめとする生物多様性による環境の調整機能は、私たちの安定した生活の基盤を提供するものであり、今日でもなおその重要な役割を担っています。
次に、森林が提供する生態系サービスとして、森林資源と木造建築物について見てみましょう。わが国は、世界有数の木造建造物の国であり、その長い歴史の跡は、現在四千棟以上にのぼる国宝・重要文化財建造物に示されています。日本の重要な建造物文化財の85%が木造、半数近くの屋根が植物性資材で葺かれているため、これらの文化財の維持には、定期的な保存修理が必要になります。我が国では、文化財としての建造物に大きな価値を認め、保存修理に必要な森林資源が維持・保存されてきました。現在、これらの森林資源を利用しながら、全国で毎年300棟以上の木造文化財の修理が行われています。
これらの修理には大径木の木材が必要であり、修理に用いられた木材の約3分の1は、比較的大径で長尺の木材が占めています。文化財の補修に用いられるような大径木の材の供給のためには、100年生以上の森林が持続的に維持されている必要があります。これを可能にしている伝統的な森林管理のあり方について、20年に一度行われる伊勢神宮の式年遷宮における建造物の保存修理を例にとって見てみましょう。
伊勢神宮の式年遷宮は、690年に始まり2013年には62回目が予定されています。この式年遷宮に伴う建造物の補修は、毎回、大径かつ長尺の木材を中心に、丸太の材積量で約8,500m3のヒノキ材が必要となります。たとえば、58回目の式年遷宮の際に注文された丸太の本数は11,000本以上であり、そのうち口径30cm以上の中規模の材が約3000本、70cm以上の大径木が600本以上必要とされました(図2-1-4)。
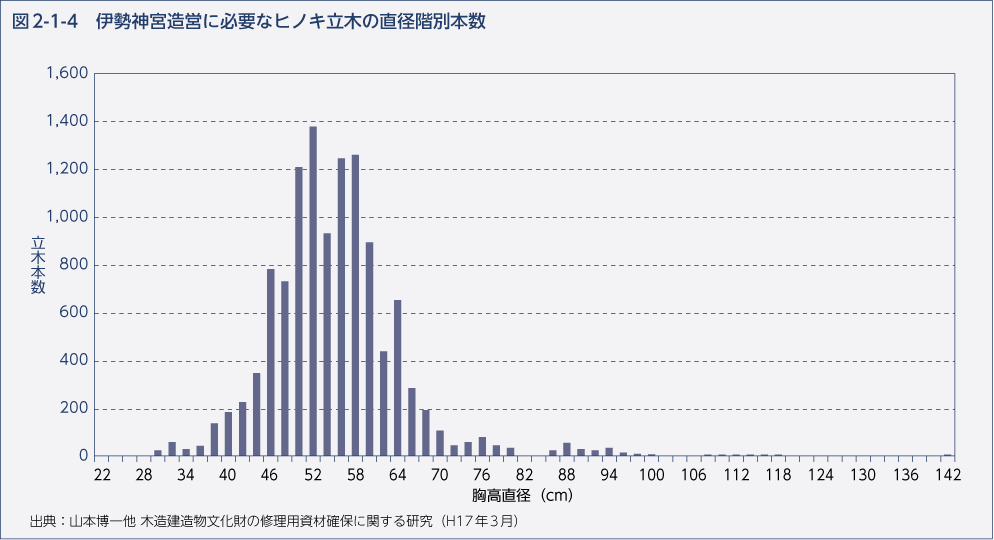
戦後、神宮備林が林野庁の所管に移されてからは、林野庁における国有林野施業実施計画において木曽ヒノキ文化財等択伐複層型施業群等として施業方法を定め、50年程度を回帰年として長期にわたる計画的で持続的な管理が実施されています。
また、伊勢神宮の境内地として管理されてきた神宮宮域林には、禁伐されている神域(267ha)、天然林で構成される第一宮域林(1,094ha)、御造営用材の生産等の森林施業が行われている第二宮域林があります。この第二宮域林では、神宮司庁によって、200年で単位面積(ha)あたり100本程度の大径木の生産を目標とする、長期的な森林管理がなされています。
さらに、式年遷宮によって立て替えられた後残された廃材は捨てられることなく、全国の神社の材等として余すところなく再利用されます。我が国においては、森林を大切に守り、育て、そこから生産された材を無駄なく使い切る知恵を持っていると考えることができます(図2-1-5)。
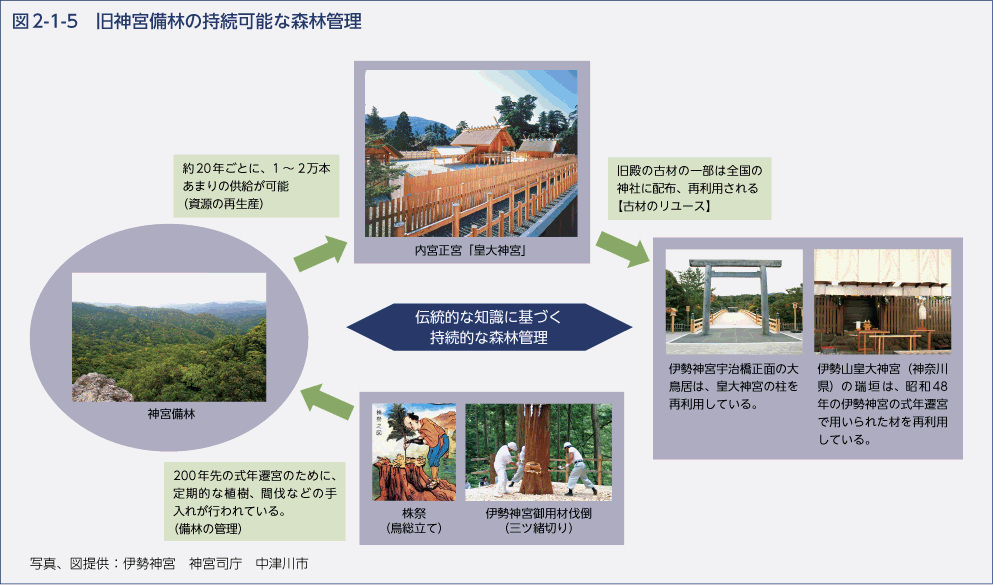
人間を「風土的過去」を背負った存在であると捉えていた和辻哲郎は、その著作「風土-人間学的考察-」の中で、「食物の生産に最も関係の深いのは風土である。(中略)我々の食欲は、食物一般というごときものを目ざしているのではなく、すでに永い間にできあがっている一定の料理の仕方において作られた食物に向かう。」と記しています。
私たち人間は、地域の自然から手に入る生物資源を、生態系サービスがもたらす食糧資源として利用してきました。私たちは、食品となりうる生物資源であればなんでも利用しているのではなく、それぞれの地域の風土に育まれた資源を入手し、加工し、食することで地域固有の食文化を発達させてきました。
また、食品の加工にあっては、自らの手で料理するだけではなく、乳酸菌や酵母などの微生物の力を活用して加工する技術を用いてきました。微生物による発酵作用を用いて農林水産物の原材料を加工した伝統的な発酵食品は、世界各地で見ることができます。たとえば、小麦粉からパンが、米から日本酒が、大豆から味噌や納豆などが作られます。
発酵食品は主としてその地域で採ることができる自然資源を利用して作られています。また、その地域の風土を生かした発酵技術が用いられているために、それぞれの地域では、発酵技術の伝承を通じた地域独特の文化が育まれていると考えることができます。たとえば、酒類の場合、その原料として、米、イモ、サトウキビ等様々なものが利用され、地域の特色が生まれています(図2-1-6)。魚を用いた発酵食品としては、塩漬けにした魚やその内臓を発酵させた液を抽出する魚醤(ぎょしょう)や塩辛、米と魚を用いて乳酸発酵を進めたなれずし、サバなどをぬかに漬け込んだへしこ等があり、我が国の各地において地域の特色のある食文化が形成されています(図2-1-7)。
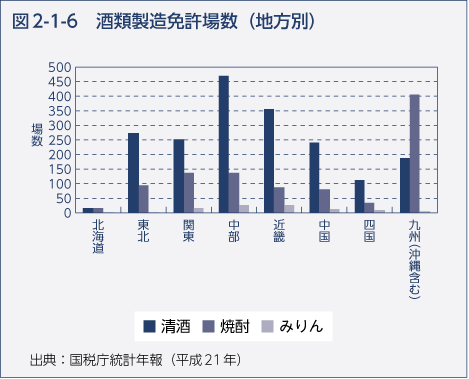
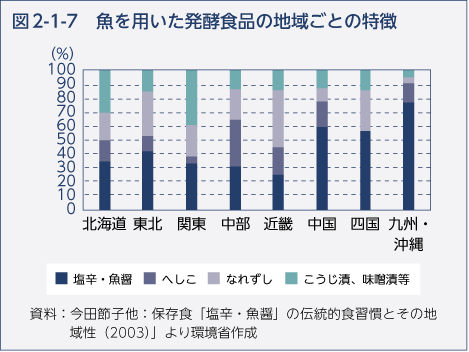
生物多様性の損失が発酵食品の材料の安定的な供給に影響を与え、伝統的な発酵食品の生産ができなくなることによって、結果として地域の個性を失わせる可能性もあります。これについて、魚を用いた発酵食品であるなれずしを例にとって考えてみましょう。
滋賀県では、琵琶湖固有種であるニゴロブナを用いたなれずしの一種である「ふなずし」が、正月などのおめでたい席で供されるなど、伝統的な発酵食品として親しまれてきました。琵琶湖において、近年のフナ類の1kgあたりの単価は、ニゴロブナが3,000円程度であるのに対して、その他のフナ類が1kgあたり400円前後と、ニゴロブナの重要性は非常に高いと考えることができます。
ところが、戦後、琵琶湖周辺の湖岸整備や土地利用の変化により、琵琶湖に生息する魚類の生息にとって重要な内湖、ヨシ帯等が失われました。また、昭和30年代後半から水質の悪化が進むとともに、昭和40~50年代には外来種であるブラックバス(オオクチバス)やブルーギルが琵琶湖に侵入して大繁殖しました。これらの影響によって、琵琶湖の魚介類の生息環境は著しい悪影響を受けました。
その結果、昭和40年頃には最大約1,100トンの漁獲がみられた琵琶湖のフナ類は、近年100トン前後で推移しています。ニゴロブナの漁獲も減少を続け、現在では約40トン程度まで落ち込みました(図2-1-8)。そのため、ニゴロブナを原料とする「ふなずし」は地域に住む人々の食卓に上りにくい食品となっています。このように生物多様性の損失は、地域独自の食文化の継承の面からも大きな影響があることがわかります。
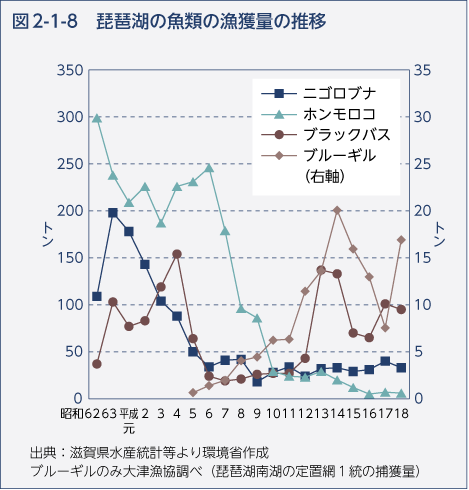
滋賀県では、失われつつある滋賀県の伝統食である「ふなずし」等の湖魚料理の普及のため、「琵琶湖産魚介類販路開拓事業(H21~)」の事業の一環として、伝統食「ふなずし」の食文化継承を目的とした「ふなずし飯漬け講習会」が平成22年度から行われています。

近年、先進国を中心に、遺伝的・生物化学的な研究や開発等、遺伝資源の利活用を含めたバイオ・テクノロジーの活用が進んでいます。一般的に、バイオ・テクノロジーは遺伝子や生物由来の物質を利用して新たな医薬品や高品質の作物などを開発する先端技術として用いられており、医療、環境、食料など様々な分野において、新しいビジネスの機会を提供する重要な技術として注目されています。
これらを背景に、我が国におけるバイオ・テクノロジー等の新しい技術開発に関して、生化学、遺伝子工学等の特許登録件数については、平成2年には472件だった特許件数(登録)が平成21年には約5倍の2,412件まで増加しています(図2-1-9)。
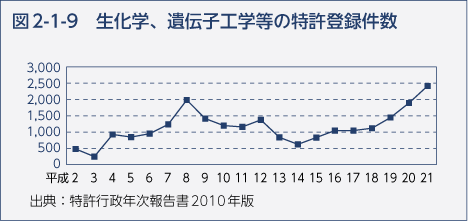
このようにバイオ・テクノロジーへの注目が増し、遺伝資源の重要性が高まる中、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS:Access to genetic resources and Benefit-Sharing)に関して、これまでも、遺伝資源の提供国と、遺伝資源を円滑に取得して人類の福利に貢献する研究開発等を促進すべきとする利用国との立場の違いを乗り越えるため、国際的な議論が進められてきました。COP10を契機として、遺伝資源の利用から生じた利益を公正かつ衡平に配分することによる、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献する仕組みが構築されつつあります。なお、これについては第3章において詳細に触れることとします。
最後に、我が国の豊かな自然が育んできた我が国の独自の文化について考えてみましょう。私たちの文化的な活動は、その生活している地域の環境や生活を反映し、また、他の文化との交流を通じてその根底にある知恵や技を伝えるとともに、人々が日々の暮らしを営む中で感じる精神的な豊かさや感動、生きる喜びなどを表現する手段となっています。私たちの暮らしに身近な自然は、このような文化の形成に大きな影響を与えていると考えられます。
近年、これまで身近であった自然物の中には、身近ではなくなりつつあるものがあると考えられます。気象庁が実施している生物季節観測の種目のうち、トノサマガエルやホタル等主に都市域で観測継続が困難となっている種目については、平成23年から観測継続が困難な地域での観測を行わないこととなりました。
また、過去には夜空に無数に見ることができた星が見にくくなっている現状もあります。我が国最古の歌集として重要な古典である万葉集には、当時の歌人や一般民衆と考えられる人々によって、様々な自然物が詠み込まれています。柿本人麻呂の「天の海に雲の波立ち月の舟星の林に漕ぎ隠る見ゆ」という和歌は、空を海に、雲を波に、月を舟にそれぞれ見立てた上で、その「月の舟」が「星の林」をこぎ渡るという独特の優雅な感性で詠まれた秀歌です。
ところが、現代の日本の夜空においては、この「星の林」のように星が無数にある状態を実感することは困難になっていると考えられます。環境省が実施している全国星空継続観察調査では、2009年8月に雲等の障害物のない状態で観察を実施できた318地点において、明るい一等星のデネブを含むはくちょう座が見えた地点は5割程度でした。この内訳を見ると、街灯が少ないと考えられる森林山間地は8割以上の地点で観察できたのに対し、商業地帯では1割程度しか観察できませんでした(図2-1-10)。数多くの星が見える夜空の景観は、都市域に住む人が失ってしまった豊かな自然の風景の一つであると考えることができます。
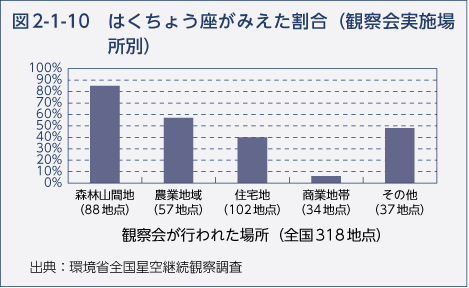
このように、近年、身近な自然が姿を消しつつある現状は、今後の文化の形成にどのような影響を与えるのでしょうか。これについて、万葉集に収録されている和歌に詠み込まれている動植物を例に見てみましょう。
万葉集には、現存する約4,500首の中に約50種類の野生動物及び約140種類の野生植物を確認することができます。これについて、動物の種類別に出現する歌を整理すると、野生の哺乳類については、シカやイノシシ、クジラ等が現れます。これらの哺乳類が歌い込まれている歌は、詩情を表すものとしての野生生物のとらえ方のみならず、食料資源等としての意識の一端もうかがい知ることができます。
また、ホトトギスやウグイスなどといった季節を告げるものとして野鳥が多数現れるだけではなく、鳥類ではキジやカモといった狩猟の対象種が出現するほか、当時の社会派歌人として知られる山上憶良の手による貧窮問答歌(ひんきゅうもんどうか)には、トラツグミのようにその細い鳴き声から連想したと思われる寂しさの象徴としての野鳥が歌に詠まれています。
一方、現代の日本人の和歌における自然認識において、これらの野生生物のとらえ方は大きく変化していると考えられます。例えば、一般からの公募に基づき秀歌を選定した「平成万葉集」(読売新聞社編平成21年)の和歌1,000首に出現する野生生物の種数は、動物で約20種類、植物で約30種類程度であり、万葉集に出現した種数の3割程度でした。また、現代の和歌にはペットや園芸種の割合が増えていることや、過去には歌われていたが現代では歌われなくなった種があるなどの傾向も見ることができます(表2-1-3)。
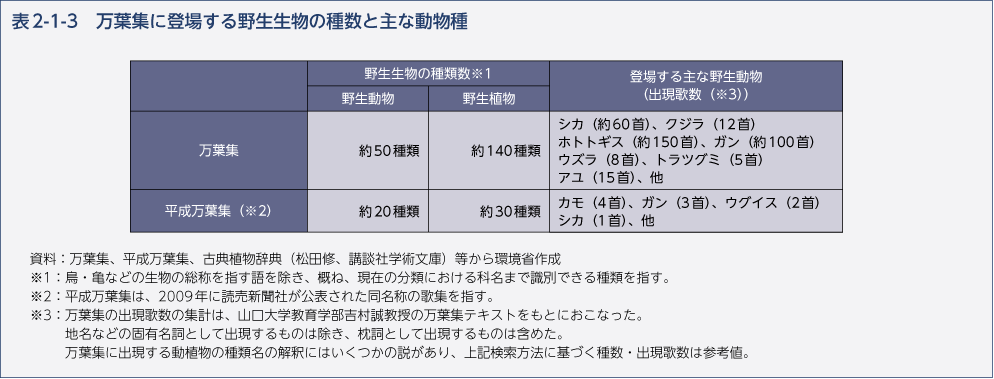
これらの変化については、文学としての和歌の表現技術や表現の対象に対する日本人の精神面での変化の他に、和歌を詠む背景となる環境が変化したことも大きな影響を与えていると考えられます。たとえば、空が明るくなって星が見えにくくなったこと、騒音等によりトラツグミ等の鳴き声を聞くことが難しくなること、又は歌に詠まれるほど身近であった種が地域的に絶滅のおそれのある種となったこと等が考えられます。
地域で継承されてきた伝統的な文化は、地域の人々の心のよりどころとなり、地域の連帯感をはぐくみ、共に生きる社会の基盤を形成する役割を担っています。貨幣的な価値に置き換えることができない価値を有する伝統的な文化を守り伝えるためにも、その文化の基盤となっている地域固有の生物多様性を含む自然環境の保全の取組を進めることが重要なのです。
現代版 蝸牛考(かぎゅうこう)
わが国には、カタツムリを指す非常に多様な地方の呼称があります。柳田国男の「蝸牛考」(昭和5年。蝸牛とはカタツムリの意)では、この語の呼称が、京都を中心とした同心円状に分布することを指摘しています。柳田国男は、このカタツムリを指す呼称が長い時間をかけて、近畿地方を中心に同心円の内側から外側にむかって順次伝播していったと推定しました。
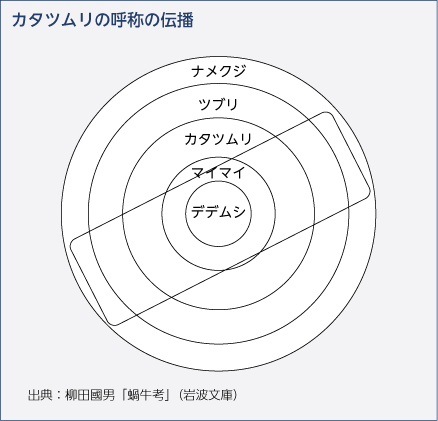
日本語地図解説(昭和47年、国立国語研究所)によれば、カタツムリに関する地方名は、ナメクジ、マイマイ、ツムリ(ツブロ等含む)、タマクラ、カタツムリ(カサツブリ等含む)、デンデンムシ、デエロ、ツノダシ、その他の孤立的な語形に分類され、これらの語の変化型を含めて全体として約470種もの呼び名が確認されています。まず「ナメクジ」や貝類全般を指す「ミナ」等が普及し、その後、カタツムリ、マイマイ等の呼称が用いられ、現在、近畿地方を中心に広く用いられているデンデンムシがもっとも新しい語形の一つであると考えられています。文部省唱歌の「かたつむり」の歌詞の冒頭部分は、カタツムリという生物を指す地方名である「でんでんむし」と「かたつむり」が並んで歌われているということになります。
ところで、このように私たちの生活や文化に深く根付いているカタツムリについて、最近、生物多様性の観点からも興味深い報告がいくつかなされています。
我が国のカタツムリなどの陸産貝類に関しては、732種・亜種が確認されており、そのうちの陸産貝類は大半が日本固有種です。日本固有種が多く、生物地理学的に特異な貝類相が発達している理由としては、複雑な地形と多くの島嶼群の存在によって地理的な隔離がもたらされたことなどが考えられています。小笠原諸島などの海洋群島では、これらの陸産貝類はさらなる種分化を経て著しい多様性を見せ、島の面積に比例して種数も多くなります。
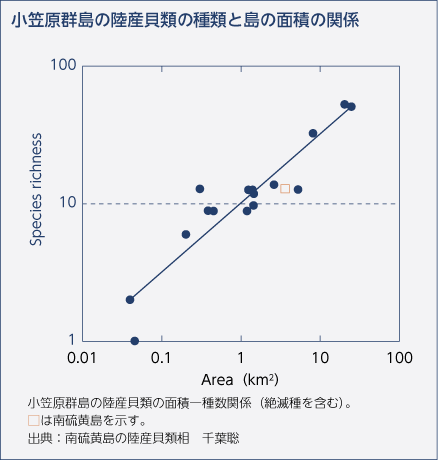
こうしたカタツムリの多様性は、カタツムリを主食とする生物にも影響を与えます。セダカヘビ属のヘビの仲間は、カタツムリを主食とし、沖縄県の八重山諸島から中国南部からインド、東南アジアにかけて広く分布しています。もともとカタツムリは右巻きの種が多いことから、このセダカヘビは右巻きの貝を食べるためにアゴの形状等を右巻きに適した形に進化させており、左巻きのカタツムリを与えても上手に食べることができません。このことが左巻きのカタツムリに有利に働き、セダカヘビが生息している地域では、左巻きのカタツムリを多く観察することができます。

カタツムリを含む陸産貝類は腹足によって地面を這うという移動手段の制約もあり、その生息域である森林の伐採や大規模な土地造成などの人間活動が起因して、環境省のレッドリストでは、約3割が絶滅危惧種として選定されています。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |