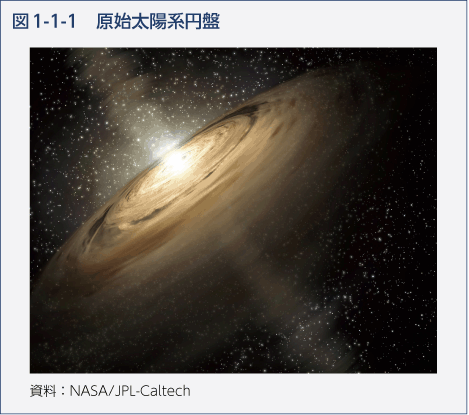
宇宙のちりやガスから誕生した原始の太陽は、やがてその中心で水素からヘリウムが合成される核融合反応を起こし、光を放出するようになったとされます。一方で、太陽を取り巻いていた塵の一部は、集合しながら微惑星をつくり、それらが合体・成長して原始の地球を含む惑星へと進化していきました。(図1-1-1)。
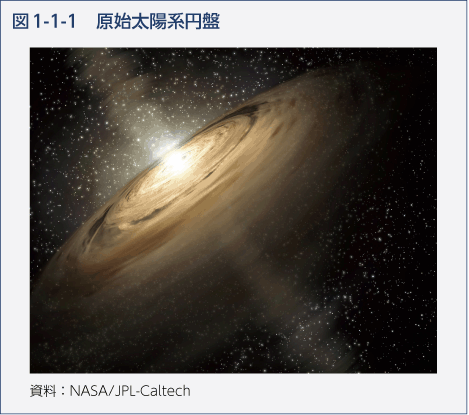
原始の地球が誕生する過程で地球に衝突した無数の小惑星や隕石には、様々な原子が含まれており、これに起源とする鉱物資源が、現在の私たちの社会経済活動を支えています。
誕生したばかりの原始の地球は、小惑星や隕石が衝突した際のエネルギーによって地表が溶け、高熱のマグマの海と呼ばれる状態であったと考えられています。この溶けたマグマが冷え固まり、岩石や鉱物で構成された大地と原始の海が形成されていく過程で、もともと微惑星に含まれていた重い鉄などの金属は地球の中心に移動しました。その後、火山活動や水を介した濃縮作用などにより、現在の地球の鉱床が形成されました(図1-1-2)。白金などのレアメタルは、45億年前、その多くが地球の核に移動してしまったために、現在は、地殻での含有率が低くなっています。
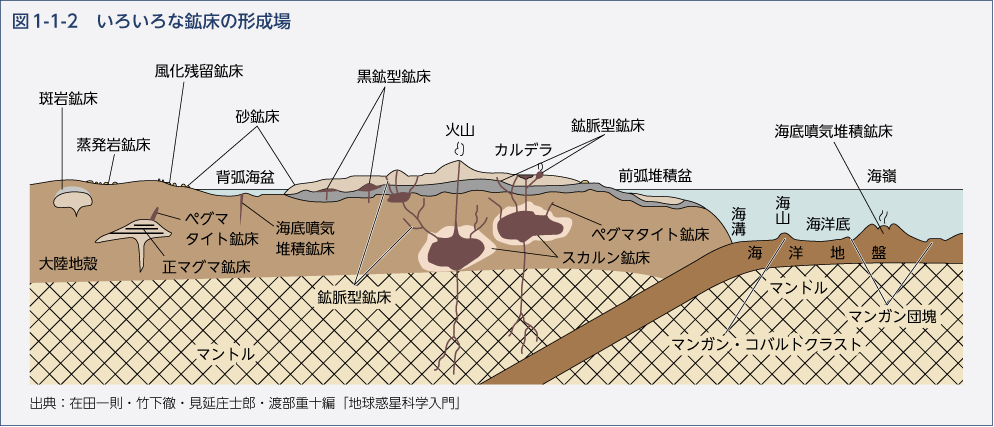
近年、注目されているレアアース(希土類元素)は、火山活動によるマグマだまりで濃縮し鉱床になったものと、雨などによる濃縮作用によって粘土の粒子に吸着されてできた鉱床があります。前者はウランなどの放射性元素と混じっている場合もあって取り扱いが難しく、また後者については、その取り扱いは比較的容易だが中国などごく限られた地域にしかないなど、採掘条件が整いにくいことから希少性が高くなります。
原始の海で有機物から原始生命体ができたのは約40億年前と考えられています。光合成を行うラン藻類などが39億年前頃に出現したことで、原始の地球の大気に酸素が増え始めました。その酸素が地球を取り巻くオゾン層を形成し、太陽からの紫外線を防ぎました。また、現在と同様の大気構成となって安定した気候が維持されることで、陸上に生命が進出できる環境が整いました。その後、植物が陸上に進出して太古の森を創り、動物もその環境の中に上陸することで、陸上でも複雑な生態系が形成され始めました。
これらの動植物が生み出した有機物から肥沃な土壌が生まれることになります。また、こうした有機物の一部は、地殻変動などで地中深くに埋まり、強力な圧力と膨大な熱が加わることで、長い歳月を経て石油や石炭など、現在の私たちの人間活動を支える化石燃料になったとされています。
現在、私たちが地球から得ている様々な資源は、地球が誕生してから長い年月をかけて作り上げてきた限りあるものであり、人間の時間的なスケールでは再生不可能な地下資源や持続可能な利用をしなければ永久に損失してしまう生物由来の資源等で成り立っています。
小惑星イトカワと地球
私たちの太陽系は、太陽および8つの惑星とその衛星、そして多くの小惑星や彗星などの小天体で構成されています。小惑星等の小天体は軌道がわかっているものだけでも10万個程度あり、主に火星と木星の軌道の間に存在します。
人類がこれまで地球外の天体に着陸して岩石や細かい粒子を直接採取したことのある天体は地球の衛星である月だけでした。しかし、太陽系の惑星や月のような大きな天体はその誕生から現在までの間に大きく変成してしまっているため、太陽系の初期のころの物質の組成について知ることができません。惑星が誕生するころの物質の組成の記録を比較的よくとどめている小惑星からサンプルを持ち帰る技術(サンプル・リターン)が確立されれば、惑星や小惑星を作るもとになった材料がどのようなものであったかについての手がかりを得ることができます。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)では、2003年(平成15年)5月に打ち上げた小惑星探査機「はやぶさ(MUSES-C)」ミッションにおいて、小惑星「イトカワ」を探査しました。
「はやぶさ」が詳細に観測したところ、このイトカワは長径540m平均直径320mほどの小さな天体で、海に浮かんだラッコのような形をしており、その表面は、岩石が露出した部分と砂礫が降り積もった部分で構成されていることが分かりました。

この「はやぶさ」ミッションでは、電気推進エンジンの稼働や、自立航行でのイトカワとのランデブー、イトカワの科学的観測等、様々な成果を得ることができましたが、その中でも最大の成果の一つは、イトカワの表面の粒子を地球に持ち帰ることに成功した点でした。
2010年(平成22年)6月に地球に帰還したカプセルに回収されていた微粒子の中で、電子顕微鏡による観察で岩石質と同定した微粒子について、粒子表面・内部構造、元素組成、高分子有機物質の有無、鉱物の種類と存在度等の物理・化学的な特性の解析が行われています。この解析結果によって、地球の誕生に関する極めて貴重な科学的知見が得られることが期待されます。
なお、2005年(平成17年)9月に「はやぶさ」がイトカワに到着したとき、イトカワは地球から約3億2,000万km離れた位置にありました。この「はやぶさ(1m×1.6m×2.0m)」の宇宙空間の旅程をたとえるならば、大きさ約0.02mmの砂粒(「はやぶさ」)を、北海道択捉島の日本北端地点から発射し、約3,300km離れた沖縄県与那国島の日本西端地点に置いた長径約5mmの米粒(イトカワ)に命中させ、再び日本北端まで戻ってくる精度で仕事をしたことになります。
このように、地球誕生のシナリオの一端を解明し、また、それによって私たちの暮らす地球がいかにかけがえのない存在であるかを知るために、高い水準にある我が国の科学技術が世界に大きな貢献をしています。
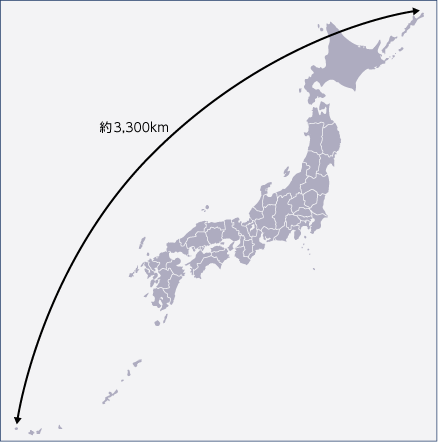
地球には、化石燃料、鉱物、土地等の有限な資源、水や大気など地球上を循環している物質及び生物が生み出すバイオマス等の再生可能な資源、さらに、太陽光や地球内部の地熱など、地球の外部から吸収したり地球自身が有するエネルギー資源が存在しています。私たちが望む豊かな生活はこの地球の資源を基盤としています。また、社会経済活動においては、資源・エネルギー源を採取し、様々に活用し、最終的には廃棄物や温室効果ガス等として地球環境へ排出するという営みが繰り返されています。
このような人間活動の中には、環境に対して負荷をほとんど与えないものもあれば、汚染物質等の排出のように環境に著しい負荷を与えるものもあります。しかし、今日、私たちが日々営む活動の過程で、多くの資源を使って大量生産を行い、生産した製品等を大量に流通させ、消費し、不用物を大量に排出するという側面が大きくなり、様々な環境負荷を与えるようになっています(図1-1-3)。このことが、私たち自身の生活のみならず、私たちの生活を支える生物多様性にも影響を及ぼしているという現状を忘れてはなりません。
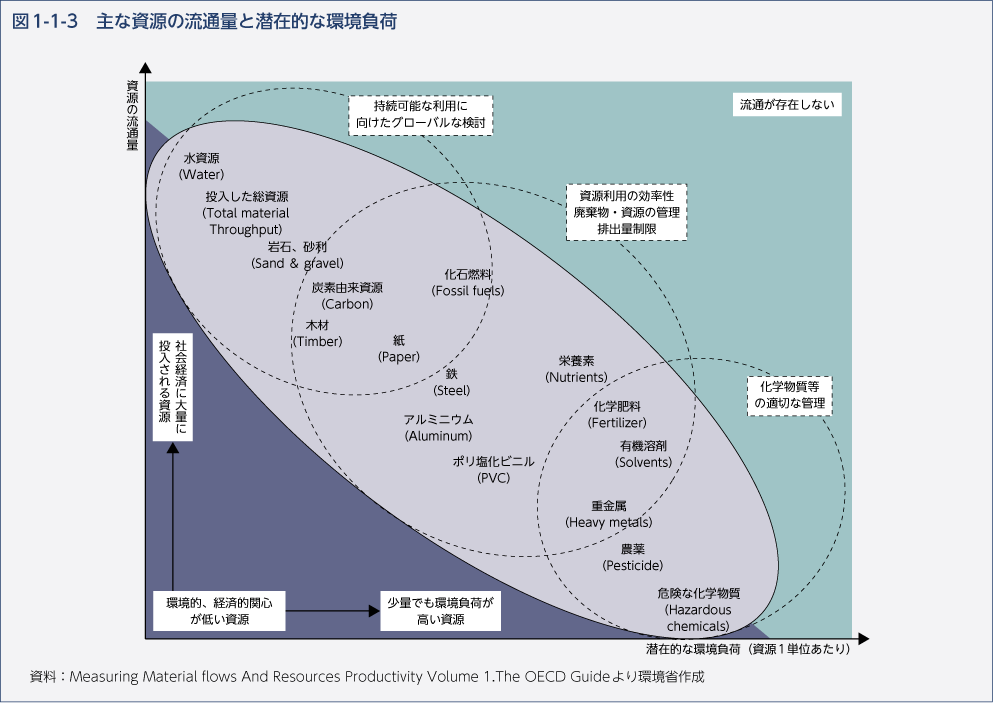
私たちが豊かな生活を営むためには、資源・エネルギーの有限性や一度失われると二度と取り返すことのできない生物多様性そのものの価値を知った上で、地球環境の持続可能性をどう確保していくのかが問題になります。
以下では、持続可能性や豊かさに関する国際的な認識の進展や、その評価に向けた世界の取組を概観するとともに、世界の持続可能性及び我が国の持続可能性と豊かさの現状について、特に環境の側面に焦点をあてて考察をしたいと思います。
1960年代から1970年代にかけて、飛躍的な経済成長を遂げた先進諸国では地域的な公害が大きな社会問題となる一方で、開発途上国では貧困からの脱却が急務でした。こうした中、1972年(昭和47年)にストックホルムで、国連人間環境会議が開催され、ストックホルム宣言によって環境保全を進めていくための合意と行動の枠組みが形成されました。しかし、先進諸国と開発途上国との間での公害をめぐる認識の対立は厳しく、その後も、先進国においては、大量生産・大量消費・大量廃棄型のライフスタイルと経済活動の拡大、途上国においては、貧困から脱却するための開発が優先的に進められ、持続可能とはいえない開発が進みました。
しかしながら、この頃、「成長の限界」(ローマクラブ報告)、「西暦2000年の地球」(アメリカ合衆国政府特別調査報告)を始め、人類の未来について深刻な予測が相次いで発表されると、地球上の資源の有限性や環境面での制約が明らかにされ、世界の人々に大きな衝撃を与えました。
こうした中、「持続可能な開発」という用語を一般的に定着させるきっかけとなったのは、1987年(昭和62年)、我が国の提唱に基づき国連に設置された環境と開発に関する世界委員会の報告「我ら共有の未来(Our Common Future)」でした。
これらの動きを踏まえ、1992年(平成4年)6月にブラジルのリオデジャネイロで開催された「環境と開発に関する国連会議(地球サミット)」において、「持続可能な開発」という概念が全世界の行動原則へと具体化されました。この地球サミットでは、持続可能な開発を実現するための行動原則である「環境と開発に関するリオ宣言」とその具体的な行動計画である「アジェンダ21」等が採択されました。その際、各国が協力して地球温暖化対策に取り組むための気候変動枠組条約及び生物多様性の保全とその持続可能な利用をするための生物多様性条約がコンセンサスにより採択されました。こうした動きを背景として、「持続可能な開発」という概念が一般的に定着することとなりました。
その後、地球温暖化に対する国際的な議論が進み、1997年(平成9年)には、京都で開催された気候変動枠組条約第3回締約国会議において京都議定書が採択されました。2008年(平成20年)には、G8北海道洞爺湖サミットにおいて、先進国の首脳が地球温暖化について2050年までに世界の温室効果ガス排出量を少なくとも50%削減することが示されました。
一方、生物多様性の保全と持続可能な利用に関する国際的な動きも活発となり、2002年(平成14年)には、南アフリカのヨハネスブルグで開催されたヨハネスブルグ・サミットにおいて、「持続可能な開発に関するヨハネスブルグ宣言」が政治宣言されるとともに、生物多様性条約第6回締約国会議(COP6)がオランダのハーグで開催され、生物多様性の損失速度を2010年までに減少させるという2010年目標が決定されました。この目標の達成年にあたる2010年(平成22年)10月、愛知県名古屋市において、生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)が開催され、生物多様性の保全に関する新たな世界目標となる「愛知目標」や遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する「名古屋議定書」が採択されました。
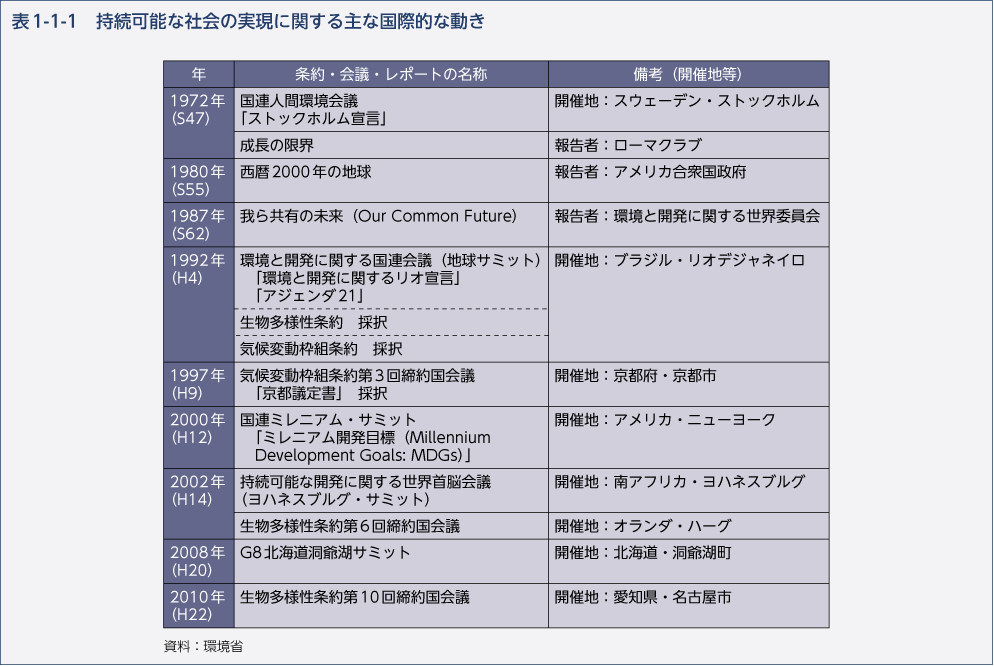
持続可能性に関する懸念が高まると、真の豊かさや発展とは何かを改めて考えることが重要となります。持続可能な開発については様々な考え方がありますが、前述の「我ら共有の未来」で示された「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことがないような形で、現在の世代のニーズも満足させるような開発」との定義が広く受け入れられている考え方の一つです。この考え方は、従来の経済活動の規模による発展の評価手法の見直しを迫るものであり、現在世代だけではなく将来世代の豊かさを評価することや、経済活動の規模だけではなく真の豊かさを評価することが必要ではないかという問題意識を広める契機となりました。
こうして、先に見たような持続可能な社会の実現に向けた取組に併せて、経済協力開発機構(OECD)や国連などの国際機関等において、持続可能性や豊かさを評価するための指標の開発に関する議論や提言が進められてきており、国際的な潮流となっています(表1-1-2)。
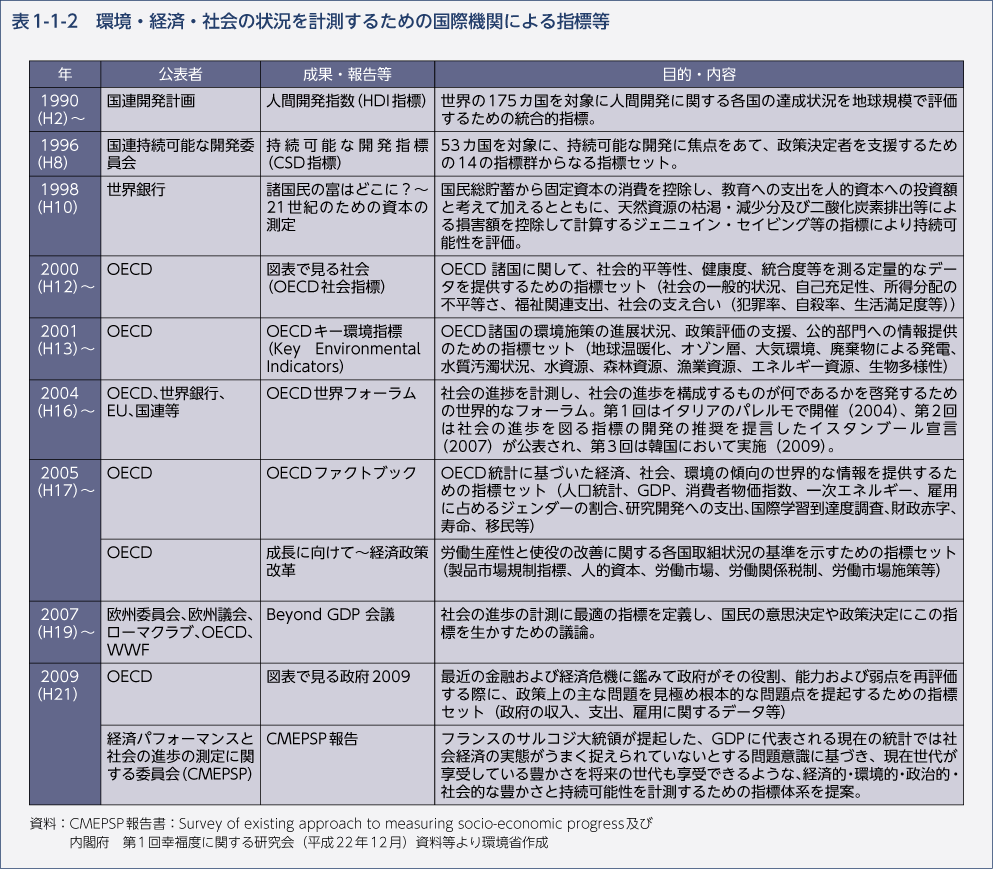
国連開発計画(UNDP)では、1990年(平成2年)から、GDP、平均寿命、識字率、教育水準に関する指標の各値に重み付けをして計算した統合的な指標として、人間開発指数(HDI:Human Development Index)を用いた人間の総合的な開発の程度を計測・評価しています。
1998年(平成10年)に世界銀行によって開発された指標「ジェニュイン・セイビング(Genuine Savings)」は、国民総貯蓄から固定資本の消費を控除し、教育への支出を人的資本への投資額と考えて加えるとともに、天然資源の枯渇・減少分及び二酸化炭素排出等による損害額を控除して計算されます。例えば、ジェニュイン・セイビングがマイナスとなることは、総体として富の減少を示しており、現在の消費水準を持続することはできないことを意味します。
OECDでは、「図表で見る社会~OECD社会指標」「OECDキー環境指標」「成長に向けて~経済政策改革」等、環境・経済・社会に関する様々な指標を用いた国際的な社会の進歩の状況の評価を実施してきました。これらの指標セットは、他の国際機関や各国等が指標を開発する際の基礎として広く世界に浸透することとなりました。
また、OECDが中心となって、世界銀行、EU、国際連合等が協力して実施している世界フォーラムでは、社会の進捗を計測し、社会の進歩を構成するものが何であるかを啓発するための取組が行われており、第2回の開催地であるトルコ・イスタンブールにおいては、社会の進歩を図るための指標開発の推奨等を提言した「イスタンブール宣言(2007)」が公表されています。
このような流れの中、これまで、生産・消費などの人間の経済活動がどの程度の規模で行われているのかを計測するために用いられてきたGDPに関する見直しの動きを見ることができます。GDPは、その国の所得の程度を示すものではあっても、可処分所得がGDPと連動しないなど各個人や家計の所得・消費のあり方を十分に示すことができないこと、人間の福利を計るために必要と考えられるサービス・財の質などの要素を含んでいないこと、家事などの家計労働や余暇(レジャー)活動のように市場化されていない部分をとらえることが困難であること、短期的な経済活動に焦点を当てており自然資源や人的資本等の長期的な資本の蓄積に重点が置かれていないことなどにより、日常生活において実感される豊かさや国民の満足度とは異なる動きを示すこともあります。
欧州委員会、欧州議会、ローマクラブ、OECD、世界自然保護基金(WWF)から構成される「Beyond GDP会議」においては、社会の進歩の計測に最適な指標を定義し、国民の意思決定や政策決定にこの指標を生かすための議論が行われています。2009年には会議の成果が公表され、社会の進歩を測定する指標を改良するための5つの主要な行動([1]環境や社会に関する指標を用いたGDPの補完、[2]政策意思決定のための即時的な情報提供、[3]所得分配や社会の不平等に関するより正確な報告、[4]ヨーロッパにおける持続可能な開発指標に基づく持続可能な発展に関する点数表の開発、[5]環境と社会問題を勘定に含めた国民経済計算の展開)が示されています。
また、フランスのサルコジ大統領が提起した、GDPに代表される現在の統計では社会経済の実態がうまく捉えられていないとする問題意識に基づき、経済パフォーマンスと社会の進歩の測定に関する委員会(Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress:CMEPSP)が立ち上げられました。同委員会による報告では、豊かさや持続可能性を一つの指標で測定することの難しさ、複雑な指標群によって豊かさや持続可能性の本質を見失う恐れがあること、持続可能性についての概念が明確でないことなど、各指標についての様々な課題を認識した上で、環境的・経済的・社会的な側面から、豊かさ(Well-being又はQuality of Life)と持続可能性を測定するための指標体系の提案をしています。
この報告では、持続可能性を、将来世代への豊かさの確保であるととらえたアプローチが示されています。
その持続可能性を測定する主な手法として、[1]合成指標の開発、[2]様々な指標を組み合わせた指標セット、[3]GDPが計測していない要素などを修正した環境・経済統合勘定(SEEA)等、[4]調整純貯蓄(Adjusted Net Savings;ANS)又はジェニュイン・セイビングと呼ばれる、国民総貯蓄から固定資本の消費を控除し、教育への支出を加え、天然資源の枯渇・減少分及び二酸化炭素排出等による損害額を控除する手法、[5]人間の活動によって生物圏の再生産能力がどの程度消費されたかを測定する環境フットプリントと呼ばれる手法等があげられています。同報告書においては、これらの指標を組み合わせた指標セットを用いて、特にストックに注目した測定を進めることが重要であるとする提案がなされています。
また、豊かさ(Quality of Life:QoL)を評価する手法として3つのアプローチが示されています。第1に、個々人の生活への満足度や感情について質問票に回答すること等によって調査して分析する主観的幸福のアプローチです。第2は、各人の人生について、その人が行う様々な行為や存在そのもの(機能:functioning)と、その人が有する「機能」に関する自由な選択(選択の自由度:capability)の組み合わせであるととらえるケイパビリティ・アプローチです。第3は、厚生経済学等の理論に基づく、所得分配の公平性等、個人の選好を加味した非貨幣的な価値による豊かさを評価する経済的なアプローチです。
これらの手法は異なるアプローチではあるものの、互いに相似している点もあります。同報告においては、豊かさ(QoL)の測定にあっては、主観的な要素(個人の置かれている状況や実際に感じている感情)の測定と客観的な要素の測定(健康、教育、余暇などの個人的な活動、ガバナンスの状況、社会的なつながり、環境の状況、個人の安全・安心等)に焦点をあてるのが重要であるとの提言がなされています。
さらに、これらの成果を踏まえ、フランス持続可能な開発省では、2010-2013持続可能な開発9つの戦略と新指数を公表しています(表1-1-3)。
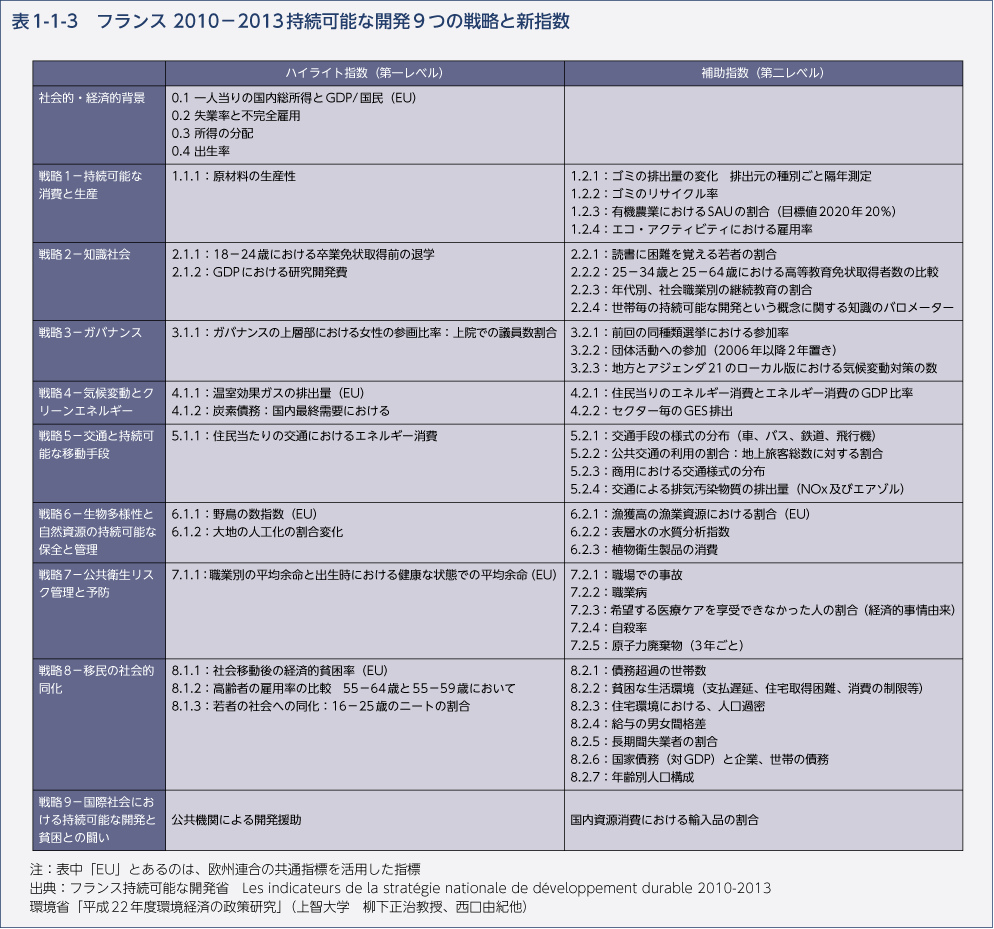
以上に見たような、GDPの有用性とその限界、豊かさ(QoL)の測定及び持続可能な開発と環境の測定に関する議論は、現在世代が享受している豊かさを将来世代も享受できるような豊かで持続可能な社会の実現のために重要な評価手段の構築を目指すものであり、今後も、我が国を含めた国際的な議論が進展していくものと考えられます。
次の節では、地球と我が国の持続可能性と豊かさについて、主に環境の側面から概観してみましょう。
スモール・イズ・ビューティフル
人間は、小さい。だからこそ、小さいことは素晴らしいのである。
エルンスト・F・シューマッハー「スモール・イズ・ビューティフル」
シューマッハーは、1973年に現代社会において、どのようにして人間性を確保、拡幅するのか、という問題意識に基づき「スモール・イズ・ビューティフル」を執筆・出版しています。折しもこの時期、先進諸国を中心に公害が社会問題となっており、ストックホルムでは国連人間環境会議が開催され、ストックホルム宣言(1972年)のもと、地球規模での持続可能な社会の枠組みの構築に向けて、世界が歩みを進めようとしていた時期でした。しかし、現実の社会経済は持続可能とはいえない大量生産・大量消費・大量廃棄が続いており、本書においては、こうした危機の根源は、有限な自然という資本を食いつぶすほどのどん欲な物質至上主義と巨大技術信仰の追求にあるとしています。
また、このような現代の生産様式が、もともと人間性の向上にも資するような仕事を細切れにして、だれもがあまりやりがいを感じない、むしろ人間性を阻害する仕事にしてしまっている、と説いています。そしてこれを世界が巻き込まれている第一の危機としました。第二の危機は、崩壊の兆候を見せる人間の生活を支えている自然環境の危機であり、第三の危機として、眼前に迫る資源枯渇を挙げています。
そこで、シューマッハーは、物質的なものに第一義的な地位を与えるのではなく、本来の従属的な地位を与えるような生産様式を編み出すべき、としています。これは人間の身の丈にあった技術、人間の顔を持った技術が重要だとする「中間技術」の開発の必要性の主張につながっています。この考え方は、「人間は、小さい。だからこそ、小さいことは素晴らしいのである」という言葉に集約され、この著作の表題となりました。
シューマッハーは本書の中で「富や教育や研究開発といった資源をさらに動員して、公害と戦い、野生の動植物を保護し、新しいエネルギー資源を発見し、平和共存に関して今より実効のある協定を結びさえすれば、現代の破壊的な力を手なづけることができると信じている限りは、われわれは真理から逃げている」と手厳しい指摘もしています。
そのために必要な「道徳的な選択」について、彼は、知恵(prudentia)、正義(justitia)、勇気(fortitudo)、節制(temperantia)が重要であるとしています。また、偏見のない客観性に基づく十全な知恵は、現実を静かに黙想し、その間、自己中心的な関心を一時的でも抑えるような態度をとることによって、初めてもつことができるものとしています。この知恵をもって、正義、勇気、節制を身につけることができるとしています。
そして、文明の存続に、これらは決して欠くことのできない徳目であるとしたのです。
| 前ページ | 目次 | 次ページ |