「つなげよう、支えよう森里川海」ミニフォーラム in 宝塚
WEB開催レポート
- 開催日時
- 平成28年1月30日(土) 13:30~16:30
- 開催場所
- 宝塚市立西公民館 セミナー室
(宝塚市小林2丁目7番30号) - 参加者数
- 78名
- 主催・共催
- 主催:環境省、共催:宝塚市、協力:兵庫県阪神北県民局、後援:北摂里山博物館運営協議会
- プログラム
「つなげよう、支えよう森里川海」ミニフォーラムin宝塚が開催され、宝塚市の地域住民の方々、環境に関わる活動を行っている方等に、ご参加いただきました。
KISSFMの中野耕史氏の司会で、環境省による主催者挨拶の後、宝塚市中川智子市長から御挨拶が行われ、『宝塚は自然と町がうまく共存している稀有な地域であり、まち山保全の活動が長年多く行われ、子供たちと一緒に取り組むことで次世代にもつなげる努力をしている。自然は人々により生かされており、人がよりそって守っている。この取組も広くアピールして、今後につなげていきたい』と挨拶。
その後「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの紹介、京都大学農学研究科教授 栗山浩一氏 より、『自然の恵みはタダなのか?~森里川海の経済価値を考える~』についての特別講演をいただき、その後① 宝塚市自然保護協会会長 足立勲氏『感じることから始めよう 生物多様性の保全』、② 北雲雀きずきの森きずな会代表 藤井明氏『まち山の自然と生物多様性を守り、引き継ぐ』、③ 丸山湿原群保全の会代表 岸恭子氏『過去に学び未来に継ぐ丸山湿原』、④ 武庫川流域圏ネットワーク代表 山本義和氏『安全で魅力的な武庫川を求めて』4つの地域の取組事例発表がありました。
- (1)主催挨拶
- 近畿地方環境事務所長 秀田智彦

- (2)共催挨拶
- 宝塚市 中川智子 市長

- (3)「つなげよう、支えよう森里川海」プロジェクトの紹介
- 環境省 自然環境局 野生生物課 課長補佐 中島慶次

- (4)特別講演
- 京都大学農学研究科教授 栗山浩一氏
「自然の恵みはタダなのか?~森里川海の経済価値を考える~」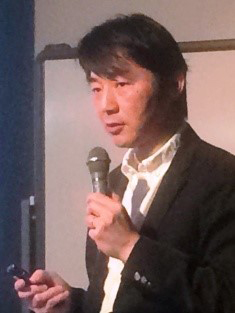
- (5)事例紹介
-
① 宝塚市自然保護協会会長 足立勲氏
「感じることから始めよう 生物多様性の保全」② 北雲雀きずきの森きずな会 代表 藤井明氏
「まち山の自然と生物多様性を守り、引き継ぐ」③ 丸山湿原群保全の会代表 岸恭子氏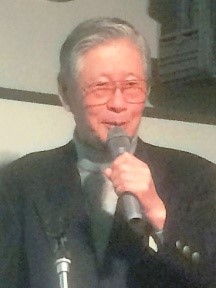
「過去に学び未来に継ぐ丸山湿原」④ 武庫川流域圏ネットワーク代表 山本義和氏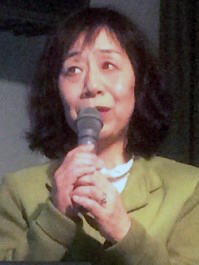
「安全で魅力的な武庫川を求めて」
- (6)パネルディスカッション、メッセージ記入
-
パネルディスカッションでは、栗山先生の司会で、事例発表の登壇者との意見交換を、会場からの質問にも答える形で行いました。積極的な発言で時間も足りなくなるくらいでいたが、「昆虫少年をもっと」、「ボランティアの高齢化問題、次世代の参加を」、「現場にきて、みて、参加してほしい」、「事業にまず参加すること」などの発表者の意見をうけ、栗山先生から、「市民が積極的に取り組んでいる地域ではあるが、サポートする仕組みを国が作っていかないといけない。この取組を参考に、日本全体で森里川海をつなげるようにしていかねば」、とまとめる形で終了しました。
参加していただいた方にも、今日の講演を聞いて、また森里川海への想いを、えんんたくんに書いていただきました。会場から集まった意見や質問の一部を紹介します。
●栗山氏の講演に対して
「森里川海の経済価値を高めるには、いかに多くの人に自然環境の必要性を認識してもらえるかにかかっていると思う。」「市民の協力が大切だと思った。」といった意見のほか、事例として紹介のあった神奈川県の取組について、「大変興味深かった。」「お金の使い方を決める方法をもっと詳しく知りたい。」などの感想もみられました。●足立氏の事例発表に対して
「『まずは触れて感じるところから』『価値観の押しつけをしない』といった理念、大切だと思った。」「会の取組を広げていくのに大切なことは?」といった意見、質問がありました。●藤井氏の事例発表に対して
「観察会の多さから困ったことは?」「ボランティアの活動資金、特に不法投棄のゴミを片付ける費用はどのようにしたのか?」といった質問や、「まち山という言葉から多くのことをイメージし、考えることが出来ると思う。」といった感想もありました。●岸氏の事例発表に対して
「作業人員の確保はどのようにしているか?」「活動や団体のことを色々な人に知ってもらうにはどうすれば?」といった質問や、「湿原保全のためにも、子どもたちの原風景になるような体験、誘導が大切」といった意見もありました。●山本氏の事例発表に対して
「外来種駆除における地域との連携構築に感銘を受けた。」「いかに経済的価値を見出し、雇用を生み出すかが課題。またその広報、アピールが大切」といった意見、感想がありました。
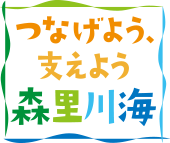

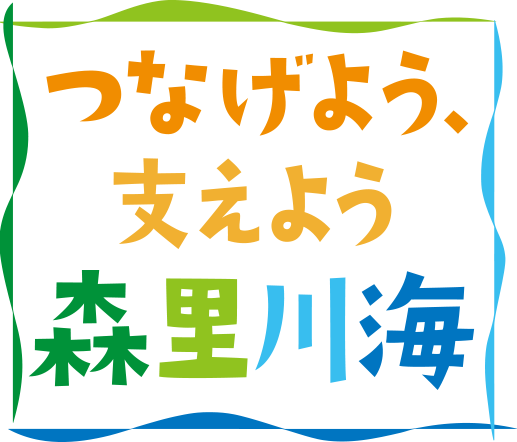


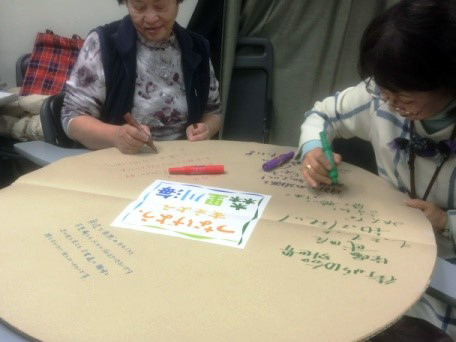

 森里川海プロジェクトFacebookは
森里川海プロジェクトFacebookは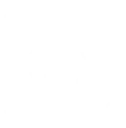 森里川海プロジェクトInstagramは
森里川海プロジェクトInstagramは