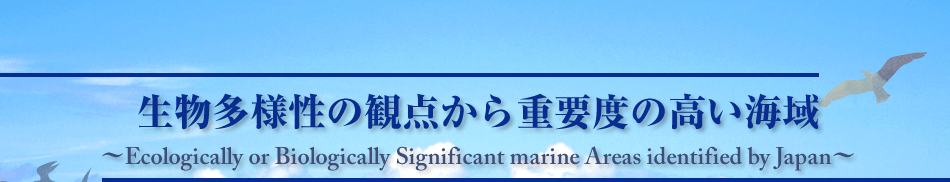環境省ホーム > 政策分野・行政活動 > 政策分野一覧 > 自然環境・生物多様性 > 生物多様性の観点から重要度の高い海域 > 沖合表層域 > 419 オホーツク海海域
沖合表層域 419 オホーツク海海域
【注記】沖合表層域は物理的に流動する(海流の流路や季節により海域特性が変動する、またこれらにともない生物の産卵場、分布域なども変動する)特色があることから、重要海域の区域を空間的に固定して抽出することは困難である。また、利用できるデータや手法も現段階では非常に限られている。これらの課題はあるが、沖合表層図は、平成23-25年度時点で活用出来るデータ、解析手法を用いて機械的に行った結果として、沖合表層域の重要な海域の確率論的な分布を示すものとして作成された。しかし、生態学的特徴からは連続していると考えられるような場所が、機械的な解析により分断されているなど問題もあるので、今後の見直しまでにさらなる調査を行ってデータの充実を図り、また解析手法の見直しも行い、精度を上げていく必要がある。
基本情報  出典
出典
| 面積(平方キロメートル) | 18085 |
|---|
※抽出基準ごとに表示されている数字は各重要海域の解析スコアの最大値を表示している。
選定理由  抽出基準
抽出基準
基準5、8が高く、MARXANにより選定されたため
特徴  出典
出典
当該海域は、世界で最も低い緯度で季節海氷が生成する海域で、わが国唯一の氷海域である。サハリン東岸に沿ってカラフト寒流が南下している。対馬暖流由来の宗谷暖流は宗谷海峡から流入し、北海道オホーツク海沿岸に沿って知床半島周辺まで流れている。冬のオホーツク海北部で季節海氷が形成される際に、低温、高塩分で栄養塩類が豊富な海水が沈降し、オホーツク海中冷水を形成する。オホーツク海中冷水は、オホーツク海から北西北太平洋の中層域に栄養塩に富んだ水塊として拡がり、この海域の春の植物プランクトンの大増殖を始めとして、豊かな生物生産を支えている。季節海氷の底面には付着珪藻類(アイスアルジー)が繁茂して沈降し、底生生物群集(主にろ過食者)の餌となっている。親潮海域同様に、オキアミ類、カイアシ類などの大型動物プランクトンが豊富で、これらを餌とするタラ類、カレイ類、カニ類など水産有用種の他、海鳥類、鰭脚類、鯨類の索餌海域にもなっている。冬-春は極域の氷縁生態系に似た寒冷性海洋生物(タラ類などの底魚類、ウミワシ類、氷上繁殖型アザラシ類)が優占するが、夏-秋には暖流系表層回遊魚も来遊する。