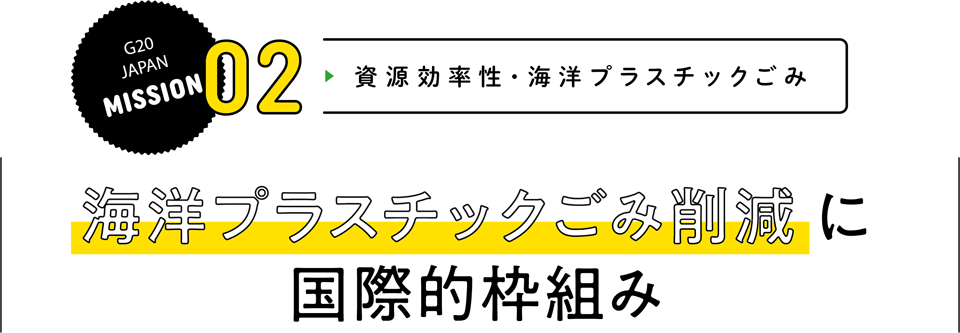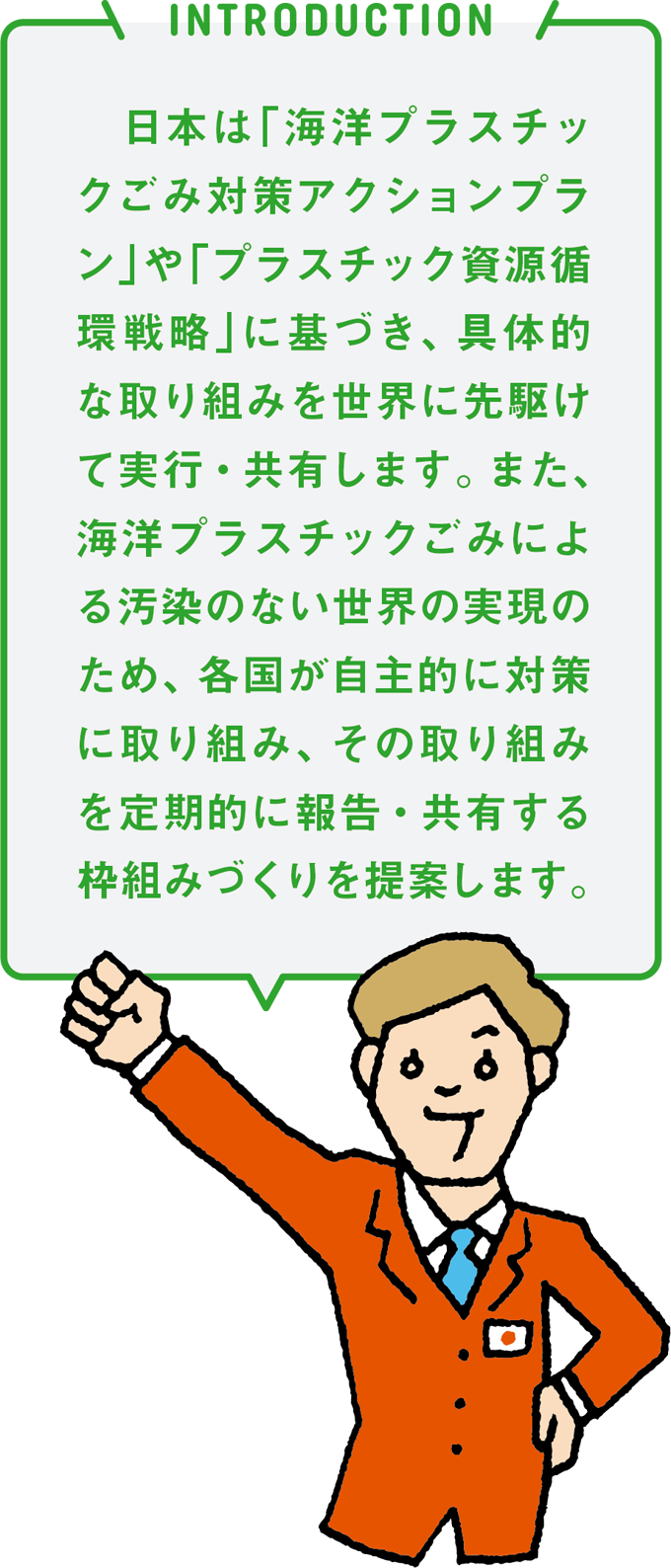
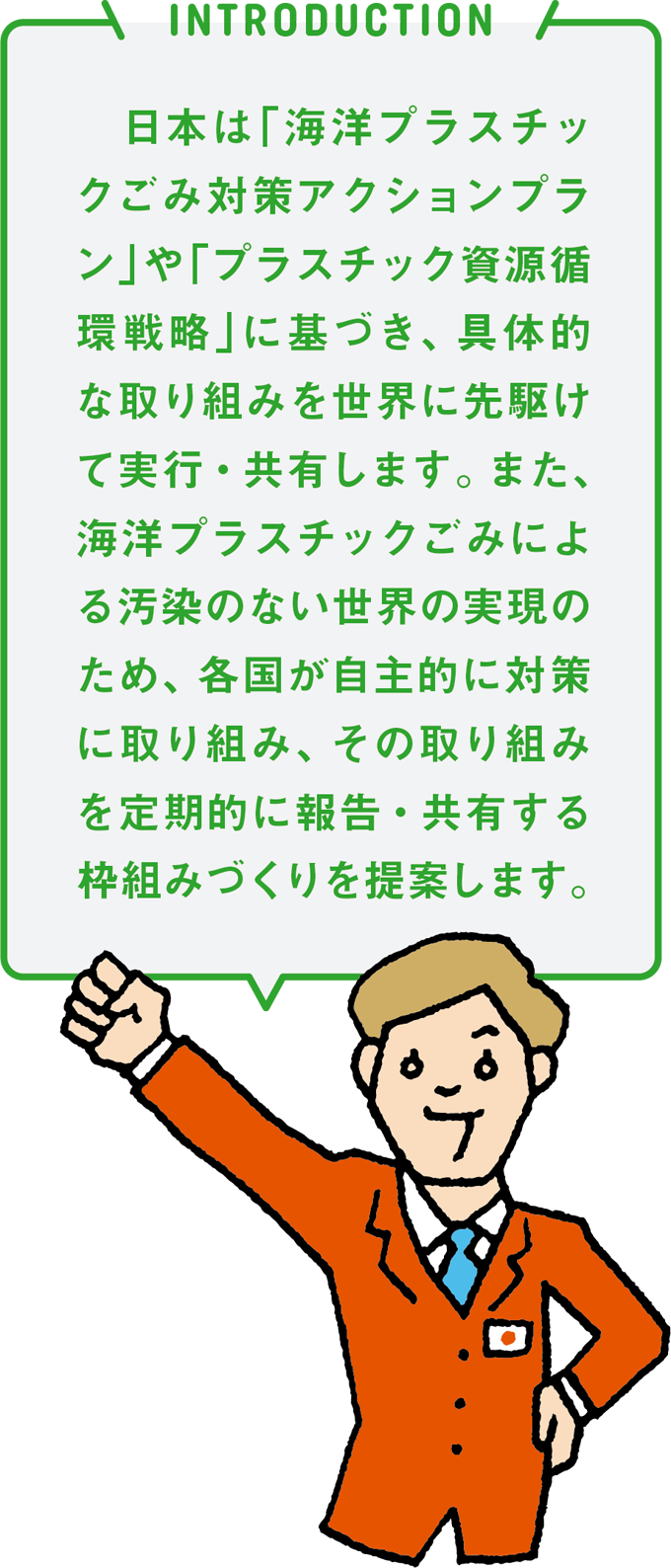
今回の会合では、日本が主導し、各国の海洋プラスチックごみ対策を共有する「G20海洋プラスチックごみ対策実施枠組」に合意。海洋ごみについては、2017年のG20ハンブルクサミットで採択された「G20海洋ごみ行動計画」があるが、各国の取り組みや成果を把握する仕組みは設けられていなかったため、海洋プラスチックごみの分野で実効性のある国際的な枠組みができたのは、今回の合意が初めてとなった。
この枠組みは、新興国や途上国も含めたG20各国が自主的に海洋プラスチックごみ対策を計画・実行した上で、事例や情報を共有し、さらに対策をアップデートしていこうとするもの。具体的には、プラスチックごみの海洋流出を防ぐための廃棄物管理、回収など包括的なライフサイクルアプローチの推進、海洋ごみの現状と影響を測定するための科学的基盤の強化などを行っていく。
今年10月には、日本で開催する「G20資源効率性対話」の場において、枠組みの合意を受けた第1回目の情報共有を行う。各国が対策の現状について報告し、その後の取り組みにつなげていく。

海洋生分解性プラスチックの開発
微生物の働きで水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチック。日本で使われているものの多くが土壌などでの分解に適した素材で、海の微生物が分解しやすい素材はわずかです。国内では企業などを中心に、海洋流出しても影響の少ない海洋生分解性プラスチックの開発が進められており、環境省もこうした技術開発を支援していきます。

日本独自の技術を用いた植物由来の海洋生分解性プラスチック
イラスト/鈴木麻子