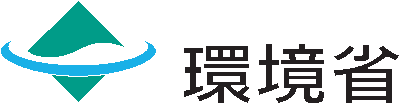地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業
(環境省R&D事業)とは
我が国の温室効果ガス削減に係る目標としては、2030年度に46%削減、更には2050年までにカーボンニュートラル(ネット・ゼロ) 、そして長期目標として「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」における早期の脱炭素社会の実現が掲げられています。
これらの目標を実現するためには、あらゆる分野で更なるCO2削減が可能なイノベーションを創出し、早期に社会実装することが必要不可欠です。具体的には、CO2排出削減技術の高効率化や低コスト化等のための技術的な課題を解決し、優れたCO2排出削減技術を生み出し、実社会に普及させていくことで、将来的な地球温暖化対策の強化につなげることが重要です。一方、CO2排出削減に貢献する技術開発は、開発リスクが大きく、収益性が不確実で、産業界が自ら対策強化を行うインセンティブが小さい等の理由により、民間の自主的な技術開発に委ねるだけでは必ずしも十分に進まない状況にあります。
このため、国の政策上必要な、CO2排出量を大幅に削減する技術の開発・実証を、国が主導して推進していくことが必要不可欠です。特に、第六次環境基本計画における「循環共生型社会」の概念の下、急速に拡大しているゼロカーボンシティ宣言自治体等における先導的な技術開発の取組を支援し、各地域の特性を活かして、脱炭素かつ持続可能で強靱な活力ある地域社会を構築することが極めて重要です。
このような背景の下、本事業は将来的な地球温暖化対策の強化につながるCO2排出削減効果の高い技術の開発・実証を強力に進め、CO2排出量の大幅な削減を実現するとともに、地域の活性化と脱炭素社会の同時達成を後押しし、脱炭素ドミノを誘引することで、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」で掲げる早期の脱炭素社会の実現、ひいては第六次環境基本計画で掲げる「循環共生型社会」の構築に貢献することを目的としています。