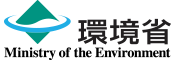支援ツール 自治体職員・相談員用
放射線に関する『よくある質問』

線量測定
一般説明用ページへ
- モニタリングポストの数値に変動が起こるのはなぜですか。
-
モニタリングによる空間線量率測定値の変動には2つの要因が考えられます。
一つは、気象条件の変化です。例えば、降雨があると、空気中の塵などに付着している自然の放射性物質が雨とともに降って地面に溜まるため、検出される放射線の量が一時的に多くなることがあります。
もう一つは、測定すべき放射線自体が統計的な変動(揺らぎ)を持っており、同じ条件で多数回測定しても、その測定値は一定の範囲内で変動するという性質を持っているからです。参考リンク
- 木材の放射線に関する基準について、国で定めているものはありますか。
-
現在は、国で定めているものは無く、組合が定めている自主基準があるようです。
参考リンク
- 自家消費野菜等放射能簡易測定所等の町内の施設ではきのこの原木が測定不可であるため、きのこの原木の放射性物質濃度を測定できる機関を調べて欲しい。
-
関連情報をお知らせします。
参考リンク
- 木材の基準値である40Bq/㎏の根拠を教えて下さい。
-
実証実験により、薪1kgを燃焼させると灰5g、木炭1kgを燃焼させると灰30gが残り、薪及び木炭に含まれていた放射性セシウムの約9割がその灰に残るとのデータが得られました。
これは、灰1kg当たりの放射性セシウムの濃度が薪1kgと比べて182倍、木炭1kgと比べて28倍となることを意味します。
このため、薪及び木炭の燃焼により生じる灰が、セメント等で固化する等の対策を講じなくても一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度である8,000Bq/kg以下となるよう、薪の指標値を40Bq/kg(8,000÷182=44≒40)、木炭の指標値を280Bq/kg(8,000÷28=286≒280)としました。参考リンク