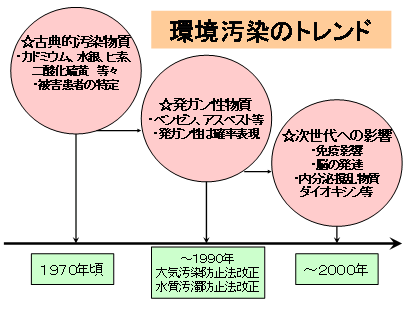保健・化学物質対策
「環境ホルモンの諸問題」
環境ホルモン学会 会長
森田 昌敏
(2006年8月3日 掲載)
ホルモンとは、体内で作られ、体の機能や発達などをコントロールしている信号伝達物質である。信号伝達 / 制御のシステムが乱れると、病気やその他の健康の異常が現れるが、そのような乱れは内因的な原因でも起こるし、外から取り込んだ物質によっても引き起こされる。外から来る場合、その物質を外因性内分泌攪乱物質と呼び、通称として環境ホルモンと呼んでいる。従って環境ホルモンには、人工的に作り出される農薬、医薬、工業化学品の他に、人や家畜から排出される天然型のホルモンや大豆イソフラボンで代表される植物エストロゲンなども含まれている。環境ホルモンという言葉の環境は広い意味であり、大気や水のような一般環境ばかりでなく、食品や職場環境を含め、自己を取り巻く全ての周辺からの影響として考えるところである。重要なことは、物質や汚染ルートが何であれ、受け手である人や野生生物の側からみた視点に立つことである。
いわゆる有害物質の環境汚染問題を考える時、私達はあるトレンドの中にあることに気づく。(図1) 工業化が急速に進み、公害病が顕在化した 1960 年代から 1970 年代にかけては、"公害病"を中心とした対策が進められた。(第 1 期) これらは応急的な対応という側面を持っており、それが一段落した時に、潜在的な悪影響に目が向けられ始めた。主要なターゲットは環境発ガン物質である。(第 2 期) 研究面では、発ガンのメカニズムの解明やリスク評価手法の開発が進み、 1990 年代に、それらを受けて化学物質の規制が進み始めた。大気汚染防止法、水質汚濁防止法のみならず、飲水の安全性、食品の安全性、労働者の安全性に向けて、 "見えざる発ガンリスク"の低減への努力がなされている。そして今私達は第 3 の期に立っている。"見えざるリスク"の課題として、胎児や乳幼児へのリスクをどう扱うかというステージである。
化学物質の生体影響は、生命の初期段階で強く表れ、その影響は成長後にも傷跡として残ることがあることは知られているが、そのリスクをどのように認知し、コントロールすべきであろうか?この問題は、社会の持続可能性の点から、特に少子化の進む先進国において重要度が高い。一方で、環境ホルモンについて政策的な対応を考えるには証拠が十分でないという意見も強い。おそらく現在は、このような課題に対して、研究の積み重ねの重要な時期であると言えよう。その一方で、市民への警告が急がれる場面がある。例えば、胎児への悪影響を心配しての、妊婦さんのキンメダイの摂食回数制限やサプリメントとしての大豆イソフラボンの摂取についての指示は厚生労働省のタイムリーなアクションと言えよう。
環境ホルモンとの関連可能性が指摘される問題は広い。人への影響という面に絞ったとしても、若い男性の精子数の減少、女性の子宮内膜症者の著増、生殖器ガン、子供の喘息とアトピーの増加、注意散漫多動症等々多岐に亘っている。その因果関係の有無を明らかにするのには膨大な費用と時間を要する。そしてその費用は誰が持つべきかについても議論のあるところである。しかしこの問題は、私達の高度の科学技術文明と表裏の関係である可能性は高く、先進国政府が取り組まねばならない基本的且つ重要な課題であると考えている。環境ホルモン学会は、このような研究領域の情報交流の場として世界に先駆け設置されたが、研究者ばかりでなく、環境省、厚生労働省を始めとする中央政府、地方自治体、関係業界そして市民と共に歩み続けたいと考えている。
<図1>