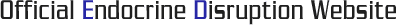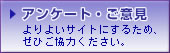取組紹介
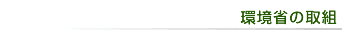
「国際協力関連事業」
無脊椎動物試験に関するOECDの動きと日本の取組
| 年月 | OECDの動き | 日本の取組 |
|---|---|---|
| 2003年10月 | 第1回無脊椎動物専門家会合
|
ミジンコ科数種における、幼若ホルモン様物質によるオス仔虫生産誘導についての基礎データを報告し、甲殻類における内分泌かく乱化学物質スクリーニング試験法として提案 |
| 2004年5月 | 第16回WNT (Meeting of the National Co-ordinators of the Test Guidelines Programme)
|
|
| 2004年12月 | 第3回VMG-eco
|
試験に用いるミジンコの系統によって幼若ホルモン様物質に対する感受性が異なることを報告 |
| 2005年2月 | 各国から送付されたミジンコを用いた系統差に関するプレ・バリデーション開始 | |
| 2005年11月 | 第2回無脊椎動物専門家会合 | プレ・バリデーション結果報告及び、Enhanced TG 211リングテスト実施を提案 |
| 2005年12月 | Invitation Letter配布 | Invitation Letterの作成 |
| 2006年2月 | バリデーション・リングテスト開始 | 参加研究機関へのプロトコール、試験物質、試験系統の配布 |
| 2007年1月 | 第5回VMG-eco | バリデーション・リングテスト結果報告 |
| 2007年3月 | 第19回WNT OECD事務局より、現行のTG211でも雄仔虫の出現はオプショナルな項目として挙げられており、本プロジェクトの成果はこの項目に関するガイダンスとして、TG211の附録にできるのではないかとの示唆あり。またBIACより、本試験法の目的、根拠及び規制的な必要性が理解できないとの強い意見あり。 |
|
| 2007年6月 | 第3回無脊椎動物専門家会合 TG211に新たなエンドポイントを付加することにより対応することが決定。試験法の意義、必要性について各国の理解を得る。報告書作成、統計処理の検討について、参加国からのボランティア援助の約束。 |
バリデーション・リングテスト結果報告 |
| 2008年1月 | 第6回VMG-eco TG211の改訂ではなく、Annexとして仔虫性比を付け加えることによって、必要に応じて使えるようにするという位置付け。 |
BIACからのコメント、John Green氏による統計解析結果などを受けて、FinlandのJukka Ahtiainen氏の協力を得ながらDraft Validation Reportを第20回WNTまでに準備 |
| 2008年4月 | 第20回WNT Draft Validation Reportは提案通り承認された。また、TG211に関しては、従来のTGにオプションの観察事項として産出された仔虫の雌雄を観察するとの記述があったため、大幅な改訂の必要がないことが合意された。関連する部分に関しては提案の通り承認すべきとされた。 |
Draft Validation Reportに対する日本化学工業協会のほうからコメントをBIACとしてOECDへ提出 |
| 2008年10月 | 10月3日付けで改訂版TG211が発行された。 | |
| 2009年6月 | 第4回無脊椎動物専門家会合 TG 211を用いた化学物質暴露で試験個体が死んだ場合、統計にどう反映させるかについて、ガイドラインに記載するように北欧の国々から4月のWNTで意見が出ていた。これについて、議論を行った。TG 211改訂の歴史的な経緯をふまえ、現行のままでよいとの意見が大勢を占めた。 |
日本のデータ277試験のうち対象となる53試験についての再計算を行い、結果を示した。試験個体が試験中に死亡した場合、それらの個体を解析から除外しても含めても、37試験では結果に違いはみられなかった。一方、残り16試験のうち、14試験でNOECが安全域にシフトし、2試験では反対にNOECが高くなった。 |
| 2010年4月~ | ミジンコを用いた多世代試験法について、検討を行った。 | |
| 2011年4月~ | ミジンコを用いた多世代試験法について、継続して検討を行った。 幼若ホルモン様化学物質の検出法について、短期スクリーニング試験法の開発に着手した。 |
|
| 2011年11月 | 修正されたTG211が第8回VMG-eco協議の上で合意された。 | |
| 2011年12月 | 事故死した個体の扱いについてなど、さらにいくつかのコメントを付加してWNTに要請された。 修正TGの草案が2012年4月のWNTでの承認に向けて提出されている。 |