海辺の後背地が山地になっている海岸には、岩盤や大きな岩石が露出した磯と礫や砂が堆積した浜が交互に現れます。これらの場所では立体的な構造とさらに細かな隙間やひさしなどの細かな地形があり、それぞれの地形に応じて多くの生物がすんでいます。平らな砂浜では砂浜表面かあるいはもぐってすむことしかできませんが、磯浜では動かない安定した岩礁に付着して生活する動物が多く、海藻類も多く付着しており、その間にも多くの小さな生物がすんでいます。
瀬戸内海は外海とは異なり、大きな岩礁域はありませんが、700余りの多くの島々があり、これらの間を流れる潮流や、河川水の流入による塩分の低下、冬季の水温低下などの環境により外海域とは異なった生物相を示しています。また、瀬戸内海は干潮と満潮の潮位差が大きく、平均潮位差は備讃瀬戸より西側で3~4m、東側で1~3mあります。 潮が引いたときの磯に出て、どのような生物がいて、どのような生活をしているか調べてみませんか?
潮が引いたときに活動を始める生物もいますが、磯に付着している生物の多くは潮が満ちている時に活動をします。水にもぐらないで生物を見るためには潮が引かないと見ることができませんが、そのときには岩礁の間にできた潮だまり(タイドプール)を覗いてみましょう。手(触手)を広げたイソギンチャク類や、身体全体を膜(外套膜)ですっぽり包んで、ちょっと見ただけでは殻を持った巻貝とは見えないブドウガイなどがはっているところを見ることができます。
1.磯に出る準備(その1)
磯にいる生物を調べるためには次のような準備をして出かけましょう。
1.1 目標
何をどのように調べるのか目標を立てます。
例えば、最初は、どこに、どんな生物が、どのようにすんでいるかを調べるのが良いでしょう。同じ所でも何度か行くうちに、見落としている生物、いつ行ってもすぐ見つかる生物などが分かります。慣れてくれば、違う場所ではどう違うのか、それはなぜ違うのか、といったことに疑問が出てきます。
1.2 記録
観察したことは記録しておくようにしましょう。ポケットに入るくらいの小型のノート類(野帳)、シャープペンシル又は鉛筆が必要です。ぬれても破れない紙(耐水紙)でできた小型のノート(レベルブック;通常紙と耐水紙の2種類ありますので注意)も市販されています。
1.3 地形図
調べに行く場所の地形図があれば、大きな範囲で見て、どのような地形の所に行くのか見ておきましょう。
地形図は大きな本屋さんがあれば、国土地理院が発行している2万5千分の1の地形図が市販されています(検索図でその場所の地名、番号を調べます)。
1.4 資料
また、近くに自然博物館などがあれば、機会があるときに行って、該当する所や付近の資料(過去に調べた結果、その地域の一般的な磯生物の解説書など)を購入しておけば便利です。
1.5 潮位(海面の高さ)
海辺の採集、観察は潮が引いていない時でもできる場所や種類はいますが、生物が多くすんでいて、陸上から見ることができるのは潮が引いた干潮のときです。ですから、採集、観察に出かける前には必ずその日の干潮の時刻がいつなのか調べておくことが必要です。
潮の満ち引きは地球の自転と、太陽の周りを回る公転及び月と太陽の引力によって起こります。最も大きな力は太陽に比べずっと近い所にある月の引力で、月と面している所では引力により海面が引っ張られて高くなります。これと反対側の所もこれは遠心力によりやはり高くなります。海面が低くなる所は、これらと直角の方向の所になります。地球は1日に1回自転しますから、満潮と干潮は1日にほぼ2回繰り返します。干潮と満潮の時刻は毎日同じではなく、少しずつずれて行きます。これは、月が地球の周りを1回りするのにかかる日数がおよそ27.3日で、引力が最も大きくなる位置に来る時刻が少しずつ遅れて来るからです。このため、満潮、干潮の時刻は1日におよそ50分ずつ遅れることになり、2週間後にほぼ同じ時刻に満潮、干潮が現れます。
当日のおよその干潮、満潮の時刻を知りたい場合は、新聞の天気予報欄に載っています。代表的な場所の時刻ですから、満潮、干潮の時刻には少しずれがあります。そのほかに、釣り具屋さんのレジのそばに近くの釣り場の港における潮位表を普通では無料で置いてありますから、これで行く場所に最も近い所を見れば、月毎あるいは半年から1年分の時刻が分かります。もっと詳しく知りたい場合は、日本全国の標準港における1年間分の潮位を計算により求めた表が海上保安庁と気象庁より発行、市販(約3,000円)されています。
1.磯にでる準備(その2)
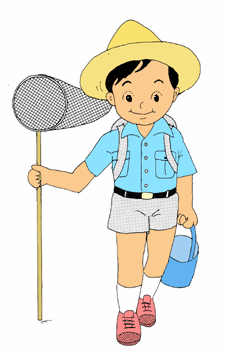
1.6 服装
磯に観察や採集に行く時には、けがや日射病にならないように、図に示したような動き易い服装をして、観察が充分できるようにしましょう。
| 服装位置 | 注意事項 |
|---|---|
| 頭 | 海辺にはふつう日影はありません。必ず帽子をかぶりましょう。麦わら帽子のようなツバの広い帽子がいいでしょう。しかし、あまり大きすぎると観察や写真を撮影する時、風が強い時などには邪魔になる場合があります。ある程度ツバが固く、風でばたばたとあおられないものが便利でしょう。 |
| 上着 | 図では半袖ですが、できれば長袖が良いでしょう。岩と岩の間を抜けるときや、一度に強い直射日光を受けないためです。また、ポケットが多く付いていると便利です。ポケットの代わりに、最近は様々な種類、大きさのナップザックやウエストポーチがあります。海水に濡れたり、汚れたりし易いので、古くなったものなどを利用すると良いでしょう。 |
| ズボン | 上着と同じ理由で、できれば長ズボンが良いでしょう。岩と岩の間を抜けるときやカキ殻などですれる場合があります。 |
| 手 | 岩の角やフジツボ、カキの殻などでけがをしないように、またウニなどのトゲのある生物を持ったりするために、必ず手袋を用意しましょう。汚れたり、破れたりしますから、普通の軍手が便利です。伸縮性のある小さな軍手も市販されています。海水で皮膚がふやけて、ふだんより傷がつき易いので必ず用意しましょう。 |
| 足 | ぬれてもよい古くなった靴下とズックシューズがよいでしょう。足首もすり易いので靴下をはいたほうがよいでしょう。ビーチサンダルなどのつっかけ型のものは滑りやすく、露出部が多くてけがをし易いのでやめましょう。 |
1.磯にでる準備(その3)
1.7 道具
磯に観察や採集に行く時には、表のような道具があれば便利です。服装で挙げたものは省略してあります。
| 道具名 | 説明 |
|---|---|
| ピンセット | 採集した生物をつかむのに便利です。 |
| いそがね | 古くなった大き目のドライバー(マイナス)、食事用ナイフ(ただし、食事用には使えなくなります)、スクレパー(さび落しの小型のもの)でもよいでしょう。 |
| ルーペ | 虫めがね |
| 箱めがね | なくてもよいです。大き目の空缶と厚手の透明ビニール片、ビニールテープでも簡単に作ることができます。最近は軽くて簡単なものも市販されています。 |
| たも網 | 目の細かな柄の短いものが便利です。小さなものでは、金魚用の網で大型のものや、お風呂の垢取り用の網も便利です。 |
| バケツ | 布、ビニール製のおりたためるものが便利です。 |
| 容器 | 採集した生物を分けて入れるときに使います。いろいろな大きさの空いたビニール袋、ふた付きケースなどです。チャック付きの小型ビニール袋も市販されていますが、写真フィルムの入っているプラスティックケースをためておけば、ふた付きで密閉できて大変便利です。 |
| ハンマー、タガネ | これは岩礁に穴を開けてすんでいるカモメガイなどを採集するときなど、特別な場合に使うだけで、いつも必要とはかぎりません。 |
| 図鑑 | 軽くて、小さな、携帯用のものが便利です(参考文献のところを見てください)。 |
| モノサシ、巻尺 | 生物の大きさや地形の距離をはかるときに使います。生物のおよその大きさを測るには、小型ノート(野帳)の端にあらかじめ5mmか1cm区切りの目盛を書いておき、それを測るものに当てるか、測るものを持ってきて当てれば簡単で、便利です。 巻尺はグループでもう少し本格的に調べる場合に使います。それまでは、特に必要はないでしょう。また、市販のハンディタイプのもの(コンベックス)は高価ですので、荷造り用の細なわに目盛を付けて作成するとよいでしょう。 |
| その他 | 道具ではありませんが、持っていったほうがよいものとして、タオル、傷消毒用液、傷テープなどがあります。 |

