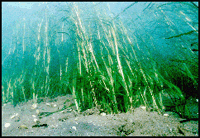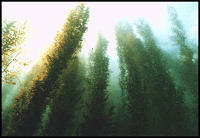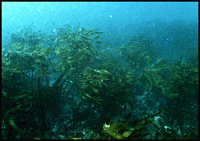藻場とは、海藻が茂る場所のことです。
藻場は、その構成種から見て、「アマモ場」(アマモの仲間から構成される)、「ガラモ場」(ホンダワラの仲間から構成される)、「アラメ場」(アラメから構成される)、「カジメ場」(カジメから構成される)、「コンブ場」、「ワカメ場」等にタイプが分かれます。
アマモ場は、主として内湾や入り江の波の静かな平坦な砂泥底に、ガラモ場やアラメ場、カジメ場は岩礁域に形成されます。また、ガラモ場、アラメ場、カジメ場は、水深によって分布が分かれていることがあります。これは波や光量に関係しており、ガラモ場、アラメ場は比較的浅い場所に、カジメ場は比較的深い場所に分布しているようです。 瀬戸内海では、アマモ場、ガラモ場、カジメ場が多く見られるようです。
海のゆりかごとしての藻場
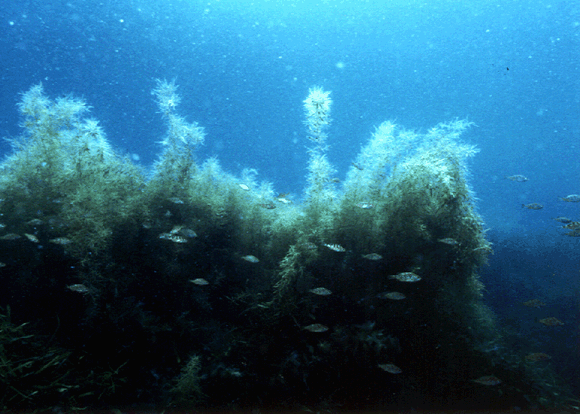
海藻が作る茂みは、波や潮流による水の流動をやわらげるとともに、魚の子供や赤ちゃんである幼稚魚に、外敵から身を守る隠れ場所を与えます。
そして、海藻上や根の間等には幼稚魚の餌となる小型生物が豊富に生息しています。アイナメやイカのように藻場を産卵場所とする生物もいます。
また、ガラモ場の構成種であるホンダワラ類は、海底から離れると海面を漂う「流れ藻」となり、トビウオやサンマの産卵床やモジャコ(ブリの幼魚)等の生育場等として重要な働きをします。
このように、藻場は、魚の赤ちゃんを保育する「海のゆりかご」としての役割を果たしています。
藻場は海のレストラン
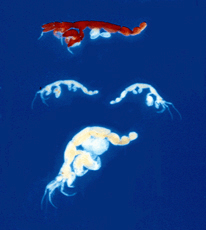

藻場には、たくさんの海藻が生えていますが、それらを直接食べている魚は、メジナ類、ブダイ類、アイゴ類等意外と少ないです。魚が海藻を食べているように見えるのは、実は葉上の生物をついばんでいることが多いです。
海藻の葉上には小型の甲殻類であるワレカラ類、ヨコエビ類などの多くの生物が生息しています。これらの葉上生物は、海藻に付着した微小な藻類や、プランクトンや海藻の死骸や破片を食べています。そしてこれらの豊富な葉上生物を魚類が餌として食べています。
そのほか、海藻は、アワビ、サザエ、ウニの好餌料として重要です。さらに、枯れた後も微生物によって分解されて小さな破片となり、生物のよい餌となります。
アマモ場で見られる生物
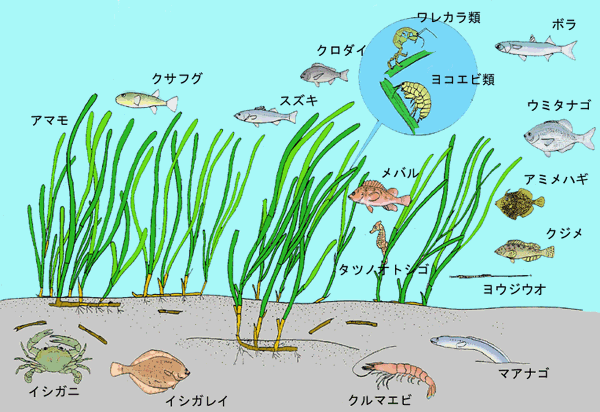
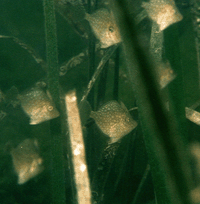
瀬戸内海における藻場の重要な位置にあるアマモ場について、そこで見られる生物をご紹介します。
よく茂ったアマモの葉上にはワレカラ類、ヨコエビ類、ゴカイ類等多くの小動物が生息しています。また、アマモの根元の砂泥は、カニ類、エビ類の良いすみかとなっています。
さらに、これらの小動物とともに、アマモ場には多くの魚が生息しています。そして、それらの魚はそれぞれの一生の中でアマモ場を様々な形で利用しています。
アミメハギ、タツノオトシゴ、ヨウジウオは、アマモ場でその一生をすごします。
ウミタナゴは、アマモ場で稚魚を産み、ワレカラ類やヨコエビ類を食べて育ち、冬には深みに移動します。
クロダイも、幼稚魚期にはアマモ場でワレカラ類やヨコエビ類を食べて育ち、成長とともにアマモ場から外へ出て行きます。スズキの幼稚魚は、アマモ場周辺で動物プランクトンを食べて過ごし、成魚になると内湾全域から沖合いへ移動します。メバル、クジメ、アイナメの幼魚はアマモ場で育ち、成魚になるとガラモ場へ移動します。
アナゴも幼魚期にアマモ場を良い生育場所としています。
また、アオリイカは産卵のためにアマモ場にやって来ることが知られています。
ガラモ場、カジメ場で見られる生物
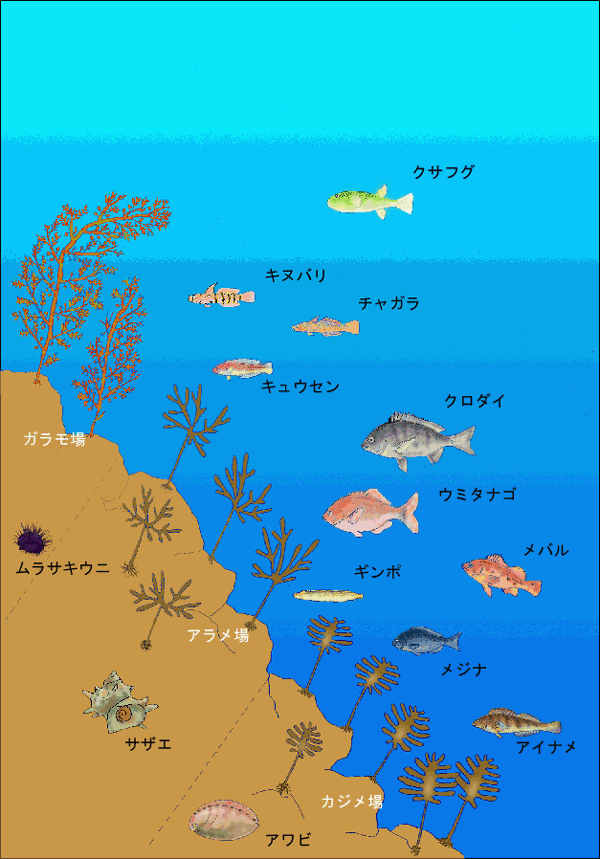
ガラモ場、アラメ場でも多くの魚が見られます。
メバルの生まれたばかりの稚魚は海面を漂い、成長とともに藻場の中で暮らすようになります。その後、動物プランクトンやエビ類、ワレカラ類、ヨコエビ類を餌として、群れで藻場内の中層を泳ぎながら生活しています。
アイナメやクジメは、普段は付近の海底でじっとしており、餌を食べるときは葉上のワレカラ類、ヨコエビ類を海藻ごとかぶりつきます。
クロダイ、ウミタナゴ、メジナ、クサフグ等は餌を食べるために藻場へやって来ます。ギンポ、キヌバリ、チャガラは藻場が広がる岩礁域のくぼみや穴に産卵します。
海底には、ムラサキウニやバフンウニ、サザエ、アワビが見られます。これらの生物は海藻そのものを餌としています。
以上藻場で見られる生物のほんの一部をご紹介しました。実際には、もっとたくさんの生物を見ることができるでしょう。