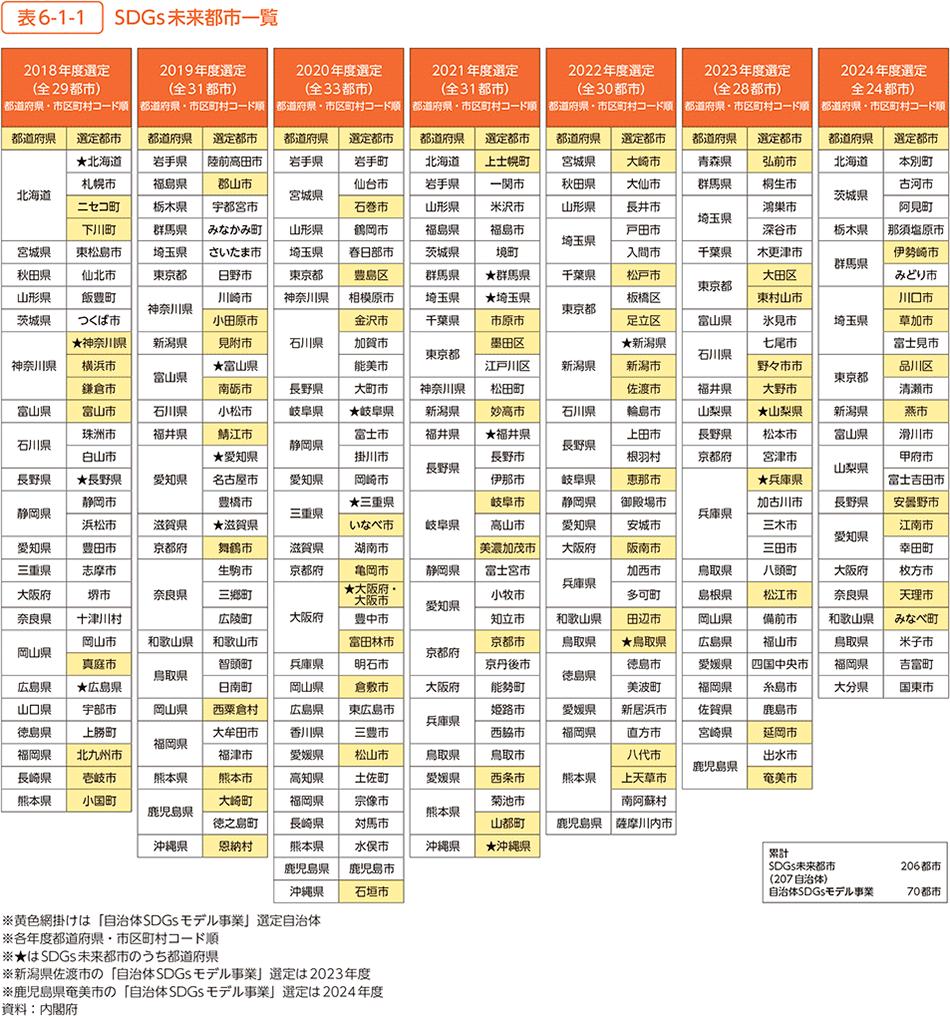2023年5月に環境大臣から中央環境審議会に対して諮問された環境基本計画の見直しについて、約1年に及ぶ審議を経て、同審議会から環境大臣に新計画案についての答申が提出されました。この答申を受けて、2024年5月に第六次となる環境基本計画を閣議決定しました。
私たちは、気候変動、生物多様性の損失及び汚染という3つの危機に直面しています。現代文明は持続可能ではなく転換が不可避であり、社会変革が必要であるとともに、2030年頃までに行う選択や実施する対策は、現在から数千年先まで影響を持つ可能性が高いとも指摘されています。こうした状況を踏まえ、第六次環境基本計画では、環境保全を通じた現在及び将来の国民一人一人の「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現を最上位の目的とし、環境収容力を守りつつ、環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる「循環共生型社会」(「環境・生命文明社会」)をビジョンとして掲げました。そして、自然資本(環境)があらゆる経済社会活動の基盤であるという認識の下、GDPといった市場的価値のみならず、健康や主観的幸福感といった非市場的価値も引き上げる「新たな成長」を実現していくこととしています。
政府の予算のうち環境保全に関係する予算について、環境保全に係る施策が政府全体として効率的、効果的に展開されるよう、環境省において見積り方針の調整を図り、環境保全経費として取りまとめています。2025年度予算における環境保全経費の総額は、2兆3,456億円となりました。
地球温暖化による環境への影響、化学物質による健康や生態系への影響等、環境問題の多くには科学的な不確実性があります。しかし、一度問題が発生すれば、それに伴う被害や対策コストが非常に大きくなる可能性や、長期間にわたる極めて深刻な、あるいは不可逆的な影響をもたらす可能性があります。このため、このような環境影響が懸念される問題については、科学的に不確実であることを理由に対策を遅らせず、知見の充実に努めながら、予防的な対策を講じるという「予防的な取組方法」の考え方に基づいて対策を講じていくべきです。この予防的取組は、「第六次環境基本計画」においても「環境政策における原則等」として位置付けられており、様々な環境政策における基本的な考え方として取り入れられています。関係府省は、「第六次環境基本計画」に基づき、予防的な取組方法の考え方に関する各種施策を実施しました。
「第五次環境基本計画」で提唱され、SDGsを地域で実践するためのビジョンである「地域循環共生圏」は、「第六次環境基本計画」においても計画の中心概念である「ウェルビーイング/高い生活の質」の実現に向けた「新たな成長」の実践・実装の場として位置付けられました。「地域循環共生圏」の創造を推進するため、環境省では、「環境で地域を元気にする地域循環共生圏づくりプラットフォーム事業(2019年度~2023年度実施)」、「地域循環共生圏づくり支援体制構築事業(2024年度~)」等により各地域での地域循環共生圏のビジョンづくりやそれを実現するための取組実施の支援、またそうした支援ができる主体(地域循環共生圏づくりに向けた中間支援の担い手)育成を進めています。さらに、全国各地でつくられた地域循環共生圏のビジョンを実現するため、2019年に運用を開始したポータルサイト「環境省ローカルSDGs-地域循環共生圏-」等を活用した情報発信・普及啓発を進めています。
詳細については、第1部第3章第1節を参照。
また、SDGsの環境的側面における各主体の取組を促進するため、環境省では2016年から「ステークホルダーズ・ミーティング」を開催しています。これは、先行してSDGsに取り組む企業、自治体、市民団体、研究者や関係府省が一堂に会し、互いの事例の共有や意見交換、さらには広く国民への広報を行う公開の場です。先駆的な事例を認め合うことで、他の主体の行動を促していくことを目的としています。
SDGsの達成に向けた我が国の取組を広範な関係者が協力して推進していくため、行政、NGO、NPO、有識者、民間セクター、各種団体等の関係者が集まり、意見交換を行うSDGs推進円卓会議が、総理大臣を本部長とするSDGs推進本部の下に設置されています。2023年12月に改定されたSDGs実施指針を踏まえ、2030年以降も見据えて国際的な議論を主導していくべく、2024年5月には国連未来サミットに関する意見交換、同年10月には2025年実施予定の我が国のSDGs達成に向けた取組を振り返る自発的国家レビュー(Voluntary National Review:VNR)に関する意見交換を実施しました。
また、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」(2023年12月閣議決定)において、地方創生に取り組むに当たって、SDGsの理念に沿った経済・社会・環境の三側面を統合した取組を進めることで、政策の全体最適化や地域の社会課題解決の加速化を図ることが重要であるとしています。国、地方公共団体等において、様々な取組に経済、社会及び環境の統合的向上等の要素を最大限反映することが重要です。したがって、持続可能なまちづくりや地域活性化に向けて取組を推進するに当たっても、SDGsの理念に沿って進めることにより、政策の全体最適化や地域課題解決の加速化という相乗効果が期待でき、地方創生の取組の一層の充実・深化につなげることができます。このため、SDGsを原動力とした地方創生の推進や地域循環共生圏の創造の後押しを行います。
さらに、内閣府では2018年度から2024年度にかけて、地方公共団体(都道府県及び市区町村)によるSDGsの達成に向けた取組を公募し、優れた取組を提案する都市をSDGs未来都市として計206都市選定し、その中でも特に先導的な取組を自治体SDGsモデル事業として計70事業選定しました。今後もこれらの取組を支援するとともに、情報発信を通じて成功事例の普及展開を図ります。また、2022年度から2024年度にかけて、地方公共団体が広域で連携し、SDGsの理念に沿って地域のデジタル化や脱炭素化等を行う地域活性化に向けた取組を「広域連携SDGsモデル事業」として選定し、6団体を支援しました。加えて、SDGsの推進に当たっては、多様なステークホルダーとの連携が不可欠であることから、官民連携の促進を目的として「地方創生SDGs官民連携プラットフォーム」を設置し、マッチングイベントや分科会開催等による支援を実施しています。さらに、金融面においても地方公共団体と地域金融機関等が連携して、地域課題の解決やSDGsの達成に取り組む地域事業者を支援し、地域における資金の還流と再投資を生み出す「地方創生SDGs金融」を通じた、自律的好循環の形成を目指しています。また、SDGsの取組を積極的に進める事業者等を「見える化」するために、2020年10月には「地方公共団体のための地方創生SDGs登録・認証等制度ガイドライン」を公表するとともに、2021年11月には、SDGsの達成に取り組む地域事業者等に対する優れた支援を連携して行う地方公共団体と地域金融機関等を表彰する「地方創生SDGs金融表彰」を創設しました。
このような取組を通じて、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」において設定されている、SDGsの達成に向けた取組を行っている都道府県及び市区町村の割合の目標を2024年度に60%と設定しており、2023年度には65%と目標達成となりましたが、引き続き地方創生SDGsの普及促進活動を進めていきます(表6-1-1)。