国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)(平成12年法律第100号)に基づく基本方針に即して、国及び独立行政法人等の各機関は、環境物品等の調達の推進を図るための方針の策定・公表を行い、これに基づいて環境物品等の調達を推進しました。
基本方針の見直しを行い、より高い環境性能を示す「基準値1」について、調達に際しての支障や供給上の制約等がない限り調達を推進していくものとして定義を見直し、国等の率先調達により初期需要創出への貢献が求められる先端的な環境物品等について、特定調達品目及び基準値1への位置付けを図ることができる運用に変更しました。さらに、分野横断となる共通の判断の基準として「原材料に鉄鋼が使用された物品」について、削減実績量が付され、かつ、カーボンフットプリントが算定・開示された鉄鋼(グリーンスチール)の使用を「基準値1」に設定しました。
また、プリンタを始めとした6品目において再生プラスチックの使用等の循環性基準を判断の基準に設定しました。乗用車、バス等、トラック等、トラクタにおいて、燃費基準値の引上げ、ガス温水器、石油温水機器においてエネルギー消費効率の強化、食堂において見える化及び有機農業について判断の基準への追加を行いました。さらに、備蓄用作業服を新規品目として追加しました。
グリーン購入の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。
そのほか、地方公共団体等でのグリーン購入を推進するため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。
国際的なグリーン購入の取組を推進するため、グリーン購入に関する世界各国の制度・基準について情報を収集し、環境省ウェブサイトで公開しました。
国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(環境配慮契約法)(平成19年法律第56号)に基づく基本方針に従い、国及び独立行政法人等の各機関は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(以下「環境配慮契約」という。)を推進しました。
環境配慮契約の取組を更に促進するため、最新の基本方針について、国の地方支分部局、地方公共団体、事業者等を対象とした全国説明会及びオンライン説明会を開催しました。
地方公共団体等での環境配慮契約の推進のため、実務支援等による普及・啓発活動を行いました。
消費者が環境負荷の少ない製品を選択する際に適切な情報を入手できるように、環境ラベル等環境表示の情報の整理を進めました。我が国で唯一の第三者認証によるエコラベル(旧タイプI:ISO14024)であるエコマーク制度では、ライフサイクルを考慮した指標に基づく商品類型を継続して整備しており、2025年3月31日時点でエコマーク対象商品類型数は76、認定商品数は5万3,990となっています。
事業者の自己宣言による環境主張である自己宣言環境主張(旧タイプII:ISO14021)や民間団体が行う環境ラベル等については、各ラベリング制度の情報を整理・分類して提供する「環境ラベル等データベース」を引き続き運用しました。こうした中、農林水産省では、2024年3月から、農産物の生産段階における環境負荷低減の努力を評価し、分かりやすく表示する「みえるらべる」の取組の本格運用を開始しています。
製品の環境負荷を定量的に表示する環境表示としては2通りの宣言方法があります。複数影響領域を表す環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)(旧タイプIII:ISO14025)は、我が国では唯一SuMPO EPDがあり、地球温暖化の単一影響領域を表す環境表示はカーボンフットプリント(ISO/TS14067)があります。
ISO14001を参考に環境省が策定した、中堅・中小事業者向け環境マネジメントシステム「エコアクション21」を通じて、環境マネジメントシステムの認知向上と普及・促進を行いました。2024年3月時点でエコアクション21の認証登録件数は7,552件となりました。
環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号。以下「環境配慮促進法」という。)では、環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付け等について規定しています。環境報告書の作成・公表及び利活用の促進を図るため、環境配慮促進法に基づく特定事業者の環境報告書を一覧できるウェブサイトとして「もっと知りたい環境報告書」を運用しました。また、バリューチェーンマネジメントの取組促進のために、2020年8月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~OECDガイダンスを参考に~」や2023年5月に公表した「バリューチェーンにおける環境デュー・ディリジェンス入門~環境マネジメントシステム(EMS)を活用した環境デュー・ディリジェンスの実践~」を題材に、環境デュー・ディリジェンスや情報開示の普及促進を図りました。さらに、国際的な環境デュー・ディリジェンスを巡る規制の動向も踏まえ、「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に向けた懇談会」を開催し、今後の日本企業の環境デュー・ディリジェンスの対応のあり方を議論し、その結果を取りまとめ、日本企業が環境デュー・ディリジェンスに取り組む上でのポイントを示しました。
各種公害規制が遵守され、公害の防止に資するよう、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に基づき、特定工場に対し、公害防止管理者等を選任し、公害防止組織を整備すること及びその旨を都道府県知事等に届け出ることを義務付けています。
国家資格である公害防止管理者は、国家試験の合格又は資格認定講習の修了のいずれかにより取得が可能であり、国家試験は1971年度から、資格認定講習は一定の技術資格を有する者又は公害防止に関する実務経験と一定の学歴を有する者を対象として、1972年度から実施されています。
環境保全に資する製品やサービスを提供する環境ビジネスの振興は、環境と経済の好循環が実現する持続可能な社会を目指す上で、極めて重要な役割を果たすものであると同時に、経済の活性化、国際競争力の強化や雇用の確保を図る上でも大きな役割を果たすものです。
我が国の環境ビジネスの市場・雇用規模については、2023年の市場規模は約130兆円、雇用規模は約292万人となり、2000年との比較では市場規模は約2.1倍、雇用規模は約1.5倍に成長しました。環境ビジネスの市場規模は、2009年に世界的な金融危機で一時的に落ち込んだものの、それ以降は着実に増加しています。
民間資金を環境分野へ誘引する観点からは、金融機能を活用して、環境負荷低減のための事業への投融資を促進するほか、企業活動に環境配慮を組み込もうとする経済主体を金融面で評価・支援することが重要です。そのため、以下に掲げる取組を行いました。
我が国におけるESG金融(環境(Environment)・社会(Social)・企業統治(Governance)といった非財務情報を考慮する金融)の主流化のため、金融・投資分野の各業界トップと国が連携し、ESG金融に関する意識と取組を高めていくための議論を行い、行動する場として2025年3月に「ESG金融ハイレベル・パネル」を開催し、第六次環境基本計画の内容を踏まえつつ、金融を通じたグリーンな経済システムの構築に向けた宣言を同パネルから発出しました。また、ESG金融を含むサステナブルファイナンスの取組を推進するに当たり、脱炭素、資源循環、自然共生の統合的アプローチに向けた金融面からの取組について議論を行いました。さらに、ESG金融に関する幅広い関係者を表彰する我が国初の大臣賞である「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」を引き続き開催し、積極的にESG金融に取り組む金融機関、諸団体やサステナブル経営に取り組む企業を多数の応募者の中から選定し、2025年2月に開催された表彰式において発表しました。また、気候変動関連情報を開示する枠組みであるTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言、生物多様性・自然資本関連情報を開示する枠組みであるTNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)提言、さらにはISSB(国際サステナビリティ基準審議会)によるサステナビリティ開示基準等にのっとり、気候関連リスクや自然関連リスクとその備えについて金融機関や投資家から情報開示が求められており、我が国ではこれらの提言に基づく情報開示を推進しているところです。具体的には、環境省では、2024年度に地域金融機関3機関に対して脱炭素社会実現に向けた移行計画の策定支援や、投融資先に対する実効的なエンゲージメントを支援するパイロットプログラムを、金融機関3機関に対して、金融機関の投融資ポートフォリオにおける自然との接点や自然関連リスク・機会の把握・分析を支援するパイロットプログラムをそれぞれ実施しました。加えて、気候変動対応が地域社会にとって「機会」となるよう、多様な地域金融機関による脱炭素化事業支援事例等を調査し、事例集として公表しました。事業者向けには、情報開示の実施・高度化を促進することを目的に、気候関連財務情報開示に加え、関連する自然資本、水資源や資源循環の情報開示に向けた勉強会を全6回開催しました。本勉強会内容や最新動向について調査した結果は「サステナビリティ(気候・自然関連)情報開示を活用した経営戦略立案のススメ(2025年3月)」並びに環境三社会実現に向けた手引きに反映し、我が国の事業者へ周知しました。経済産業省においても、2019年に世界の産業界や金融界のトップが一堂に会する、世界初の「TCFDサミット」を開催し、2023年10月には国際GX会合(GGX)と統合し、2024年10月には「GGX Finance Summit 2024」を開催しました。また、経済産業省が2018年12月に策定した「気候関連財務情報開示に関するガイダンス(TCFDガイダンス)」について、民間主導で設立されたTCFDコンソーシアムがその改訂作業を引き継ぎ、2022年10月には改訂版として「TCFDガイダンス3.0」を公表するなど、日本におけるTCFD開示の浸透に貢献してきました。その結果、TCFDの活動停止時点で、我が国のTCFD賛同機関数は世界最多の約1,488となりました。同コンソーシアムでは国際的な議論の変化を踏まえた日本における最適な開示について開示側と活用側が議論を続けており、2024年8月には事業計画とのリンクを意識した開示である「移行計画」の開示要請の高まりを受け、「移行計画ガイドブック」を公表しています。
金融機関が自主的に策定した「持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則(21世紀金融行動原則)」(約300機関が署名)について、署名金融機関による最優良取組事例を選定し表彰する等、引き続き支援を行いました。2021年5月に金融庁、経済産業省、環境省が共同で「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を策定し、鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント、自動車分野における技術ロードマップを取りまとめ、公表しました。2025年3月には当該基本指針の改訂も実施しています。また、国内におけるトランジション・ファイナンスの環境整備を更に進めるため、トランジション・ファイナンスの調達に要する費用に対する補助や情報発信も行っています。2023年6月には、資金供給後のトランジション戦略の着実な実行と企業価値向上への貢献を担保するために、金融機関向けのフォローアップガイダンスを策定しました。また、トランジション・ファイナンスを通じて金融機関の投融資先の排出量(ファイナンスド・エミッション)が一時的に増加することを懸念し、投融資を控える行動が生じ得るという課題について、2023年10月に課題解決に向けた考え方を整理し公表しました。
さらに、2023年度から、10年間で150兆円超のGX投資を実現する呼び水として、2024年2月に世界初の国によるトランジション・ボンドとしてクライメート・トランジション利付国債の発行を開始し、2025年2月までに約3.0兆円を発行しました。
中小企業等がリースで脱炭素機器を導入する場合に総リース料の一定割合を補助する事業、バリューチェーンの脱炭素化や地域の脱炭素化に資する融資に対する利子補給事業など、再生可能エネルギー事業創出や省エネ設備導入に向けた支援を引き続き実施したほか、地域資源を活用した金融機関の取組に対する支援の結果を踏まえて「ESG地域金融実践ガイド3.0」を公表しました。
国内におけるグリーンボンド等による調達促進に資するため、グリーンボンド等の調達に要する費用に対する補助や、グリーンボンド等による資金調達の概要やガイドラインの内容等をテーマとした「グリーンファイナンスセミナー」を実施しました。また、グリーンファイナンスポータルにて、国内におけるグリーンファイナンスの実施状況等、ESG金融に関する情報の一元的な発信を行いました。加えて、2024年11月には、我が国のサステナブルファイナンス市場をさらに健全かつ適切に拡大していくことを目的とした「グリーンファイナンスに関する検討会」において、ガイドラインの構成変更、国際原則の改訂の反映及び国内市場の現状を踏まえた解説の追加を目的としてガイドラインの改定を行いました。さらに、検討会の下に設置した「グリーンリストに関するワーキンググループ」において、グリーンな資金使途等を例示したガイドラインの付属書1別表について、内容の拡充に係る検討を進めています。
日本政策金融公庫においては、大気汚染対策や水質汚濁対策、廃棄物の処理・排出抑制・有効利用、温室効果ガス排出削減、省エネ等の環境対策に係る融資施策を引き続き実施しました。
政府関係機関等による環境保全事業の助成については、表6-2-1のとおりでした。
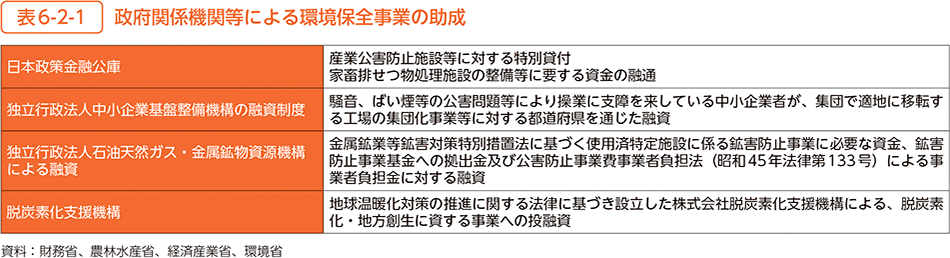
2024年度税制改正において、[1]地球温暖化対策のための税の着実な実施、[2]民間取組促進によるネイチャーポジティブ実現に向けた税制措置の推進、[3]鳥獣被害対策の推進を目的とした特例措置の延長(狩猟税)、[4]廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除特例措置の延長(軽油引取税)、[5]公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設、汚水・廃液処理施設)に係る課税標準の特例措置の延長(固定資産税)等を講じました。
環境関連税制等のグリーン化については、2050年ネット・ゼロのための重要な施策です。
我が国では、税制による地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギー起源CO2排出抑制のための諸施策を実施していく観点から、2012年10月に「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例」が導入されました。具体的には、我が国の温室効果ガス排出量の8割以上を占めるエネルギー起源CO2の排出削減を図るため、全化石燃料に対してCO2排出量に応じた税率(289円/トンCO2)を石油石炭税に上乗せするものです。急激な負担増を避けるため、税率は3年半かけて段階的に引き上げることとされ、2016年4月に最終段階への引上げが完了しました。この課税による税収は、エネルギー起源CO2の排出削減を図るため、省エネルギー対策、再生可能エネルギー普及、化石燃料のクリーン化・効率化などに充当されています。
車体課税については、自動車重量税におけるエコカー減税や、自動車税及び軽自動車税におけるグリーン化特例(軽課)及び環境性能割といった環境性能に優れた車に対する軽減措置が設けられています。