水質汚濁に係る環境基準のうち、健康項目については、カドミウム、鉛等の重金属類、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など、公共用水域において27項目、地下水において28項目が設定されています。
生活環境項目については、生物化学的酸素要求量(BOD)、化学的酸素要求量(COD)、全窒素、全りん、全亜鉛等の基準が定められており、利水目的等から水域ごとに環境基準の類型指定を行っています。水環境に係る課題は、水質汚濁に加えて、CODの高止まり、栄養塩不足など、地域によって多様化しています。このため、水環境の状況、地域のニーズや実情に応じて、水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準の柔軟な運用が可能となるよう、関係の通知を改正しました。また、水浴について、環境基準の水域類型における利用目的から外して大腸菌数のみ適用することとし、告示を改正しました。
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づき、都道府県等は環境基準に設定されている項目について、公共用水域及び地下水の水質の常時監視を行っています。また、要監視項目についても、都道府県等の地域の実情に応じ、公共用水域等において水質測定が行われています(要監視項目である PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタン酸)への対応については、第2節3を参照)。
水質汚濁防止法が2013年に改正されたことを受けて、国は2014年度から全国の公共用水域及び地下水、それぞれ110地点において、放射性物質の常時監視を実施しています。モニタリング結果は、専門家による評価を経て公表しました。
2023年度の全国47都道府県の公共用水域、地下水の放射性物質のモニタリングの結果では、水質及び底質における全β放射能及び検出されたγ線放出核種は、過去の測定値の傾向の範囲内でした。
また、東京電力福島第一原子力発電所の事故を受けて、「総合モニタリング計画」(2011年8月モニタリング調整会議決定、2025年3月改定)に基づき、2011年から福島県及び周辺地域の水環境における放射性物質のモニタリングを継続的に実施しています。公共用水域のうち河川、沿岸域の水質からは近年放射性セシウムは検出されておらず、湖沼の水質について2023年度は164地点のうち2地点のみで検出されました。地下水中の放射性セシウムについては、2011年度に福島県において検出されたのみで、2012年度以降検出されていません。
水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)については、2023年度の公共用水域における環境基準達成率が99%(2022年度99.1%)でした。
生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)のうち、有機汚濁の代表的な水質指標であるBOD又はCODの環境基準の達成率は、2023年度は89.1%(2022年度87.8%)でした。水域別では、河川93.8%(同92.4%)、湖沼52.6%(同50.3%)、海域80.5%(同79.8%)であり、湖沼では依然として達成率が低い状況です(図4-2-1)。
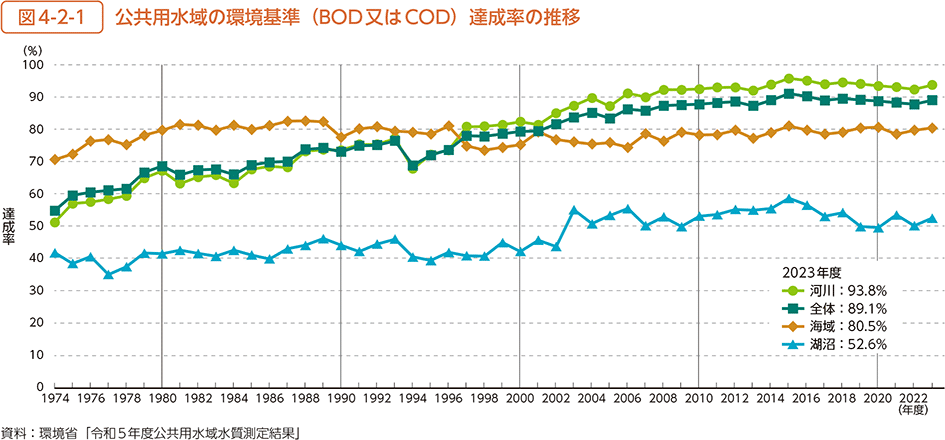
[![]() Excel]
Excel]
閉鎖性海域の海域別のCODの環境基準達成率は、2023年度は、東京湾は68.4%、伊勢湾は50.0%、大阪湾は66.7%、大阪湾を除く瀬戸内海は79.1%でした(図4-2-2)。
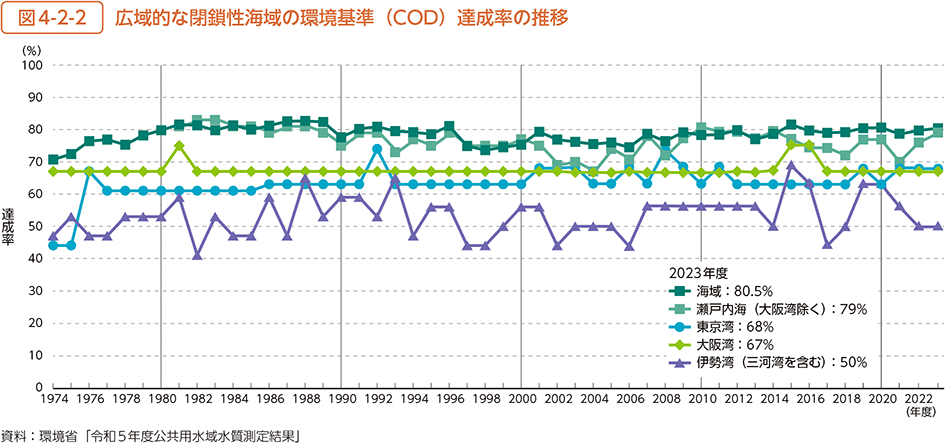
[![]() Excel]
Excel]
全窒素及び全りんの環境基準の達成率は、2023年度は湖沼50.8%(同54.0%)、海域88.2%(同90.1%)であり、湖沼では依然として低い水準で推移しています。閉鎖性海域の海域別の全窒素及び全りんの環境基準を達成した水域数は、2023年度は東京湾は6水域中5水域、伊勢湾は7水域中6水域、大阪湾は3水域中3水域、大阪湾を除く瀬戸内海は57水域中55水域でした。
2023年の赤潮の発生状況は、東京湾43件、伊勢湾17件、瀬戸内海85件、有明海41件でした。また、これらの海域では貧酸素水塊や青潮の発生も見られました。
2023年度の地下水質の概況調査の結果では、調査対象井戸(2,785本)の5.1%(142本)において環境基準を超過する項目が見られました。調査項目別に見ると、過剰施肥、家畜排せつ物の不適正処理、生活排水の地下浸透等が原因とみられる硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の環境基準超過率が2.2%と最も高くなっています。さらに、汚染源が主に事業場であるトリクロロエチレン等の揮発性有機化合物(VOC)についても、依然として新たな汚染が発見されています。また、汚染井戸の監視等を行う継続監視調査の結果では、3,875本の調査井戸のうち1,609本において環境基準を超過していました(図4-2-3、図4-2-4、図4-2-5)。
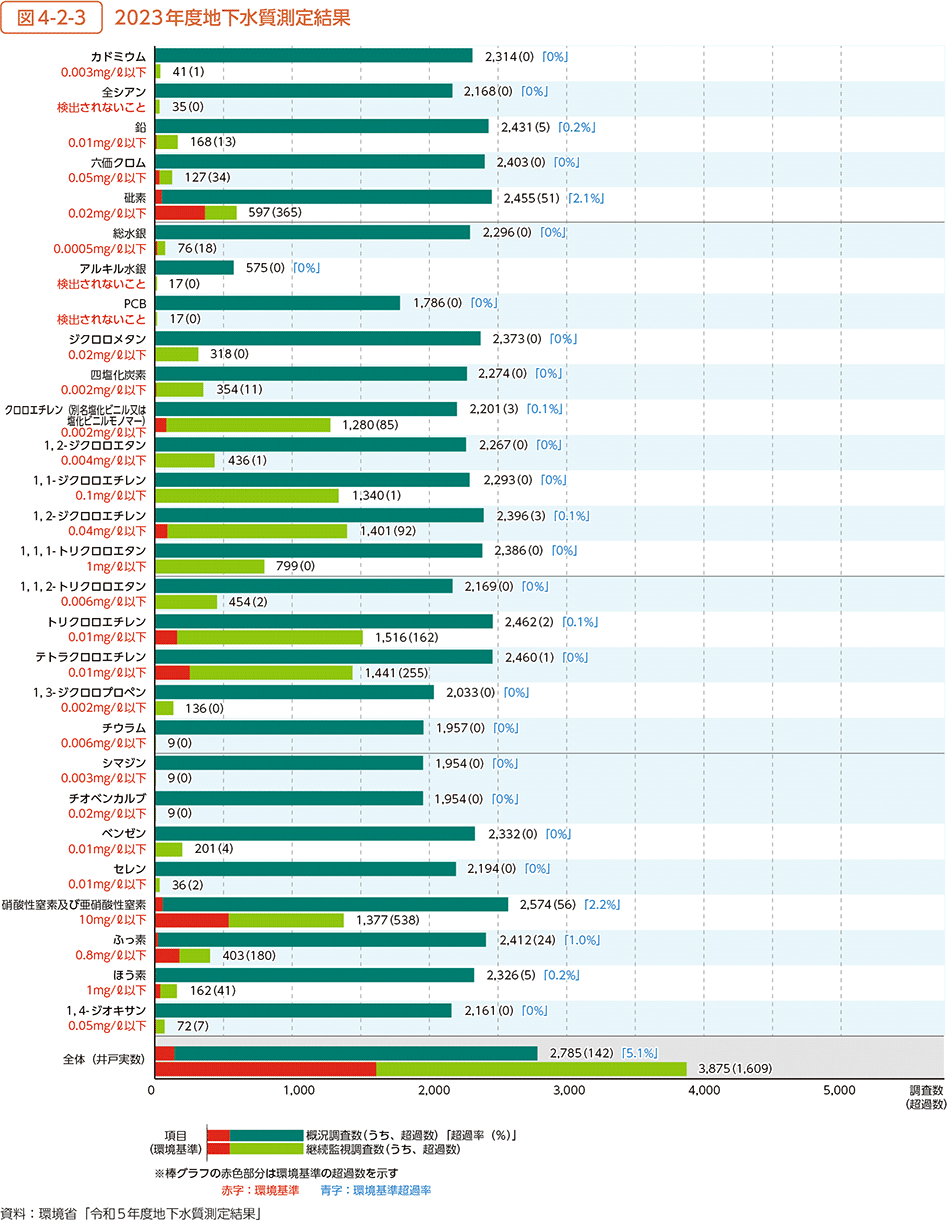
[![]() Excel]
Excel]
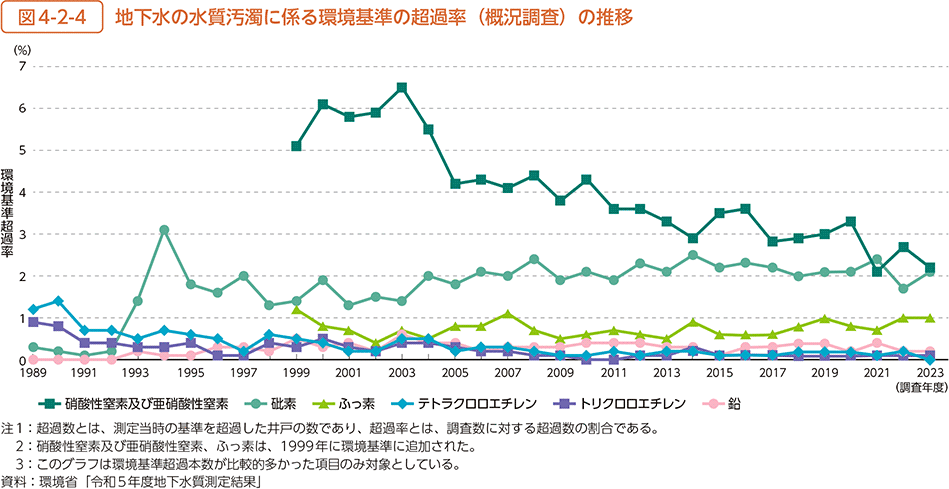
[![]() Excel]
Excel]
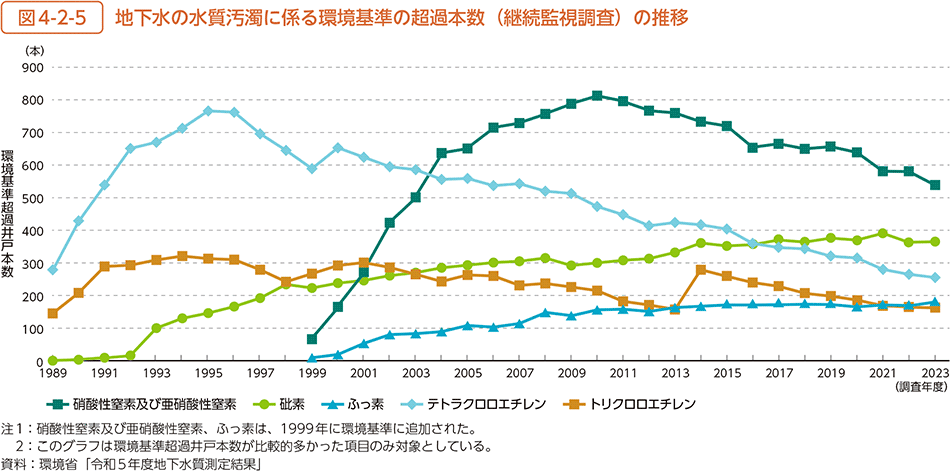
[![]() Excel]
Excel]
公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されていますが、環境基準の達成のため、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準の設定が可能であり、全ての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
排水基準の設定されている項目のうち、亜鉛含有量について、一律排水基準を直ちに達成させることが困難であるとの理由により、これまで暫定排水基準が適用されていた業種の排水基準値について見直しの検討を行い、2024年12月から、新たな暫定排水基準が適用されました。
汚水処理施設整備については、現在、2014年1月に国土交通省、農林水産省、環境省の3省で取りまとめた「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」を参考に、都道府県において、早期に汚水処理施設の整備を概成することを目指し、また中長期的には汚水処理施設の改築・更新等の運営管理の観点で、汚水処理に係る総合的な整備計画である「都道府県構想」の見直しが進められています。2023年度末で汚水処理人口普及率は93.3%となりましたが、残り約830万人の未普及人口の解消に向け(図4-2-6)、「都道府県構想」に基づき、浄化槽、下水道、農業等集落排水施設、コミュニティ・プラント等の各種汚水処理施設の整備を推進しています。
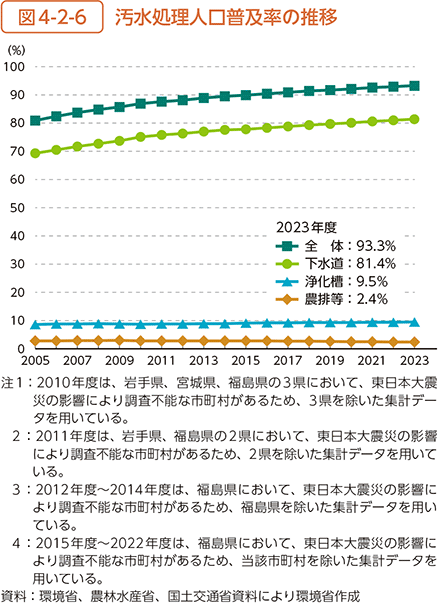
[![]() Excel]
Excel]
浄化槽については、「循環型社会形成推進地域計画」等に基づく市町村の浄化槽整備事業に対する国庫助成により、整備推進及び維持管理の向上を図りました。2023年度より汚水処理施設概成目標達成のため、アクションプランに定める整備進捗率を上回って浄化槽整備を加速化する事業への助成率を引き上げるとともに、公共浄化槽を対象とした少人数高齢世帯の維持管理費用の補助を開始し、2024年度より少人数高齢世帯の維持管理費用の補助の対象を個人設置型浄化槽に拡充するなど、浄化槽整備事業に対する一層の支援を行っています。2023年度においては、全国約1,700の市町村のうち約1,400の市町村で浄化槽の整備が進められました。
下水道整備については、「都道府県構想」に基づき、人口が集中している地区等の整備効果の高い区域において重点的に下水道整備を行いました。
合流式下水道の改善については、合流式下水道緊急改善事業等により、2023年度末までに全ての都市で施行令に基づく対策を完了しました。2024年度より特定水域合流式下水道改善事業を創設し、水域の特性と水環境へのニーズ・利用用途に応じた水質保全対策を推進しています。
下水道の未普及対策や改築については、「下水道クイックプロジェクト」の新たな手法を用いて、従来の技術基準にとらわれず地域の実状に応じた低コスト、早期かつ機動的な整備及び改築を推進しております。施工が完了した地域では大幅なコスト縮減や工期短縮等の効果を実現しました。
農業集落排水事業については、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する農業集落排水施設の整備又は改築を行うとともに、既存施設について、広域化・共同化対策、維持管理の効率化や長寿命化・老朽化対策を適時・適切に進めるため、地方公共団体による機能診断や計画策定等を推進しました。
水質汚濁防止法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重点地域の指定を行っています。2024年3月末時点で、41都府県、209地域、333市町村が指定されており、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。
水質汚濁防止法に基づいて、地下水の水質の常時監視、有害物質の地下浸透制限、事故時の措置、汚染された地下水の浄化等の措置が講じられています(図4-2-7)。また、2011年6月に水質汚濁防止法が改正され、地下水汚染の未然防止を図るため、届出義務の対象となる施設の拡大、施設の構造等に関する基準の遵守義務、定期点検の義務等に関する規定が新たに設けられました。これらの制度の施行のため、構造等に関する基準及び定期点検についてのマニュアルや、対象施設からの有害物質を含む水の地下浸透の有無を確認できる検知技術についての事例集等を作成・周知しています。
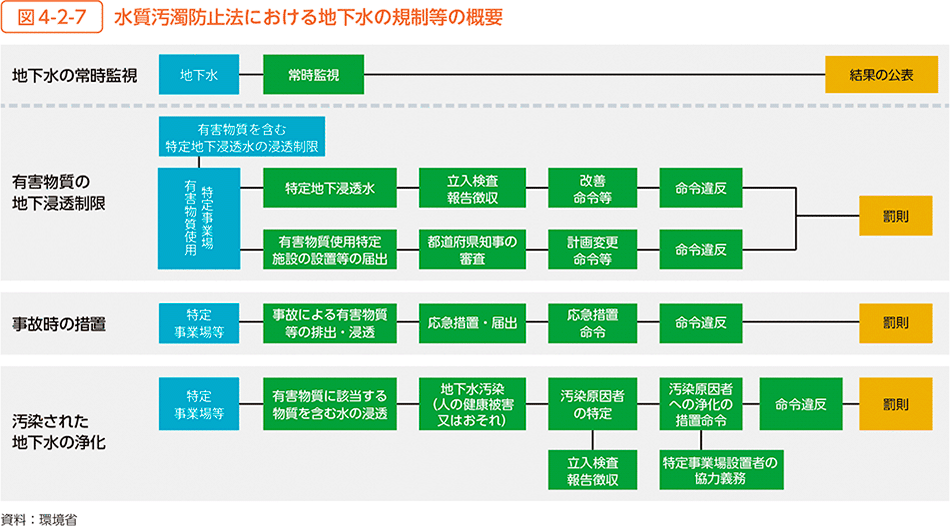
環境基準項目の中で特に継続して超過率が高い状況にある硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、過剰施肥、不適正な家畜排せつ物管理及び生活排水処理等が主な汚染原因であるとみられることから、地下水保全のための硝酸性窒素等地域総合対策の推進のため、「硝酸性窒素等地域総合対策ガイドライン」の周知を図るとともに、地域における窒素負荷低減の取組の技術的な支援等を行いました。
地盤沈下は、地下水の過剰な採取により地下水位が低下し、粘性土層が収縮するために生じます。2023年度に地盤沈下観測のための測量が実施された21都道府県30地域の沈下の状況は、図4-2-8のとおりでした。
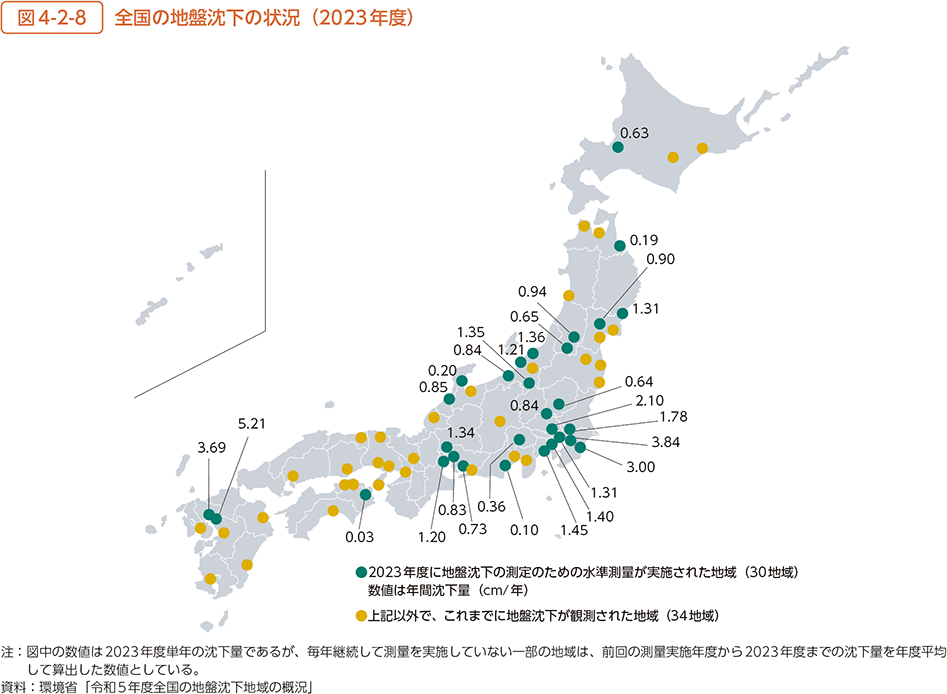
[![]() Excel]
Excel]
2023年度の地盤沈下の経年変化は図4-2-9に示すとおりであり、2023年度までに地盤沈下が認められている地域は39都道府県64地域です。かつて著しい地盤沈下を示した東京都区部、大阪府大阪市、愛知県名古屋市等では、地下水採取規制等の結果、長期的には地盤沈下は沈静化の傾向をたどっています。しかし、消融雪地下水採取地、水溶性天然ガス溶存地下水採取地など、一部地域では依然として地盤沈下が発生しています。
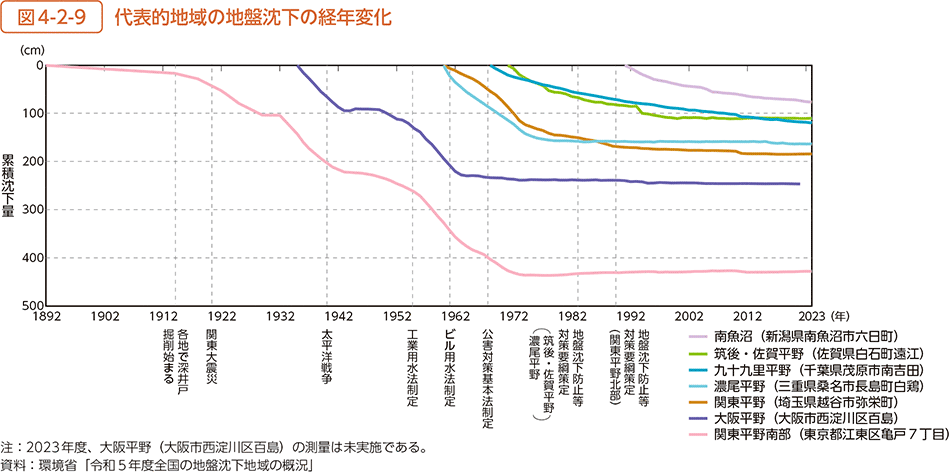
[![]() Excel]
Excel]
長年継続した地盤沈下により、建造物、治水施設、港湾施設、農地等に被害が生じた地域も多く、海抜ゼロメートル地域等では洪水、高潮、津波等による甚大な災害の危険性のある地域も少なくありません。
地盤沈下の防止のため、工業用水法(昭和31年法律第146号)及び建築物用地下水の採取の規制に関する法律(昭和37年法律第100号)に基づく地下水採取規制の適切な運用を図りました。
雨水浸透ますの設置など、地下水かん養の促進等による健全な水循環の確保に資する事業に対して補助を実施しました。
濃尾平野、筑後・佐賀平野及び関東平野北部の3地域については、地盤沈下防止の施策の円滑な実施を図るため、協議会において情報交換を行うとともに、地盤沈下防止等対策要綱に関する関係府省連絡会議を2025年2月に開催し、今後も地下水採取量に係る目標量を現行どおりとすることが確認されました。
全国の地盤沈下に関する測量情報を取りまとめた「全国の地盤沈下地域の概況」及び代表的な地下水位の状況や地下水採取規制に関する条例等の各種情報を整理した「全国地盤環境情報ディレクトリ」を公表しました。また、持続可能な地下水の保全と利用の方策として、「地下水保全」ガイドライン及び事例集の周知を図りました。さらに、湧水保全に取り組んでいる関係機関・関係者の相互の情報共有を図るため、全国の湧水保全に関わる活動や条例などの情報を「湧水保全ポータルサイト」により発信するとともに、湧水の実態把握の方法や保全・復活対策等について紹介した「湧水保全・復活ガイドライン(平成22年3月)」の周知を図りました。令和6年能登半島地震では生活用水等の代替水源として湧水の重要性が再認識されたこともあり、更なる水環境保全・活用の普及啓発を図るべく、地域の名水や湧水に関してSNSで周知しました。
地下水・地盤環境の保全に留意しつつ地中熱利用の普及を促進するため、「地中熱利用にあたってのガイドライン(令和5年3月改訂)」及び一般・子供向けのパンフレットや動画で周知を図るとともに、「再生可能エネルギー熱「地中熱」に関する懇談会」を開催しました。
水道水質基準に適合する安全な水道水を国民に供給するため、最新の科学的知見に基づき、水道水質基準等の設定・見直しを、着実に実施しています。有機フッ素化合物であるPFAS(ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物)のうち、PFOS及びPFOAについては、2024年6月に内閣府食品安全委員会がまとめた「有機フッ素化合物(PFAS)に関する食品健康影響評価書」等を踏まえて、検討を進めています。また、2024年5月から9月にかけて、水道におけるPFOS及びPFOAに関する全国調査を実施し、全国の水道事業者等における検出状況を把握するとともに、11月及び12月には取りまとめ結果を公表しました。同調査結果も活用しつつ、水道法(昭和32年法律第177号)に基づく水質基準への引上げを含めた対応を進めていきます。
また、公共用水域等におけるPFOS及びPFOAを含むPFASについては、「PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議」と「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」の2つの専門家会議にて検討を行っており、2024年11月には「PFOS 及び PFOA に関する対応の手引き(第2版)」を公表しました。このほか、PFASと健康影響の関連性を明らかにするために「PFASに関する総合研究」等を実施するとともに、リスクコミュニケーションを促進するために「PFOS、PFOAに関するQ&A集」の更新やリーフレット、ポータルサイト等の作成を行いました。
湖沼については、湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に基づき、11の指定湖沼において、「湖沼水質保全計画」を策定し、河川浄化等の水質の保全に資する事業、各種汚濁源に対する規制等の措置等を推進しています(図4-2-10)。このうち、2024年度においては、3湖沼について計画改定を行いました。また、湖辺域の植生や水生生物の保全など湖沼の水環境の適正化に向けた取組として、水草の大量繁茂への対策を示した技術資料を作成しました。
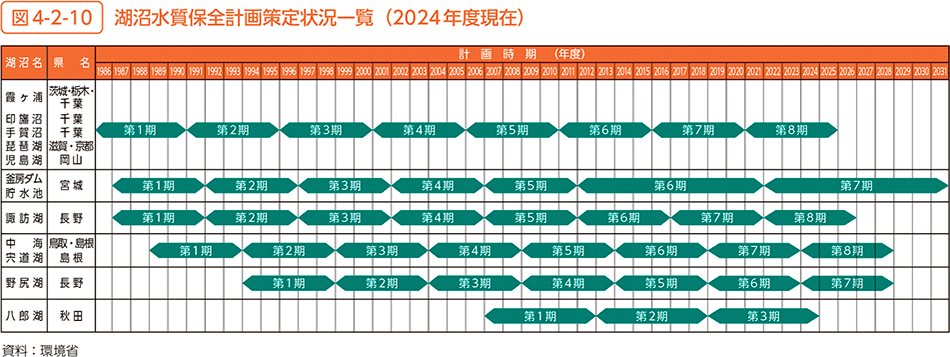
琵琶湖については、琵琶湖の保全及び再生に関する法律(平成27年法律第75号)に基づき、主務大臣が定めた「琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針」及び滋賀県が策定した「琵琶湖保全再生施策に関する計画」等を踏まえ、関係機関と連携して琵琶湖保全再生施策の推進に関する各種取組が行われています。また、気候変動の影響や生態系の変化を踏まえ、従来の湖沼水質保全の考え方における流入負荷を減らして湖内の水質を改善するという考え方に加え、物質循環を円滑にすることで水産資源を保全し、水質の保全との両立を図るという考え方の下、気候変動の影響予測や物質循環に係る検討、琵琶湖の内湖を対象とした植物プランクトンの異常増殖に係る対策の検討を行いました。
閉鎖性が高く富栄養化のおそれのある海域として、全国で88の閉鎖性海域を対象に、水質汚濁防止法に基づき、窒素及びりんに係る排水規制を実施しています。
また、瀬戸内海においては、瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律(令和3年法律第59号)に基づき、地域ごとのニーズに応じて特定の海域への栄養塩類供給を可能とする栄養塩類管理制度を創設しています。
下水道終末処理場においては、豊かな海の再生や生物の多様性の保全に向け、近傍海域の水質環境基準の達成・維持等を前提に、冬期に下水放流水に含まれる栄養塩類の濃度を上げることで不足する窒素やりんを供給する、栄養塩類の能動的運転管理を進めました。
人口、産業等が集中した広域的な閉鎖性海域である東京湾、伊勢湾及び瀬戸内海を対象に、COD、窒素含有量及びりん含有量を対象項目として、当該海域に流入する総量の削減を図る水質総量削減を実施しています。
これまでの取組の結果、陸域からの汚濁負荷量は着実に減少し、これらの閉鎖性海域の水質は改善傾向にありますが、COD、全窒素・全りんの環境基準達成率は海域ごとに異なり(図4-2-11)、赤潮や貧酸素水塊といった問題が依然として発生しています。また、「きれいで豊かな海」を目指す観点から、藻場・干潟の保全・再生等を通じた生物の多様性及び生産性の確保等の総合的な水環境改善対策の必要性が指摘されています。
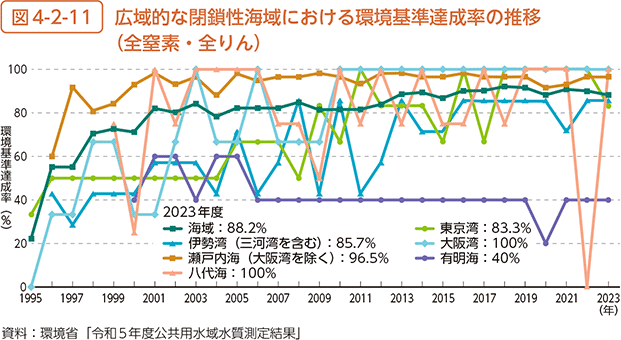
[![]() Excel]
Excel]
このような状況及び課題等を踏まえ、2022年1月に策定した第9次総量削減基本方針に基づき、関係都府県において総量削減計画の策定及び総量規制基準の設定が実施され、これらに基づく取組が進められています。
具体的には、一定規模以上の工場・事業場から排出される汚濁負荷量について、都府県知事が定める総量規制基準の遵守指導による産業排水対策を行うとともに、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業集落排水施設、コミュニティ・プラント等の整備等による生活排水対策、合流式下水道の改善、その他の対策を引き続き推進しました。
瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)の改正(2022年4月施行)や、同法に基づく「瀬戸内海環境保全基本計画」(2022年2月閣議決定)に基づき、瀬戸内海の有する多面的な価値及び機能が最大限に発揮された「豊かな海」を目指し、関係府県において、瀬戸内海の環境保全に関する府県計画の変更が進められました。加えて、法改正で新たに盛り込まれた栄養塩類管理制度について、兵庫県における「栄養塩類管理計画」の策定(2022年10月)に続き、2024年3月には香川県、2025年2月には山口県においても同計画が策定されました。
また、湾・灘ごとの水環境の変化状況等の分析、藻場・干潟分布状況調査、気候変動による影響把握及び適応策の検討、水環境と水産資源等の関係に係る調査・検討を進めています。
同法に基づき、瀬戸内海における埋立て等については、海域環境、自然環境及び水産資源保全上の見地等から特別な配慮を求めています。同法施行以降、2024年11月1日までの間に埋立ての免許又は承認がなされた公有水面は、5,024件、13,782.5ha(うち2023年11月2日以降の1年間に11件、52.1ha)です。
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成14年法律第120号)に基づき設置された有明海・八代海等総合調査評価委員会が2017年3月に取りまとめた報告、及び2022年3月に取りまとめた中間取りまとめを踏まえ、有明海及び八代海等の再生に関する基本方針に基づく再生方策の実施を推進するとともに、赤潮・貧酸素水塊の発生や底質環境、魚類等の生態系回復に関する調査等を実施しました。また、2026年度をめどとした評価委員会報告の取りまとめに向け、評価委員会で審議を進めました。
藻場・干潟の保全・再生・創出と地域資源の利活用の好循環を創出し、藻場・干潟が持つ多面的機能を最大限発揮することを目指す「令和の里海づくり」モデル事業を2022年度から実施しています。2024年度は、沿岸地域における里海づくりに取り組む19団体を支援しました。さらに、今後の里海づくりのあり方検討会において、過年度の取組から得られた成果や課題を踏まえ、環境省が取り組むべき今後の里海づくりの理念や指針、藻場・干潟の保全や利活用のあり方について検討し、「今後の里海づくりのあり方に関する提言」を取りまとめ、2025年3月に公表しました。また、里海づくりの手引書や全国の里海づくり活動の取組状況等について、ウェブサイト「里海ネット」で情報発信を行いました。
2024年5月にインドネシアのバリにおいて開催された第10回世界水フォーラムにおいて、WEPAの知識と経験の共有を通した水質改善への取組を紹介しました。また、2025年2月に第20回WEPA年次会合をラオス(ヴィエンチャン)で開催し、参加国における水環境管理に関する情報の共有を行うとともに、流域管理の課題解決に関して意見交換を実施しました。さらに、WEPA参加国の要請に基づく水環境改善プログラムとして、タイにおける汚濁負荷管理ガイドラインの策定やフィリピン及び共通の課題を抱える参加国における沿岸管理手法等についての調整を行いました。
我が国企業による海外での事業展開を通じ、アジア等の水環境の改善を図ることを目的に、2011年度からアジア水環境改善モデル事業を実施しています。2024年度は、過年度に実施可能性調査を実施した2件(ベトナム)の現地実証試験やビジネスモデルの検討を実施したほか、新たに公募により選定された民間事業者が、インドネシアにおける「エビ養殖産業における閉鎖循環式陸上養殖による沿岸水域の水質改善とエビ収穫量の向上モデル事業」の実施可能性調査を実施しました。