2020年1月に策定された「革新的環境イノベーション戦略」を受け、環境・エネルギー分野の研究開発を進める司令塔として、2020年7月から「グリーンイノベーション戦略推進会議」が開催され、関係省庁横断の体制の下、戦略に基づく取組のフォローアップを行ってきました。また、第203回国会での2050年カーボンニュートラル宣言を受け、2020年12月に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(以下「グリーン成長戦略」という。)が報告され、2021年6月には、更なる具体化が行われました。
グリーン成長戦略においては、革新的技術の研究開発・実証から社会実装までを継続して支援する2兆円のグリーンイノベーション基金やネット・ゼロに向けた投資促進税制等の措置のほか、重要分野における実行計画が盛り込まれています。
具体的には、洋上風力・太陽光・地熱産業(次世代再生可能エネルギー)、水素・燃料アンモニア産業等のエネルギー関連産業に加え、自動車・蓄電池産業、半導体・情報通信産業等の輸送・製造関連産業のほかに、資源循環関連産業やライフスタイル関連産業等の家庭・オフィス関連産業に係る現状と課題、今後の取組方針等が位置付けられました。
環境省において、高品質GaN(窒化ガリウム)基板の製造からGaNパワーデバイスを活用した超省エネ製品の商用化に向けた要素技術の開発及び実証、低コスト化を達成するための技術開発等、先端技術の早期実装・社会実装に向けた取組を推進しているほか、次世代エネルギーの社会実装に向け、地域資源を活用して製造した水素を地域で使う地産地消型のサプライチェーンを構築する実証を実施しています。また、環境省、国立環境研究所、JAXAの共同ミッションとして実施している温室効果ガス観測技術衛星GOSATは、2009年の打上げ以降、二酸化炭素やメタンの濃度を全球にわたり継続的に観測してきました。2018年には、観測精度向上のための機能を強化した後継機GOSAT-2が打ち上げられ、現在、これらのミッションを発展的に継承したGOSAT-GWについて、2025年度前半の打ち上げを目指して開発を進めています。GOSATシリーズから得られるデータを利用して、大規模排出源の特定やパリ協定に基づく各国の排出量報告の透明性の確保を推進し、脱炭素社会への移行を目指しています。また、資源循環関連産業に係る取組として、バイオプラスチックの利用拡大に向け、2021年1月に「バイオプラスチック導入ロードマップ」を策定し、バイオプラスチックの現状と課題を整理するとともに、ライフサイクル全体における環境・社会的側面の持続可能性、リサイクルを始めとするプラスチック資源循環システムとの調和等を考慮した導入の方向性を示しました。バイオプラスチックの導入促進に向け、技術実証や設備導入の支援を実施し、社会実装を推進しています。さらに、2024年5月に成立し、公布された二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和6年法律第38号)の全面施行に向けた下位法令等の整備を進めるとともに、CCUS/カーボンリサイクルの早期社会実装に向け、CO2の分離・回収から輸送、貯留までの一貫した技術の確立や、廃棄物処理施設から出る排ガスのCO2を利用して化学原料を生成し、社会で活用するモデルの検討や実証事業等に取り組みます。
また、持続可能な社会の実現に向けては、自然再興・炭素中立・循環経済の各分野及びこれらの統合的推進のための様々な技術的課題等を解決するイノベーションの創出と社会実装を行うスタートアップ(以下「環境スタートアップ」という。)に対する支援が重要です。環境省では、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)に基づくSBIR(Small/Startup Business Innovation Research)制度等を踏まえ、成長ステージに応じた、研究開発・事業化支援、優れた環境スタートアップ起業の表彰、事業化段階における信用付与や株式会社脱炭素化支援機構による投融資等のシームレスな環境スタートアップ支援を行っています。また、2024年度より新たに既存企業からの出資を要件にしたオープンイノベーション枠を設け、事業化の促進を図っています。
事例:環境スタートアップ大賞環境大臣賞(Gaia Vision)
環境省では将来有望な環境スタートアップへの表彰等による、新たなロールモデルの創出や事業機会の拡大の支援を目的として、2020年度より環境スタートアップ大賞を実施しています。2023年度に環境大臣賞を受賞したGaia Visionは、洪水シミュレーション技術や、気候データ分析技術を活用した気候変動リスク分析プラットフォーム「Climate Vision」やリアルタイム洪水予報ソリューション「Water Vision」を提供しています。拠点のリスク管理やグローバルサステナビリティ開示対応を行う製造・物流・金融業界等で広く利用されており、気候変動適応における高い技術力と社会的なインパクトが評価されました。
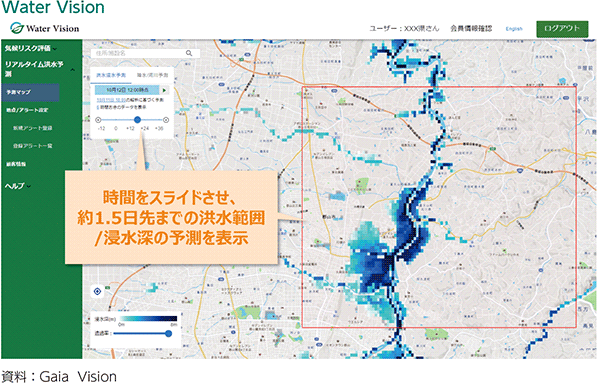
コラム:人工光合成
CCU技術の一つとして、人工光合成が注目されています。人工光合成は、太陽光と水を用いて、エネルギー蓄積反応を利用し、CO2が発生しない水素等のエネルギーやCO2還元生成物であるオレフィン等の有用化合物を合成する技術であり、日本においても研究開発が進められています。光触媒や太陽電池に太陽光が当たることにより生じた電気エネルギーから水分解などにより目的生成物を生成する手法や太陽光から特定の物質を生成する能力を持つ微生物を活用する手法など、様々な手法が存在します。現在、環境省においては、人工光合成技術を活用したCO2電解技術の開発・実証を進めています。
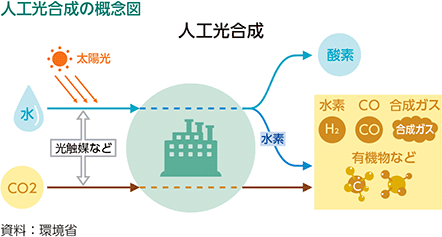
コラム:人流データ
近年の情報通信技術の発達に伴って、スマートフォン等の端末から得られるビッグデータを脱炭素まちづくりに活用する動きもあります。
環境省においても、事業者と連携しつつスマートフォン等から得られる移動に関するデータ(人流データ)を地方公共団体等に提供し、コンパクト・プラス・ネットワークの推進など、地域の脱炭素化に活かしてもらう取組を進めており、以下はその一例です。
・兵庫県加古川市では、都市機能の集約等を目的として2021年に加古川駅から徒歩12分の場所にあった図書館を駅前に移転させました。その際にかつての図書館に来訪する人たちの交通手段の変化を比較したところ、車によりアクセスする人の割合は移転前の68%から移転後は62%に減少するとともに、若い女性による活用が進んだことも示されました。
・富山県富山市においては、2020年~2023年にかけて収集した人流データを用いて富山市内の移動の状況について詳細に分析を行いました。その結果、徒歩移動の範囲が半径600m付近を境に大きく減っていることが明らかになりました。現在、富山市においては、民間事業者や県と連携して、ちょうど徒歩移動の外周にあたる川沿いの整備を始めとした賑わいの創出、ウォーカブルの促進に取り組んでいます。
人流データを活用した脱炭素まちづくりの推進に関しては大きく[1]行政機能の集約等によるコンパクトなまちづくりの推進、[2]電車やバス等の公共交通の利活用促進、[3]市域の中心部におけるウォーカブルの推進等が考えられます。
人流データを活用したマーケティング等は既に民間の事業者等により取組が進められていますが、今後地方公共団体においても、企画部門や都市計画、健康福祉、環境部署が連携してこうした脱炭素まちづくりに取り組むことが期待されます。
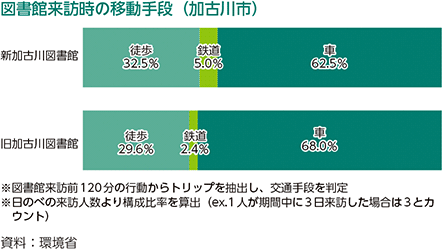
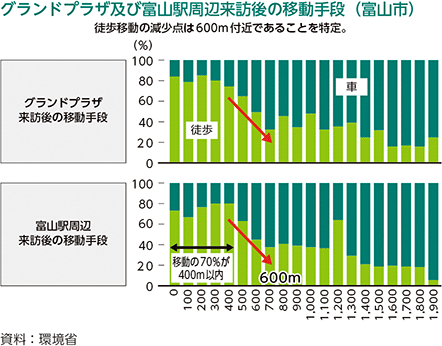
コラム:2025年日本国際博覧会
2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)は「いのち輝く未来社会のデザイン」をメインテーマとし、ポストコロナ時代の新たな社会像を提示していくことを目指しています。また、「未来社会の実験場」というコンセプトの下、会場を多様なプレイヤーによる共創の場とすることにより、イノベーションの誘発や社会実装を推進しようとしています。
本コンセプトの具体化に向けた環境分野の取組として、再エネ水素を使ったメタネーション実証事業の実施や福岡館と連携した環境にまつわるバーチャルコンテンツの展示を行っております。また、本年9月にはネイチャーポジティブに向けた取組に関する展示や、資源循環や海洋プラスチックごみ対策に資する取組等の展示等を行います。
とりわけ、シグネチャーパビリオンの一つである福岡伸一氏プロデュースの「いのちの動的平衡館」と連携したバーチャルコンテンツの展示では、web上において、環境上の異変が起きている森・海・都市等をフィールドに、環境問題にまつわるいくつかの問いかけに対して、自分自身の考え方に沿って分岐路を選択しながらゴールを目指します。ゴールでは、問いかけへの回答から導き出された自身に適した環境配慮アクションを行動指針としてユーザーに提案するなど、ゲーム体験を通じて楽しみながら環境保全に対する理解促進と行動変容を促すコンテンツを展開しています。
環境省では大阪・関西万博の機会を捉えて、我が国の優れた環境技術や我が国の目指す未来像について引き続き発信していきます。